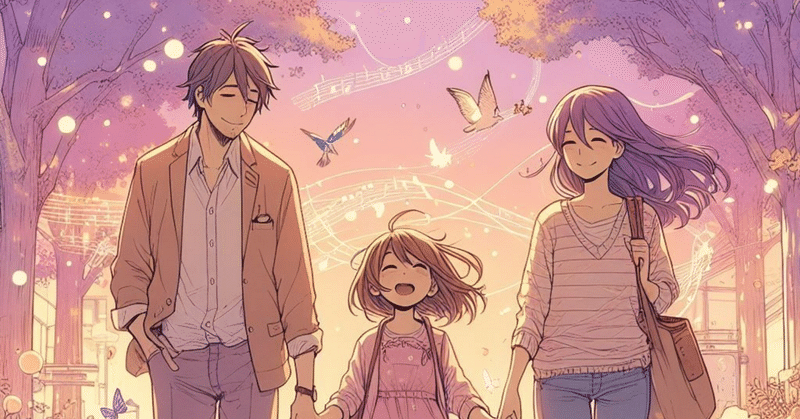
吾が幼きを幼いつくしみ、以て人之幼きに及ぼす
日本の人口が減少していくことがまぎれもなく事実で、とくにZ世代に若者はやく45.7%が子供を欲しくないことがBIGLOBEの調査で分かった。なぜ子供を産まないのかを考察する。
その中で17.7%のZ世代の若者が子供を欲しくない理由は「お金の問題」、「お金の問題以外」は42.1%だった。「お金の問題以外」の中に「育てる自信がない」「子供が好きではない」「自由がなくなる」が主だった。この調査の結果では金銭面での問題は思うほど重大ではなさそうだが、金銭面以外の支援が欠かせない。
ここである言葉を打ち出したいと思う。「吾が幼きを幼いつくしみ、以て人之幼きに及ぼす」だ。この言葉をテーマにして解決策をまとめていく。
社会化子育て
「社会化子育て」という概念は、単に家庭内の教育に留まらず、社会全体が子どもたちの成長と発達に関わる役割を果たす必要があるという考え方を指している。これは、教育、地域コミュニティ、政策など、様々な社会的要素が結びつき、子どもたちの健全な成長をサポートするシステムの重要性を強調している。今の日本は確かに社会化子育てのシステムが、例えば出産一次支援金、18歳以下の医療費無料などあると言えるが、我々出した策は今より以上支援、かつ一部の行政強制の部分が設けられている。
「社会化子育て」は主に五つの部分から構成する。
第一の分野は、公共サービスの強化である。具体的には、増税を通じて教育・保育施設への財政支援を拡大し、教育従事者の確保と数の増加を目指す。この施策は、国民全員が出生から成人に至るまでの間、無料かつ高品質な教育を受けられるようにすることを目的としている。この教育システムは、宿泊施設、食事、交通、教材、フィットネス、社会実践力育成、心理的発達に関する費用もカバーし、これらに限定されず、幅広い支援を提供する。
当政策の主要目的は、政府サービスの活用による家庭内での育児負担の軽減と、子育ての一元化を通じた総投資の効率化である。現行の家庭ごとの子育てモデルでは、十分な出生率を維持できていないという課題が明らかになっている。これは、特定の階層や地域に限らず、社会全体の問題なのだ。統計によれば、経済的に豊かな家庭ほど出生率が低い傾向にある。家族の所得水準を下げることで出生率が改善される可能性はあるが、実際にはこの選択は現実的ではない。したがって、国は子育ての責任を積極的に負担し、集中的な投資を行うことで、この問題に対処する必要がある。
社会化子育てにおける第二の重要な側面は参加方法である。家族が社会化された子育てプログラムに参加する方法には、基本的に「自発的参入・退出」と「強制参加」の二つの形態が存在する。多くの家庭にとって、「自発的参入・退出」の方式が適用される。これにより、育児の負担が過大と感じた際には、子育ての一部または全部を社会化子育て機関に委ねることができ、状況が改善されればいつでもこれらのサービスから撤退し、再び家庭内での育児を行う選択も可能である。一方、「強制参加」の原則は、問題を抱える一部の家庭に適用される。国は、未成年者の健康状態や発達を監視し、特定の基準を下回る場合には社会的介入を行う。これには、学校の養護教諭や心理学者による健康チェックやカウンセリング、地域社会による家庭環境の監視などが含まれる。この制度により、子どもが不適切な環境に置かれている場合、初期段階での教育的介入から、必要に応じて親権の剥奪や子どもの保護措置へと対応策が段階的に進展する。子どもが家庭に戻る際には、厳格な手続きが求められる。
これは、複数の重要な目的を達成することを目指している。第一に、家庭内での子育てに伴う負担を軽減することで、出産への意欲を高めることが挙げられる。第二に、未成年者の基本的人権の保護を重視し、彼らの福祉を保障することが目標である。さらに、将来の人口の健全な発展を確保するために、人口の質に一定の基準を設定し、社会全体の発展に寄与することを意図している。
第三として、データ規制の重要性が浮かび上がる。家庭内での未成年者の生活に関する規制に加え、公的な養育施設における規制は、さらに厳格なものである必要がある。技術の進歩を活用し、教師や生徒に記録装置を配布することで、日常活動を詳細に追跡する体制を確立すべきである。このようなデータは通常秘匿されるが、事故や犯罪発生時には、責任の所在を明確にするための重要な手段となる。
目的は、公的機関の業務におけるリスクを最小化し、追跡可能な業務データを通じて、社会化された支援システムへの国民の信頼を確立し強化することにある。これは、公的な養育施設における透明性と信頼性を向上させることで、社会全体の利益に資するものである。
第四としては、公的施設における保険によるサポート体制である。この制度では、施設に入所する未成年者の親権は家族から国の公的機関に移され、国が統一的に管理する保険プログラムに加入する。事故が発生した場合、この保険からの賠償が行われることになる。また、教師や施設の職員は、規則に従って行動している限り、個人的な責任を負うことはない。
この政策の主目的は、教師やソーシャルワーカーが上司からの圧力や事故発生時の責任の不安から解放され、より積極的に職務に従事できるようにすることにある。実際には、一部の公立小学校では、事故発生時の責任問題を恐れて、生徒の活動を制限するケースが報告されている。保険制度の導入により、教育従事者の不安を軽減し、彼らの労働意欲を刺激することが期待されている。
第五の重要分野は、家庭と学校間の協力関係の構築である。子どもが公的な施設に通うことが自発的であれ非自発的であれ、親は社会化された子育てプログラムに参加し、そのプロセスを監督することが推奨される。これには、親が自らの時間を活用して、先進的な家庭教育の方法を学び、個人の経験を共有し、子どもとの強い情緒的絆を維持することが含まれる。
本政策の根本的な目的は、子育ての負担軽減によって親子関係の質的向上を図り、社会全体の協力による子育て環境の充実を目指すことにある。子育てにおけるプレッシャーが緩和されることで、親子間の親密な関係構築により多くの時間と空間が確保されることが期待される。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
