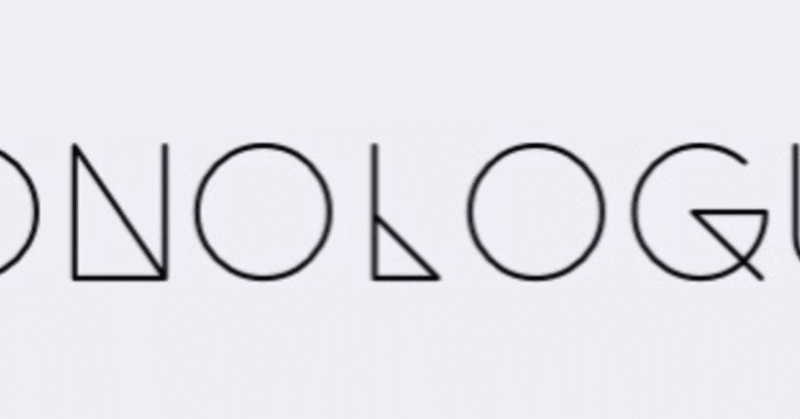
[化学]混ざりやすい単語を区別しよう!②
こんにちは、Monologueの森田です。
早くも連載記事「混ざりやすい単語を区別しよう!」の第二弾です。
今回は、質問箱などで要望のあったものを中心に触れていきたいと思います。
・これらの区別、できていますか?
皆さんは、この6つの言葉の区別ができているでしょうか?
質量数 相対質量 原子量 分子量 式量 物質量
わからなかった皆さん、大丈夫ですよ。これから1つ1つ説明していきます。
①質量数とは?
この話をしていくうえでまず「質量数」の説明をしていく必要があったので、ここで説明します。
質量数とは、原子核に含まれている陽子の数と中性子の数の和のことを指します。
「同位体」のことを覚えていますか?これは、「原子番号が等しく、質量数が異なる原子」という定義でした。この定義を覚えておくと、「質量数って何?」って聞かれたときに答えが浮かびやすいかな、と思います。
ちなみに、原子番号は陽子の数に等しいので、同位体は、原子番号が同じで、中性子数が異なる原子とも言い換えることができます。
②相対質量と原子量の違い
相対質量と原子量?値同じじゃん!!という風な感じで混同されがちですが、もちろん区別があります。それでは定義を見ていきましょう。
・相対質量:質量数12の炭素原子1個の質量を12としたときの、各原子の相対的な質量
・原子量:各元素の同位体の相対質量と存在比から求められる平均値
かみ砕いて説明していきます。まずは相対質量です。
質量数12の炭素原子の質量は1.9926×10^-23g、質量数1の水素原子の質量は1.6735×10^-23gと、このままの状態だと原子の質量を扱うのは非常に大変です。
そこで、「質量数12の炭素は12だ!」という基準を設けることで、原子の質量を扱いやすくしよう!として考えられたのが相対質量なのです。
相対質量を用いると、質量数1の水素原子の相対質量は1.0078となり、最初の値よりも遥かに扱いやすいですね。
原子量は、この「相対質量」を用いた考え方です。
先ほどもちらっと触れましたが、自然界に存在する多くの元素には、質量数、すなわち相対質量の異なる「同位体」が存在します。
原子量は、これらの「同位体」も含めて、それぞれの元素がどれくらいの質量なのかな?というのを表す数字なのです。
つまり、相対質量はそれぞれの原子の質量、原子量は同位体を考慮したそれぞれの元素の概ねの質量を指すということになります。
③原子量と分子量と式量の違い
原子量の考え方が理解できれば、分子量も式量も理解できます。
これらの違いは、
分子量:分子式に含まれる元素の原子量の総和
式量:組成式やイオン式に含まれる元素の原子量の総和
ということだけです。これはわかりやすいですね。
④物質量とは?
最初のように並べられると、「物質量?どれだっけ?」となるかもしれませんが、物質量はほかの5つとは話が違います。
物質量は、molを単位として表した物質の量のことです。
......これに尽きますね。
molに関しては、「混ざりやすい単語を区別しよう!①」のアボガドロ数とアボガドロ定数の違いを覗いてみてください。
さて、今回は、この6つに触れてみました。いかがだったでしょうか?
これらの単語を1つ1つ区別して覚えて、こんがらがらないように覚えていきましょう!
▼Monologueホームページ
http://www.programmer-monica.com
© Monologue.inc
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
