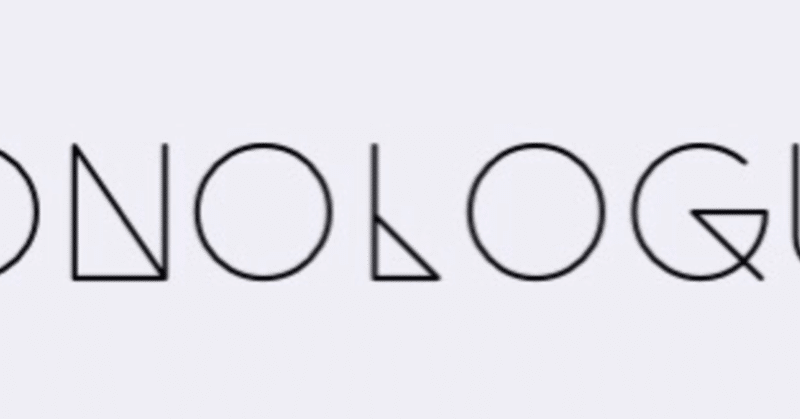
[化学]混ざりやすい単語を区別しよう!①
こんにちは、Monologueの森田です。
今回から「混ざりやすい単語を区別しよう!」と題して連載記事をお送りいたします。
化学には名前が似ていて混同してしまいがちな単語がいくつかあります。この記事では、それらをピックアップして区別して覚えよう!ということでやっていきたいと思います。
①電子親和力と電気陰性度
まずは王道のこれです。本当に名前が似ていて、電気親和力?え?なんだっけ?みたいになってしまいがちです。では早速これらの定義を見ていきましょう。
・電子親和力:原子が電子1個を受け取って、1価の陰イオンになるときに放出するエネルギーのこと ; 1価の陰イオンから電子1個を取り去るのに要するエネルギー
・電気陰性度:共有結合している原子間で、原子が共有電子対を引き寄せる度合いを数値であらわしたもの
まず「電子親和力」は簡単に言うと「陰イオンへのなりやすさ」です。陰イオンになりやすい物質ほど電子親和力は高くなります。そのため、17族のハロゲンは1価の陰イオンになりやすいため、この値が大きいです。
ここで注意しておきたいのは、「電子親和力が最大の元素がClであること」です。「周期表において右上にいけばいくほど陰性って習ったから最大はFだよ!」と思いたくなりますが、残念ながら違います。これは覚えるしかありません。
なお、理由に関してはこの記事に詳しく載っていたので参考にしてください。→https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1386913073
また、ここで同時に押さえておきたいのは「イオン化エネルギー」です。
イオン化エネルギーの定義は「気体状態の原子から電子1個を取り去って、1価の陽イオンにするために必要なエネルギー」です。これをかみ砕いて言うと、「陽イオンへのなりにくさ」となります。そのため、1族や2族元素などは陽イオンになりやすいため、この値が小さく、18族元素は単体で安定のため、この値が大きいです。(ちなみに最大はHe)
これらをまとめると、電子親和力は「陰イオンへのなり'やすさ'」、イオン化エネルギーは「陽イオンへのなり'にくさ'」を表す、ということになります。こちらも混ざりやすいので注意しましょう。
次に「電気陰性度」です。電気陰性度は、簡単に言うと「共有結合で結ばれている原子を引っ張る強さ」を表します。そのため、原子間で電気陰性度に差があると、電気陰性度の大きい原子のほうに共有電子対が引き寄せられるため、電荷の偏りが生じます。これが「極性」です。
電気陰性度は名前の通り「陰性の強さ」なので、希ガスを除いて周期表の右上にいけばいくほど電気陰性度は大きくなります。よって、電気陰性度が最大の元素はFです。
本当はここで水素結合の話とかも触れたいところなのですが、これは後日結合のまとめ記事を作る予定なのでそこで紹介します。
②アボガドロ数とアボガドロ定数
次はこの2つです。「え?そもそも違いあったの?」という人も多いかもしれません。たしかに値自体は6.02×10^23と同じであるため、区別しづらいかもしれませんが、これらは定義も単位も違います。それでは見ていきましょう。
・アボガドロ数:炭素12g中に含まれる炭素原子の数 (単位なし)
・アボガドロ定数:1molあたりの粒子の数 (単位 /mol)
アボガドロ数は単純に「炭素12g拾ってきたから原子の数数えてみたら6.02×10^23個あったよ~」、ただそれだけです。
一方で、アボガドロ定数は、「このアボガドロ数を利用して『mol』という単位を定義しよう!」みたいな感じです。
なので、化学のテストの最初に書いてある6.02×10^23という数字はアボガドロ定数を指している、ということになります。
③アレニウスとブレンステッド・ローリーの酸・塩基の定義
今回最後となるのはこの2つです。まずは定義を見ていきましょう。
・アレニウス:水溶液中で水素イオンを生じる物質が酸、水酸化物イオンを生じる物質が塩基。
・ブレンステッド・ローリー:相手に水素イオンを与える分子/イオンが酸、相手から水素イオンを受け取る分子/イオンが塩基。
では順番に見ていきましょう。アレニウスの定義は単純でわかりやすいですね。例を挙げると、HClは水溶液中で水素イオンと塩化物イオンに電離するから酸、NaOHは水溶液中でナトリウムイオンと水酸化物イオンに電離するから塩基、というわけです。
次にブレンステッド・ローリーの定義です。こちらはアンモニアの例を考えるとわかりやすいと思います。例えば、塩化水素とアンモニアが反応した場合、アンモニアはアンモニウムイオンとなって塩化物イオンとともにイオン結晶を作ります。この際、アンモニアは塩化水素から水素イオンを受け取ってアンモニウムイオンとなったため、アンモニアは塩基ということになります。
ちなみに僕はブレンステッド・ローリーの定義を「文字数理論」に則って覚えています。
酸(1文字):与える(2文字) 塩基(2文字):受け取る(4文字)
酸のほうが塩基よりも文字数が少ないから、文字数の少ない「与える」が来るわけです。逆に塩基は酸よりも文字数が多いから、文字数の多い「受け取る」が来るといった塩梅です。
このように、紛らわしいものは「文字数通りに来るか否か」で覚えると楽かもしれません。
文字数通りに来ない、と覚えたパターンを例示します。
・古期造山帯(8音) : 石炭(4音)
・新期造山帯(9音) :石油(3音)
この2つは、「文字数通りに来ない!」と覚えていたのでここに書き記すことができました。
まあ意外と使えたりするので使ってみてください(?)
さて、ここまでいかがだったでしょうか?次回は④~またいくつか触れていきたいと思います。乞うご期待!
▼Monologueホームページ
http://www.programmer-monica.com
© 2020.3.2 Monologue
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
