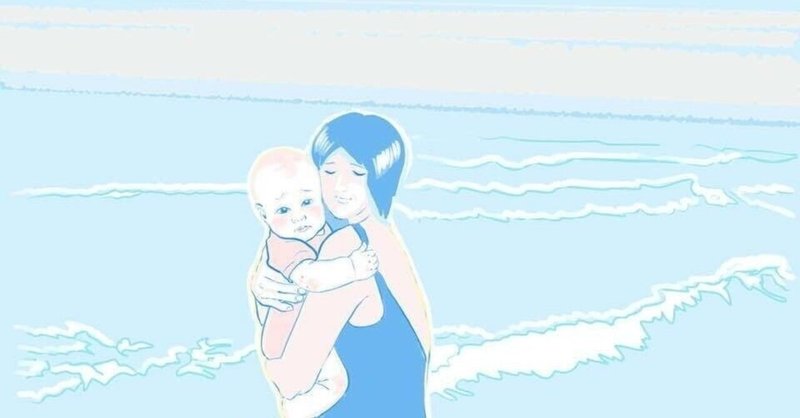
精神科で出会った「孤(子)育て」に翻弄された母親との出会い、そして今わたしにできること
現代では、育児情報があふれています。しかし子育ては、マニュアル通りはいきません。思い通りにいかない子育てに悩み、相談する相手もいないまま孤独感がつのれば、子育ては「孤育て」に変化します。
私が5年前まで働いていた精神科では、子育てに疲弊し、心のバランスを崩して入院になる女性も少なくありませんでした。「私は精神病ではない!」と頑なに入院を拒む女性に出会うたび、「もう少し早く誰かが気づいてあげれば」と思えてなりません。
今回は、私が精神科で出会った2人の母親のエピソードを振り返りながら、「孤育て」をふせぐためには何が必要なのかについて、考えていきます。
子育てに自信がなくなり言葉を失った元モデルのAさん

Aさん28歳、170cmのスレンダーなスタイルが抜群の彼女は、元モデルさんです。結婚後もモデルを続けていたAさんは、妊娠を機に活動を休止しました。
活動休止後は家でひとり過ごす時間が増え、「孤独だった」と、Aさんは話します。営業職のご主人の帰宅時間は遅く、たまの休みも夫婦で過ごす時間はほとんどなかったそうです。お互い働くことでバランスがとれていた夫婦関係は、少しずつ崩れていきました。

Aさんが異変を感じはじめたのは、出産後から1か月が経ったころです。
出産前から育児情報を集め子育ても勉強をしていた彼女は、「子どもは泣かせていけない」と思い込み、子どもの姿が見えていないと不安でしかたありません。子どもの泣き声に過敏に反応する日々は、Aさんの神経をすり減らしていきました。
その様子を見かねた夫は、自分の母親にAさんのサポートを頼みます。しかしお姑さんとは、1年に数回顔を合わす程度の仲だったAさんは、夫の提案に乗り気ではありませんでした。
とはいえ地方出身のAさんは他に頼れる相手はおらず、夫からの提案を受け入れるしかなかったそうです。
そしてお姑さんとの関係が、ますますAさんを追い詰めます。
Aさんを悩ませたのは、お姑さんからのアドバイスでした。オムツの当て方・抱っこの仕方・泣き止ませ方まで、子育て経験者の指摘は、育児マニュアルを否定します。
お姑さんは、Aさんや子どものためを思っていたのでしょう。しかしAさんは、以前にも増してふさぎ込むようになりました。

ご両親と妹さんに付き添われて入院してきたAさんは、言葉を失っていました。聞こえているのに話せない、自分の意思で立つことも歩くこともできない、意思のコントロールができない。そんな状態です。
よほどのストレスがかかっていたのでしょう。しかし入院になったAさんのそばには夫の姿はなく、その後一度も姿を見たことはありません。
Aさんの夫は、妻の異変に気づけず入院にも付き添わない、冷たい男性でしょうか。実は距離が近いからこそ、異変に気が付けないことは、珍しくありません。おそらくAさんは、限界まで自分の気持ちを押し殺していたのでしょう。もしかすると、Aさん自身も心の異変に気が付いていなかったのかもしれません。
幸いにもAさんの経過は良好で、少しずつ表情や言葉が戻ります。そして入院してから3か月後には自力歩行ができ、笑顔が見られました。Aさんが入院して8か月、退院の許可がおります。子どもの写真を見て涙していたAさんは、この8か月どんな思いで過ごしていたのでしょうか。
そして迎えた退院の日、そこにも夫の姿はありませんでした。
ご両親と妹さんに付き添われ退院していったAさんが、今どこで暮らし子どもと再会できたのか、今となっては知る由もありません。
Aさんが思い悩んでいだ時、「大丈夫ですよ。それでいいんですよ」と言ってあげる人がそばにいれば、別の未来があったのではと、思えてなりません。
理想の母親像を求めて感情を抑え続けたHさん

Hさん35歳、夫と2歳になる娘さんの3人家族です。
上場企業に勤め、仕事に打ち込んでいたHさんは「自分は生涯結婚しないだろう」と思っていたそうです。しかしHさんは今のご主人と出会い、恋に落ちます。
そして次の人事では昇進が確定というタイミングで、Hさんの妊娠が発覚します。すでに、妊娠3か月でした。元々結婚する気も出産する気もなかったHさんは、真剣に堕胎を考えたそうです。
最終的に母親になる選択をしたHさんは、女の子を出産しました。子どもが産まれた瞬間、涙が止まらなかったと話します。
しかし仕事一筋だったHさんには、子育てを相談できる友人はいません。公園デビューに挑戦してもママ達の輪に入れず、子どもと家で過ごす時間が長くなっていきます。
この時期Hさんは、「社会から取り残されていく焦りを感じていた」そうです。

1年半の育児休暇が終わり、職場に復帰したHさんに待っていたのは、辛い現実でした。同期の昇進を横目にしながらも、子どもを中心した生活では、思うように仕事ができません。
「仕事を理由に、子どもに寂しい思いをさせていはいけない」と思っていたHさんは、定時になれば退社し、子どもとの時間を優先していきます。しかし仕事が生きがいだったHさんは、思い通りにならない子育てに、イライラがつのるばかりでした。
「この子さえいなければ、私は昇進できたのに」と考えてしまう自分を、責める日々が続きます。
子どもがイヤイヤ期を迎えると、何をするにも時間がかかります。出勤時間がせまってくれば、子どもをせかさなければ間に合いません。
登園の朝、服を着ないとごねる子どもに、Hさんのイライラは限界を迎えました。そして次の瞬間、子どもの頬を叩いてしまったのです。一瞬何が起きたのか、ぼうぜんとするHさん。しかし子どもの泣き声が部屋に響き渡り、我に返ります。
Hさんは、当時を振り返り
「子どもを叩くと、泣く。泣き声と泣き顔を見ていると、気持ちがすっと楽になるの。最低の母親よね」
そう言いながらふっと笑ったHさんは、自分の中の憎悪と戦っていたのではないでしょうか。
夫との口論をきっかけに錯乱状態となったHさんは、救急搬送で入院となりました。

理想の母親像を求めて感情を抑えた結果、子どもを傷つけたと悔やんでいたHさんは、入院してから3か月後に退院の日を迎えました。
Hさんのお迎えには、ご主人と娘さんの姿があります。うれしそうにHさんに駆け寄り、離れていた時間を取り戻すように甘えていた娘さんの姿は、とても印象的でした。
子どもに手をあげるなんて、ひどい母親かもしれません。しかし完璧な母親像を求めるあまり、自分の感情を抑えてしまう女性は少なくありません。それはやがてストレスとなり、子どもが標的になってしまいます。
Hさんが思い悩んでいた時、「自分の気持ちを押し込めなくてもいいですよ」と言ってくれる人がそばにいれば、Hさんは気持ちをコントロールできたのかもしれません。
少子化がクローズアップされています。しかし少子化は、子どもを産めば解決する問題ではありません。子育てに正解を求めては孤独になり、SOSを出せずに「孤育て」になっている女性を減らすことが、先決ではないでしょうか。
そのために私ができることは何か、これからも模索をしていきたいと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
