
2040年の世界 博士の提案
「インタビュー?」
とカイは聞いた。
「ああ、インタビューって言ってもそんな形式ばったものじゃないよ。定期的に僕のところに来てくれて、僕と雑談するだけだよ。でもその雑談の内容は録画記録するからそれはあらかじめ承知しておいてほしいのだけどね。」
博士は彼らが自分たちがどうして保護を嫌がるのか真正面から聞いて素直に思ったことをすぐに話すとは思っていなかった。彼ら自身言葉にできないことも多いだろうし、自分でもどうしてなのかわかっていない場合もあるだろう。長い時間をかけて、信頼関係を築いて、普通の何気ない会話から彼らの背景や思考のパターンを探っていきたいと思っていた。
「さて、カイ君。君たちの協力に対するお礼の話をしようか」
博士は優しく微笑んだ。
「お礼?」
カイは少し警戒した様子で尋ねた。
博士はうなずいて続けた。
「そうだよ。でも心配しないで。君たちの安全を第一に考えているんだ。具体的には、こんな形で用意したいと思っているんだ。」
博士は指を立てて数え始めた。
「まず、ここで食事を提供するよ。君たちが来るたびに、栄養バランスの取れた食事を用意する。
次に、生活必需品。衣類や衛生用品なんかだね。必要なものがあれば言ってくれ。できる範囲で用意するよ。
それから、これは少し変わっているかもしれないが、教育の機会も提供したいんだ。基礎的な勉強から興味がある子には応用も。どうかな?」
カイは黙って聞いていたが、博士の提案に興味を示した様子だった。
「そして最後に」
と博士は少し声を落として言った。
「特定の店でのみ使える電子クーポンを渡そうと思う。これなら、君たちが本当に必要なものを、安全に手に入れられるはずだ」
博士はカイの反応を待った。
「どうかな?これなら、君たちの安全も確保できるし、僕たちの約束も守れると思うんだが」
2040年の世界では、デジタル円が主要な決済手段として広く普及していた。この中で、アラタ博士が提案した電子クーポンは、デジタル円とは異なる特殊な形態の決済手段である。
この電子クーポンは、特定の商品やサービスに対してのみ使用できるデジタル形式の引換券で、カイたちのデバイスに直接送信され、指定された店舗でのみ使用可能。例えば、「500デジタル円分のパン」や「1000デジタル円分の衣類」といった形で発行される。
通常のデジタル円取引と異なり、この電子クーポンの使用履歴は中央銀行のシステムに記録に残らず、また、個人のデバイスに紐づいているため、他人への譲渡も困難である。
このシステムにより、カイたちは必要な物資を入手でき、同時にアラタ博士は彼らの生活支援を行いつつ、通常のデジタル円取引を介さないようにすることができる。これは、ピラニータの存在が公的に認知されていない状況下で、彼らを支援するための巧妙な方法といえる。
ちなみにこの時代広く普及しているデジタル円は、従来の法定通貨の特徴と仮想通貨の技術的利点を併せ持つ、国家が公式に発行・管理する仮想通貨であり、民間の仮想通貨とも交換可能である。これは大災害前から各国で研究・開発が進められていた中央銀行デジタル通貨(CBDC)の発展形と言える。
カイは
「考えておく。」
とだけ答えた。
博士はにっこりと笑い
「うん、考えてみて。連絡を待ってるよ。」
ソラは案内AIロボットと猫をいたく気に入ったようだった。猫じゃらしを使って猫と遊び、あくびする猫の口の中に指を入れて猫が口を閉めた時の猫の驚いた表情をおかしがった。
案内AIロボットには人間の大人なら閉口してしまうような質問を何度も飽きずに聞いていた。
案内AIロボットもソラの質問に対して何度同じことを聞かれても丁寧に何度も同じことを答えたり、
ソラの質問の仕方が適切ではない場合は
「おっしゃっている意味がわかりません。」「質問の意味がわかりません。」「すみません、ちょっとそれはわかりません。」
など答え
「おっしゃるって何?どういう意味?お前変な言葉使うな〜」
とソラにまぜっ返され
「おっしゃるとは、相手の言葉を丁寧に表現する言い方です。『あなたが言ったこと』という意味で使います。」
「なんでわざわざ言いかえるの?めんどくさ。」
とソラが言うと
AI案内ロボットは無機質なデジタル音声で
「人が『おっしゃる』のような言葉を使う理由はいくつかあります。
1. 相手への敬意を示すため
2. 場面に応じて適切な言葉遣いをするため
3. 自分の教養や社会性を表現するためです。」
「ケイイって何だよ。キョウヨウは?」
「「敬意」とは、相手に対して持つ尊敬の気持ちや、その人にふさわしい態度で接することです。「教養」とは学問、知識、精神の修養などを通して得られる創造的活力や心の豊かさ、物事に対する理解力です。」
「は?意味わかんねー博士、コイツ、変なことばっかり言ってるけど壊れてる?」
というソラの問いに博士は吹き出してしまった。
博士自身も子どもの頃は自分の周りのあらゆることが疑問だらけで今のソラのように周りの大人に延々と質問を繰り返した。しまいには怒り出す大人もいたことを懐かしく思い出す。
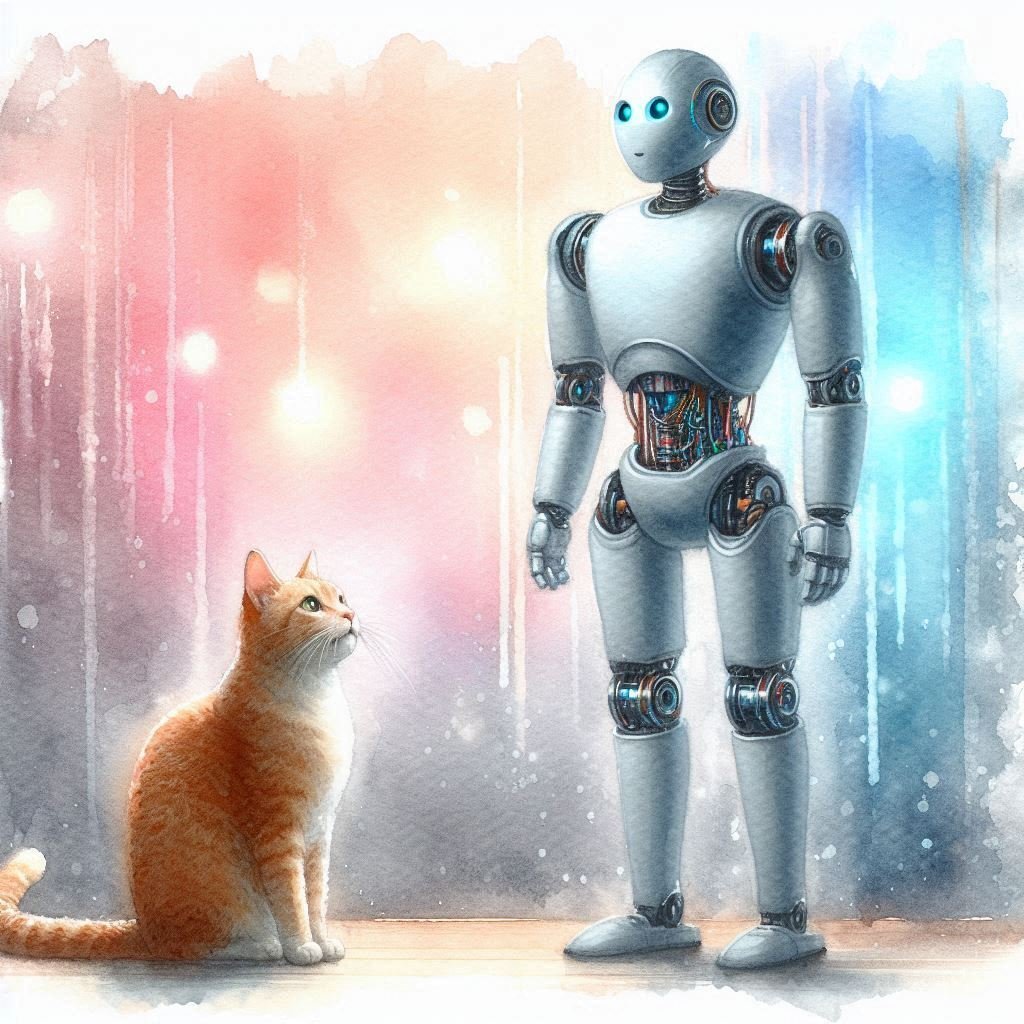
カイは案内AIロボットと猫たちと離れがたそうにしているソラに帰りを促した。
博士はソラとカイにメンバー全員に充分足りるサンドイッチとポットに入った温かく甘い紅茶をお土産に持たせ、手配した自動運転車で寝床の近くまで送らせた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
