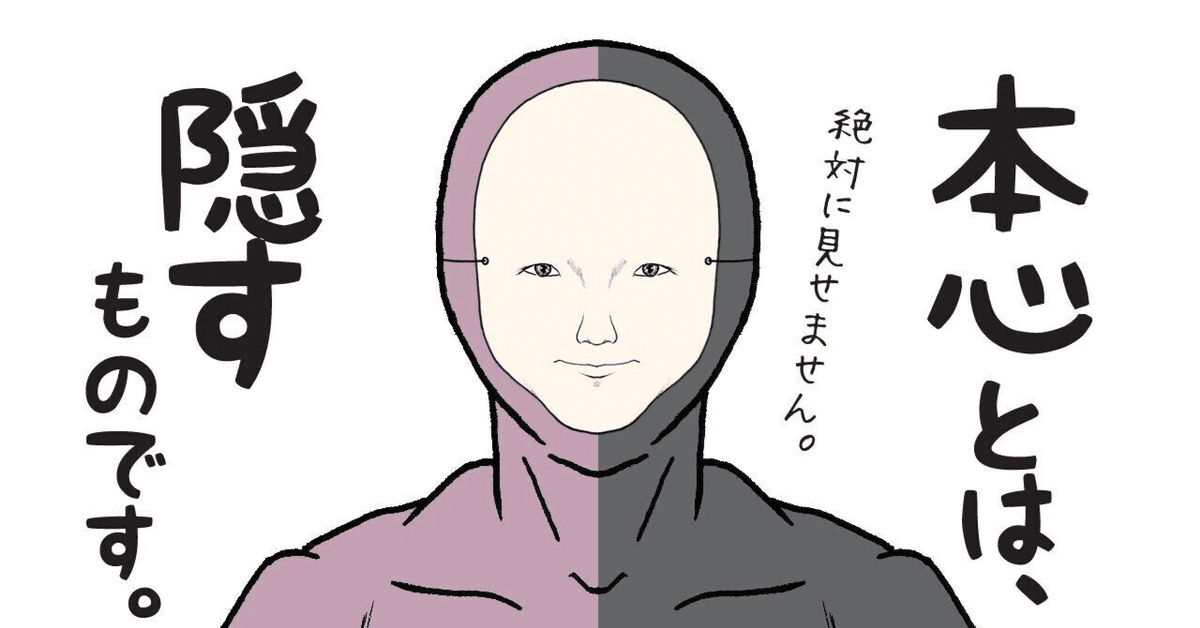
二世問題アレコレ
◉毎日新聞で、被差別部落出身の方のインタビューが載っていました。この方、両親は関西出身で、ご自身は東京で生まれ育っているそうで。地域的な連続性が、実は絶たれているんですよね。そこで思い出したのが浜田雅功氏、子供が幼い頃に標準語を喋ると「気色悪い」と怒っていたという話。その話を聞いた関西の人は、「さすが浜ちゃん、ええ教育しとる」と拍手するかもしれませんが。半分ジョークにしても、自分は微妙に引っかかりました。いくら両親が生粋の関西人でも、生まれ育ってもいない関西の文化と方言を、強要されても難しいんですよね。ここを起点に、いろんな二世問題を考えてみたいです。
【日常から問う部落差別 上川多実さん著『<寝た子>なんているの?』】毎日新聞
関西の被差別部落をルーツに持つ上川多実さんは、“見えない壁”とずっと闘ってきた。「部落ってなに?」「部落差別なんてまだあるの?」。無理解に出合うたび、一つ一つ異議申し立てをしてきた。その来し方をつづった初めての著書『<寝た子>なんているの? 見えづらい部落差別と私の日常』が里山社から刊行された。
上川さんは1980年、東京生まれ。自分が「部落民」だという認識は幼いころからあった。父は部落解放同盟の支部で、母は解放同盟系列の書店で働き、「差別に負けずに生きていきなさい」と言われて育った。
記憶は鮮明だ。4歳、保育園でのできごと。将来の夢を先生が尋ねて代筆していく。「しぶ(支部)で働きたい」と言っても通じない。次に「書店」と言うと、先生は困った顔をした。結局「おかあさんのおしごとのおてつだいをしたい」とされ、教室に張り出された。
ヘッダーはnoteのフォトギャラリーより、メイプル楓さんのイラストです。
◉…▲▼▲▽△▽▲▼▲▽△▽▲▼▲…◉
■移民二世問題■
例えば、知り合いで岡山の生まれの人がいて。奥さんも小学生の同級生。でも、彼はいちおう長男なので、盆暮れに帰省すると、彼の息子に祖母が「この家は将来は〇〇ちゃんのものになるんだからね」と言うわけです。まぁ、田舎ではよくある話なんですが、小学生の息子は「ボク、大きくなったら岡山に引っ越さないといけないの?」と不安になる。東京で生まれ育った彼には、祖父母の話す備前の方言は、何を言ってるかわからない代物。まぁ、方言は方言ですから、そこは同じ日本語。数年も住めば馴染みますが。
でもこれが、別の言語だと…。この二世問題、ネイティブではない移民二世も同じで、アイデンティティ・クライシスが起きやすいようで。例えばアメリカのスペイン語系移民の二世も、ネイティブの新規移民のようにはスペイン語は上手くない問題があるそうで。なので、ネイティブの新規移民にはバカにされるんだとか。ところがアメリカ社会では、スペイン系として差別される。つまり、二重の差別があるんですね。自分が行ったこともない父祖の国のことを、アイデンティティとして求められることの辛さ。そこにどう折り合いをつけるのか? 個人的な経験も在ったので、身につまされます。
アメリカでメキシコからやってくる、スペイン語系移民二世問題も、日本の在日コリアン二世問題も、浜田家の関西人二世問題も、根っこは同じに感じます。友人の在日コリアンとか、本当は帰化したいが、祖父母が反対してるので健在なウチは出来ない……とか言う人間が多かったです。それが方便なのか事実なのか、自分には解りませんが。でもこの祖父母の反対って、自分が東京での生活を選択した(強制連行神話は崩壊しています)のに、標準語を話す息子を責める浜田雅功氏と、根は同じではないかと。子には子の、孫には孫の、人格とアイデンティティがあるのに。
■活動家二世問題■
移民一世のアイデンティティを、否定する気はないですが、それが二世三世への強要になったら、不幸になるのではないか? 日本人のアイデンティティは、けっこうな部分で日本語話者か否か、という部分に依存すると自分は考えています。そんなことに、西日本生の田舎モンは、思いを致します。ウチの田舎の鹿児島では、移民十何世である朝鮮人陶工の子孫が、日本人との通婚を禁じた薩摩藩の方針もあって、未だにアイデンティティ・クライシスになったりします。ところが、故郷を離れて大阪や東京の大都会に出てくると、そんなクライシスは雲散霧消するのですから。
実際に知り合った有田焼の陶工の子孫とか、同じく陶工の子孫でもある呉智英夫子には、そんな苦悩は微塵もないわけで。先祖はどうあれ、自分は日本人であるというアイデンティティに、揺らぎはない。だから自分は、頑なに帰化を拒むのは、けっきょくは薩摩藩の不同化政策と同じで、かえって問題を拗らせるのではないか…と。だから、鄭大均教授の在日と帰化の考えに、自分は近いです。でもそれが正しという気はないですし、押し付ける気もないです。これも、寝た子ですか? さて、冒頭の記事に対して、被差別部落関係の問題を鋭く斬り込む示現舎の宮部さん(神奈川県人権啓発センター)が、こんな指摘をされています。
これは部落差別とは関係なくて、活動家2世問題では。
— 神奈川県人権啓発センター(公式) (@K_JINKEN) March 24, 2024
この人の場合、自分の家庭の常識が世間の非常識であることを受け入れられず、世間に敵意を向けている。その口実が差別だのマイクロアグレッションだのなのでしょう。
これは部落差別とは関係なくて、活動家2世問題では。
この人の場合、自分の家庭の常識が世間の非常識であることを受け入れられず、世間に敵意を向けている。その口実が差別だのマイクロアグレッションだのなのでしょう。
全日本同和会のスローガンなんて「子らにはさせまいこの思い」なのに、トップが世襲の時点で実践してないし、解放同盟も2世が質悪いです
— 神奈川県人権啓発センター(公式) (@K_JINKEN) March 24, 2024
全日本同和会のスローガンなんて「子らにはさせまいこの思い」なのに、トップが世襲の時点で実践してないし、解放同盟も2世が質悪いです
当事者ではない自分には、正誤の判断は下せませんが。ここらへんのアイデンティティ・クライシスは、梁石日先生などの在日文学にも、滲みます。ただ、それを文学で昇華できるクリエイターと、一般人を同一視してもしょうがないと思います。作家なんて、全国に数千人レベルの、特殊例ですから。それでも、西日本の人間として、指摘に納得できる部分はあります。東京に上京して、幼稚園から青学みたいな良家の子女と話すと、その育ちの良さと被差別部落についての基本的な知識の無さに、驚きます。でも、それは同時に悪いことなのかと言われると──自分は違うと思います。
■魚屋差別は寝た子■
例えば、江戸時代は仏教の殺生戒の影響もあってか、魚屋は殺生をする商売なので子供に奇形児が生まれるという、ストレートな差別がありました。一心太助の粋で鯔背な魚屋のイメージと、そういう差別は併存していました。これは、猟師も同じで。では今、「寝た子を起こすなり論はおかしい、魚屋差別を真剣に考えよう」とかいわれても、大概の日本人はキョトンとするでしょう。青学の先輩後輩に感じた育ちの良さとセットの、被差別部落への知識の無さは、魚屋への差別があったことの知識の無さと、相似形な訳です。
これも、寝た子でしょうか? そもそも、寝た子を起こすな理論も、寝た子なんていない理論も、ズレているという点では同じに思えます。しょせん文化、時代の変遷の中で、魚屋への差別が消えていったように、部落差別も消えていくでしょう。少なくとも、制度としての差別が解消されたら、後は個人の心の中の問題。差別心がなくても無知から差別することもあれば、差別心ギラギラでも一生それを隠し通せば、それは内面の問題です。内心の自由に、踏み込むべきではないというのが、言論の自由とも密接な問題。
著書の、Amazonのリンクを上に。興味がある方は、ぜひお読みを。自分の感想は、宮部さんに近いモノです。上京して、浅草弾左衛門とか、そっちの歴史に詳しい人と話したとき、差別は結果的に関西に教えられた部分がある、と語っておられましたね。西日本、特に関西の苛烈な差別は、江戸のそれとは比較にならず。同和問題では、その関西の贖罪意識がスタンダードとして、関東にも押し付けられてしまった面も、あるでしょうね。自分は出自の差別には反対ですが、同時に親から子への強要にもまた、反対する立場です。二世問題は、社会のいろんな部分で起きうることです。かのガンジーでさえ、カースト制度を肯定していたように。
◉…▲▼▲インフォメーション▲▼▲…◉
noteの内容が気に入った方は、サポートで投げ銭をお願いします。あるいは、下記リンクの拙著などをお買い上げくださいませ。そのお気持ちが、note執筆の励みになります。
MANZEMI文章表現講座① ニュアンスを伝える・感じる・創る
どっとはらい( ´ ▽ ` )ノ
売文業者に投げ銭をしてみたい方は、ぜひどうぞ( ´ ▽ ` )ノ
