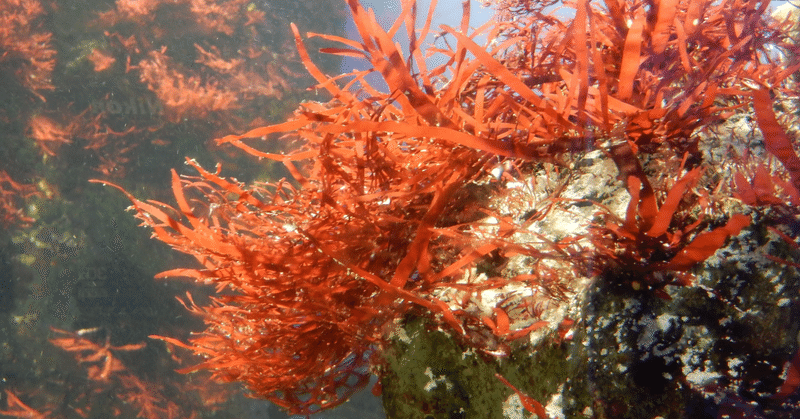
藻類バイオマスで日本が産油国に?
◉うっかり見逃していましたが、藻類バイオマス・エネルギーで、興味深い記事がありました。藻類の専門家でもある渡邉信筑波大学大学院教授が、下水処理場を使って藻を繁殖・濃縮し、原油化するという画期的なプロジェクトを研究されているのですが。ようやく、国の予算がついたとのこと。東京大学が大学内ベンチャーとして、ミドリムシを利用したユーグレナの研究で、健康食品やジェット燃料の精算など、ユニークな試みをやっているのですが。基礎研究はもちろんとても大事なんですが、こういう実学と地続きの研究は、結果的に研究費を生み出すんですよね。
【ついに国の予算がついた…藻類バイオマスエネルギーで日本が本当に産油国になる日】プレジデント・オンライン
藻類バイオマスエネルギー研究を続ける(一社)藻類産業創成コンソーシアム理事長で筑波大学共同研究フェローの渡邉信(わたなべ・まこと)さんのプロジェクトに国の予算がついた。10年ほど前、「日本を産油国にする」と言って顰蹙を買った渡邉さん。しかし、時代はその発言を追うかのように、新エネルギーに向かって大きく舵を切り出した――。
ヘッダーはnoteのフォトギャラリーより、鳥羽水族館の紅藻類の写真だそうです。
◉…▲▼▲▽△▽▲▼▲▽△▽▲▼▲…◉
■効率が良い藻類バイオマス■
石油精製細菌や、オーランチオキトリウムなどの「石油を生産する藻類」の話題が、一時期盛んだったのですが……。最近はあまり聞かなくなっていたのですが……。自分らの世代だと、アントニオ猪木さんのアントン・ハイセルでの、サトウキビの絞り粕を利用した家畜飼料の話題から、バイオマス・エネルギーというとサトウキビや甜菜、トウモロコシなどを使ったものをイメージしがちですが。藻類を用いらバイオマスエネルギーは、トウモロコシの穀物エネルギーに比べて300~800倍ものエネルギー生産能力があるようで。これは、かなり効率がいいですね。
例えば、アメリカは日本の25倍もの国土面積があり、トウモロコシの作付面積が、日本の国土面積と同じぐらいあるそうで。ただでさえ、平地が少なくて山がちな日本では、アメリカのようなバイオマスエネルギーも太陽光発電も、とても無理です。でも、300~800倍も効率がいいのなら、25分の1の狭い国土でも、休耕田とか上手く利用できますし。渡邉信教授によれば、下水処理場で下水を藻に浄化させつつ、藻を生産するという、今ある施設を有効利用できるという、なんとも具体的なお話が。夢が広がりますね~。こちらの動画でも、紹介されていました。
まぁ、こちらの動画はちょっと煽り過ぎな感はありますが、
■下水処理場で石油生成?■
プレジデント・オンラインはこの話題に力を入れているのか、2022年の時点で、こんなふうに報じられていました。記事内容的には、こちらと合わせて読むと、理解が進みますね。混合栄養藻類という言葉は、初めて知りましたが。さすがに研究者として藻類を追求されており、興味深いですね。具体的な産油量はともかく、下水処理場は日本かく地にあり、地産地消できると効率的にも面白いですし。そういう設備が上手く稼働すれば、それこそ過疎地にユーグレナの繁殖場を作って、一緒にジェットエンジン燃料とか生産すれば、効率が良さそうです。
【「日本を産油国にする」と宣言して顰蹙を買った藻類バイオマスエネルギーが、再び注目される3つの理由】プレジデント・オンライン
脱炭素社会の実現のために、藻類バイオマス燃料が再び注目を集め始めている。そのうえロシアのウクライナ侵攻による深刻なエネルギー危機で、その存在感はさらに強くなるはずだ。筑波大学研究フェローでMoBiolテクノロジーズ会長の渡邉信氏は、この15年、藻類によるバイオマスエネルギーの研究に傾注してきた。10年ほど前「日本を産油国にする」と宣言して顰蹙を買ったという、藻類バイオマス燃料研究の第一人者に、その特性と研究の現況を聞いた――。
現実的には、日照量も世界平均よりも低い高温多湿な日本では、こういう生産は難しい問題もあるでしょうけれど。でも、今の過疎地の産地の木々を切り倒して、約にも断たない太陽光パネルを敷き詰めるよりも、よほどマシに思えます。繰り返しますが、風力発電や太陽光発電は、ベースロード電源になりえませんので。そんなものに莫大な予算を投じて、利権に群がらせてる状況は、自民党はアホかとしか思いませんので。こういう研究の予算が、年3000万円の2年とか、悲しくなりますね。洋上風力発電のダメさの証明に、何百億かけてるんだって話です。
■バイオマスに〝も〟期待■
さて、2月14日に書いたこちらのnoteでは、「バイオマス発電は完全に、曲がり角に来てしまったようです。」と書いていますが。バイオマス自体には、別の意味で期待はしているんですよね。とくに、世界第6位の排他的経済水域――その面積は約447万平方kmで日本の国土面積の12倍――を持つ、日本の地理的条件もありますから。それこそ、ホンダワラを洋上で栽培して、バイオマスに利用する研究とか、実はけっこう期待しています。富栄養化した海洋の浄化にも、利用できますから。それこそ、東京湾でホンダワラ栽培の、バビロン計画があっていいです。
今後の日本は、もともと強かった素材研究、ロボット工学、iPS細胞を含む医療研究、バイオテクノロジーなどなどをベースにした、新しい産業分野の育成が必要ですが。海洋開発や研究って、大きなフロンティアだと思うんですよね。こういう、藻類の研究が未来のエネルギーになるかも知れませんから、植物学や農学とか、もっと重視して。文系の自分ですが、社会学者とかの有害振りを見ていると、科研費とか文系にあんまり回さなくてもいいよと思ってしまいます。沖縄科学技術大学院大学のような研究の場を、もっと増やしてほしいぐらいです。
どっとはらい( ´ ▽ ` )ノ
売文業者に投げ銭をしてみたい方は、ぜひどうぞ( ´ ▽ ` )ノ
