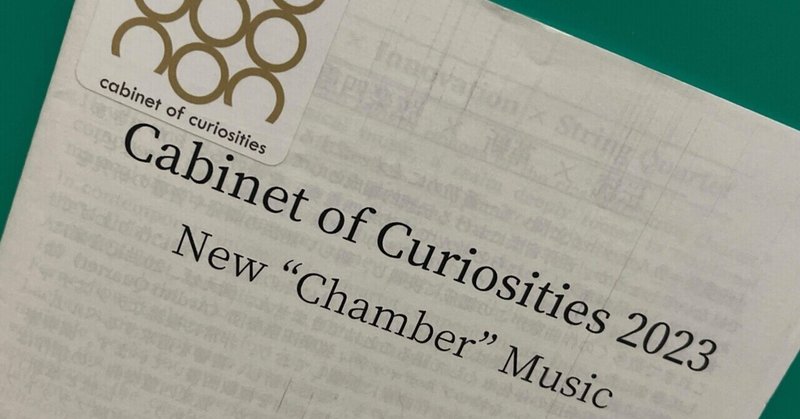
Cabinet of Curiosities 2023
年末のこのフェス、3回目とのこと。
昼公演:弦楽四重奏の現在
演奏:河村絢音(ヴァイオリン)、對馬佳祐(ヴァイオリン)、中山加琳(ヴィオラ)、北嶋愛季(チェロ)、佐原洸(エレクトロニクス)
◯チヨコ・スラヴニクス(1967):ディテールの傾き (2005/06)
◯クララ・イアノッタ(1983):ジャム瓶の中の死んだスズメバチ(iii)(2017-18)
◯レベッカ・サンダース(1967):矢羽根(2012)
《アフタートーク》
望月京、桑原ゆう、森紀明、渡辺裕紀子
スラヴニクス作品…長く持続する4つの音それぞれの音高が保たれたり移ろったりすることで、響きが途切れる事なくゆっくり推移していく。奏者が互いの音を慎重に聴き合いつつ進む。これも一種のミニマリズムか。初めは響きの展開がおもしろく聴ける部分があったが、その後は曲調に変化が乏しく、集中が途切れた。
イアノッタ作品…エレクトロニクスが加わり、楽器音が増幅され、残響なども施される。そのため手や弦が楽器に触れる時などの僅かなノイズまでよく聴こえる。そして、個々の音の持つ色あいをじっくり味わうことができる。ハーモニクスによる和音も美しい。4人の奏者とエレクトロニクスとがよく噛み合い、聴きごたえのある演奏が展開された。
サンダース作品…主にヴァイオリンとヴィオラの間でスル・ポンティ・チェルロ〜による、鋭い音が飛び交い、最低音域で蠢くチェロと明確な対比を示す。緊密なアンサンブルが求められる作とおぼしく、息の合った演奏が爽快であった。ただ、音色が限定的で、音楽がさほど拡がらない印象。
本公演の趣旨は弦楽四重奏の現在、といのことである。長い伝統のあるこの合奏形態にどう対峙するかを強く意識した作品たちと思われた。ただ、そこからなんらかの超克に繋がっているかと言えば、確信は持ちにくい。サンダース作品は、特殊な奏法による響きはおもしろいけれど、基本的な曲の建て付けは、いわゆる現代音楽のそれである。スラヴニク作品は、音の聴取を強く意識してはいるのだけれど、根本的なところで従来の弦楽四重奏の響きの解体には至っていない。
アフタートークで望月氏が語っていらした通り、音楽作品に関して進歩史観的な捉え方が適合しなくなって久しい。現代にあっては新しい音、新しい試みに価値を見出すのではなく多様化する個々の関心に沿って、それぞれが取り組むしかない、というのはその通りだと思う。
しかし、ならばなぜ弦楽四重奏なのか、いまだにこの形態が使われ続けるのはなぜか。「伝統」には抗いがたい魅力があるのか。この合奏形態を使い続けつつ、さらに伝統とは異なる魅力を創出することは可能なのか。アフタートークでは、せっかく作曲家が複数人いらっしゃるのだから、議論のとば口なりと示してほしかった。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
夜公演:新しい四重奏
演奏:大石将紀(サクソフォン)、神田佳子(打楽器)、 黒田亜樹(ピアノ)、山田岳(エレクトリック・ギター)、有馬純寿(エレクトロニクス)、橋本晋哉(指揮)
◯エンノ・ポッペ(1969):肉(2017)
◯オリバー・サーリー(1988):ヴェールに包まれたままの(2015)
◯マルコ・モミ(1978):ほとんどどこにもない(2014)
《アフタートーク》
望月京、桑原ゆう、森紀明、渡辺裕紀子
ポッペ作品…ロックの解体をめざすということらしいのだけれど、解体し過ぎて、もはや何のアダプテーションなのかがよくわからない。かのジャンルで用いられる楽器を使った、「普通」の「現代音楽」という印象。この作家らしい、ちょっと皮肉な味わいも薄い。
マーサリー作品…フェルドマンを上回る音のかそけさ。初めはふーんと思って聴いていたけれど、ずっと一本調子で、静謐さの必然性がだんだんわからなくなってしまった。
モミ作品…エレクトロニクスも加わり、各奏者が特殊奏法も繰り出しつつ、声や口笛も駆使して、さまざまな音を作り出す。夜公演では最も賑やかな作品であった。ポピュラー音楽を思わせるビートなども登場して多彩であるが、基本的に同じような楽想が何度も繰り返され、曲が進んでいっても風景が変わらない。どこへ向かおうとしているのかよくわからなかった。
奏者たちはいずれも力演、音の一つひとつを真摯な姿勢で紡いでいたと思う。しかしながら作品のほうが演奏と釣り合わず、いずれも今ひとつ。
今回の2つの公演は「四重奏」がテーマだった。たしかに舞台上で音を発する奏者は4人なのだけれど、夜の公演ではたまたま演奏家を4名必要とする作品ということに帰着するのではないかと思われた。
今回の公演の趣旨は、弦楽四重奏を典型とする、従来的な「四重奏」を見直し、解体するというものだったのかもしれない。けれど、最後のトークで桑原氏が語っていらしたように、そもそも「四重奏」ということになんらかの含意があるのか、見出せるのか、主催者に明確な見解があったのだろうか。作品とトークを聴く限りでは判然とせず、残念だった。
ヴェーベルンの「四重奏曲」は、弦楽四重奏のーただしやや距離のあるーバリアントであるピアノ四重奏というフォーマットを問う趣旨があったかと思われる。今回の夜公演は、問題意識が明確で、かつ検証に耐える作品が選ばれていたなら、もっと聴き応えのあるものになっただろう。
夜公演のトークでは、フロアから話の本筋とはあまり関係のない発言があった。しかし、運営側はそれを放置していて違和感があった。運営側が二つの公演を貫く明確な方針を欠いていたことが、そうしたノイズを呼び込むことにもつながったのではなどと感じた。(2023年12月23日 ドイツ文化会館1階ホール)
助成:公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京[東京芸術文化創造発信助成]
芸術文化振興基金助成事業
公益財団法人野村財団
協力:日本音楽財団(日本財団助成事業)
ゲーテ・インスティトゥート東京
(サントリー芸術財団佐治敬三賞推薦コンサート)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
