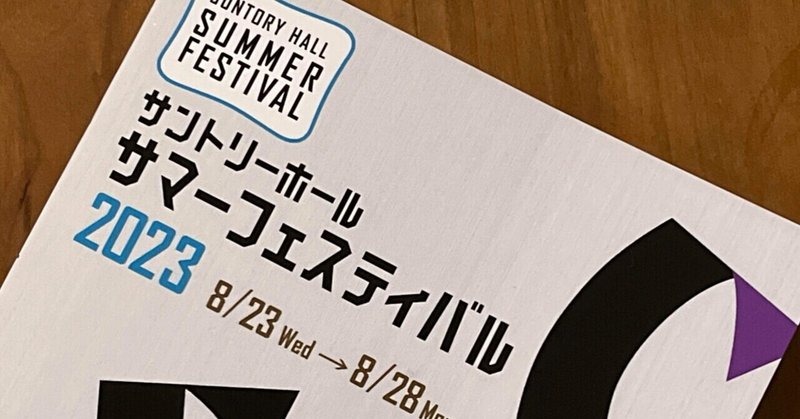
サントリーホール サマーフェスティバル 2023テーマ作曲家 オルガ・ノイヴィルト サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ No. 45 (監修:細川俊夫) 作曲ワークショップ×トークセッション
第一部
オルガ・ノイヴィルト × 細川俊夫 トークセッション
第二部
若手作曲家からの公募作品クリニック/実演付き
内垣亜優:『チェロ・チュロス・チョリソー』ソロ・チェロのための
室元拓人:『トカラ・イヴォーク』フルート、ヴィオラ、チェロのための
山田奈直:『鯨』ソロ・クラリネットのための
レクチャー:オルガ・ノイヴィルト/細川俊夫
フルート:齋藤志野
クラリネット:田中香織
ヴィオラ:甲斐史子
チェロ:下島万乃
通訳:蔵原順子
後援:オーストリア大使館/オーストリア文化フォーラム東京
助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】
第一部はオペラ「オルランド」のトレーラー動画なども流しつつ、1時間ほどノイヴィルト氏と細川氏によるトーク、第二部は3人の若い作曲家の作品の演奏と、ノイヴィルト氏の講評という構成。
のちにノーベル賞を受賞するイェリネク氏と意気投合し、オペラで協働するまでに至った経緯について、自分同様、特定の分野にとらわれず、境界を超えて活動している点が要因だったと語る。その後、ウィーン国立歌劇場の委嘱でヴァージニア・ウルフの『オーランドー』によるオペラを作曲した際も、主人公が男性として生まれ、のちに女性に生まれ変わる、つまり性別の境界を超越すること、そして時間を超えて生き続けるといったプロットが重要だったという。「越境」はこの作家の一つのキーワードだと言えるのかもしれない。トークの終わりでも、既存の枠に囚われないことの重要性を訴えていたし、少しだけ既存の音源を聴いてみても、器楽音と電子音響との区分が敢えて曖昧に仕立てられていたりもする。「越境」は、今回のシリーズで実演に触れる際の一つの手がかりとなりそう。
内垣作品…先日のコントラバスの作品は、素朴ながら真っ直ぐな表現に好感が持てた。今回の作は「チェロ」という楽器名を出発点として、ことばの響きを楽器でトレースするという趣向である。出だしのことばのリズムをなぞる部分はおもしろいのだけれど、そのあとはことばとの関わりがやや希薄になっていた。講評で、自分の内にある激しい部分をもっと表出すべきと指摘されていたのは、このあたりか。また、チェロの特性をもっと活かして「チェロ、チュロス、チョリソー」の3語に共通する強い子音を打ち出すべきだとも。日本語の語感としては、子音を共有しつつ母音が交代することでリズムが作られる点がおもしろいのだと思う。ドイツ語のように子音優位の言語圏の話者に対して、そういった母音の機能を伝えることは意外に難しいのかもしれないと感じた。
室元作品…トカラ列島の渡来神にまつわる宗教行事に取材したものという。神々がやってきて、しばしこの世で過ごし、また帰って行くというストーリーを辿ったというのだけれど、神々が訪れてからの部分は起伏に乏しいように感じた。思い返してみて、物足りなく感じた要因の一つは宗教的な要素や雰囲気が感じ取れないことだったかと思う。書法的には、さまざまな特殊奏法を無理なく織り込み、破綻がない感じ。講評ではそのあたりが高評価だった。ただ、フルートの特殊奏法の記法に関して、ラッヘンマン作品、細川作品に前例があるのだから、敢えて事新しく記譜法を作り出す必要はない、などテクニカルなアドバイスもあった。なお、終結部でシリカゲルやビニールの緩衝材(プチプチ)で音を立てるのは個人的にはやや唐突に感じた。ノイヴィルト氏はなぜそういった人工物を使うのかと質問していたが、問題視はしなかった模様。作曲者は、火のはぜる音など自然音を表現したかったとのことだったけれど、それなら、木の枝などを自然物を選んだほうがよかったか。
山田作品…鯨が「歌」を歌いつつ、深海を回遊するさまを表現したとの由。ステージの四方に譜面台を置き、時折移動しつつ演奏する。が、中盤まではいささか変化に乏しい印象。ノイヴィルト氏は『白鯨』に基づく作品「追放された者」(2008-2010、2012改訂)を書いており、鯨の生態をかなり研究した由。曰く実際の鯨はもっとずっと行動的だとのことで、山田作品ではそういう激しさの表現が足りないと語る。個人的には、回遊感を出すなら、客席の周囲を動く形もアリかと感じたし、奏者が複数でもよかったかとも思った。終盤で客席に背を向けて演奏する部分では最高音域を利用していたのだけど、この辺りで録音などで耳にした鯨の歌らしい響きがようやく出てきた。やや出し惜しみな感じ。講評でも、終結部近くのシークエンスは高く評価されていた。(サントリーホール ブルーローズ)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
