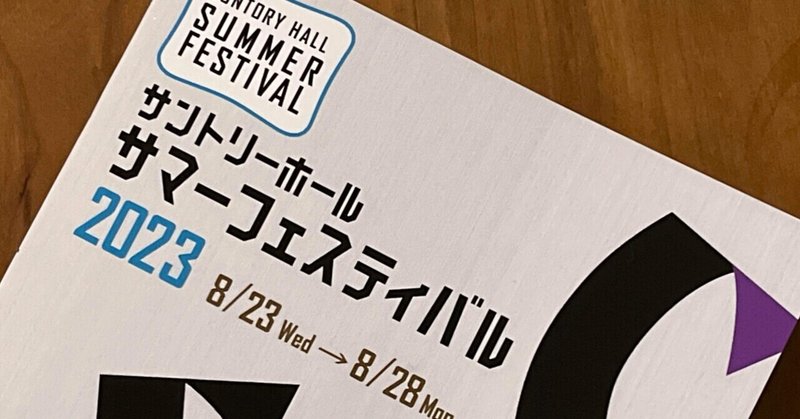
サントリーホール サマーフェスティバル 2023テーマ作曲家 オルガ・ノイヴィルト サントリーホール国際作曲委嘱シリーズ No. 45 オーケストラ・ポートレート
ヤコブ・ミュールラッド(1991~ ):
『REMS』(短縮版)オーケストラのための(2021/23)世界初演
オルガ・ノイヴィルト(1968~ ):
『オルランド・ワールド』(2023)サントリーホール委嘱世界初演*
オルガ・ノイヴィルト:
『旅/針のない時計』オーケストラのための(2013)
アレクサンドル・スクリャービン(1872~1915):
交響曲第4番 作品54「法悦の詩」(1905~08)
メゾ・ソプラノ:ヴィルピ・ライサネン*
指揮:マティアス・ピンチャー
東京交響楽団
後援:オーストリア大使館/オーストリア文化フォーラム東京
助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】
オーケストラ公演に先立って、小ホールで、今回のもう一つの企画である「ありえるかもしれない、ガムラン」のオープニング。ホール中央に大きな四阿風の構築物が組まれ、ガムランの楽器群がセッティングされている。

今回のプロデューサー三輪眞弘氏、建築に関わったアートコレクティブKITAメンバーの挨拶のあと、ガムラン・グループ、マルガサリによる、時に繊細、時にバーバリスティックな、聴きごたえのある演奏を楽しんだ。
7時近くなって、大ホールに移ると、舞台に用意されているのは大オーケストラのセッティングである。全く異なる世界に軽く眩暈を起こす。
ミュールラッド作品…全曲を通じて日本音階に似た音階が用いられている。響きは綺麗で、弦楽器群は絶えずぬるぬると動く。強烈なクライマックスが用意されるが、全体に調子が大きく変化することはなく、申し訳ないけれど、短縮版で十分かと思った。
ノイヴィルト新作…前半は、男性として誕生したオルランドの歌ということで、独唱は音域が低く、オーケストラが分厚いこともあって、声がほとんど聴こえない。後半、オルランドが女性に転身したあとは、メゾ・ソプラノとしての本来の歌唱になるので、幾分聴き取りやすいかと思ったが、やはりよく伝わってこない。歌手の声量の問題とは思われず、作品設計の問題と推測する。オーケストラの多彩な音色、不定形の音塊がさまざまに展開していくさまは実に雄弁で魅力的なのだけれど、これではオペラの筋を精密に辿ることができない。(休憩後のオーケストラのみによる旧作を聴きつつ、やはりどうにも独唱を貧弱に見せてしまう建て付けだったという感を強くした)設計ミスだったのか、はたまた、作家としては専らオーケストラに語らせれば良いという姿勢だったのか。いずれにせよ、テクストに対する配慮が欠けていると感じざるを得ない。新作とは言いつつ、既存のオペラ作品からの編集である。話題を呼んだオペラの一端に触れられるのはありがたいにしても、独立した作品として聴かせようとするなら、歌をきちんと聴かせるための手立てを講じるべきだった。
ノイヴィルト旧作…時計の機械音を模したリズムが複数重なりあうシークエンスがしばしば登場する。ユダヤの民族音楽的なふしがソロ・ヴァイオリンをはじめさまざまな楽器にあらわれる。作家自身の(現実には経験しなかったものも含めた)記憶の輻輳を表現するものか。曲が進むにつれ、ふしが徐々に明確な姿をとりはじめ、オーケストラ全体に広がっていく。記憶は単に振り返るためのものでなく、現在の自分を形成する部材である、時間の流れの中での蓄積がなければ、自分自身は存在し得ない、そういったメッセージが感じられる。時の境界を超えて今日に繋がる血縁・地縁、その中で、音楽史と作家の個人史が交錯する。ただ、やや冗長だったか。
スクリャービン作品…東響は熱演だったのだけれど、いかんせんノイヴィルト旧作でお腹いっぱいになったところへ、これでもかこれでもかと迫ってくる陶酔で、いささか消耗した。ピンチャー氏の仕切りは、実に要を得たものだったと思うけれど、もう少しだけ抑制していただけるとありがたかった。(2023年8月24日 サントリーホール大ホール)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
