
【Re:テラバイト】について
皆さん初めましての方は初めまして、そうでない方は前回までの記事を読んでいただきありがとうございます。その辺の決闘者の衣玖(いく)と申します。
今回は以前より組んでいた【電算機獣テラ・バイト】のリメイク記事となります。
詳細は記事を読んでほしいですが、大雑把に書くと【幻影彼岸】をベースに《No.34 電算機獣テラ・バイト》を出して《極神皇トール》の着地を狙うデッキでした。
今回は基本思想を変えず、事故を極力起こさないような構築を目指しました。
令和最新版の【電算機獣テラ・バイト】です。
当然の話ですが、マスターデュエルのランクマッチや公認大会、大規模CSなどに持ち込むようなデッキではありません。ご注意ください。
クソカード医学会基準では重症度3(高難易度ソロモードで戦える)程度となります。
テラバイトの強みと弱み

わざわざ専用デッキを組まなければならないほどのカードである理由は一体何でしょうか?
またこのカードにできることは何でしょうか?
これらを考えることで、デッキの軸を決めることができます。
強みを活かしつつ、弱みをどう潰すかという話ですね。
強み

まず《No.34 電算機獣テラ・バイト》の効果に目を向けると、1ターン限りのコントロール奪取効果を備えていることがわかります。
なぜか起動効果でエンドフェイズまででレベル4以下の攻撃表示モンスター限定のコントロール奪取ですが、テキスト欄が真っ白よりは個性があるでしょう。
アニメで最初に使用した北野右京は、奪ったモンスターに《ウィルスメール》を適用させてダメージを稼いだ上で自壊させコントロールを返さない戦術をとっていました。
またその守備力の高さも立派な特長です。
ランク3における守備力は《No.30 破滅のアシッド・ゴーレム》に次ぐ2位であり、デメリットを持たないモンスターではトップの高さです。
その鉄壁さを見込まれ、「遊馬vs片桐大介」戦では先鋒として遊馬の盾となりました。
そのためこの2点を活かせる構築を行いたいというのが根本にあります。
弱み

まず大前提として、レベル3モンスター×3という素材はあまりにも重すぎます。
任意のモンスターのコントロールを得られるランク3モンスターはこのカードしか存在しませんが、わざわざレベル3モンスターを3体揃えてモンスター1体のみを奪うならば、Lモンスターに頼る方が安定するでしょう。
配置次第では《転晶のコーディネラル》で任意のモンスターを奪うことができますし、モンスターを1体分足せれば《ヴァレルロード・ドラゴン》で奪い攻撃に参加させることもできます。
よって、場に出すための消費を軽減する手段の確保は必須でしょう。
次にコントロールを奪えるモンスターの範囲が狭すぎる点が問題です。
改めて書きますが、奪えるモンスターは攻撃表示のレベル4以下のモンスターです。
そんなモンスターは普通フィールドに残っていません。素材にされて場から消えているか、守備表示で放置されていることでしょう。
そのため相手のレベルを操作することを検討する必要があります。
最後に守備力の高さが現代環境としてはほぼどうでもいい点が大問題です。
ランク3では2番手の守備力の高さと書きましたが、所詮は守備力2900です。
今どき《青眼の白龍》程度の攻撃力を持つモンスターは息をするように出てきますし、仮にアニメと同様の戦闘破壊耐性を備えていたとしても破壊や除外、バウンスなどの除去はポンポン飛んできます。
それでも活かすのであれば、意地でも戦闘に持ち込ませるような構築を目指したいですね。
総じて、重い・的が無い・硬くないという三重苦を背負っています。
構築方針

まず素材が重いという問題は、《RUM-幻影騎士団ラウンチ》を使用することで解決しました。
闇属性のXモンスターであることから、X素材が無くなったランク2の闇属性Xモンスターを用意できればお互いのメインフェイズにランクアップさせて出すことができます。
その素材となるランク2の闇属性Xモンスターも《幻影騎士団カースド・ジャベリン》というモンスターが存在し、そのカード名も活かせることから「幻影騎士団」を軸に構築することが決まりました。
奪える相手モンスターが存在しないという問題も、「幻影騎士団」が解決してくれました。
このテーマにはなぜか《幻影騎士団ロスト・ヴァンブレイズ》というカードが存在し、対象モンスターの攻撃力を600下げつつレベルを2にするというこのために生まれてきたかのようなテキストをしています。
これによりレベルを持つモンスターであれば、コントロールを奪えるようになりました。
そして意地でも戦闘に持ち込むという点ですが、《反転世界》で高い守備力を攻撃力に変換することにしました。
基本的には引ければラッキーであり《極神皇トール》とはアンチシナジーとなるカードですが、その場合は《天穹覇龍ドラゴアセンション》をS召喚することで本来よりも高い攻撃力を得ることができます。
この2体の大型Sモンスターの使い分けも合わせて、戦闘を主体とした勝利を目指します。
デッキレシピ

上記の三重苦を克服すべく組んだデッキがこちらになります。
百聞は一見にしかずです。
かつての構築と比較すると、《ライトロード・ドミニオン キュリオス》の不採用および「彼岸」モンスターの全リストラが大きな変更点となっています。
また《幻影騎士団ティアースケイル》の規制緩和による初動札の増加も事故防止に役立っています。
そのため以前よりも「幻影騎士団」要素が強くなりました。
ただし相変わらず《幻影騎士団ブレイクソード》は強すぎるので出禁です。
各カードの役割

以前は終着点を《幻影騎士団ラスティ・バルディッシュ》と《ライトロード・ドミニオン キュリオス》の2パターンにしていましたが、今回は《幻影騎士団ラスティ・バルディッシュ》のみに絞っています。
というのも《聖騎士の追想 イゾルデ》が以前よりも格段に出しやすくなったため、《ライトロード・ドミニオン キュリオス》による墓地肥やし運ゲーをする必要性がなくなったことが大きいです。
まずは基本展開から載せていきます。
基本展開

1.レベル3モンスター×2を用意
2.レベル3モンスター×2
⇒《M.X-セイバー インヴォーカー》X召喚
3.《M.X-セイバー インヴォーカー》ef
→《H・C モーニング・スター》特殊召喚
4.《H・C モーニング・スター》ef
→《ヒロイック・コール》サーチ
5.《M.X-セイバー インヴォーカー》
+《H・C モーニング・スター》
⇒《聖騎士の追想 イゾルデ》L召喚
6.《聖騎士の追想 イゾルデ》ef
→《ケンドウ魂 KAI-DEN》サーチ
7.《聖騎士の追想 イゾルデ》ef
《執念の剣》《月鏡の盾》墓地
→《ヒーロー・キッズ》Ass
8.Ⅰ《執念の剣》効果、Ⅱ《ヒーロー・キッズ》Aef
→《ヒーロー・キッズ》B,Css
→《執念の剣》デッキトップ
9.《ヒーロー・キッズ》A+B
⇒《幻影騎士団カースド・ジャベリン》X召喚
10.《聖騎士の追想 イゾルデ》
+《ヒーロー・キッズ》C
⇒《S:Pリトルナイト》L召喚
11.《幻影騎士団カースド・ジャベリン》
+《S:Pリトルナイト》
⇒《幻影騎士団ラスティ・バルディッシュ》L召喚
この《幻影騎士団ラスティ・バルディッシュ》で《幻影騎士団サイレントブーツ》か《幻影騎士団ダスティローブ》を落としつつ《幻影翼》をセット、落としたモンスターの効果で《RUM-幻影騎士団ラウンチ》をサーチすることで《No.34 電算機獣テラ・バイト》が着地する準備は完了です。
既に《幻影翼》があるならば《幻影騎士団ロスト・ヴァンブレイズ》をセットすることで相手モンスターのレベルを操作する準備まで可能です。
なお《ヒーロー・キッズ》は素引きするとリクルートできなくなってしまうため、その場合は以下のような展開になります。
1.レベル3モンスター×2を用意
2.レベル3モンスター×2
⇒《M.X-セイバー インヴォーカー》X召喚
3.《M.X-セイバー インヴォーカー》ef
→《H・C モーニング・スター》特殊召喚
4.《H・C モーニング・スター》ef
→《ヒロイック・コール》サーチ
5.《M.X-セイバー インヴォーカー》
+《H・C モーニング・スター》
⇒《聖騎士の追想 イゾルデ》L召喚
6.《聖騎士の追想 イゾルデ》ef
→《ケンドウ魂 KAI-DEN》サーチ
7.《聖騎士の追想 イゾルデ》ef
《執念の剣》墓地
→《彗聖の将-ワンモア・ザ・ナイト》ss
8.《執念の剣》効果
→《執念の剣》デッキトップ
9.《聖騎士の追想 イゾルデ》
+《彗聖の将-ワンモア・ザ・ナイト》
⇒《軌跡の魔術師》L召喚
10.《軌跡の魔術師》ef
→《ヴェーダ=ウパニシャッド》サーチ
11.《ケンドウ魂 KAI-DEN》発動
12.《ヴェーダ=ウパニシャッド》発動
13.P召喚
⇒《ヒーロー・キッズ》A
《彗聖の将-ワンモア・ザ・ナイト》
14.《ヒーロー・キッズ》Aef
→《ヒーロー・キッズ》B,Css
ここから先は《幻影騎士団カースド・ジャベリン》を経由して《幻影騎士団ラスティ・バルディッシュ》をL召喚することで同様の準備が可能です。
仮に《彗聖の将-ワンモア・ザ・ナイト》までをも引いてしまっていても、それをスケールに置き、《聖騎士の追想 イゾルデ》の効果で《ヴェーダ=ウパニシャッド》をサーチすることで《ヒーロー・キッズ》をP召喚できます。
これらのことがレベル3モンスター×2を用意するだけでできるため、かつての戦士族×2を用意する構築よりも敷居が下がりました。
初動札

レベル3モンスター×2が揃えば何でもいいのですが、サーチ手段があったりシンプルに複数枚搭載できたりした方が引きやすく再現性も高くなるため、手札1枚からの初動札には以下のモンスターを採用しています。
《幻影騎士団ティアースケイル》
《魔界発現世行きデスガイド》
《転生炎獣ガゼル》
いずれも召喚権を消費しますが、上記の展開には召喚権を消費しないため問題なく運用できます。
人によっては《SRベイゴマックス》や《捕食植物オフリス・スコーピオ》などを採用してもいいでしょう。
規制されていない分、マスターデュエルではそちらの方が引きやすいかもしれません。
レベル3モンスター×3を要求する《No.34 電算機獣テラ・バイト》を実質レベル3モンスター×2で出せるとなれば、その重さも幾分軽減できているでしょう。
フィニッシャー

コントロール奪取した後は、そのモンスターの運用方法を考える必要があります。
ターン終了時には相手に返さなければならないため、各種素材などに使用するのが一番手っ取り早いでしょう。
しかし、L素材だけはダメです。
せっかく《No.34 電算機獣テラ・バイト》の効果で奪うのであれば、奪うモンスターの特徴を活かした利用方法で処理した方が面白いでしょう。
適当に奪ってL素材にするならば《精神操作》や《心変わり》で事足ります。
そのため筆者はS素材にすることにしました。
さらに出すモンスターは素材がやや重くともフィニッシャーに相応しい効果と火力を備えたモンスターが望ましいです。
具体例を出すと申し訳ないのですが、《A・O・J フィールド・マーシャル》のような産廃寄りのパッとしないモンスターでは力不足です。
そこで目をつけたのが《極神皇トール》でした。
全体効果無効、自己再生+地味バーン、それなりの高火力と欲しい要素を概ね揃えています。
素材も「極星獣」チューナーこそ指定していますが、非チューナーに指定はありません。
一般的に棒立ちでチューナーが残ることはないので、素材にする部分も合格です。
さらに《天穹覇龍ドラゴアセンション》にも目をつけました。
《オシリスの天空竜》のように手札の枚数に依存した攻撃力を得るモンスターですが、その数値はS召喚成功時にチェーンブロックを組んで決定します。
つまりその後は手札の枚数が増減しても関係ないということですね。
この効果にチェーンして《反転世界》を発動すれば、たとえ手札が1枚でも《極神皇トール》を超える攻撃力を得られます。
ついでに《No.34 電算機獣テラ・バイト》も攻撃に参加できるようになります。
この2体をフィニッシャーに据えて、S素材を《No.34 電算機獣テラ・バイト》で奪うことをコンセプトにした構築となっています。
ただし構築上、別にモンスターを奪わずとも出すことができてしまいます。
あくまで基本は奪うことを前提に、相手がXモンスターやLモンスターを並べる場合は自力で出す、といった形になります。
まとめ
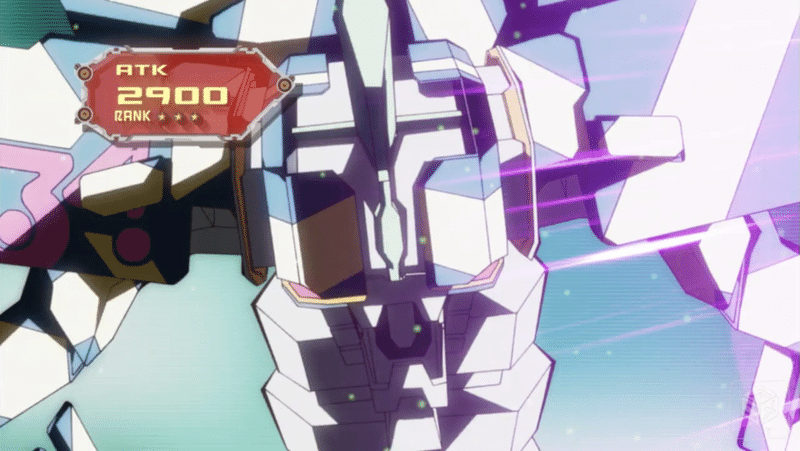
以上が新たな進化を遂げた【電算機獣テラ・バイト】です。
以前までの最大の課題であった《ヒーロー・キッズ》の素引きに対する回答として、《彗聖の将-ワンモア・ザ・ナイト》および《ヴェーダ=ウパニシャッド》の登場によるP召喚の安定を図れたことが際立った変更点です。
展開に必要なカードさえ確保しておけば他は自由枠となるため、この構築をベースに自分用の【電算機獣テラ・バイト】を組んでも面白いかもしれません。
皆さんも好きなカードでデッキを組んでみてはいかがでしょうか?
競技用のデッキとは異なる視点でデッキを組むことで、新たな発見を得られるかもしれません。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
