
【主人公よくばりセット】について
皆さん初めましての方は初めまして、そうでない方は前回までの記事を読んでいただきありがとうございます。その辺の決闘者の衣玖(いく)と申します。
今回は歴代主人公の力を結集した【主人公よくばりセット】の記事です。
マスターデュエルのランクマッチや遊戯王OCGの公認大会などに持ち込もうとは断じて考えないでください。
遊戯王の日くらいならいいかもしれません。
早速デッキ内容を見てみましょう。
デッキレシピ

紙束です。
メインデッキには各主人公の使用カードをそれぞれ7枚ずつ、エクストラデッキは仲良く分けられないので使いやすいものを優先して採用しています。
主人公間でシナジーのあるものを探して採用したので、こんなカード使ったっけ?みたいなものがあるかもしれません。
それぞれのカードについて解説するので、そこは安心して読んでください。
また採用カードはアニメ版準拠です。
漫画版は考慮していません。
なお戦略と呼べるものはほぼ無く、引いたカードを叩きつけるだけです。
このデッキを使う場合は右手を光らせて常に最強のドローを繰り返しましょう。
武藤遊戯使用カード

言わずと知れた、『遊戯王デュエルモンスターズ』の主人公です。
以下のカードを採用しています。
《ブラック・マジシャン》
《超電磁タートル》
《ブラック・マジシャン・ガール》
《ソウルテイカー》
《サイクロン》
《聖なるバリア-ミラーフォース-》
《魔法の筒》
《呪符竜》
遊戯には象徴的なカードが多く、インフレが加速したドーマ編を範囲に含めていることからパワーカードが乱立する魔境と化していました。
そんな中、《サイクロン》《呪符竜》以外のカードは全てドーマ編以外からの出典となります。
《ブラック・マジシャン》

武藤遊戯の相棒とも呼べるモンスターであり、物語の最初から最後まで遊戯を支えてきた魂のカードです。
このデッキではその活躍とは裏腹に事故要因として活躍し、手札でこちらを見つめ続けることが多くなるでしょう。
《呪符竜》の融合素材に指定されているため、主に「オッドアイズ」モンスターと共に融合することが基本的な使われ方となります。
《超電磁タートル》

神同士の激突を鎮めたカードです。
【シャドール】などではデッキから直接墓地へ送ることでその効果を発揮させていましたが、このデッキでは狙って墓地へ送ることはほぼ不可能なので基本的には素直にセットすることになります。
またレベル4の素材として使用することも多く、攻防共にこのデッキを支える存在です。
一応《調律》や《ガガガガードナー》で墓地へ送ることもできますが、上手く揃う場面の方が少ないので気合いで墓地へ落としましょう。
《ブラック・マジシャン・ガール》

《ブラック・マジシャン》の弟子となる存在で、あのパンドラさえも知らないカードです。
ステータスの増加は肝心の《ブラック・マジシャン》が手札で暇を持て余すことが多いことからほとんど役に立たず、なんと素直に生け贄召喚することが多々あります。
このカードの真価は元々のレベルが6という点にあり、《マスター・ピース》によって《No.39 希望皇ビヨンド・ザ・ホープ》のX素材になることが仕事です。
《超電磁タートル》と同様の手段で墓地へ送り、奇襲する形で《マスター・ピース》の発動を狙いましょう。
《ソウルテイカー》

マリクの《神・スライム》を《オベリスクの巨神兵》の効果のコストに充てたカードです。
原作では速攻魔法であり、相手モンスター1体を強制的に生け贄に捧げ、代わりに相手のライフポイントを1000回復させる効果でした。
このデッキでは貴重な単体除去であり、使いどころに悩むカードでもあります。
《禁じられた聖槍》や《分断の壁》では対応できないようなステータスの相手を処理するのが最も効果的でしょう。
相手のライフポイントを回復させてしまう点も込みで、使用者の腕の見せどころとなります。
《サイクロン》

ドーマ編で使用された、古き良き除去カードです。
単純な魔法・罠カードの除去手段が事実上これしか存在しないため、《ソウルテイカー》と同様に使いどころはしっかり見極めましょう。
ピンポイントで危険なカードを撃ち抜く勘の鋭さも主人公には要求されます。
《聖なるバリア-ミラーフォース-》

肝心な時に仕事しないことでお馴染みの攻撃反応型罠カードです。
《ソウルテイカー》とは異なり発動タイミングが限られますが、代わりに全体除去ができるため一長一短です。
攻撃力を下げることで迎撃が可能になりダメージも与えられる《分断の壁》とも立場を争いますが、引いたカードを叩きつけるこのデッキでは可能な限りアドバンテージ差をつけるためになるべく1:2交換以上を心がけましょう。
《魔法の筒》

相手の攻撃を吸収して跳ね返す、魔法使い族の必殺技です。
破壊に対してはどの決闘者も一定の警戒を持っていますが、前時代的なこのカードに対する警戒を強める人はほとんどいません。
なるべく大型のモンスターの攻撃を跳ね返し、相手に致命傷を与えましょう。
《呪符竜》

《ティマイオスの眼》によって現れた《ブラック・マジシャン》の派生です。乗っただけ融合。
OCG化が非常に遅かったおかげで単純な融合モンスターとして登場し、緩い融合素材だったおかげで採用することができました。
このデッキでは墓地の魔法カードは再利用できないため、自分の墓地の魔法カードは全て力に変えましょう。
相手の魔法カードも吸えれば御の字です。
手札で腐りがちな《ブラック・マジシャン》を戦力に変える稀有な手段となるため、出せる際は積極的に出しましょう。
単純な高火力は正義です。
遊城十代使用カード

『遊戯王GX』の主人公であり、遊戯王OCG準拠の歴代主人公で唯一「遊」の字が苗字にあるキャラクターです。
以下のカードを採用しています。
《E・HERO ネオス》
《スケルエンジェル》
《カードガンナー》
《マジック・ストライカー》
《死者蘇生》
《融合》
《神の宣告》
《E・HERO ネオス・ナイト》
十代といえばやはり「E・HERO」ですが、彼らの融合をベースに考えると手札事故が激しく採用を見送らざるを得ませんでした。
一方で汎用カードや「E・HERO」とは関係ないカードもいくつか使用しており、そちらの方が使い勝手が良かったため採用しています。
《E・HERO ネオス》

正義の闇を纏う、2年目以降の十代のエースモンスターです。
残念ながら《ブラック・マジシャン》と同様に事故要因となって手札で腐る場面の方が多いカードとなっています。
融合素材としては他の戦士族と共に《E・HERO ネオス・ナイト》になるくらいですが、戦士族は全体的に使い勝手の良いものを取り揃えているため融合さえできれば優秀な戦力になってくれるでしょう。
《スケルエンジェル》

幼少期の十代のデュエルシーンで墓地に置かれていることが確認できるカードです。
つまり使用したのはアニメ作中の時間軸ではなく、デュエルで実際に活躍したシーンもありません。
ただしカード性能は優秀で、リバース時に1枚ドローする強制効果を持っています。
レベルも2であることから《ジャンク・シンクロン》に対応し、光属性であることから《オッドアイズ・セイバー・ドラゴン》のコストに充てることもできるためこのデッキの潤滑油として機能します。
引いたらとりあえずセットしておきましょう。
《カードガンナー》

十代の墓地効果を持つカードをピンポイントで落としまくった、極めて優秀なカードです。
ランダムな墓地肥やしはコストであり、《クレーンクレーン》で蘇生しても墓地肥やしができる点が非常に優秀です。
破壊された時にもカードをドローでき、《ブラック・マジシャン・ガール》などを墓地へ送りつつ《マスター・ピース》などを引き込むことができれば理想的です。
アタッカーとしても高い数値を持っており、《スケルエンジェル》と同様にこのデッキを支えてくれるカードと言えます。
《マジック・ストライカー》

度々登場して最終的に十代を勝利へ導いたモンスターです。
墓地の魔法カードをコストに特殊召喚できるため、展開力に乏しいこのデッキでは珍しく盤面を横に広げることができます。
直接攻撃が可能であり、自身の戦闘による自分への戦闘ダメージも0になるため、気兼ねなく突撃させることができます。
またレベル3であることからS素材やX素材に、戦士族であることから融合素材にも使え、とにかく優秀なカードとなります。
《死者蘇生》

遊戯王という作品を象徴するカードであり、歴代主人公達も使ったり使わなかったりしたカードです。
イメージとして強いのはやはり武藤遊戯のカードとしてですが、彼のカードは強力なものが多くて枠が足りませんでした。
結果、テーマ外のカードの使用が少なかった十代の使用カードとして採用されることになりました。
墓地に落ちたカードを再利用する貴重な手段のため、使い時はしっかりと見極めましょう。
《融合》

こちらも古より遊戯王を支えてきたカードです。
遊戯や遊矢も使用しましたが、「E・HERO」を操る十代にこそ相応しいカードでしょう。
なおピン挿しのため基本的には事故要因です。
足りない融合素材は使う人のドロー力で補ってください。
《神の宣告》

万能カウンターの始祖であり、相手の大型モンスターを問答無用で潰せる貴重な手段です。
十代が《人造人間-サイコ・ショッカー》の精霊とのデュエルで使用しました。
彼は割とガチ寄りのカードを使用していたため、このデッキでも採用することができました。
ライフポイントを守る手段はこのデッキにそこそこ搭載されているため、重いライフコストを払ってでも採用する価値があります。
むしろ逆境でも使えることを喜びましょう。
《E・HERO ネオス・ナイト》

映画『超融合〜時空を超えた絆〜』で《ジャンク・ガードナー》と融合した《E・HERO ネオス》の姿です。
2回攻撃でき高い攻撃力を得られる代償として、相手に与えるダメージが0になってしまいます。
採用している戦士族の攻撃力が低めであることから《呪符竜》よりも低い攻撃力になりがちですが、一方で殲滅力に長けています。
ただし選り好みしていられる余裕は無いため、手札が揃い次第融合するといいでしょう。
不動遊星使用カード
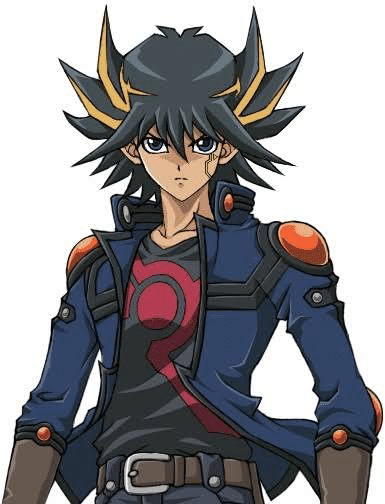
『遊戯王5D's』の主人公であり、一見クールなようですぐ熱くなる秘めた熱血漢です。
以下のカードを採用しています。
《エフェクト・ヴェーラー》
《速攻のかかし》
《スピード・ウォリアー》
《ドリル・シンクロン》
《ジャンク・シンクロン》
《調律》
《くず鉄のかかし》
《ジャンク・ウォリアー》
《ドリル・ウォリアー》
《スターダスト・ドラゴン》
不動性ソリティア理論という言葉が耳に入りますが、遊星は淡々と反撃の機会を窺いながらリソースを一気に吐いて相手を仕留める展開を得意としています。
このことから防御寄りのカードの使用率が高く、ガードの硬さがこのデッキの硬さに繋がりました。
《エフェクト・ヴェーラー》

現在でも使われる手札誘発です。
ロットンの《ガトリング・オーガ》による先攻1ターンキルを防ぐ活躍をしましたが、再戦時には手札のこのカードをガン見していたら《ピンポイント・シュート》の効果でハンデスされてしまいました。
相手の先攻展開を止める唯一の手段ですが、このカードで稼いだ1ターンで相手を仕留めることはほぼできません。
あくまでカジュアルな環境において相手の動きを鈍らせることができる程度のカードと認識しておいてください。
《速攻のかかし》

手札誘発版の《攻撃の無力化》と呼べるカードであり、モンスターであることから再利用もしやすいです。
このカードで攻撃を防ぎ続け、《ドリル・ウォリアー》でこのカードを回収しながらダメージを稼ぐ「かかしドリル」と呼ばれる戦法が存在し、後述する《ドリル・シンクロン》共々それを狙った採用になります。
単体でも高い防御力を誇り、ほぼ確実に1ターンを稼いでくれる優秀なカードです。
《スピード・ウォリアー》

《ジャンク・シンクロン》と並んで遊星を支え続けたモンスターです。
召喚したターンは攻撃力が1800まで上昇し《ジャンク・シンクロン》で蘇生できることから多くのデュエルで活躍し、《E・HERO ネオス》に次ぐ「過労死枠」となりました。
このデッキでも下級モンスターの打点が低いことから切り込み隊長として活躍し、墓地に眠っても安眠の時は訪れません。
戦士族のため《E・HERO ネオス・ナイト》の融合素材にもなります。
アニメよろしく相手の下級モンスターを殴り倒す活躍をさせてあげましょう。
《ドリル・シンクロン》

視聴者モンスターデザイン応募企画で誕生したモンスターです。
何やら貫通能力を付与する効果を持つようですが、基本的には素材になるだけなので関係ありません。
《ドリル・ウォリアー》がレベル6のため、《マジック・ストライカー》の自己特殊召喚や《クレーンクレーン》による蘇生と組み合わせて並べましょう。
《ジャンク・シンクロン》

こちらも遊星を支え続けた元祖チューナーモンスターです。
レベル4か5のS召喚に繋げることができますが、その場合の選択肢が《アームズ・エイド》と《ジャンク・ウォリアー》しか存在しないため、後者のためにレベル2のモンスターを蘇生させることが多くなるでしょう。
たまに《フォトン・スラッシャー》の特殊召喚からレベル1モンスターを蘇生させて《スターダスト・ドラゴン》に繋ぐこともあります。
いずれにせよ手札1枚から攻撃力2000超えのモンスターを出せることは強力なため、要所で出してS召喚に繋げましょう。
《調律》

遊星が珍しく使用した通常魔法です。
「シンクロン」チューナーのサーチと申し訳程度の墓地肥やしができます。
手札に欲しいカードと墓地に落ちてほしいカード/落ちてほしくないカードを考えながら発動タイミングを見定めましょう。
《くず鉄のかかし》

遊星の窮地を何度も救った罠カードです。
使い減りしない防御札は貴重であり、相手はまずこのカードへの対処に迫られることになります。
《聖なるバリア-ミラーフォース-》や《魔法の筒》のような強力な罠カードに対するデコイとしても機能するため、テキスト以上に強力なカードです。
2回目の発動ができればラッキーですが、除去された時は役目を終えたと思って感謝しましょう。
《ジャンク・ウォリアー》

アニメ『遊戯王5D's』で最初にS召喚され、同時に最後にS召喚されたモンスターでもあります。
レベル2以下のモンスターの攻撃力を吸収する効果は展開力に乏しいこのデッキでは上手く扱えませんが、《ジャンク・シンクロン》1体から出せるアタッカーとしては優秀な攻撃力を持ちます。
事実上のバニラですが、このデッキでは貴重なアタッカーのためガンガン活躍させてあげましょう。
《ドリル・ウォリアー》

こちらもまた視聴者モンスターデザイン応募企画によって生まれたカードです。
攻撃力を半分にして直接攻撃できるようになり、手札1枚をコストにフィールドから離れ、返しのターンで帰還しつつ墓地のモンスターを回収する効果を持ちます。
《速攻のかかし》とのコンボが凶悪なだけでなく、《カードカー・D》や《エフェクト・ヴェーラー》も使い回せるようになるため状況に合ったカードを回収しましょう。
《スターダスト・ドラゴン》

シグナーの龍の1体であり、《ジャンク・ウォリアー》と並んで遊星を支え続けたモンスターです。
チューナーの枚数が限られるこのデッキではS召喚すること自体が難しく、またフィールドに維持し続けることも難しいです。
《禁じられた聖槍》や《分断の壁》などの効果で相手の攻撃力を下げることで戦闘から身を守り、破壊効果には自身の効果で対応していきましょう。
九十九遊馬使用カード
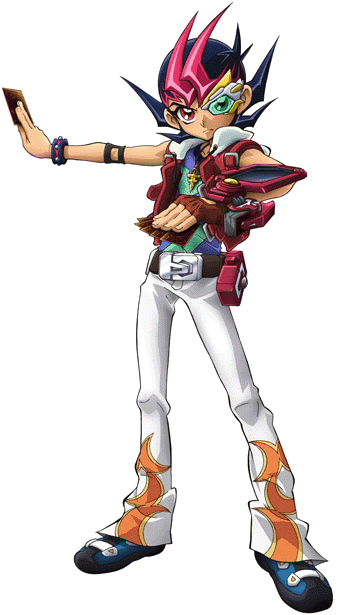
『遊戯王ZEXAL』の主人公であり、何事にも諦めずに挑戦する「かっとビング精神」の持ち主です。
以下が採用カードです。
《カードカー・D》
《クレーンクレーン》
《ガガガガードナー》
《ギラギランサー》
《ハーフ・アンブレイク》
《ピンポイント・ガード》
《マスター・ピース》
《No.17 リバイス・ドラゴン》
《No.39 希望皇ホープ》
《No.39 希望皇ビヨンド・ザ・ホープ》
言葉遊びをしているカードを多用する他、遊星ほどではありませんが防御に長けたデュエリストです。
比較的汎用性の高いカードも使用しており、タッグデュエルではサポートに回ることが多い遊馬らしいカードの選出となりました。
《カードカー・D》

デメリットがあるものの1:2交換で手札が増やせるモンスターです。
デッキを掘る手段に乏しいこのデッキでは引いたカードが力の全てとなります。
手札誘発や罠カードで身を守れるため、ドロー後にターンが終わるデメリットも許容できます。
無論、特殊召喚すること自体もほとんど無いため実質ノーデメリットでドローできます。
むしろ自身を特殊召喚できないことから《ジャンク・シンクロン》で蘇生できないことが一番のデメリットです。
《クレーンクレーン》

特にこれといった誓約もなくモンスターを蘇生させるモンスターです。
基本的にはランク3を作るために生まれたと思われるモンスターですが、『遊戯王ZEXAL』放映時期に登場したカードとしては珍しく「このカード(の効果で特殊召喚したモンスター)はシンクロ素材にできない」という文言がありません。
そのため《No.17 リバイス・ドラゴン》のX素材になれるだけでなく、《ドリル・シンクロン》を蘇生して《ドリル・ウォリアー》を出すこともできます。
事前準備が必要とはいえ1枚でアタッカーを用意できるため、非常に優秀なモンスターです。
《ガガガガードナー》

手札を糧として攻撃に耐え続けるナイスガイです。
直接攻撃に反応して手札から特殊召喚でき、手札1枚を捨てることでその戦闘でのみ戦闘破壊耐性を得られます。
連続攻撃を受ける際は手札を大量に捨てる必要がありますが、守備力2000と比較的高めの数値であり、墓地に置きたいカードや手札で腐っているカードを捨てられるためなかなか優秀です。
《ギラギランサー》

《サイバー・ドラゴン》と同じ条件で出せる半上級モンスターです。
レベル6の半上級モンスターということで各種素材に使いやすく、打点もそこそこの数値のため戦闘もこなせます。
しかしなぜか自分のターン終了時に500ダメージを受けるデメリットを持っているため、可能であれば速やかに各種素材にして処分したいところです。
《ハーフ・アンブレイク》

遊馬を何度も救ってきた、モンスターを戦闘破壊から守るカードです。
基本的には自分のモンスターを守るために使いますが、相手モンスターも対象にできることから、痛い直接攻撃を半減させる使い方もできます。
臨機応変に使いましょう。
《ピンポイント・ガード》

墓地のモンスターを完全蘇生しながらターン中の破壊も受けなくなるカードです。
攻撃反応型である点がネックですが、レベル4以下のモンスターを完全蘇生しつつ破壊されなくなる耐性を付与するため非常に優秀な防御札となります。
次のターンに各種素材に使いたいモンスターを蘇生させると良いでしょう。
《マスター・ピース》

墓地のモンスターを素材に「ホープ」をX召喚するカードです。
このデッキでは《No.39 希望皇ホープ》と《No.39 希望皇ビヨンド・ザ・ホープ》を狙えますが、後者は素材そのものがフィールドに並べづらいことからこちらを優先して狙いたいところです。
罠カードのため相手のバトルフェイズに《No.39
希望皇ビヨンド・ザ・ホープ》を出すことができれば攻撃の手を緩めさせることができるため、罠カードであることを最大限に活かしましょう。
《No.17 リバイス・ドラゴン》

遊馬が手に入れた、2枚目の「No.」です。
X素材を使うことで攻撃力が500上がりますが、X素材が無い場合は直接攻撃できなくなるデメリットを付与されます。
普通にプレイしていても2ターンも生き残ることはほとんど無いので、使い切りの2500打点のアタッカーとして運用することになります。
《クレーンクレーン》1枚から出せるため、とにかく突撃させましょう。
《No.39 希望皇ホープ》

『遊戯王ZEXAL』の顔とも呼べる、遊馬の相棒となる「No.」です。
モンスターの攻撃を2回まで止められる効果を持ちますが、X素材が無い状態で攻撃対象にされるとそのまま破壊されてしまいます。
素直にX召喚して防御に徹したり、《マスター・ピース》によって特殊召喚してバトルフェイズ中に追撃したりとそれなりに小回りの効く運用ができます。
ただしこのデッキには相方となる《ダブル・アップ・チャンス》が無いため、自分の攻撃を止めるメリットはほぼありません。
《No.39 希望皇ビヨンド・ザ・ホープ》

ナッシュとの決戦で登場した切り札です。
X召喚に成功した時に相手のモンスターの攻撃力を0にでき、フリーチェーンでXモンスターを除外することで「希望皇ホープ」を蘇生させつつ回復することができます。
後者の効果は使える場面がほぼ無いため、基本的には《マスター・ピース》で特殊召喚し前者の効果を使用して攻撃力3000による一撃を叩き込むことになります。
出す苦労に見合ったモンスターなので狙える時は狙って出しましょう。
榊遊矢使用カード

『遊戯王ARC-V』の主人公であるエンタメデュエリストです。
以下が採用カードです。
《EMディスカバー・ヒッポ》
《EMウィップ・バイパー》
《オッドアイズ・ドラゴン》
《オッドアイズ・セイバー・ドラゴン》
《スマイル・ワールド》
《超カバーカーニバル》
《分断の壁》
《クリアウィング・シンクロ・ドラゴン》
《覚醒の魔導剣士》
《ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン》
遊矢の代名詞といえばやはりP召喚ですが、スケールを揃えて手札から吐き出すP召喚の戦法を取るには手札を増やす手段が乏しかったことから、Pモンスターそのものの採用を諦めました。
他カードの強いシナジーを持たないカード群を採用することで、他の主人公達の中に溶け込めたのではないでしょうか。
《EMディスカバー・ヒッポ》

遊矢の相棒となる、アクションカードを探すことが得意なカバです。
その特技はOCGでは発揮できず、効果も産廃なため基本的に《超カバーカーニバル》で特殊召喚するためのモンスターとなります。
簡単に出せるレベル3の素材として活用しましょう。
《EMウィップ・バイパー》

フィールドのモンスターの攻守を入れ替えられるモンスターです。
その効果から攻守共に1700未満の相手は一方的に倒すことができ、フリーチェーンであることから相手の攻撃も透かすことができます。
ただしメインフェイズにしか使えないため、メインフェイズ1の終わり際に発動させることが無難でしょう。
変わったところでは《流星輝巧群》などの攻撃力参照カードに対して発動することで不発にできる可能性があります。
いずれにしてもコンバットトリックには使えないという欠点があるため、攻守を操作した上で各種カードのサポートを駆使して相手モンスターを倒しましょう。
《オッドアイズ・ドラゴン》

開幕1話から消滅した遊矢の元エースモンスターです。
《ブラック・マジシャン》ほどではないですがわざわざ2体をリリースしてまで出したいモンスターではなく、基本的には融合素材か《オッドアイズ・セイバー・ドラゴン》の特殊召喚のために墓地へ送られることになります。
直火焼きですらないバーン効果が活きる場面はほぼ無いですが、相手のLPが1000前後であれば引導火力になり得るため忘れないでおきましょう。
《EMウィップ・バイパー》や《禁じられた聖槍》によるサポートを受けられるとなお良いですね。
《オッドアイズ・セイバー・ドラゴン》

まさかのアニメ出演を果たした《オッドアイズ・ドラゴン》の進化形態です。
相手モンスターを戦闘破壊すると追加で相手モンスターを破壊でき、高い攻撃力と出しやすさも相まってエースモンスターと呼べるほどの活躍が期待できます。
召喚コストには手札で遊んでいる《超電磁タートル》か役割を終えた《スケルエンジェル》あたりが使えるでしょう。
リリースすることがコストのため、《ワンタイム・パスコード》で特殊召喚した「セキュリティトークン」を充てることもできます。
《スマイル・ワールド》

遊矢の父・遊勝から回り回って遊矢に託された笑顔印の呪いのカードです。
発動後はフィールドの全モンスターの攻撃力が上がっていることから、戦闘補助としては全く役に立ちません。コンボ前提のカードです。
雑な使い方としては、お互いのモンスターが1体ずつのみ存在している場合に《禁じられた聖槍》をチェーンして相手モンスターに発動することで攻撃力の差を1000もつけることができます。
他にも上昇値は攻撃力のみであることから《EMウィップ・バイパー》で攻守を入れ替えたり、そもそも守備表示モンスターへの攻撃や直接攻撃をしたりすることで、相手モンスターの攻撃力上昇のデメリットを軽減できるでしょう。
《超カバーカーニバル》

高い汎用性を誇る攻防一体のカードです。
《EMディスカバー・ヒッポ》をどこからともなく特殊召喚しつつ、任意で「カバートークン」を可能な限り生成できます。
「カバートークン」が生成された後は「カバートークン」以外のモンスターを攻撃対象にできないため、《EMディスカバー・ヒッポ》が無事であればそのターンを凌ぐことができます。
無論《EMディスカバー・ヒッポ》のみを出して各種素材に充てることもできます。
流石に環境で活躍したカードは一味違いますね。
《分断の壁》

遊矢のデッキには珍しい防御カードです。
攻撃力のマイナスは永続であり、2体が並んでいるだけでも1600のダウンとなるため非常に優秀なデバフカードと言えるでしょう。
欠点はやはり攻撃反応型という発動タイミングくらいでしょうか。
対象を取らないステータスダウンのため《ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン》さえも処理できる可能性が見出せますが、その前に除去されては元も子もありません。
しかしそれを踏まえても優秀なため内定しました。
《クリアウィング・シンクロ・ドラゴン》

同化したユーゴから受け継いだモンスターです。
比較的高レベルのモンスターが多いこのデッキでは、自身だけでなく他のモンスターも守れるため雑に出しても仕事してくれます。
最大のライバルは同時に採用している《サイバース・クアンタム・ドラゴン》であり、こちらはやや受け寄りすぎるきらいがあります。
主体的に活用させるなら、《EMウィップ・バイパー》と併用させるといいでしょう。
《覚醒の魔導剣士》

S召喚に目覚めた遊矢が発現させたSモンスターです。
「魔術師」Pモンスターが採用されていないため、直火焼き効果のみを目当てに出すことになります。
《スターダスト・ドラゴン》と比較すると、こちらは攻撃的なカードであることから攻める場合はこちらに軍配が上がるでしょうか。
《分断の壁》などで弱体化したモンスターを倒せると大ダメージが見込めるので、狙える時は狙っていきましょう。
《ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン》

ユートが消滅する際に遊矢に託されたモンスターです。
《フォース》を内蔵しており、攻撃力を奪った相手をそのまま殴り倒せば2500のダメージが素通りすることになります。
非常に攻撃的な効果である他、まとめて2つのX素材を取り除くことからそれらを利用して《マスター・ピース》で《No.39 希望皇ホープ》を出すこともできます。
ステータスの変動は永続のため、《オッドアイズ・ドラゴン》や《覚醒の魔導剣士》の補助もできる優秀なモンスターです。
藤木遊作使用カード

『遊戯王VRAINS』の主人公である藤木遊作およびそのアバターであるPlaymaker/Unknownです。
以下が採用カードです。
《サイバース・シンクロン》
《ドットスケーパー》
《切り込み隊長》
《クロック・ワイバーン》
《フォトン・スラッシャー》
《ワンタイム・パスコード》
《禁じられた聖槍》
《サイバース・クロック・ドラゴン》
《サイバース・クアンタム・ドラゴン》
《リンクリボー》
《デコード・トーカー》
ハノイの騎士との戦いに身を投じたPlaymakerはサイバース族を主体としますが、それ以前の遊作は汎用カードを使ったデッキで戦っていました。
メインデッキに採用している約半数はUnknown時代の頃のカードであり、それらを据えつつもサイバース族を取り入れた、やや異質なカード選出になりました。
《サイバース・シンクロン》

Playmakerが使用したチューナーモンスターです。
ネーミングは恐らく意図的なものでしょう。
レベル4以下のモンスター1体のレベルを倍にできる効果を持ち、召喚権を使わずに出した《マジック・ストライカー》や《EMディスカバー・ヒッポ》と共にレベル7のSモンスターへ繋げることができます。
無論、自身も対象にすることができます。
EXモンスターゾーンのモンスター用の身代わり効果も持つため、あえてLモンスター以外をメインモンスターゾーンへ出すことも考えられます。
状況に合わせた展開の選択をしましょう。
《ドットスケーパー》

緩い条件でフィールドに舞い戻る下級モンスターです。
まず目を引くのは高い守備力です。
《超電磁タートル》を抜き去り、このデッキの下級モンスターで最も高い守備力を誇ります。
レベル1のため《リンクリボー》のL素材になれる他、S素材のレベル調整もこなすことができます。
ただし蘇生と帰還はいずれかターン1、さらに1デュエル中に1度ずつしか使用できないため、再利用手段が他にある場合は効果の発動を慎重に検討しましょう。
《切り込み隊長》

太古より遊戯王を支え続けてきた下級モンスターです。
Unknown時代の遊作が使用し、L召喚の補助に充てていました。
《クレーンクレーン》は墓地からの特殊召喚ですが、こちらは手札で遊んでいる《ドリル・シンクロン》と共に《ドリル・ウォリアー》になることができます。
他の戦士族への攻撃を自身に誘導する効果もありますが、ステータスが低いため速やかに各種素材に充てた方が良いでしょう。
《クロック・ワイバーン》

Playmakerの使用したカードの中でも特に優秀なモンスターです。
効果としては「クロックトークン」を生成するだけですが、この「クロックトークン」が《リンクリボー》のL素材にできることから、《デコード・トーカー》のL素材2体分に充てられます。
さらに《サイバース・クロック・ドラゴン》の融合素材をこのカードと《融合》のみで用意できることから、攻撃力3500の打点を突然確保することができます。
加えてレベル4とレベル1が同時に揃うことで、ランク4のX召喚と《リンクリボー》といった構えや、レベル7のS召喚+《リンクリボー》またはレベル8のS召喚という使い分けもできます。
総じて素材として極めて優秀なカードであり、状況に応じてあらゆる姿へと変化します。
《フォトン・スラッシャー》

『遊戯王ZEXAL』にて天城カイトも使用していたモンスターです。
高い攻撃力と緩い条件による特殊召喚方法を備える代償として単体でなければ殴れないというデメリットを持ちます。
基本的には各種素材に充てることとなりますが、下級モンスターの打点が低いこのデッキではアタッカーにもなり得ます。
単体であれば攻撃自体は可能ということを覚えておきましょう。
《ワンタイム・パスコード》

やたらステータスの高いトークンを生成するだけのカードです。
高いステータスを持つ代わりに守備表示での特殊召喚に固定されており、戦力にすることはほぼできません。
いつでも特殊召喚できる《フォトン・スラッシャー》くらいの感覚で扱いましょう。
《禁じられた聖槍》

攻防一体である汎用カードです。
対象のモンスターの攻撃力を800下げる代わりに魔法・罠カードの効果を受けない耐性を付与します。
先述した通り《スマイル・ワールド》と併用した戦闘補助ができますが、単体でも問題無く使うことができます。
自分のモンスターを《サンダー・ボルト》などから守るためにも使えますが、打点が下がる点には注意しましょう。
《サイバース・クロック・ドラゴン》

超打点を得られる融合モンスターです。
基本的には《クロック・ワイバーン》+《リンクリボー》で融合召喚するため攻撃力は3500となりますが、《デコード・トーカー》を素材にしたり相手のLモンスターを《死者蘇生》で奪って素材にしたりするとさらなる打点を得られます。
ランダムな墓地肥やしで《ブラック・マジシャン・ガール》などが落ちれば御の字であり、処理されても魔法カードのサーチができるためなかなか優秀です。
《サイバース・クアンタム・ドラゴン》

攻撃的な効果を持つ汎用Sモンスターです。
相手モンスターと戦闘するダメージステップ時にそのモンスターをバウンスしつつ、追加の攻撃権まで得られます。
この戦闘は相手からの攻撃にも反応するため、攻撃を牽制することもでき、他にLモンスターが存在する場合は自身へ攻撃を誘導することから戦闘面で優位に立てます。
《クリアウィング・シンクロ・ドラゴン》とは一長一短の関係となるため、状況に合わせた方を出しましょう。
《リンクリボー》

実質的に相手の攻撃を1回止められるLモンスターです。
レベル1モンスターをリリースすることで自己再生もでき、1枚あれば繰り返し使える便利なカードです。
適当に置いておくのも良いですし、《サイバース・クアンタム・ドラゴン》と並べることで攻撃を牽制するのも良いでしょう。
効果を発動できなくさせるカードは天敵です。
普通に死にます。
《デコード・トーカー》

初めて登場した汎用Lモンスターです。
やや相手依存ですが攻撃力は最大3800まで到達し、対象を取る効果に対してもリンク先のモンスターをリリースすることで発動を無効にし破壊できます。
より攻撃的な《デコード・トーカー・エクステンド》よりもカードを守れる点で長けており、何よりもPlaymakerの相棒とも呼べるモンスターのため採用しています。
高い攻撃力も合わさり、非常に頼りになるモンスターです。
最後に

以上がこのデッキに採用したカードです。
戦術らしい戦術はありません。引いたカードを叩きつけてください。
各主人公になりきってごっこ遊びをする分には割と飽きないデッキだと思います。
改善案などある人は構築を練って記事を投稿してください
おまけでは泣く泣く不採用にしたカード達を主人公ごとに3枚ずつ紹介しておきます。
暇な人は読んでください。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
おまけ(不採用カード)
武藤遊戯不採用カード
《魔導戦士ブレイカー》

アニメのドーマ編で使われた、《狂戦士の魂》による羽賀フルボッコで有名なモンスターです。
攻撃力1900による運用か攻撃力1600にしつつも魔法・罠カードを破壊するかを選べるという、元禁止カードらしく真っ当に強力なカードです。
不採用の理由は、魔法・罠カードに強力なカードが多すぎたためです。
合計7枠しか使えず、そのうち2枠を《ブラック・マジシャン》《ブラック・マジシャン・ガール》で埋めているため枠がありませんでした。
《翻弄するエルフの剣士》

随所で登場し遊戯の窮地を救ってきた頼れる剣士です。
簡単に上級モンスターを並べられる現環境ではそれなりに硬い壁となり、装備カードなどで打点を補強してあげると戦闘には強いモンスターとなります。
不採用の理由は、アドバンテージに直結しないためです。
壁モンスターである点に絞れば《超電磁タートル》や《ビッグ・シールド・ガードナー》などの単純に守備力が高いモンスターに軍配が上がり、その中でも検討に検討を重ねた結果《超電磁タートル》の採用が決まったのです。
そもそも《魔導戦士ブレイカー》すらも不採用になる状況では採用は厳しいでしょう。
《心変わり》

モンスターのコントロールを奪える通常魔法です。
元禁止カードらしく奪ったモンスターに使用制限がかからず、リリースや各種素材に充てることでの除去ができます。
不採用の理由は、実質的な除去カードであるものの除去が確実ではないためです。
リリースするには上級モンスターを引いておく必要があり、各種素材に充てるにしても頭数やレベルが合わなければいけません。
雑にLモンスターを出せるデッキでもないことから《ソウルテイカー》に軍配が上がりました。
遊城十代不採用カード
《N・グラン・モール》

鬼畜モグラの蔑称を持つ「ネオスペーシアン」の1体です。
戦闘を行う相手と仲良く手札に戻る効果を持ちます。
かつての制限カードは伊達ではなく、アニメでは《F・G・D》に突撃したところ《スキルドレイン》を発動され返り討ちに遭いかける光景まで見られました。
しかしこのカードを召喚してバウンスし続けるだけでは試合展開が進まず、戦闘以外の方法で簡単に処理されるため不採用となりました。
十代の他のカードの枠もかなりカツカツなのです。
《ヒーロー見参》

特にサポートが無いものの、名前繋がりで十代に度々使われたカードです。
相手の攻撃宣言時に手札の1枚を選択し、それがモンスターの場合は特殊召喚できます。
アニメでは《E・HERO エッジマン》や《E・HERO ネオス》のみが手札に存在する状態で発動しその特殊召喚に繋げる場面が見られました。
このデッキでも概ね似たような運用ができますが、事前に手札の魔法・罠カードを伏せておかなければ特殊召喚を確定させることはできず、特殊召喚したモンスターも普通に攻撃されるため不採用となりました。
《E・HERO フレイム・ウィングマン》

十代のマイフェイバリットモンスターです。
通称「直火焼き」効果の由来であり、攻撃力分の数値をそのまま相手のLPにぶつけることができます。
融合素材は共にレベル3の戦士族であり各種サポートカードに対応しやすいものでしたが、手札3枚を消費して出すのには見合わないステータスであり、その後のリカバリー手段にも乏しいことから不採用となりました。
というか素材が2体とも名称指定のため素材そのものがまず揃いません。
不動遊星不採用カード
《マッシブ・ウォリアー》

遊星が度々使用する、守ることに特化したモンスターです。
似たような立ち位置のカードに《シールド・ウィング》も存在します。
壁モンスターとしては優秀であり、レベル2であることから《ジャンク・シンクロン》の蘇生にも対応します。
ではなぜ不採用なのかというと、場持ちが良すぎるためです。
《ギラギランサー》や《フォトン・スラッシャー》のようなモンスターを特殊召喚するためにフィールドは空っぽの方が都合が良いことが多いです。
守ることに特化させるなら、いっそのこと《ガガガガードナー》のように手札で発動するタイプの方が扱いやすいと感じました。
《ワン・フォー・ワン》

レベル1モンスターを呼び出す、現役の制限カードです。
このデッキに採用されているだけでも《ドットスケーパー》や《サイバース・シンクロン》などの優秀なレベル1モンスターが存在するため、採用自体は検討できる範囲です。
ではなぜ不採用かというと、手札コストが重く、リクルートしたレベル1モンスターから展開できないためです。
コストはモンスターのみに限られており、そこから展開に繋がるわけでもありません。
たとえ手札で腐り続ける《ブラック・マジシャン》であろうと、大事な手札であることに変わりはありません。《融合》とドラゴン族さえ揃えば立派な融合素材になるため、雑に捨てていいカードというわけでもないのです。
《ジャンク・デストロイヤー》

S召喚と同時にフィールドのカードを破壊するモンスターです。
これに限らず《ニトロ・ウォリアー》や《ターボ・ウォリアー》などについても纏めて触れます。
というか《クイック・シンクロン》が思った以上に弱かったのが不採用の原因です。
EXデッキを圧迫し、レベルの調整もほとんどできないこのデッキで「シンクロン」チューナーを利用するSモンスターを大量に採用するのは流石に無理がありました。
また《クイック・シンクロン》自体も《ワン・フォー・ワン》と同様にモンスターをコストに要求するため、手札消費が凄まじいてす。
当初は《ジャンク・デストロイヤー》くらいなら……と思って採用していましたが、悪い部分が目立ちすぎて抜けました。
九十九遊馬不採用カード
《ガガガマジシャン》

遊馬をずっと支えてきたモンスターです。
レベル変動効果を持ち、多くのサポートカードの恩恵を受けられるため様々な活用ができます。
不採用の理由はS素材にできないためです。
このカードの他にも《カゲトカゲ》なども同様の理由で不採用になっています。
X召喚黎明期のカードだったため、レベルを変動させて多くのデッキでS素材にされることを懸念したのでしょう。
結果としてその目論見は成功し、こうして不採用になってしまう原因となりました。
《破天荒な風》

使い切りの《デーモンの斧》のようなカードです。
上昇値自体は大きく、《サイクロン》などで除去されない強みも存在します。
不採用の理由はフリーチェーンではないからです。
こちらのモンスターのステータスの低さから、戦闘破壊を狙われるケースが非常に多いです。
そのためコンバットトリックとして機能するカードは相手の不意を突きつつアドバンテージ差をつけられる可能性があるカードとして採用候補に挙がりますが、ステータスが高いだけの置物になるこのカードは残念ながら採用に至りませんでした。
《No.11 ビッグ・アイ》

遊馬を苦しめたジンの持っていた「No.」の片割れです。
永続のコントロール奪取ができ、素材の重さに見合った性能のカードと言えます。ただし近年のレベル7がやたら場に揃えやすいということは考慮していない。
主人公達のカードにはレベル7のモンスターが多いため素材そのものは用意できますが、それらをフィールドに揃えられないという問題から不採用になりました。
《E・HERO ネオス・ナイト》を融合召喚した後に《死者蘇生》で《E・HERO ネオス》を蘇生させるなどすれば揃えられますが、実質的に手札4枚を要するため流石にディスアドバンテージが目立つため採用できませんでした。
榊遊矢不採用カード
《オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン》

第1話にて《オッドアイズ・ドラゴン》が書き換わったことで遊矢が手に入れた新たなエースモンスターです。
このカードに限らずPモンスター全般についてもここで触れます。
というのも、P召喚のシステム自体が上スケールと下スケールを揃えることで初めて使用可能になるという都合上、デッキの大半をPモンスターで占めることが構築のセオリーとなります。
ところがこのデッキでは他の主人公がPモンスターを使用していないことから最大でも7枚しか採用できません。
一応Pモンスターを採用したタイプの構築を考えたこともありましたが、《EMモンキーボード》からレベル8のSモンスターを呼び出すくらいしか安定した動きがありませんでした。
ということでPモンスターは全て切り捨て、Pモンスターではないカードから採用カードを選出することになりました。
《シャッフル・リボーン》

条件付きの蘇生と条件付きのドローを備えたカードです。
決して弱いカードではないのですが、それぞれに癖があることがネックとなってしまいました。
蘇生効果は他にモンスターが存在しない場合のみであり、《フォトン・スラッシャー》や《ギラギランサー》の特殊召喚条件と重複してしまいます。
高レベルのモンスターでも蘇生でき攻撃にも参加させられる点は優秀ですが、最高打点3000を蘇生させるだけでは味気ないです。
蘇生させたモンスターはターン終了時までに処理しなければならないこともあり、基本的には素材調達用のカードとなります。
ドロー効果も一時的にフィールドのカードを手札に変換できますが、ターン終了時に手札1枚を除外しなければならない点が難点です。
総じて、弱くはないもののこのデッキだと扱いきれないことから不採用となりました。
【インフェルニティ】なんかだと採用の余地があるんじゃないんですかね?
《スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン》

ユーリが所持していた四天の龍の一体です。
《超融合》を使えば相手の闇属性モンスターを処理することもでき、逆転の一手として使えるカードです。
不採用の理由は融合召喚できる場面がほとんど無いためです。
そもそもこのデッキでモンスターがずらずらとフィールドに並ぶ場面はほとんどありません。
さらに《融合》を引いて出せる場面ではこのカードは不要でしょう。
《超融合》で相手モンスターを吸えますが、相手依存のカードでEXデッキを1枠埋めるのは難しい部分があったため、最終的に抜けました。
藤木遊作不採用カード
《リンクスレイヤー》

遊作の初台詞となったモンスターです。
《サイバー・ドラゴン》以上に緩い条件で特殊召喚でき、手札を捨てることでその数だけ魔法・罠カードを破壊できます。
不採用の理由は、そのレベルが素材に使いづらかったためです。
その召喚条件から《フォトン・スラッシャー》との比較になりますが、あちらと異なりレベル5であることからランク4の素材にできない点が大きく目立ちました。
S素材としてはこちらの方がやや使いやすいですが、大差無いので総合面であちらに軍配が上がりました。
《トランザクション・ロールバック》

墓地の罠カードを再利用できるカードです。
効果のコピーという面白い悪用できそうなカードですが、ライフポイントを半分削る諸刃の剣となります。
不採用の理由ですが、発動の機会に乏しいためです。
②の効果のために《おろかな副葬》のようにこのカードを直接墓地へ叩き込む手段は少なく、①の効果を活かそうにも罠カードを一切採用しないデッキも少なくありません。
手札コストで捨てても墓地の情報から相手に警戒されるため、奇襲性が皆無であり活躍できないことから不採用となりました。
《ファイアウォール・ドラゴン》

攻撃力2500である主人公のエースモンスター枠です。
禁止カードを経てエラッタされ、健康体となって復活しました。
不採用の理由は明白で、コンボ前提のリンク4モンスターは出せる場面も活躍させることもできないためです。
相互リンクは絶望的であり、バウンス効果は発動の機会がまずありません。
またリンク先のモンスターが墓地へ送られると手札からサイバース族モンスターを特殊召喚できますが、特殊召喚できるモンスターがデッキに3枚しか入っていないので発動すらできないことがよくあります。
とりあえずで適当に出せる《スターダスト・ドラゴン》でさえも滅多に出ないのに、それよりも遥かに素材が重いこのカードを出すことはまずありません。
結果としてエースモンスターの座は《デコード・トーカー》に譲ることになりました。
皆さんも遊び心を詰め込んだ紙束デッキを組んでみてはいかがでしょうか?
同じ気持ちで遊べる友達も必要ですが、普段の殺伐としたデュエルとは違う雰囲気で楽しめるでしょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
