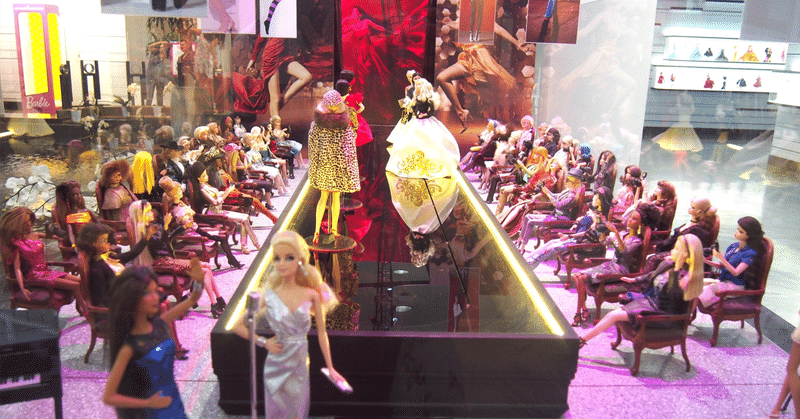
24/5/12 バービー
マンションの大規模修繕の対応を早朝に(と言っても8時30分頃)しなければならなかったので、休日なのに6時起き。もっと寝たかったけど、8時半から二度寝は人としてどうだろうと思ったので、Netflixで「Barbie」を見た。
娘は映画館で見たらしく、その時に勧められて気になってはいた。私は子どもの頃から女の子らしさ皆無で、人形を使った遊びやゴム飛び、おはじき、あやとり等の女子定番の遊びはほとんどしていない。子ども時代の遊びといえば、自転車乗り回したり、裏山の防空壕で戦争ごっこ(今考えるとなんてガキだ)、鬼ごっこの記憶。そんな子だったから、バービー人形を買ってもらったことはないし、欲しいと思ったこともない。ねだって買ってもらったのは、仮面ライダーの変身ベルト。キキ・ララの小さなプラスティック人形と持ち運び可能な取手付きの家は買ってもらった記憶があるけれど、あれは私の希望だったんだろうか。
映画「Barbie」の前評判は、娘以外からも耳にしており、バービー人形が好きかどうかはあまり関係ないことは理解していた。見たいと思ってはいたけれど、結局映画館で上映されている期間に間に合わず、それでも今はNetflixとかAmazonプライムという配信があるから、契約さえしていれば自宅にいてもいつでも見ることができる。すごい時代が来たもんだ。
朝ドラの「虎に翼」にハマっているタイミングってのもあるけれど、今はフェミニズムをテーマとして扱う作品が増えたなと思う。(「虎に翼」も「Barbie」も、フェミニズムのことだけじゃなく、他に複雑なテーマ(人種差別、母と娘の関係性、ルッキズム、男性性などなど)も盛り込まれていることも、一応記しておきます。)映画への批評は、ネットに溢れんばかりに載っているので、興味がある方にはそちらを読んでいただくとして。
ここは私の日記なので、私の内面を書いていきますが、ようやく変化を素直に喜べる時代になってきたと受け止めていいのだろうか、と言うのが、見終わった最初の感想でした。
私の若い頃は、男女雇用機会均等法なんて法律は建前として存在しているだけで、女だから叶わないことや、女だから当たり前に押し付けられることがバンバン存在していた。私個人のことだが、就職活動時に女だから断られたり、仕事でミスした時(私はミスだとは思っていない案件も含めて)「これだから女はダメだ」と言われることなんて、ザラだった。仕事中、屈んでいたら背後から(服の上からではあったけど)ブラジャーのフォックを外されたこともあるし、ベロベロに酔っ払った番組プロデューサーの車に無理やり乗せられて、首都高3周に付き合ったこともある。(生きててよかった)
それでも「そんなもんだ」と思ったり、「仕方ない」と諦めたりしてきた。ミスした(ミスしたように感じさせた)私が悪い、そもそも女がやるべき仕事じゃない仕事をしたがっているのだから仕方ない、皆が笑っているならいいや、受け流すことができるのが大人の女・・・と思っていた。思わされてきた。
私はもっと戦えばよかったのだろうか。そもそも戦ってなんかなくて逃げてたのだろうか。勝ち取るまで頑張るべきだったのだろうか。ここ数年、そういう思いを抱えて若かりし自分を振り返る機会が増えた。今回の「Barbie」でもそうだし、朝ドラの「虎に翼」でもそうだ。他にもネットでたまたま読んだ記事や、読んだ本でもそういう思いを抱く回数が増えた。
私の母は、私が小学生くらいの頃には「今からの女は学もないと」と言っていた。しかし私が成長すると、少しずつ考えを変化させ「仕事は銀行勤めがいいんじゃないか」とか「あんまり気が利き過ぎると鼻につくから、ちょっとくらい抜けた女が可愛げがある」とか言ってくるようになった。東京の学校に進学できたのは、母の応援があったからこそだったが、今振り返ると「母自身がやれなかった事を叶える存在」として見ていたように思う。事実、上京時に母に話していた仕事から変えて就職活動を始めると「こんなんだったら東京に行かせるんじゃなかった」「あんたは手元に置いておくべきだった」と言うようになった。それを完全に無視して自分を貫けるほど、私も成熟しておらず、年長者の言うことに従って間違いはない、親は子のことを思って言ってくれているという思いに囚われて、いちいち傷つき、自分のやりたいことと天秤にかけてきた。私に学費や生活費を投資してくれたことに感謝はしつつ、母のその時々でぐらつく子育てへの考えに振り回され、自分の芯を見失ってきた過去にいくばくかの後悔が残る。
もちろん、私自身が自分でやりたいこと、せねばならぬことを見失わずやれていれば良かったのであり、今と時代も違うし、そんな昔のことをあーだこーだ言っても仕方ない。結局母も「女はこうあるべき」に振り回されていたと思うし、16年前に他界した彼女ともう話す手段はないのだから、そういうものだったと受け止めるしかない。そもそもここに父の存在が語られないことに疑問を持つべきで、父は自分の出世にしか興味がない人で、私たち子どものことに興味を持ったことはほとんどなかったから、そりゃ登場しないよねって思う。
時代だったと言ってしまえばその通りで、80〜90年代の社会、家族は、今とは全く空気感が違う。あの頃に戻ってはいけないし、変わらねばならないと思う反面、変化から起きる反発がどういう形で出てくるのかが少々気になるところである。
「Barbie」の中で、後半特に頻出する「誰でも何にでもなれるし、輝ける」という言葉。時代が変わったとは言え、それがそう容易ではないことは、大人になった誰もが知る現実だ。性別や人種などあらゆるものから解放され、差別なく区別なく自由に、何にでもなれると言われれば聞こえはいいし、実際建前は何十年も前からそうだし、そのために戦ってきた人たちがたくさんいる。だけど、「どんな自分になりたいか」を本当に自由に、それぞれの価値観で選べるようになるのか、私の肌感覚では程遠さも感じている。ようやくスタート地点に立てたと信じていいのだろうか。そもそも今までの価値観に違和感を感じる必要がなかった人たち(今まで良い思いをしてきた側の人たちと書くと、反発を生むだろうか)からしてみれば、変化のパワーが大きければ大きいほど、自分たちの立場が脅かされる恐怖を感じるだろうし、そもそも変わる必要性を感じないのではないか。そう言う人たちが権力側に多いのだから、そこは忘れずにいたいところだ。(Barbieの中に出てくる権力者は、わりと柔らかく描かれている)
家族(主に母)や善に縛られ、女に生まれたからにはとか、女だからという言葉に振り回されてきた若かりし頃の自分と重ねると、胸が疼く。恵まれた時代の到来のようで、まだまだこれからだと感じた「Barbie」なのでした。
追記
個人的には、ケン役のライアン・ゴズリングが最高だった!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
