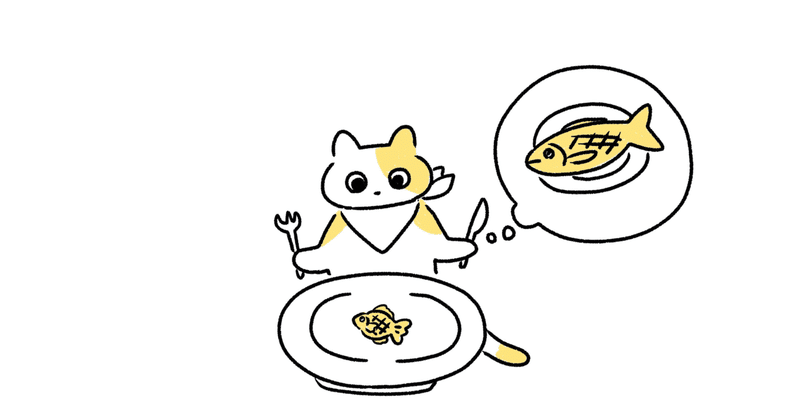
研究授業と理想の授業の間で
難しいなと感じています。研究授業で求めている子どもの姿は、自分で考え、表現し、友達と学び合い、さらに深め、自分の力にしていくような姿です。
しかし、45分の授業の流れを作ってみると、目当てを立てたり、問いを持たせたりすることで大忙しです。
さらにペアで話し合わせたり、全体で共有したり、発表させたり振り返らせたり、いろいろ書いたりして子どもが落ち着いて自分の学びたいことに向かっていく授業にはならないのです。
あくまで研究授業は、先生の手のひらの上で子どもたちが考えさせられ、動かされているものを作ることが多いです。
そうして、先生に操られている子供たちの姿を、「よく学習訓練がなされていますね。」「安心して先生と学べていますね。」などと評価されてしまうのです。こういった指導は、もう何十年も前から変わっていないと思います。こういった研究授業の形式の中に、タブレットパソコンが入ったり入らなかったりする位の変化しかしていないのが実情ではないでしょう。
つまり、理想とする子どもの姿を求めるための、理想の研究授業にはなっていないんだなぁと感じているところです。
しかし、先生の手が離れているから良い授業なのかと言えばそれもなかなか難しいところです。先生が指導することによってたどり着ける学びもあるからです。
つまるところ、子どもに何を学ばせるか、そのためにどんな活動をさせるか、もしくはどんなものとの出会いをさせるかを突き詰めなければいけないのでしょう。
普段行っていない深い授業を、急に行うことはできません。それは先生も大変だし、子どもたちも混乱することでしょう。研究授業を通して、そういった深い学びの方法について考え、これから続けていくと言うのであればまだわかるかもしれません。
研究授業は、いろんな方のアドバイスによって出来上がることが多いので、いつも以上にやりたいことが膨らんでしまいます。でもそれは自然なことではありません。理想の授業を行えるような理想の研究授業になるといいなと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
