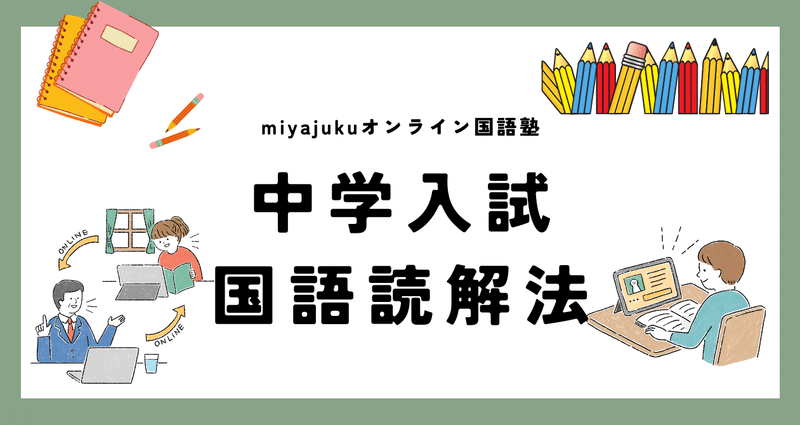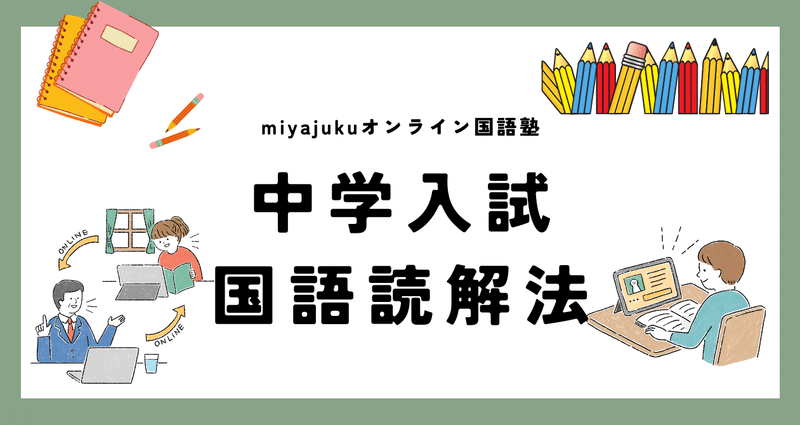中学入試 国語読解法 その3 説明文(論説文)の読解のしかた ④ キーワードの見つけ方
a 説明文の読解に役立つキーワード
小学校の国語の授業では、ちゃんとした説明文(論説文)の学習をすることはあまりありません。ちゃんとしたというのは「序論→本論→結論」の構成が整ったそれなりに読みごたえのある内容の文章です。教科書に出てくるのは物語文が中心で、難度の高い説明文にぶつかると「なにが書いてあるかわからない」となりがちです。
ですから「なにが書いてあるかわからない」レベルの問題文に数多くあたって、国語の読解テクニックを使ってそれらの文章をしっかりと読みとる練習を数