
【特集】第26回参院選(2022年)自民党――地方の衰退と一強体制の虚構
今回から各政党の個別の議論を行っていきます。選挙区、比例代表、候補者の個人票など議論するべきことは多岐にわたり、自民党ばかり扱っていると今年が終わってしまうので、今回の自民党PART1の後は他の政党を一つずつ取り上げ、それが一巡した後にPART2に進む予定です。
さて、先に「何人に一人が自民党に投票しているのか」という記事で自民党の絶対得票率の地図を公開した際に、自民党が本当に強かった時代とは違い、近年は5人に1人の票によって勝つような選挙がなされていることを述べました。けれどそうは書きつつも、かつての自民党がいかに強かったのかというデータは示せませんでした。
そこで、今回は総務省や選挙管理委員会がWebで公開していないデータまで用いて、全ての市区町村について過去39年分の絶対得票率の計算を行いました。地図とアニメーションによって自民党の票の動きを完全に可視化します。

39年間の投票率の動向
日本では1982年8月の公選法の改正によって第13回参院選(1983年)から比例代表制が導入され、無所属や候補者個人ではない「政党の票」を全国レベルで統一的にとらえる条件がそろいました。
今回はそのデータを用いて第13回参院選(1983年)から第26回参院選(2022年)にわたる39年間を一望することになりますが、その前にまずは投票率の推移を確認しておきましょう。

上の図1の最も赤い配色は95%以上の投票率に相当しています。薄い黄色でも60%を超えており、1980年代までの地方の投票率がいかに高かったかがうかがえます。なかでも全国的に高い1986年は衆参同日選挙でした。続く1989年の第15回参院選でも、全国集計で65%を超えています。
しかし1990年代に入ると状況は一変していきます。都市部に急速に棄権が広がり、1995年には史上最低の水準を記録します。この時期の投票率は若い世代ほど、そして相対的に都市化が進んだ地域ほど大きく下がりました。2000年代以降になると都市部には若干の改善が見られますが、その一方で今度は地方が低下していきます。こうした推移を全国集計でまとめたのが次の図です。

この図2からは、参院選の投票率は昔から低かったわけではなく、1990年代に特異な落ち方をしたことが明らかです。この投票率の崩壊は日本政治史における特に重要な出来事なのでたびたび触れてきましたが、ここでも簡単に確認しておきます。
1990年代に投票率の崩壊が起きた原因として、これまでの政治学では当時の政界再編や政治不信が挙げられてきました。55年体制のもとでは自民党と社会党が二大政党としてしのぎを削ってきたものの、ソ連崩壊のあおりをうけて社会党の弱体化が進むと、しだいにその地位を得る次の勢力が模索されるようになります。こうしたなかで政党が集合離散し、少なからぬ人々が従来からの支持政党を失って無党派層になったことが、投票率の低下の一因と考えられてきたわけです。
しかしながら、そうしたことはあくまで当時の問題です。かつて多くの人が政治から離れたのは事実だとしても、そうした状態が30年後の現在まで続いている理由が説明されなければなりません。そのためには当時の一時的な政党離れや政治不信ではなく、この1990年代という時期に、人々をとりまく環境に大きな変化があったと考える必要がありそうです。
そこでもう一度当時の状況を振り返ると、浮かび上がるのはバブルの崩壊です。バブルの崩壊で日本経済が打撃をこうむると、大資本を守るために雇用の非正規化や労働者の権利の切り下げが進められました。当時、社会に出ていった若者たち――今、ロスジェネ(失われた世代)と呼ばれてる人たちは不安定な仕事や長時間労働を強いられ、いわばバブル崩壊で生じた打撃をおしつけられたのです。社会党の後を担う勢力が模索されたのはそういった時代でした。そのとき目指されたのはあくまで保守二大政党制であり、そのどちらも、つまり自民党も新進党もが新自由主義的な政策を掲げました。二大政党の地位をめぐる争いはロスジェネ世代や苦境に置かれた労働者を取り残したものであり、そうした人たちに失望がもたらされたからこそ、若者や都市部ほど投票率の低下は激しかったのです。
本来であれば、政治は苦境に置かれた人々に目を向け、失業者たちを新たな産業へと引き込んでいくために、社会の様々な「もの」や「こと」を組織するべきでした。それができなかった結果、生じたものが投票率の崩壊であり、その後30年も続く日本の衰退であったのです。(投票率の崩壊に関する議論は、詳しくは「武器としての世論調査』リターンズ―2022年参院選編 ― 第3回 投票率の底から」で展開されています)
かつての新進党の失敗があり、2017年には新進党2.0(小池新党)の失敗がありました。今は一部の学者や政治家らに立憲と維新をつなげる思惑が見え隠れしているようですが、苦境に置かれた人々の方を見て政治とはいかにあるべきかを悩み考え打開しようとするのではなく、安直な数合わせと強者への迎合でしか政治を考えない人々はいつの時代もいるものです。政治に失望した膨大な棄権者層をとりこむことが政権交代への道なのにそのように考えない――そうした姿勢こそが失望を失望のまま固着させ、政権交代を不可能にする道にほかならないのですが、以上のような頭の働かせ方をしない学者や政治家らが多い現状には、なにか極めて政治の堕落を思わざるを得ません。
少々筆が滑ってしまいました。ともかく、ここまで述べたように、これから検討する39年間は、投票率の崩壊という日本政治史における重大な出来事を含みます。こうした場合、各政党の得票率を考える時に留意すべき点を次にまとめました。
議席は相対、変化は絶対
選挙結果を地図化するとき、多くの場合は得票率を用いますが、得票率には相対得票率(投じられた有効票のうち、特定の勢力が獲得した割合)と絶対得票率(棄権者も含めた有権者全体のうち、特定の勢力が獲得した割合)の二種類があります。
相対得票率の良い点は、当落が各政党や候補者の相対的な票の分量によって決まるため、議席を論じるうえで最良の指標となることです。そして悪い点は、投票率の情報が抜け落ちるため、投票率が大きく異なる選挙を比較する際に用いると誤った解釈を招きうることです。
他方で絶対得票率は定義上、投票率に依存することはないですから、こちらは時系列的な変化を論じる上で最良の指標です。相対得票率から絶対得票率を計算することはできませんが、絶対得票率がわかれば相対得票率はただちに求めることができるため、絶対得票率はより豊かな情報を持つ指標だといえます。(詳しくは前回の記事:「何人に一人が自民党に投票しているのか」を参照してください)
すでに図1や図2で見たように、今回検討する選挙には投票率の大きな差があります。したがって統一的な評価をするためには絶対得票率を用いなければならないというわけです。
39年間の有権者数の動向
しかし、絶対得票率を用いるとしてもなお留意すべき点が残されています。39年の間には人口が大きく変化しているため、有権者数の動きを念頭におく必要があるのです。
そこで39年間の有権者数の変化をアニメーションで見てみましょう。1983年を100としたときの各市区町村の有権者数の指数を下の図3に示しました。
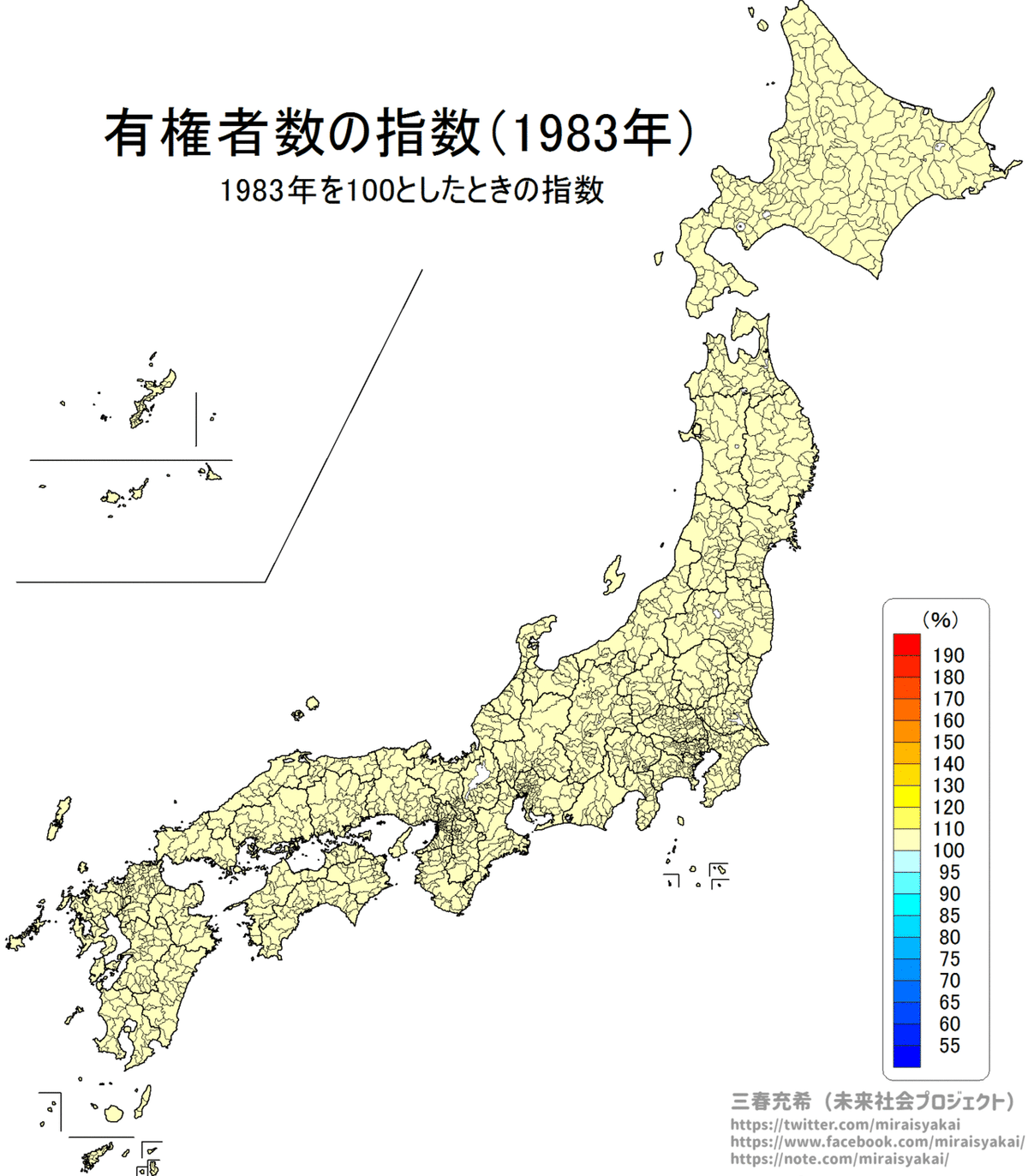
図3では1983年の有権者数を100(基準)としているため、これが150になったなら、有権者数は当時の1.5倍に増加したと読みます。有権者数が増加した自治体は黄色から赤色、減った自治体は水色から青の配色です。(細かい点ですが、図3では合併の処理を行いました。つまり境界線は厳密には市区町村ではなく、「39年間に境界線の変更がなかった最小の基礎行政区画」として扱っています)
この図3は、これだけで一つの議論が成り立つような衝撃的な地図となっています。これは、日本の少子高齢化がおよそ20年遅れてあらわれた地図にあたるのです。この39年間で都市の過密化と地方の過疎化がいかに激しく進行してきたかがうかがえます。(そして最低でも今後20年間はこの進行が止めようもなく続くのです。なお、1983年から1995年にかけて北海道で急減しているのは夕張です)
したがって絶対得票率を検討する際も、有権者全体に占める地方の比重は昔ほど大きく、最近になるほど小さくなっていることを心に留めておく必要があるといえるでしょう。
自民票のリアル
以上のことを念頭に置いたうえで、39年間の自民党の絶対得票率の推移を見てみましょう。

自民党は今も地方の町村で強いものの、かつてはその比ではなかったことが浮き彫りです。アニメーションが一回りして1983年に戻るとき、当時の地方の自民党があまりに強いことに少なからぬ人が驚かれるのではないでしょうか。
かつて自民党は戦後の経済成長を担い、農業技術の向上や道路網等の整備を通じて地方に繁栄をもたらしてきました。当時の地方の固い地盤は、そうしたことに対する人々の信頼に支えられていたはずです。
けれどもこの39年間――特にバブル崩壊からの30年は、地方では図3に示したような激しい人口減少が進みました。今度は自民党の政治の結果、地方は衰退し、共同体の維持が難しくなるほどの過疎にさらされることになったのです。
ですから地方の人たちに、もはやかつての繁栄の実感はありません。今なお地方では自民党の絶対得票率が高いものの、それは人脈などが維持されて、当時からずっと自民党に投票してきた人たちがいるためです。
もはや地方の自民党には、かつてのような理念と実感を伴った強固な支持があるわけではありません。むしろ地方の過疎化を止めるには、この30年で自民党が行ってきた政策を転換することこそが必要であるはずで、そうした点において野党は地方の自民支持層に食い込む余地を持っています。
また、第15回参院選(1989年)を見てみましょう。これは土井ブームと呼ばれる自民党が大敗した回ですが、このときの自民票の分布は直近の第26回参院選(2022年)と似ています。この大敗した時の分布に今の野党は蹂躙されているのです。
世論調査や一つ一つの選挙結果を見ていると、自民はいかにも強いように思えます。けれどこうして広い視野と長い目でとらえれば、今の自民はむしろ弱体化したものであり、野党がきちんと闘うのならいくらでもやりようがあるともいえるのです。
地方の自民や野党の闘い方に関しては以下でさらに検討を行っていますが、ここまででも内容は一応完結させたつもりです。様々なデータを示してきましたが、ぜひとも多くの人に考えてほしい問題だと思います。
アニメーションだとアップロードする際にどうしても画質が粗くなってしまうので、以下に個別の画像を示し、自由に拡大して見られるようにPDFファイルもアップロードしました。今後みちしるべでは、最低でもこの水準のデータに基づく議論を行っていきます。
