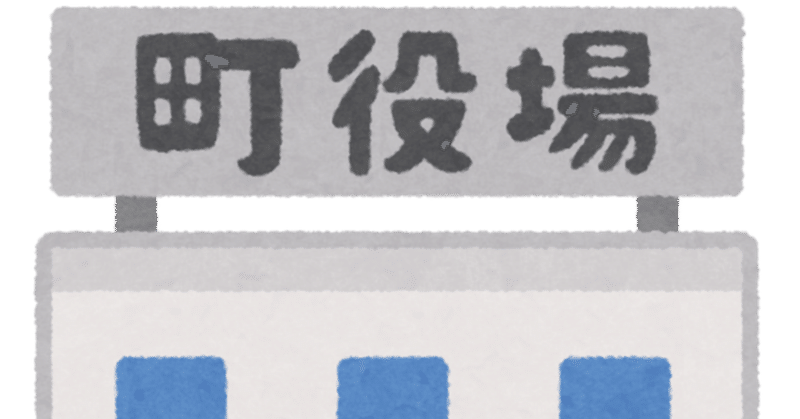
住民税計算の仕組み!実は所得税より取られているかも??
住民税を取り上げているnoteや動画は少なく地味だけと所得税よりも身近で、人によっては所得税より多めに納めているかもしれないこの税金について解説いたします。
知れば知るほど、負担額の大きさに驚く方も多いと思います。税金自体は逃れることはできませんが、自分の所得から差し引かれる過程や概要を知って、ご自身の資産形成やライフプランを立てる際にお役立てください。
住民税はどんな人に掛かる?
住民税は1月1日時点で住所がある市町村にから課税されます。原則は住んでいる方全員が対象ですが、生活保護世帯や未成年者・障がい者・ひとり親等で年間の所得が一定以下の方など住民税を負担してもらうには配慮が必要な方には課されません。また、住民税の申告や納付の窓口は市区町村ですが、徴収される住民税には市区町村の分と都道府県の分が含まれています。
住民税は所得割と均等割に分かれる
住民税には所得の多さに関係せず一律で掛かる均等割と、所得の多い少ないに影響する所得割に分かれます。均等割は全国大体同じで概ね5000円くらいです。しかし、地域の事情によって数千円の差が有ります。
例えば宮城県仙台市の場合は6200円となっています。これには東日本大震災からの復興を図ることを目的として,平成26年度から令和5年度の10年間について均等割の税率が年額1,000円が追加されているからです。更に、県民税のうち1,200円は「みやぎ環境税」と言うものが入っています。
住民税の所得割の計算
では、住民税の額に大きく影響する所得割の計算について解説いたします。
所得割の計算過程は所得税と良く似ています。まず、収入を求めますが税金の計算においては収入と所得は明確に分けます。個人事業であれば収入は経費を抜く前の売上のことです。給与をもらっている会社員であれば給与明細の額面が収入に当たります。
所得は個人事業であれば経費を差し引いた残った利益のことです。会社員にとって利益とは給与額面から差し引かれた「給与所得」のことを指します。
事業者のような明確な経費は有りませんが、給与所得者の場合でも、給与を得るためにも一定の必要経費は有るだろうという考えから、給与収入額に応じ概算で必要経費分としています。これが給与所得控除です。
計算過程の解説に入ります。収入の種類別に分けて、必要経費を差し引き所得額を出します。そこから、社会保険料控除や生命保険料控除など所得控除を行い、税金計算の元となる課税所得金額を出します。計算過程は下記のようになります。
収入ー必要経費=所得
所得ー所得控除=課税所得金額
課税所得金額✕税率10%=住民税 所得割額
収入から所得を出す過程などの基本部分は所得税と一緒です。異なるのが所得控除の各控除額に違いがあります。所得税の控除額よりも低い物が多いです。どれくらい差が出るかと言うと・・・
例えば基礎控除の場合、所得税では最大で48万円に対し住民税は43万円、扶養控除は所得税で38万円に対し住民税で33万円という具合になります。
本来は上記の式で完了ですが、所得税と住民税では課税所得金額に大きな差が出てしまいます。この差を緩和するため、調整控除がというものが入り更に住民税額が低くなります。調整控除後の金額が所得割の額になります。そこに、金額が一律の均等割が加わり住民税額が確定します。
住民税の徴収までの流れ
次に住民税はどの様な流れで決定されて徴収されるか会社員を例に解説いたします。住民税は1月1日から12月31日まで1年間の所得を元に計算されますが、同じく所得税も1月1日から12月31日まで1年間の所得を元に計算されています。会社員の場合、先に所得税の計算である年末調整を行います。
例えば令和4年分の年末調整を行うと、1年間に払わなければならない所得税と復興特別所得税の金額が確定します。この情報は皆さんの住民票が有る市区町村に1月31日を期限に共有されます。この情報が書かれた書類を「給与支払報告書」といいます。
自治体は給与支払報告書に書かれている給与の額や扶養者の人数や年齢、所得控除額などを元に住民税の計算をします。ここで算出された税額が先程お話した住民税の所得割額です。
確定申告をする方の場合は、税務署に提出した確定申告書の内容が市区町村にも共有されます。その後の計算過程は会社員の場合と一緒です。
ここまで算出された新しい住民税額は毎年6月頃に更新されます。更新された内容は市区町村から送られてくる住民税決定通知書で確認できます。もし、この金額に疑問や不明な点が有るときは決定通知書を送付した自治体に直接お問い合わせください。
住民税の納め方ですが、会社員の場合は特別徴収と言って毎月の給与から天引されます。個人事業者や自分で住民税を納めることを選択した方は、住民税の納付書を使って自分で納税をします。この方法を普通徴収と言います。
住民税で注意をしなければならない場合
ここまでは、住民税の計算や徴収方法をお話しました。ここからは住民税について注意が必要な方について説明します。
住民税額は6月から更新されますが、その計算の元になっているのは前の年の1月1日から12月31日までの所得です。例えばこの動画の撮影日である令和5年に入ってから会社を辞めて独立したり、定年退職した方の住民税は、在職中である令和4年度の給与所得を元に計算しております。
会社を辞めて一時的に手取りが下がった場合、現在の手取り額に見合わない高額な住民税額を払わなければならなくなります。会社を辞める際は生活費や社会保険料の他に住民税の額も見越して貯金をしておかなければなりません。
メルマガ登録のご案内
みらい創研グループでは毎週月曜にメールマガジンを配信します。税や社会保険に関する情報・動画やSNSの更新情報・セミナーのご案内を配信します。
Youtubeチャンネル登録のご案内
経営や生活に役立つ税務・労務・法務・会社の資金繰りや個人の資産運用など専門的なテーマを分かりやすく解説します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
