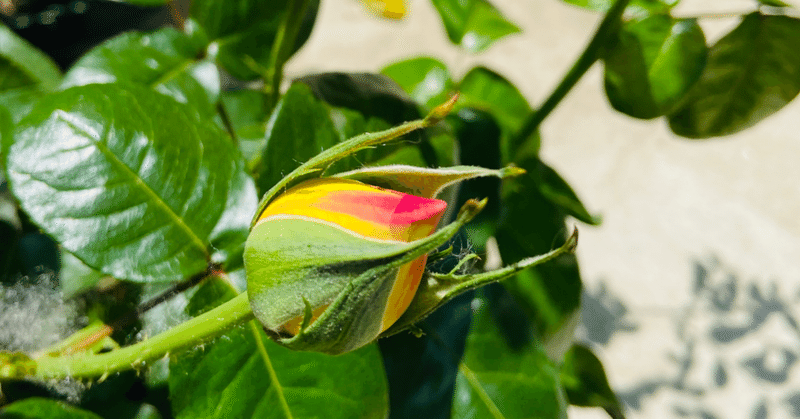
咲けない薔薇
「昔の男」とすら形容できないくらいごく数夜だけ関係をもったあのひとがくれた服は、今夜もちゃんと暖かい。4年前の早春の雨の朝以来、冬の夜にはあのひとの服に抱かれて眠り、夏の夜にはあのひとの服を抱いて眠ってきた。そうすることでしかやり過ごせなかった夜があった。花の名前を思い出すよりも、わたしを抱いたあのひとの温もりを思い出していたいから、縋れるよすががあることを嬉しいと思う。
いつだったか眠れない夜にあのひとのSNSを遡ったら、世界のあちこちでこの服を着たあのひとが笑っている写真が出てきて、ああほんとうに、気に入っていたものだったのだ、と思った。あのひとがこの服と歩いた時間の密度には及ぶべくもないけれど、せめてあのひとが愛したこの町のうつくしさを今度はわたしがこの服に見せてやろうと、折に触れては山や海へ連れ出している。
第五夜
事務作業が溜まってきていたのでほんとうはいちにち宿の部屋で過ごすつもりだったものの、昼食を調達しがてら戸外を歩くとあまりに穏やかな晴天だったので、吸い寄せられるように海へ来てしまった。港で知人と立ち話をしていたら、「そういえば」と久方ぶりの訪問者の来歴を並べられて、ふたつ目の要素で推測が確信に変わる。「知り合いだったっけ?仕事仲間を案内するのに、そろそろ港に来ると思うよ」という彼の台詞が終わらないうちに、わたしの目は遠くから歩いてくるあのひとを見つけてしまった。
4年前、わたしがあのひとと共有した時間はそのほとんどをベッドの上で絡まり合うことに費やしていたから、しゃんと立っている姿を夢以外で見るのがむしろ新鮮に思える。来るなんて聞いていない、と思うけれど、その程度の関係性でしかないな、という自嘲も過る。いつもわたしはあのひとの乗る船の水脈に浮かぶ泡沫でしかない。偶然がわたしたちを結び付け、必然がわたしたちを引き離す。
仕事仲間として紹介されたのはわたしより10ほど年上の女性で、ざらりとした感触が一瞬心を撫でるけれど、努めてそこから意識を遠ざける。もう随分前に天命を悟ってしまっているようなあのひとは、今年知命を迎える。
なりゆきで一緒に海辺を歩くことになり、一通りの観光案内はできるようになっているわたしに、「立派になって」とあのひとは目を細めて笑う。その表情に教師の匂いを嗅ぎ取って、あのひとの4年を想像する。4年前あのひとがひたすらにやさしく毛繕いしつづけてくれた、この町へ来たばかりの不安だらけのわたしではもうないのだ。あのひとが信じた通り、わたしはこの町でたしかな生き甲斐を見出している。あのひとは寒い土地で、後進の若人たちを育てている。
仕事仲間の女性はこの町は初めてだそうで、些細なことにも前のめりに興味を持ってくれる明るい性格に、つい話が弾んでしまう。あのひとの日々が明るくあるといいな、と願うわたしの毛先を風が弄ぶ。女性が足元の貝殻に夢中になっている間、あのひとと会話をする自分の語尾がどうしようもなく甘く転びそうになるのを自覚し、港へ戻ったところでさらりと手を振った。あのひとは、第三者がいるところでは不穏な顔をしない。
***
数日後の昼下がり、宿の屋上でロング缶片手に海を見ていたら、通りから知人が手を振るので、上がってきて一緒に飲んでもらうことにする。お互いの近況や町の噂話を肴に小一時間盛り上がったところで、彼があのひとのことを「そういえば中のラウンジにいるんじゃないか」と言うので二人して探しに行ってみる。果たしてあのひとは窓際の席でキーボードを叩いていたけれど、わたしたちが声をかけると目を細めてPCを畳み、「俺も酒を買ってくるか」と腰を上げた。
お酒の許容量は多いわりにすぐ頬を赤くするあのひとは、作業をしながら既に飲み始めていたようだった。飲み終えた缶をまとめて捨てに行こうと立ち上がると、「ほら」とあのひとに財布を渡されて、いそいそと3人分のお酒を買い込んで戻ってくるわたしに、あのひとはまた目を細める。傾きかけた夕陽とアルコールがあのころのようにあのひとの横顔を染めていて、胸が跳ねる。この季節には珍しいくらいの晴天なのに、耳の奥で雨音が鳴っている。知人が席を外したときに、「そのフリース、まだ着てたのか」と、ワントーン甘くなったあのひとの声が鼓膜を濡らす。
随分話が弾んでしまったけれど、夜も更けたころに知人が辞して、ラウンジの扉が閉まると空気の湿度が上がる。ふたりになった瞬間漏れてくる甘い気配を、ずるい、と思う。「元気そうで安心した」とあのひとがわたしの頭を撫でる。港で再会した瞬間から、その横顔を見ている間じゅう触れられたかった。触れられてしまったから、「一緒に寝たいです」は言わされたようなものだった。けれど、それに対して一縷の躊躇いもなく「そうか」と笑われてしまってどうしようもなく安堵する。すこし困った顔くらいはされるかと思っていた。
わたしたちはいつも狭い部屋で抱き合っている。一度自室に寄ってからわたしの部屋の戸を叩いたあのひとは、まるであのころの続きのように自然にわたしに触れる。そういえばわたしよりも適切にわたしに触れる指だったな、と思う。4年間ときおり思い出したようにとりとめのない連絡を取る程度だったのに、いざ二人になってみるとなにも変わらずにあの雨の朝から始め直せるこういう男のことを、わたしはとても好きだ。あのひとが4年経ってもわたしへの触れかたを覚えていることがうれしい。わたしが4年経ってもあのひとのかたちを覚えていることがうれしい。あのひとがいまもちゃんと動物で、わたしはうれしい。
ラウンジで飲んでいたときは左手のシルバーをちゃんと見た覚えがあったのに、声を抑えきれなくなってきたあたりであのひとの指に舌を絡めてみたら、リングがないのに気づいた。男の左手の薬指のリングを回して遊ぶのが好きなので、4年前は随分やって笑われたような記憶がある。いまさらのような今夜の機微にあるのが、やさしさか欲か分からないしどちらでもいい。もう、懐いてしまったのだ。
薄い壁は隣の部屋の物音をほぼすべて拾うことをわたしたちは知っているので、わたしは無声音で喘ぎつづけ、あのひとの吐息がそこに絡まる。声を出せたほうが遥かに楽だった、と思う。身内に籠る熱を逃しきれないからついあのひとに縋りついてしまうけれど、抱きとめてくれた腕と胸はそのうち枷に変わるので、逃げられない焦燥感と受け止められている安堵感の間で感情がへんな跳ねかたをする。どんなに崩れてもいいと言って。どんなわたしでもいいと言って。どこへも行かせないと言って。どこへでも行けると言って。溶解していくわたしを尻目に、相変わらずあのひとの鼓動はすこしも速度を変えず、ただわたしが喘ぎを殺しながらしがみついたら息が早くなった。ねえまだわたしに欲情してくれていますか。
あのひとは相変わらず、わたしの前で我を忘れた男の顔をしない。たとえわたしが我を忘れた女の顔をしても。ただあのひとは、わたしの求めているものを求めた何倍もの丁寧さと誠実さとでもって提供しつづけてくれているだけだ。ほんとうは我を忘れられないわたしは、ただ与えられることに安住していていい。請えば与えられる幸福に、泣けそうになる。どこまでもgiverなあのひとと、どこまでもtakerなわたし。強請れば強請るだけ与えられるすべてを、与えられれば与えられるだけ受け止めて、強請らなくても雨のように柔らかく降り注ぐキスに、わたしは狂いそうに安堵している。あのひとはまだ、抱くときわたしをさん付けで呼ぶ。
我儘なわたしはそのうち、落とされるだけのキスでは足りなくなって、気づいたら自分から舌を差し出すように絡みついていた。おんなの愛しかたを知っている男は、わたしを自由にしてくれる。あのひとの前でわたしは、平生全力で武装しているはずのわたしの殻をあっさりと脱いで踏み越えてしまう。己の領域を出て、無防備なままのわたしであのひとに触れてほしくなってしまう。わたしのやわらかなところをぜんぶ差し出したくなってしまう。丁寧に丁寧に撫でてくれるのを覚えているから。風にも当てずに慈しんでくれると信じているから。わたしのいちばん幼くて甘くて我儘で傷つきやすいところを、今夜だけ受けとめてほしい。どうせ明日になればまたひとりで飛ばなければいけないのだから、あのひとの懐でだけは甘えん坊でいることを許してほしい。
舌を舐められ吸われたあげくにやわらかく歯を立てられて、ああ、うれしい、と思う。その愛咬を、わたしはちゃんとやさしさとして受け取ることができる。「指を折ってください」のいち類型として、「舌を噛んでください」と思っている。あのひとが与えてくれるものならぜんぶ受け止められる、と思う。
ここ数年で、物理的な痛みを愛する女を手近に置いたのだろうか。強めに苛まれた胸の先端がじんじんとあつい。逃げても逃げてもいちばんきもちのいいところを追ってくる指に苦しくなって背を向けたら、背中をなぞった指先がそのまま尾骶骨を越える。うしろまで濡らしきっているわたしをひとしきり慣らしてからゆっくりと指を埋め込んでくるので、わたしは違和感混じりの快感に喘ぎが止まらず、結局どこまでも舌を這わされて狂ってしまう。いちばん恥ずかしいところごと抱いてくるあのひとのやりかたは、わたしの脆い部分に覿面に沁みる。
肌を撫ぜられながら、あのひとがわたしを語ることばを聴いているのが好きだ。愛撫と会話とを寄せては返す波のように繰り返しながら、声のやわらかいひとだな、と思う。あのひとの肌はすこし薄くなったけれど、その下のわたしの好きな骨は変わらない。「甘えん坊なんだから、早く誰かにもらってもらえ」と笑っていたあのひとに従って、ちゃんと甘えられる相手を選んでいたらもっと違っていたのだろうか、などとくだらないことを考えているわたしに、「結婚では満たされなかったか」とあのひとは嘆息したけれど、そこに価値判断を1ミリも滲ませないところが好きだ。
「きみは不思議なひとだね」とふわりと零されて、自分がこの女のどこに惹かれたのかを辿って言語化しようとしてくれる男はいい男だ、と思う。しばらくして落とされた、「ああ、惹きつけられてしまうのは、どこにも帰属感がないところなのかな」というあのひとのわたし評がおそらく、「男が何人変わっても、この関係において雰囲気が変わらない」ということを含意しているのは薄々察している。根暗な根無草を、よくもいつもすくいあげてくれるものだと思う。染まらないということは変わらないということではないのだけれど、誰の色もなんの色も加えずに、あのひとの前でもっと透明になりたい。
「好きなもの以外をどんどん手放していく執着のなさもだな」と重ねられたけれど、あのひとのことはわたしなりに好きだしちゃんと執着しているのを、あのひとは気づいているのだろうか。はじめから手に入らないとわかっているものは、目の前にあるときだけ独り占めできればそれでいいから深追いはしないのだけれど、記憶の珠をいつまでも執念く舐っているのはわたしだ。極めつけに最後に「好きだよ」と微笑まれて、この執着に果てはない。その「好きだよ」を安いと思わないわたしは、やっぱりあのひとに父親を仮託しているのだろう。
人が能力を発揮したり自己肯定感を得たり癒されたりする「場」を作ることにフォーカスし注力する人間は多くいるけれど、いつもどこか信用できなかったのはたぶん、当人自身がその場づくりによって自己肯定感を得ようとしているのが透けて見えていたからだった。そういう意味で、完成された自分のテリトリーに、「ここにいていいしここではなにをしてもいい」と招いてくれる、愛の総量の多い老成したひとに惹かれてしまうのはもうどうしようもない話で、そういう男に愛でられることが比較的多いのは単なる僥倖だ。そういう、20ほど年の離れた男を「いい男」と定義してしまうのがわたしの業なのだろう。あのひとにまで、「相変わらずのファザコンだな」と笑われてしまったけれど、こんな受け止めかたをされてしまえば仕方ないと思う。
甘やかして世話を焼いて抱きしめて。こんなわたしだから好きだと言って。人生を支える言葉を吐いて。
4年前、波打ち際にはぐれた渡り鳥をすくいあげて空にかえしてくれたその手で、髪の毛の先から足の爪先まで丹念に羽繕いをして、またわたしを飛ばせてほしい、などと思っていたら去り際に、昼近くなってもまだ裸のわたしの爪先から額まで順にキスを落とされて、なにも言えなくなってしまった。どうしてあのひとはいつも、わたしのほしいものをくれるのだろう。
あのひとは、甘えたがりのわたしの扱いがどこまでも巧い。生牡蠣の取り扱いが上手な相手の手にかかれば、わたしだって柔らかくひらかれて在れるのだと、あのころ気づけたのを幸せなことだと思っていた。でも、あのひとの前なら素直になれると分かったところで、あのひとの前でしか素直になれない。あのひと以上の「父親」を、わたしはまだ見つけられない。普段窓を閉めていると息苦しいとさえ感じる空間が、あのひとが隣にいる間だけ酸素に満ちて、あのひとが隣からいなくなった瞬間また酸欠に戻った。
でもわたしには、4年前のあのひとの瞳の奥の昏い感情が、もう見えない。「俺は変わったか」という問いに否と答えてしまったのは、あれは、嘘だった。今のあのひとはただわたしを愛でて慈しむだけで、もうわたしをなにかの器にしようとしない。それが諦念なのか、もう満たされてしまったのかは問えなかった。あのひとの溢れるほどの父性が行くあてを見つけたのであれば、いびつに誰かに向かわないのであれば、それはたぶん言祝ぐべきことなのだった。
ときおりあのひとの髪を梳こうとするわたしをあのひとは笑ったけれど、髪に触れるのが好きなのではなくて、ほんとうは頭を抱きしめたいのだ。からだに腕を回したらどうしても、わたしが支えてほしがっている構図になってしまうから、だから頭に触れたいのだ。与えてくれた分など到底返せないけれど、それでもなにかを返したいのだ。母性の持ち合わせはないと前から言っているけれど、あなたの傷ごと受け止めていたいのだ。甘く包んであげたいのだ。根拠のない「大丈夫だよ」を言ってあげたいのだ。わたしの「好き」に価値などないから言えないけれど。
4年前のあのひとがわたしに、「変わらずにいてほしい」と言ってくれたのが嬉しかった。それはたぶん、一緒に過ごした時間をいとしんでくれているのが察せられたからだった。どこへでも行く女だけどここへ帰ってくるし、変わってしまう女だけどこの日々を覚えてる。それじゃだめですか。あのころのわたしはそう思っていた。あのあと北国生まれの男はフィールドを離れて滑らかな肌の白さを取り戻し、男が愛したのと同じ町を愛してしまったわたしはすっかり肌を灼いてしまったけれど、結局いびつさを捨てられないのはわたしのほうで、あのひとのどこまでも甘やかな腕の中でだけ、わたしはやわらかくほころんだ咲きたての薔薇でいられる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
