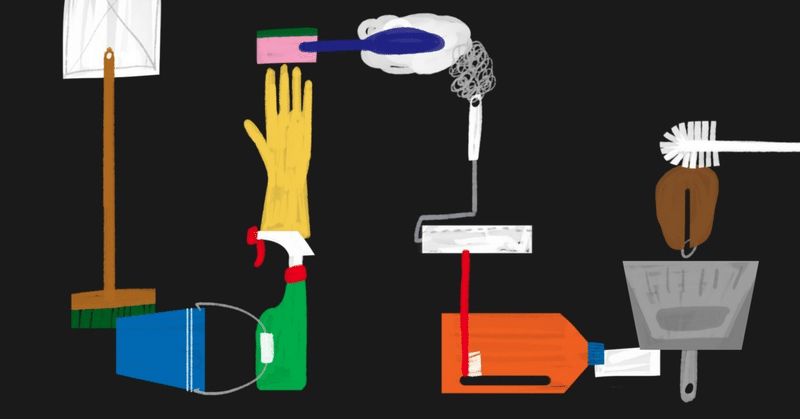
14. 掃除屋の大掃除. 仕組みを責めて人を責めず
【2024.5.20】
掃除はトヨタを徹底的にパクる。
今回もお世話になりました『トヨタ仕事の基本大全』((株)OJTソリューションズ, 2015)。
今日から大掛かりな倉庫整理を開始した。
倉庫整理改めて、「手放し会」の要点は以下の通り。
前段階:仕組みを責めて人を責めず
手放す= 基準に基づいて今必要なものとそうでないものを分ける
ものの住所を決める
ものの住所は使う人が決める
川上から川下へ
習慣づくり
※本記事は4番までを紹介
仕組みを責めて人を責めず
掃除をするにあたって1番大事なことは、キレイにすることそのものではなく、キレイな状態を保つことである。
そして、そのキレイを保つのは、誰か?
当然、使う人である。
しかし、「この人はキレイに使う」「あの人は散らかす」と、属人的になっては掃除の意味がない。
そして私が向かいあった倉庫の課題はまさに、
「◯◯さんは片付けが苦手だからね」という社内共通認識であった。
当のご本人も倉庫整理の話題を向けると、私の話が終わらないうちに、
「自分が片付けができないから…すみません…」
という調子。
そこで私がはじめに取り掛かったのは、
説得である。
便宜的に〇〇さんとしよう。
〇〇さんと話すために、わざわざ現場に同行させてもらい、車の中で繰り返し伝えた。
「片付けが出来ないことを責めるのは間違ってる。〇〇さんが片付けが苦手なことは問題ではないんです!片付けが出来ないことを承知の上で、一緒に片付けられるような仕組みがないことが問題なんです」
〇〇さんから拍手喝采。
その通りだよ!と賛同してもらえた。
こうして〇〇さんは、倉庫整理第一回における最強パートナーとなる。
手放す= 基準に基づいて今必要なものとそうでないものを分ける
「いつか、誰かが使うかもしれないから」捨てずにとっておいてあるものが大量にあった。
ここもトヨタから、「捨てる基準」を持つことにした。
あえて「捨てる」ではなく「手放す」にしたのには理由がある。
抵抗感を減らすためである。
実際に、基準作りを進めていく中で、
今は使わないけど、
「他の営業所で使えるかもしれない」
「売れるかもしれない」、などなど
意見が出た。
そして、「使えるのに、使わないから捨てるのは悔しい」という声もあった。
倉庫整理は、決して一人で進められるものではない。
関わる方々の合意も、人手としての協力も欠かせない。
そこで、
「今、ここにいる人が使う」or「使う予定がない」=手放す
と、設定していくことで
「いつ使うん?いらんやろ、捨てる!」と、ぶった斬ることはせずとも、確実に倉庫整理が進むように工夫してみた。
ただ事前に「手放す基準」を場合分けして作り込んでいたはずだったが…
実際に今日の倉庫整理一回目をやってみると、
「ときめくか、ときめかないか?3秒でときめかなかったら捨てる!」
のノリで分類していった。
基準に照らしていちいち検証するより遥かに効率良く片付けが進んだ。
ものの住所を決める。使う人が住所を決める。
どこに、何を置くか。
それがものの住所である。
住所を守って物を出し入れすれば、理論上はキレイな状態が保たれる。
ということで、手放すものと残す物を分けたところで、住所を決めていった。
図らずも、現場の方々が率先して場所を決め、置き方のルールを話し合って並べて直してくれた。
これこそ、目指していた流れではないか。
素直に嬉しかった。
「掃除屋」の役割は、片付けそのものというより、そのための仕組み作り。
つまりは、片付けに向けた道筋を作ることである。
道筋のその先が、現場の人の手によって繋がった気がした。
嬉しさのあまりに思わず、議論をリードしてくださった方に、
「私、……△△さんと出会えてよかったです!!」
と、ボキャブラリーの瞬発力が皆無な発言を、精一杯の感謝を込めて投げつけてしまった。
シェア生活を発信することで、寂しさを抱えている人々へ一つのヒントを渡せたらとの思いで執筆しております。この社会の片隅を、一緒にちょっとだけ明るくしていただける方はぜひサポートをお願いします。
