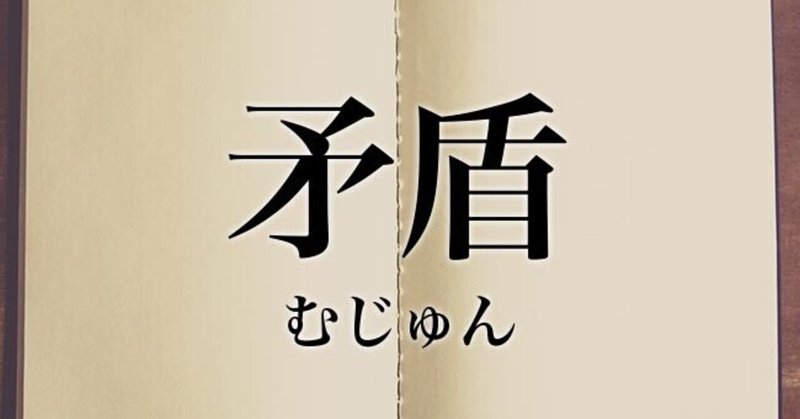
ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣
新しいことを始めてもなかなか続かない。コロナで空いた時間を使って勉強しようにも3日で終わる、
自分もその一人であり、この本を手に取って何かしたらの解決策を見いだせないかと思い読んだ。
最初は個人の習慣化の仕組みを学ぶために読んたが、読み進めてみると思ったより奥深い。個人でもチームでも社会でも「習慣」はただ行動をどうやって仕組み化するか。だと考えていたが、「習慣」はアイデンティティーや信念を体現する方法であると。
習慣を変えるのはなぜ難しいのか
「もし毎日1%よくなったら、1年後には37倍良くなるだろう」。今成功しているか、そうでないかは問題ではない。重要なのは、習慣が自分を成功へと導いているかどうかである。現在の結果よりも、現在の軌道にもっと関心を持つべきだ。P27
大きなことはすべて小さなことから始まる。あらゆる習慣の種は、たったひとつの小さな決断だ。だがその決断が繰りかえされると、習慣は芽を出して力強く成長する。P33
これらの言葉をよく聞く。頭では分かっているが、人はそんな簡単に変われる訳でないというのが私自身思うことで、上手く進められない。
ではどうしたら良いのか。まずなぜ習慣を変えるのが難しいのか。この本には、その2つ理由が書いてある。
➀変えようとするものが間違っている。
➁習慣を変えるための方法が間違っている。
この2つは一体どういうことか。
結果ベースの習慣の罠

図の通り、行動変化には3つの層があるという。
結果(成果)を変えるために目標設定をする。または結果を出すためのプロセスに注目し、仕組みと習慣の変化にフォーカスをする。結果ベースの習慣は何を達成したいかを意識する。これが普通だと考えていた。
自分もここまではやったことがある。しかし、上手くいかなかった。なぜ上手くいかなかったのか。この本によると変えようとするものが間違っている、というのだ。
では、どうすれば良いか。ここがかなり肝だが、それは自分がどうなりたいかという「アイデンティティ―ベースの習慣」に意識を向けることが重要というのだ。
習慣が大切なのは、なりたいタイプの人になるのに役立つからだ。習慣は、自分についての深い信念を育てるための手段である。P55
まず、どうなりたいかを考える。これは個人だけでなく組織にもいえる。どういう組織にしたいか考える。そして組織の習慣が体現されることでコミュニティの色を創る。どちらかが大事とかではなく、この双方向性が大事というだろうか。
とはいえ、「なりたい姿」を考え、アイデンティティ―ベースの習慣を決めたところで、どう実行していくのか。ここが決まっていても上手くいかないパターンは➁の状態に陥っている可能性が高いようだ。
習慣ループ
習慣のステップは下記の図のように、4つのステップに分けることができる。

習慣ステップが循環するように仕組み化する。具体的には以下の行動変化の法則を習慣化したい行動に組み込む。
■行動変化の法則
1、はっきりさせる
いつ、どこで、何をを明確にする。
2、魅力的にする
報酬の実現ではなく、報酬への期待。したい行動とする必要のある行動を抱き合わせる。
3、易しくする
2分以内でできるものにする。
4、満足できるものにする
即時報酬の設定をする
加えて、良い習慣に伴う抵抗を減らそう。抵抗が小さいとき、習慣は易しくなる。習慣の記録をつけることで満足度があがる。
プロはスケジュールを守る。アマチュアは生活に邪魔されてしまう。プロは何が自分にとって大事かを知っていて、目的意識をもって取り組む。P264
優れた人になる唯一の方法は、同じことの繰り返しに、いつまでも魅了されることだ。退屈に恋をしなければならない。P265
プロとアマチュアの違いは、自らが繰り返しの行動に対して楽しむために考え改善し、成長し続けること。そしてもう1つ、自分に合う習慣を選択すること。※中長期的に、探索の時間を作ることが大事。
この本では、達人とは「永遠の初心者」である、という。常に空っぽの状態であること。ものごとを新しい視点で捉え、好奇心を持って楽しむことが、大きな差を生む。
まとめ
・アイデンティティベースの習慣を形成し、習慣ループで行動変化を促す。そして同じことの繰り返しに魅了され、退屈に恋をする。小さくて持続可能でたゆむことのない改善への取り組みを続けることが、驚くべき成果を生み出すことができる。そのためには「永遠の初心者」であること。
・情報がすぐに手に入れられる時代になり、コンテンツも今まで以上に身近なものになった。誰もがクライマックスをすぐに求めるようになったこの時代に、常に空っぽの状態で目の前のことに向き合い楽しむことが大事。
・個人の習慣に対してだけではなく、顧客に価値提供する際もこの習慣を形成する行動変化のプロセスは転用可能と考える。いかに習慣ループに顧客を巻き込むか設計してみる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
