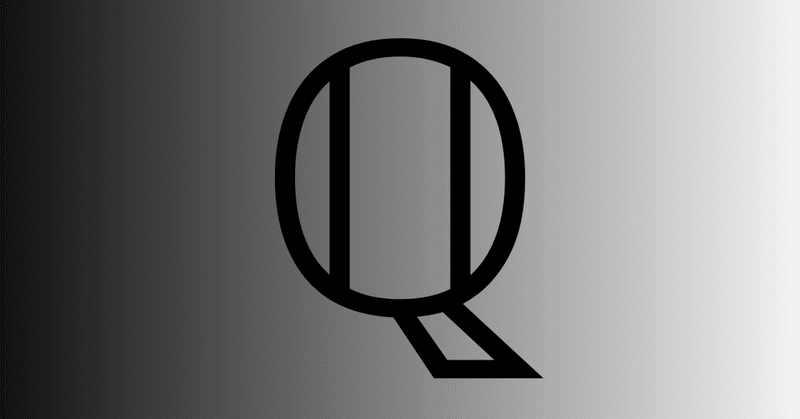
【漫画原作】「Q」第一話(「週刊少年マガジン原作大賞」応募作品)
【第一話】
(プロローグ)
この国には、八百万の神が住んでいる。
神たちはどこから生まれ、いつ人の前から姿を消してしまったのか。
今となっては知る由もない。
だが、実はその姿は見えないだけで、今もどこかで、新たな存在が生まれようとしている。のかもしれない──。
1. 啓太の家
今朝もいい天気だ。
啓太は朝五時に目を覚ますと、いつものように仏壇に手を合わせてから掃除を始めた。
昭和後期に建てられた木造建ての一軒家は、ところどころ傷みも出ているが、毎日床や柱を丁寧に拭き、畳の目に沿って塵を箒で払ってしまえば、朝を気持ちよく迎えるに何の不足もない。
こぢんまりとした二階建ての家は、啓太と姉の奈結葉がふたりで済むには十分で、丸石が五つ置かれているだけの玄関前の小さな庭も、毎朝やってくる三毛猫に餌をやるのにちょうど良い広さだった。
「Q!」
玄関前の掃き掃除を終えた啓太がその名を呼ぶと、どこからともなく「それ」は現れた。
家の中からぴょんぴょん飛び跳ねてやってきた「それ」は、啓太の肩の上を飛び越えて、啓太が庭先で掃き集めた朽ちた葉や花、土埃などが混じった小さな山に向かっていく。
「よし、食べていいぞ」
啓太の拳ほどの大きさの丸い「それ」は、啓太の掛け声とともに大きく口を開け、ゴミの山とその上で蠢く何かを一口で飲み込んだ。
「キューー!」
「そうか、うまいか。それにしても、お前がいるとエコだよな。ゴミも出ないし、それに何だか家もスッキリするし」
啓太に頭を撫でられ褒められると、「Q」は更に高い声で「キュー」と鳴いた。
(啓太の回想)
Qが現れたのは、俺が小学五年生の時。父さんが死んで暫く経った頃のことだ。
この家に現れたQは、姉の奈結葉が社会人になるまで預けられていた親戚の家にもついてきて、いつも「キュー、キュー」と子猫のような声で鳴いていた。
いつも鳴いているから、おじさんやおばさんに叱られるのではないかと怯えていたが、Qの姿を見ることができたのは俺だけで、Qと話しているのを見られた時には、「父親を亡くしておかしくなったんじゃ」なんて陰で囁かれた。
おじさんの家には、時々変なものが現れる。
居間の部屋の隅に、玄関の靴箱の下に、おばさんがよく長電話する黒電話に、「あれ」はいた。
おじさんもおばさんも「あれ」がいることに気がつかない。
俺も暫くは放っておいたが、掃除を習慣にしていた父さんの真似をして箒や雑巾で掃除を始めると、「あれ」を消したり、掴んだりすることはできないが、なぜか一か所に集めることだけができることだけは分かった。
部屋の隅で、電話の上で、もじゃもじゃと蠢くそれを集めると、Qは嬉しそうに鳴く。
ある日、冗談で「食べられるなら、食べていいぞ」と言うと、Qは本当にそれを飲み込んでしまった。
手のひらに乗るほどの大きさの球体だったQから、尻尾のようなものが生えたのは、この時だ。
見た目が球体で、アルファベットのQに似ている。俺はこいつを「Q」と名付けた。
―――
「ん-! 今日も、気持ちいい朝だー!」
啓太が振り返ると、スーツ姿の奈結葉が腕を高く上げて伸びをしている。
「なゆ、へそ見えてる」
「え! 嘘!」
「うそ。でも、スカートのファスナー開いてんぞ」
「ぎゃ! ほんとだ」
「ったく、気をつけろよな。そういうの、速攻、痴漢に狙われるぞ」
「はいはい。いつも心配ありがとうね。弟がきれい好きのしっかり者で、お姉さんは安心して働きに行けますよ」
奈結葉は少し踵を上げて、背の高い啓太の髪を片手でぐしゃぐしゃに搔き乱した。
「うざ! さっさと行けよ」
「じゃね、ケイ。朝ごはん、ちゃんと食べてくのよ。あ、あと牛乳もコップ一杯ね!」
玄関門に手を掛けた奈結葉は、長い髪をなびかせて振り返ると、啓太にびしっと人差し指をさす。
「……わかったよ!」
啓太の代りにQが奈結葉に向かってぴょんぴょん跳ねて見送ると、それを知ってか知らずか、奈結葉は笑顔で手を振ってから「いってきまーす」といって出かけて行った。
奈結葉と入れ替わるように、三毛猫が玄関の門の下をくぐってやって来た。
「お、今日も来たか。ちょっと待ってろ」
台所に向かうと、平皿に猫用の牛乳を注ぐ。
啓太は少しの間、その牛乳パックを見つめると、冷蔵庫から人間用の牛乳パックを取り出し、ガラスのカップに並々注ぐと一気にそれを飲み干した。
牛乳は苦手だが、奈結葉の言うことにはどうも逆らえない。黙っていても、すぐにばれてしまう気がした。
牛乳の入った平皿を持って玄関口に向かうと、Qは猫とじゃれ合いながら尻尾を振っている。
猫にはQが見えるのだろうか、と思い尋ねてみたが、案の定、返事は「みゃー」で残念ながら何と答えたのかは分からない。
皿の中の牛乳を小さな舌で舐めている猫と、その真似をしようとしているQを眺めながら、奈結葉の作った鮭入りのお握りを片手にかぶりつくと、制服のズボンのポケットに入れていたスマートフォンが震えた。
奈結葉からのメッセージだ。
『さっき言い忘れたけど、今度の学校でも髪のことを何か言われたら、すぐに言いなさい。幼少期のアルバム持って、押しかけてやるんだから』
再びスマートフォンが振動する。
『小さい時のケイ、かわいすぎるから、あんたの担任に自慢してやる』
啓太は、生まれつき色素が薄い。
今のところ、これといって生活に支障が出ているわけではないが、学校という場ではいささか目立つ様で、おじさんの家から通っていた中学でも教師を始め、ちょっとガラの悪い上級生にまで、入学初日から「髪を染めてきた」だの、「カラーコンタクトに違いない」だの、言いがかりをつけられて面倒くさいことになった。
奈結葉と暮らし始めて、三か月。
今月から編入した高校では、今のところ容姿のことでは何も文句は言われていない。
まあ、わりと自由な校風ではあるし、それに、「どこかが変わった奴」なんて世の中には普通にごまんといるものだ。
2. 学校
「おっはよー! 府木くん! 今朝も絶好調だねえ!」
「はぁ……、朝からそんなテンション高いの、鼓くらいだよ」
廊下を歩いていると、後ろから走ってやって来て、背中を「ばしーん」と叩いて挨拶するのがクラスメイト・鼓李帆の毎朝の日課だ。
(啓太の回想)
李帆は、幼なじみだった。
父が死ぬ前、まだこっちの小学校に通い、家が近い子供同士が数人で遊んでいた頃。李帆は、近所の子供たちの中でも、俺と同い年で、小四から小五の途中まで同じクラスだった女の子だ。
だが、「幼なじみ」といっても、特別に仲が良かったわけではない。李帆は極端に人見知りで、遊ぶ場にやって来てもほとんど自分から話すことがなかったからだ。
「あれ? もしかして、府木……啓太君? 覚えてない? 私、李帆。鼓李帆だよ」
この高校に編入した初日、声を掛けてきた李帆を見ても、すぐにピンと来なかった。
相手の目を真っ直ぐ見つめる大きな瞳、金色に近い明るい色に染まった長い髪、他の女子と同じように短くしたスカート、どれも過去の李帆と重ならない。
だから、今も彼女は「幼なじみだった」、いや、「幼なじみだったらしい」くらいにしか思えない。
――
──と、そんな主人の複雑な心境とは裏腹に、今日も学校までついてきたQが、肩の上で李帆に会えた喜びの「舞」ならぬ「跳ね」を見せている。
(もちろん、李帆には見えないのだが。)
Qは奈結葉や李帆、女子が好きだ。
「もしかして、女子と会うために俺にいつもついてんのか?」
小声でそう言うと、Qは「キュー」と小さく鳴く。「そんなことない」と言っているような気がした。
「じゃ、飯の方だな」
「飯」と聞いたQは、一度高く鳴いてから、突然、教室へと一目散に走っていった。
「おい、ちょっと!」
「え、何?」
ちょうど教室の扉に手を掛けていた李帆がこちらに振り向く。
李帆が開けた扉の隙間からQは教室に入り込み、そして、同時に教室の中から「良からぬ気配」が漏れ出てくるのを感じた。
思わず駆け寄り、扉を全開にする。
すると、教室の中には黒く暗い気配が充満していた。
「何だよ、これ……」
教室の中は、他愛もない話で笑い合う者、それとは関係なく勉強に集中する者など、生徒達はそれぞれいつもと変りなくホームルームまでの時間を過ごしている。
しかし、教室の隅々では、蛇のような、ミミズのような黒いものがいくつも群れを成し、ビチビチと身体をうねらせながら重い空気を生み出していた。
おじさんの家や今の家にいる「あれ」とは違う。こんなにも、はっきりとした姿は始めて見た。
そういえば、あの日、父さんが死ぬ前にも、こんな黒いものを左肩に見た気がする……。
「キュー!」
Qが黒いミミズを一匹、口にくわえて戻ってきた。「食べてもいいか」と聞いているようだ。
「ちょっと待ってろ」
Qを待たせると、すぐにゴミ箱と箒を両手に持ち、教室の中を颯爽と走り抜ける。
黒い「それら」をアルミ製の長方形のゴミ箱いっぱいに集めると、自分の学生鞄で蓋をしてから、すぐに焼却炉へと向かった。
「ちょっとー! 府木君! どうしたのー⁉」
李帆が何か叫んでいたが、必死で廊下を走っていて、何を言っていたのか聞き返す気にもならない。
とにかく、早くこの得体の知れないものを燃やしてしまわなければ。
この時は、なぜかそれしか考えられなかった。
ようやく焼却炉に辿り着き、炉の扉を開けると絶句した。
よく考えれば予想のついたことだが、朝の炉は火が消えており、昨日のゴミの燃えカスが炭となって横たわっているだけだった。
この冷え切った炉にゴミ箱の中身を放り込んだところで、事態は何も変わりそうにない。
「キュー! キュー!」
Qはいつの間にか追いついていたようで、「それら」が詰まったゴミ箱の上で飛び跳ねている。
「Q、おまえ、この量、食えるか?」
「キュキュー!」
Qは、「まかせとけ!」と自信満々に答えたようにも聞こえたが、いつも食べているのは庭先で集められるほどの僅かな「あれ」でしかない。
こんなはっきりした姿の、ゴミ箱いっぱいの量など、Qに食わせたことはないのだ。
腹でも壊さないか、はたまた、逆に「それら」にQが食われてしまうのではないかと心配だった。
「おや、府木くんじゃないか」
その時、背後で名前を呼ぶ声がした。
振り返ると、そこに立っていたのは、担任教師の日山柊司だ。
三十歳ほどの細身の優男は、物腰柔らかく、誰に対しても害を与えない善人のような顔をしている。
だが、その表情が不自然に思えて、時々、警戒したくなることもあった。
「どうしたんだい? もうすぐホームルームが始まるよ」
「いや、別にどうってわけじゃ……」
その時、背中側で強風が吹いた。
何を考えているのか分からない日山の瞳に気をとられ、一体何が起こったのか確認することはできなかったが、突然、何かが噴き出したような気がした。
そして、すぐさま別の大きな何かが現れて、噴き出したものを鯨のように丸のみにしたような……。
実際には何も見てはいないが、ただ、そんなことが起こったようなイメージだけが頭に浮かんだ。
「カラン、カラン」と、アルミ製のゴミ箱が地面に転がる音がして振り向くと、横たわった空のゴミ箱の上でQが「キュー」と不思議そうに鳴いた。
「何もないなら、教室に戻りましょうか」
日山は笑顔を崩さず、教室に向かうよう催促した。
3. 八尾鈴子の家
──ピンポーン。
放課後、なぜかクラスメイト・八尾鈴子の家のインターホンを押すことになっていた。
(啓太の回想)
「いやぁ、八尾鈴子君が一週間ほど学校に来てくれなくてねぇ。府木くん、確か、まだちゃんと彼女に挨拶してないでしょう。今日の放課後、挨拶ついでに、今週の宿題と授業のノートを届けてあげてください。ね」
「いや、俺、帰……」
「今朝、教室の掃除を府木君がしてくれたって聞きましたよ。うちのクラスの子たちは面倒くさがりで、これまで鈴子君が仕上げをして清潔を保てていたようなものだから、彼女が休んだ途端に散らかってしまっていたんです。本当に助かりました。きっと、ふたりは綺麗好き同士、話も合うと思うんだよ。先生は」
「別に、どうでもい……」
「あとね、これ、クラスの子が家庭科実習で焼いたパンなんだって。優しいよねぇ。食べたら学校に来る気になるかもしれないし、ちゃんと渡してあげてくださいね。じゃあ、後はよろしく」
「ちょっ……!」
こちらの言い分に全く耳を貸さず、日山は宿題やノート、それに透明な袋に入ったロールパン(丁寧にリボンまでついている)が詰め込まれた紙袋を押し付けた。
笑みだけを残して、日山は職員会議に向かってしまう。
「住所も知らねえし……」
そう呟いたら、スマートフォンに日山から八尾鈴子の家のマップが添付されたメッセージが入ってきた。
八尾鈴子。直接話したことはないが、確か、李帆と仲が良かったか。
それなら李帆に任せれば……。とも思ったが、すぐに外へと足が向いてしまったのは、渡されたパンの温もりを紙袋越しに感じ、冷めてしまうと「もったいない」と不覚にも思ってしまったからなのかもしれない。
――
「折角来てくれたのに、ごめんなさいね。鈴子―! クラスのお友達がお見舞いに来てくれたわよ。顔くらい、見せなさいー!」
鈴子の母が、一階から二階の彼女の部屋に向かって呼びかける。
鈴子の母は、専業主婦なのだろう。通されたリビングは、カーテンやテーブルクロスなどの装飾が淡い風合いの花柄と白いレースで統一されており、丁寧に編まれたパッチワークのソファーカバーなど、手づくりの品で溢れていた。
「お構いなく」
と遠慮したにも関わらず、焼きたてのクッキーやマフィンなどの菓子がテーブルを埋めていく。
その品数は、来客があることを前もって知っていたのかと錯覚するほどだった。
こんなにも甘い匂いのする家は初めてで、変な心地がする。
Qも初めて見る菓子の数々に興奮気味で、テーブルの上を駆け回り、くんくんと匂いを確かめていた。
「あの、俺、宿題と、あと、クラスの奴が焼いたパンを持ってきただけなんで、ほんとお構いなくというか……」
「あら、ごめんなさいね。男の子が来てくれたのなんて、初めてだから、嬉しくなっちゃって。……もしかして、鈴子と仲良くしてくれてるの?」
「いや、俺、今月、編入してきたばっかなんで、挨拶もちゃんとしてないっていうか……」
「そうなの。でも、来てくれて嬉しいわ。たくさんお菓子を焼いたから、遠慮しないでどんどん食べて」
「や、あの……」
鈴子の母は、ティーカップと同じ花柄の俺の目の前にある小皿に、トングで菓子を次々と運んでいく。
こんな時、どうやって断ればいいのか。
「母親」というものにどう接すればよいのか、当たり前のスキルを持ち合わせていないことに今更気がついた。
「あんた……、誰?」
その時、扉の隙間からリビングを覗き込んでいる人影があった。
「鈴子、いるなら『いる』ってちゃんと言いなさい!」
「ママ! そいつ誰なの!? 若い男、連れ込むなんて、サイテー!」
「何言ってるの! あなたのお見舞いに来てくれた、クラスメイトの府木君でしょ!」
「ふき……? うちのクラス? 本当に……?」
扉を開けて入ってきた鈴子は、長い黒髪を下ろしたパジャマ姿のままだ。
自分の身なりのことなど全く気にせず、ずかずかと歩いてくると、急に啓太に顔を近づけた。
「……よく見ると、悪くないわね」
「……は?」
「ちょっと来て!」
鈴子に腕を引っ張られ、無理やり二階の部屋へと連れていかれる。
Qは新たな女子に会えて嬉しいのか、引かれていく啓太の足元で何度も高く飛び跳ねていた。
「府木くーん! 鈴子に襲われたら、すぐに助けを呼ぶのよー!」
一階から、そんな鈴子の母の叫びが僅かに聞こえた。
「ったく、何なんだよ!」
鈴子の部屋の前で腕を振り払うと、力が強すぎたのか、鈴子は両手で顔を覆い「ううっ……」と泣き始めたように見えた。
「あ、わりぃ……」
ひるんだ刹那、鈴子は再び啓太の腕を思い切り引っ張り、自分の部屋に連れ込むと、勢いよく扉を閉じた。
「さっきから、何すんだよ! 何か用があるなら、ちゃんと言葉で言え!」
「キャサリン! 見て! EIJIを連れて来たわよ!」
鈴子の目線の先を見ると、タコのように八つの足を持つ大きな黒い生き物が壁一面にへばりついている。
今朝、教室で見たものと似た気配をした……、いや、もっと重く、吐き気がしそうなほど嫌な気配のする「あれ」だった。
「何で、何でこんなところに、こんなでかいのがいるんだよ!」
啓太は鈴子に向かって怒鳴るが、鈴子は全く聞いていない。
「キャサリン! EIJIは引退なんかしないわ! ほら、ここまで会いに来てくれたわよ!」
鈴子の言葉に反応するように、タコのような生き物の目が啓太を捉えた。
しかし、求める人物と違うと分かると、啓太目がけて足を一本振り上げる。
標的から僅かに逸れた足は、「バシーン!」と大きな音を立て、鈴子の勉強机を真っ二つに割った。
「な、何なんだよ、これ‼」
「一緒に推してたバンドボーカルのEIJIが引退して、バンドが解散するってネットニュースを見た日から、急に大きくなって暴れ出しちゃったの! 私だって、キャサリンがこんなことになるなんて、思ってもみなかったのよ! あんたがEIJIにちっとも似てないから余計に怒っちゃったじゃない! どうしてくれるのよー!」
「知るか! そっちが勝手に俺を連れて来たんだろ!」
二人が言い争っている間にも、タコのような生き物は不機嫌そうに何度も足を振り上げて、辺りに当たり散らしている。
「キューッ!」
その時、Qが突然タコの足に嚙みついた。
Qが足の一部をかじり取ると、そこだけが空白になり、タコのような生き物は怒り狂ったようにQを叩き潰そうと襲い始める。
「Q!」
Qはちょこまかと逃げ回りながら、タコ足にかじりつき、やがて一本の足を地に落とすことに成功した。
しかし、Qは腹いっぱいになったのか、突然動きを止めて、その場で眠り始めてしまう。
タコ足は、すかさずQを足で巻き取り、きつくQを締め上げた。
「Q! 起きろ! そいつから逃げろ!」
啓太はQの捕まったタコ足を何とかしようとするが、相手の物理的な攻撃は当たるのに、こちらは何の手ごたえもなく空を掴むだけだった。
「一体、どうなってんだよ!」
タコ足に叩かれ、傷を負いながらも、何とかQを取り戻そうとひたすら藻掻いていると、どこからか鈴の音が聞こえた。
「……やれやれ。できれば、邪魔はしたくなかったんだけどねぇ」
どこかで聞いたような男の声。
声のした方を見ると、知らない美形の男がいつの間にかそこに立っていた。
艶やかな長い黒髪をしているが、瞳は金色に光っており、なぜか和装をしている。
男が近づくと、暫く暴れていたタコのような生き物はガタガタと震え出す。
「君は少々暴れ過ぎだ。また一から出直しておいで」
やがて、男が右手で触れると黒い姿はさらさらと砂のように消えた。
「キャサリーン‼」
鈴子は、黒いものが消えた辺りに向かって駆け寄る。
タコのようなものが消えると、部屋の窓から夕日が差し込み、荒れ果てた様を映し出した。
「キューー!!」
Qが啓太目がけて大きく飛び跳ねてきたので、啓太は両掌でキャッチする。
「Q! 大丈夫か⁉」
Qに傷がないか隅々まで確認していると、男の足元が視界に入った。
顔を上げると、男はにこっと笑って、丸いフレームの見覚えのある眼鏡を掛ける。
すると、男は担任教師の日山の姿となった。
「改めまして、こんばんは。僕は君の担任教師で、『神様』です。これからどうぞよろしく」
「……は?」
Qは日山の周りを跳ね回る。
どうやら、色んな意味でやばい高校に編入してしまったらしい。
(つづく)
🌟つづきは、こちらから↓
いつも応援ありがとうございます🌸 いただいたサポートは、今後の活動に役立てていきます。 現在の目標は、「小説を冊子にしてネット上で小説を読む機会の少ない方々に知ってもらう機会を作る!」ということです。 ☆アイコンイラストは、秋月林檎さんの作品です。
