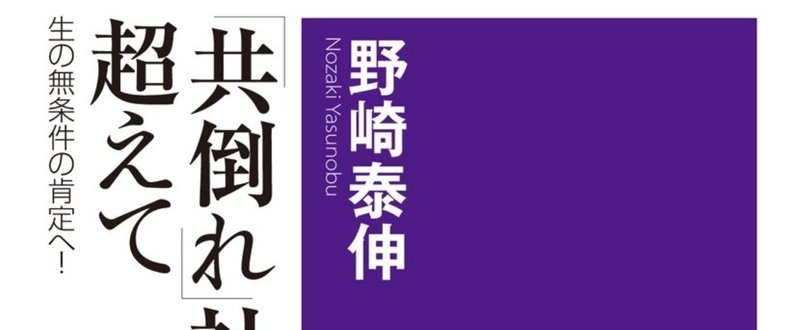
共倒れ社会を超えて
野崎泰伸著「共倒れ社会を超えて」を読みました。ちょっと難解でしたが、自分より他者が不幸であること、私はまだマシなんだと思う個人の思考のメカニズム、集団や社会の思考のメカニズムなど、知らないうちに他者を差別することで、現場の幸せや豊かさの均衡を保っている、そんなことを気付かせてくれる本でしたよ。もう一冊は、「 紙つなげ!彼らが本の紙を造っている-再生・日本製紙石巻工場」このドキュメンタリーが面白かった。 2011 年 3 月 11 日の津波に、工場も従業員もその家族、関係する大勢の人らが呑みこまれて、そこからの死力を尽くした再生の話しなんだけど、それよりも、いつも読んでいる本のルーツ、ぺらぺらと何気に捲っている紙の4割がこの石巻工場で作られていることに驚かされたのと、俺達が再生しないと出版社に紙が供給できない、するとお客さんにも本が届かなくなる。書店から4割の本が無くなることは想像出来ないですよね。そんな紙のアイデンティティに触れた一冊でした。さらにもう一冊は、時代剣客小説とでも呼びましょうか、好村兼一著「伊藤一刀斎」、時は戦国乱戦の頃、 20 歳で先の見えない貧困生活から脱出するために島抜けをして、 剣術修業の道を歩み 、愚直に一刀流開祖の信念を貫く生き方を描いた小説でした。日々の出来事から学び続けること、思い続けることの大切さが何度も何度も行間に描かれてましたよ。きっと、どの時代小説もそうなんでしょうけど、処世の術とその理屈を伝え説いてくれると思いますよ。水野晴郎じゃないけど、本って本当にいいもんですね。
20150505
ここで頂く幾ばくかの支援が、アマチュア雑文家になる為のモチベーションになります。
