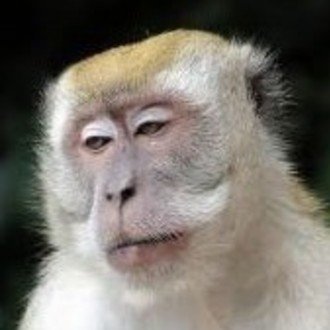日本国名の由来を追って#02/光武賜以印綬
中国側にどうやら「日本列島に有る国を指しているらしい」記述の初出は二つあります。
後漢のとき、光武帝代と安帝代に2回訪朝してきたという記述です。
建武中元二年(AD57)の項『建武中元二年、倭奴国奉貢朝賀、使人自稱大夫、倭国之極南界也、光武賜以印綬
建武中元二年、倭奴国貢を奉りて朝賀す、使人自ら大夫と称す、倭国の極めて南界なり、光武賜うに印綬を以てす』
建武中元二年(AD107)の項『安帝永初元年、倭国王帥升等獻生口百六十人、願請見
安帝永初元年、倭国王帥升等、生口百六十人を献じ、請見を願う』の二つです。
後漢書内の倭伝は、東夷伝の中に納められており、夫餘・挹婁・高句麗・東沃沮・濊・三韓が記述されています。その最後の部分で南海の倭国「邪馬台国と女王卑弥呼」について触れており、そして江南の海上に点在する島々の話で終わっています。
しかしこの南海の倭国の話は魏志内にある倭人伝からの引用で"伝"のさまを取るほどのものではない。
・・その魏志内に有る「倭人伝」ですが。これも実際に見てきた記録とは思えない矛盾が多々あります。おそらく幾つかあった「東海の島に有る国」の風聞を掻き集めて作られたというのが真実でしょう。当時の周辺国についての記録は、こうした風聞を集めて書かれたものが幾つも有りますので、そのひとつと見做すべきかと考えます。
したがって漢書に残されている「倭奴国奉貢朝賀」をもって、風伝ではなく史実の初出とすべきだと僕は思います。
さて。「光武賜以印綬」の一文ですが、福岡歴史博物館に収められている「漢委奴国王」金印について触れなければなりません。ぜひ以下ページをお読みください。
http://museum.city.fukuoka.jp/gold/
ここに収められている「漢委奴国王」が、後漢書にある「光武賜以印綬」なのか・・これは江戸時代から議論百出しておりまして定まっていません。「委奴国王」をどう読むかも定まっていない。確かに皇帝からの授与された印ならば"倭"に"委"の略字を使う訳はない。彼らは用字について極めて厳格だったからです。では「委奴国王」とは誰か?誰が「漢委奴国王」を何の目的で作ったかという大疑問にぶつかってしまいます。
その解釈は他の方に任せて「倭」→「大倭」→「大和」→「日本」の経緯を追って見たいと思います。
いいなと思ったら応援しよう!