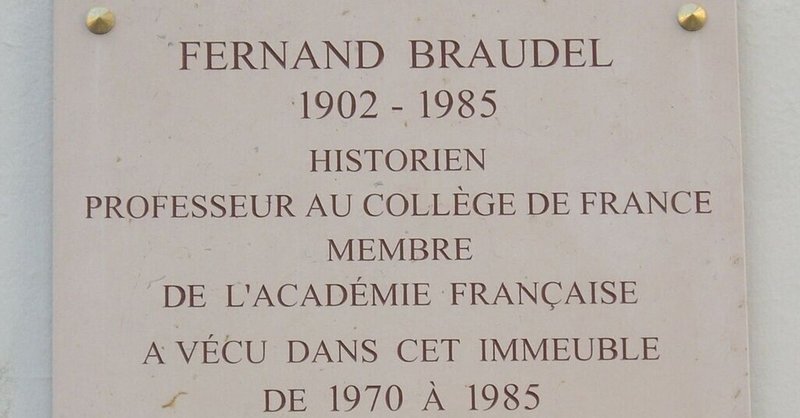
ブローデルの「長い16世紀」
水野和夫が、ブローデルの「長い16世紀」を現代に折り重ねている。
現代の長い金利ゼロ時代を「金利には5000年の歴史があるが、複数年にわたり長期金利が2%を下回ったのは過去一度しかない。中世から近代への移行期である1600年代の初め、イタリア・ジェノバでのことだ」と言う。
ブローデルの云う「長い16世紀」は、中世から近世に替わる長い迷動期をさす。
水野は言う「1453年ビザンツ帝国滅亡から、1648年ウェストファリア条約までと区分すれば、特に1517年ルターによる宗教改革の開始以降は、神聖ローマ帝国を主な舞台として、新教と旧教の争いからアウクスブルクの和議を経て、国際戦争に発展した三十年戦争、そして主権国家体制の確立に至る、まさに古い秩序が壊れて新しい秩序の基礎が固まる激動の時代」であると。
近世は、先の二つの大戦を経て現代となった。現代を象徴するのは、生産量の激増とコンピュータの登場だと僕は考えている。しかしその本性は大航海時代から続いているグローバリズム=植民地主義であり、修正ロマンティシズム(ローマ主義)である。際立った特徴は、労働の流動化による新しい"労働者"と言う階級の創出だ。これが19世紀以降の植民地主義を前世紀のそれと大きく替えてしまった。
加工輸入貿易が現代的な植民地主義として定常化すると、富は偏析すると同時に、労働の流動化によって労働者の数が飛躍的に増えて、生産コストに織り込まれる人件費が広く薄まったのである。つまり労働者が受け取る報酬が地域的偏りを起こさず、広く均等を目指して均されたのである。つまりそれは先進国の労働者の給与が激減することであり、開発国の労働者の給与が大きくなることである。
かくして先進国の労働者は貧しくなり、開発国の労働者は豊かになった。・・こう考えると。中国が豊かになった理由がよくわかるだろう。
もちろん、開発国が遍く豊かになるわけではない。すべての人々が、加工輸入貿易という名の植民地主義のもとに働くわけではないからだ。
ここ23年間で日本は先進国中唯一のGDP11%下落国になった。原因は相変わらず米国の植民地主義を受け容れたままの加工輸入貿易国で在り続けたからだ。
安倍政権/黒田BOJは、これを抜本的に変えようとした。それが金融緩和政策だった。云ってみれはフェークマネーである不換紙幣・円札を膨大に刷り、それを以てして海外の債券(主に米国の)を買いまくり、日本を海外投資型金融国に替えたのである。
しかし日本経済は、相変わらず救いようのないデフレスパイラルに陥ったままである。しかし海外投資型金融国にフェーズを替えた故に株価は上がり、不動産も上がった。
しかしデフレスパイラルである。経済的にひっ迫していくことで消費者が買い物を控えるようになり、結果売れなくなったモノの価格は下落し、それを製造販売している生産者に倒産やリストラなどが起こり、失業者が街に溢れかえってきた。
安倍政権/黒田BOJの「海外投資型金融国」に日本国を替えた英断は画期的だったが、総論良し各論悪しなところがとても日本的官僚的な瑕疵である。
「海外投資型金融国」にシフトチェンジすれば、間違いなくより富は偏析する。それを予期した法整備を安倍政権は怠った。
現在、日本国が陥っているマイナススパイラルは、政権の怠慢が原因である。そう断言できる。
菅政権あるいは次政権が行うべきは・・
①正規雇用の拡大と賃上げ誘導である。労働分配率の上昇を実現するための法整備である。
②生活必需品については細かな軽減税率を採用し民の生活を守る。
③税は、より累進性を高める。そのことで所得再分配機能を高機能化させることである・・と僕は思う。
つまり一時的にでも、日本的社会主義を補強することでしか、この危機は乗り越えられないのではないか?そう考えてしまう。
無くてもいいような話ばかりなんですが・・知ってると少しはタメになるようなことを綴ってみました
