キング・オブ・ラテン・ソウル、ソウル・ブラザー、アワ・マン・イン・トーキョー~チカーノ・ソウルの世界に近づくためのサブ・テキスト
これまで2回、宮田 信氏のインタビュー (映画『アワ・マン・イン・トーキョー』上映時と、エル・ハル・クロイ来日企画)を行なった。とてもフランクな人柄で、まだ短いお付き合いであっても気軽に友人として接してくれる方だから、インタビューでもめちゃくちゃ面白い代わりに公にはできないような話まで聞かせてくれる。独特な語り口をテキストでどう再現するかには腐心した。その言葉はまるでチカーノたち、イーストL.A.への愛情が血液のように巡っていることを示すように、どこを切っても熱くあふれだす。マイノリティたちの想いまでをも背負うような宮田氏の心情がゆがむことなく、より多くの人に届くよう願った。
このテキストは近日中に公開する<『CHICANO SOUL』日本語版クラウドファンディング応援決起集会>でのトーク・ショーの書き起こしとあわせて、読んでいただきたい。諸事情により公開順序が入れ替わってしまったが、まずはこのテキストを宮田 信ファンによるラヴ・レター、ひとつの物語としてご覧いただければ嬉しい。(10月28日トーク・ショーのログを公開しました!)
10月9日、トーク・ショーが行われるジャズケイリンのカウンターに座るわたしは映画『デトロイト』のことを思い出していた。1967年のデトロイト暴動をテーマに、実際にその場で拷問を受けて生き残った女性がアドバイザーとしてこの作品に関わっている。演技だとわかっていても吐き気を催すような拷問シーンが続く重たい政治的な映画。そして素晴らしい音楽映画でもある。主人公のひとりが実在する黒人ヴォーカル・グループ、ドラマティックスのメンバーなので、本編中に歌うシーンがいくつかあり、そのすべてのシーンで大きく心が揺さぶられるのだ。未見の方はぜひ、観てほしい。また、映画のラストにはTHE ROOTSの「It Ain’t Fair」が流れる。映画館で聴いた時には切実な、怒りと哀しみの塊をくらった。俳優の素晴らしい演技に裏付けられたドキュメンタリー・タッチの作品にメッセージや告発だけに終わらせない“エンターテイメント”の魔法をかけたのは「It Ain’t Fair」をはじめとするサウンドトラックの力であることは間違いない。

わたしたち日本人もマイノリティであることに勘づいている人は、実は少ない。わたしは小さな多民族国家シンガポールでの短い海外生活で、日本列島を中心に配置した世界地図しか知らないことを自覚した。スシ、ゲイシャ、ニンジャにヤクザ、最近であればカワイイやハラジュク……。海外でも認知されてカタカナが共通語となるような文化であれば説明もできるが、実際に生活する者にとって“リアル”な日本の伝統や文化とはなんであろうか、当時とても悩んだ。華人、マレー、インドの人々が共生しようと暮らす国では自らのエスニシティに無頓着な民族の方が珍しいようにも感じた。他民族との対立など存在しないと目を背け、近代以降大小さまざまな方向転換をせざるを得なかった日本で成長したわたしにとって、伝統的な民族音楽を意識的に親の世代から引き継ぐという経験をする方がレア・ケース。チカーノたちの音楽的なバック・グラウンドとして、マリアッチやランチェーラをどう捉えるのか、チカーノ・ソウルを理解しようとする際に少々混乱したのはそのせいだ。子ども、親、祖父母の三世代とが共有する音楽があるということがイメージできなかったが、沖縄で育まれる琉球音楽と生活の関りを想像することは助けになった。いつか、どこかの国へ移民せざるを得ない日がこのままではやってくるかもしれない。その時わたしは日本での暮らしを知らない子どもたちに、何を伝えて引き継いでいくのだろうかということも最近はよく考えている。
60年代にチカーノたちが憧れたソウル・ミュージックの源流には人種間の対立がある。先住民であるインディアンを手始めに多くの民族や人種への差別とマイノリティからの抵抗を繰り返す国、アメリカ。カルチャーと政治はいつでも背中合わせ。無論、日本で起こっていることだって構造は同じだ。カルチャーに心を奪われたなら、多くの本や映画、音楽を通じてていねいに想像していくことは楽しく、一見無関係なようでも重要だ。たとえば映画『デトロイト』劇中では略奪から逃れるために、暴徒と化した者たちの“仲間”だというメッセージとして多くの車や商店には“SOUL BROTHER”とまるでタギングのようにペンキやスプレーで書かれていた。その場しのぎでしかない言葉は見破られていたが、抑圧されたマイノリティにとって他者から真に理解を示されることに意味があると映画のシーンが教えてくれる。
そんなことを思いながら聞いていたら、トークショーではDJ HOLIDAYからの質問をきっかけにウォーやマロのようにメンバーの人種がミックスしているグループの音楽でもチカーノたちが「意識として“自分たちの音楽だ”」と考えていたことが語られだした。チカーノたちから仲間として認められるとき、肌の色など関係ないのだ。また、アフロ・アメリカンとフィリピーノとの混血でありながら、多くのラティーノから“キング・オブ・ラテン・ソウル”と称されるジョー・バターン。日本人でありながら「猫の腐乱死体が乾くまで」バリオに通うことを止めない“アワ・マン・イン・トーキョー”こと宮田 信。このふたりはまるで名誉チカーノだ。真に愛すべきものを見出す嗅覚と他者を受け入れるおおらかさはチカーノ・ソウルという音楽の大きな魅力であり、背骨だ。
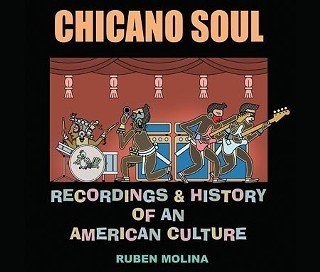
トーク・ショーでは70年代以降に活動していたエル・チカーノやティエラもトピックとなっていた。どちらも素晴らしいアルバムや曲を多数残しているが、スタイルにしか注目しない一部のリスナーやディガーにはいつぞやのチカーノ・ラップ・ブームと同様に「チカーノ・ソウルじゃない」と受け止められるかもしれない。60年代に数多く生まれた甘く切ないメロウなソウル・ミュージックとしてチカーノ・ソウルのスタイルのみを求めるのであれば、オールティーズとしての音楽メソッドを現代的な解釈で取り入れている新世代、ボビー・オローサやデリリアンズの方がより魅力的に感じられるだろう。若い世代がかつての音楽を発見し、継承している。しかしその一方で宮田氏はラティーノたちに愛されるミュージシャンとしてこの10月に女性マリアッチ・グループ、フロール・デ・トロアチェを招聘したばかりだ。さらにチカーノ・バットマンやエル・ハル・クロイたちのことをサポートし続けていることも忘れないでほしい。これも、今は60年代ではないのだから必然である。
『CHICANO SOUL』の著者であるルーベン・モリーナ氏とその日本語版タイトルの翻訳・出版を目指す宮田氏にとって“チカーノ・ソウル”という言葉は音楽的なメソッドやスタイルだけを指すものではない。伝統的なラテン音楽のマナーを背景に、カルチャーや人生から見出したフレイヴァー、異文化への憧憬をどん欲に取り入れたハイブリッドな音楽をチカーノたちが愛してきたという証だ。このことを知っていただければ『CHICANO SOUL』日本語版は単なるレア・ディスク・ガイドではなく、手に取った人のライフスタイルや思考へも大きな影響を与える、素晴らしい本へと姿を変える。
ぜひこのプロジェクトが成功して、ひとりでも多くの方の手許でこの本が末永く愛されますように。
(2019年10月 服部真由子)

