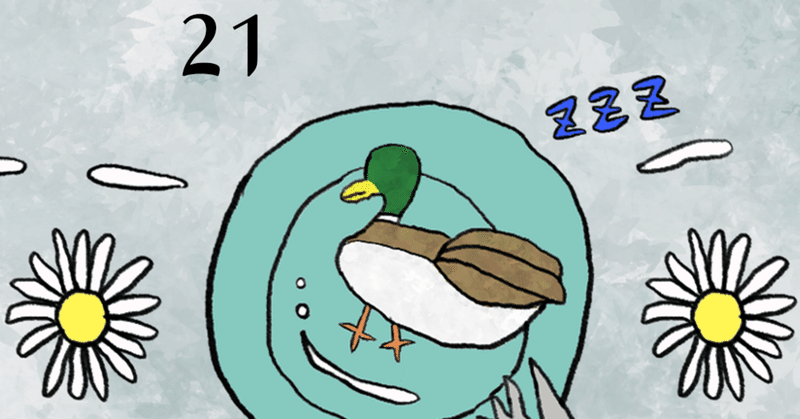
寝れるカモミール21
目的もなく歩く。歩きたいから歩く。休みたくなったら後ろに倒れれば、柔らかく暖かいものに包まれる。動きたくない、でも移動したい。口に出さずとも、その柔らかく暖かい何かが連れて行ってくれる。どこへ?どこへでも。どこにも行きたくない、ずっとここにいたい、だけどここじゃない。ごねたくてごねる、と、その何かは私をあやすようにゆったりと左右に揺れる。守れられている。そもそも多分ここに脅威は何もない。だけどそう思えるのは、きっと何かに守られているからだ。何に?なんでもいい。何かに、なぜ、守られているかなんて、ここでは考えなくていい気がする。
綺麗な明るい赤紫色の空が広がる。
ここの空はずっと私がいちばん好きな色だ。
泳ぎたいな。
気がつくと、オレンジの輪切りがグラスの縁に刺さったオレンジジュースを手に持って、ビーチチェアに寝そべっている。ストローから一口飲み込むと、つぶつぶの果肉が流れ込んでくる。ない方がいいな、と思えば、口の中
にあったはずの果肉はすぐ舌に溶けた。
落としても割れないグラスを放り投げ、目の前に広がる瑠璃色の海へ大股でずんずんと進む。生ぬるい水。少しも冷たくない。私が冷たさを求めていないから。
深く。さらに深く、潜っていくと、いつかみた一軒家があった。
ここにきたことがある。いつだったか、ついさっきのような気もするし、前世くらい遠い昔の記憶のような気もする。家の前に立つと、ちょうど家主らしき人が出てきた。
「入る?」
「あ、いいですか」
「もちろん、いつでも勝手に入っていいよ」
そう言って、その人はドアの前を私に譲った。
「留守を頼んでもいい?」
「あ、もちろん」
「ありがとう、すぐ帰ってくるよ、家の中のもの、なんでも好きにしていいから、食べるものも遊ぶものも、なんでもどうぞ」
そう言って、その人は私を残して家を離れた。
家の中に入ると、すぐ、キッチンがあった。身長と同じくらいの高さがある冷蔵庫のドア一面にいろんな種類の知恵の輪が貼り付けられている。その中のひとつを剥がして手にとると、3つの変な形の輪がつながっている。
ソファーに移動して挑戦するも、全くわからない。知恵の輪だと思ったけど、ただの繋がった輪なのかも。
「知恵の輪だよ」
3つの輪のうちの、真ん中の波を打ったような曲線を持った輪が話しかけてきた。
「バラバラになるってこと、ですか?」
「うん」
「でも、」
「知恵の輪だよ、知恵の輪、知恵使って知恵」
外れてほしいな。
知恵を絞ってそう思っても外れない、まあ、外れないならそれはそれで、諦めて冷蔵庫に戻そうとすると、真ん中の輪に止められる。
「あーまって、もうちょっと頑張ってくれない?」
「ちょっと無理そうです」
「そう言わずにもうちょっとだけ頑張ってよ、たまには1輪になりたいんだよ、もう左右の輪たちとずっと一緒だからさ」
「はあ」
「最初は4輪だったんだけどさ、1輪はすぐに外されて、それからずっと1輪生活らしい。うらやましい」
「そういうもんですか」
「ん?どういうもん?」
「なんか、1輪の方がいいみたいな」
「まあ、そりゃ輪によるだろうけど、ねえ、でも君も1人がいいんでしょ?」
「あ、え、そっか、私って1人ですか?」
「こっちからはそう感じるけど?」
1人、1人か、まあ1人か。なんでだろう。ここでは孤独を全く感じない。そもそもここに来る前、私は何者だったんだっけ。どこで何をしてたんだっけ。
「大丈夫?」
“ピーンポーン”
チャイムの音がする。ここは人の家だけど留守番をお願いされているってことは、出た方がいいのか。
「出た方がいいですよね?」
さっきまでお喋りだった輪に話しかけるも返事がない。
“ピーンポーン”
「ねえ、どうしよう、出たくないんだけど、出た方がいいですか?」
輪は何も言わない。
「ねえ、出なきゃダメ?ですかね?私1人で居たいかも、ここで誰かに会いたくないかも、お客さんってこと、ですよね?勝手に入ってくるもんね?家の人だったら?どうしよ、知らない人に会いたくないかも、あ、でもここの家主だって別に知らない人ですよね?」
“ピーンポーン”
「出たくないかも、ここに居たいかも、私も冷蔵庫にくっついてたい、ねえ、交換しない?」
「できないよ」
輪がささやくように小さな声でそう答えた。
「忘れてるかもしれないけど、君は人間、当方は輪、知恵の輪の1輪、交換ってどういうことよ、当方のこと外して左右の輪たちピアスにでもする?」
「いいじゃんそれ」
“ピーンポーン”
「冗談だよ、早く出てあげて」
「でも試してもいい?」
「何を?」
「外すの」
「それは大歓迎」
知恵の輪を外して、左右の輪をピアスにして、私は冷蔵庫に張り付きたい。
外れろ。知恵を絞って外れてください。
知恵の輪はびくともしない、全く思い通りにならない。
そもそもこの知恵の輪、隙間が全くない。知恵の輪ってどこかしらに外せる余地があるはずで、全部の輪が切れ目なく繋がっているっておかしいんじゃないか。
「ねえ、知恵の輪じゃないんじゃない?」
「知恵の輪だって」
「だって君たち完全な円だよ、知恵の輪じゃなかったんだよ」
“ピーンポーン”
「大正解」
真ん中の輪が一言そういうと、左右の輪がぐにゃぐにゃとスライムのように変形しながらそれぞれ私の左右の手首に絡みついてきた。冷たそうな見た目、鉄の色をしているくせに暖かい。ほどよい圧迫を加えながら進んでくるそれは、手首に輪をかける形で固まった。真ん中の喋る輪は左右の輪と繋がったまま目線の高さに浮いている。
「ようこそ、いや、おかえり、きみが最初の輪だったんだよ」
そう言って、真ん中の輪は冷蔵庫の方へ私をひきづるように動き出した。
「さあ帰ろう」
“ピーンポーン”
“ワン”
「あ、犬が鳴いてる」
「鳴くでしょ、そりゃ」
「行かなきゃ」
「ここに居たいんでしょ」
「でも呼ばれてる」
「出たくないって言ってたじゃん」
「出てあげなって言ってたじゃん」
チャイムと犬の鳴き声が混ざり合ってノイズになる。もはや音は意味をなさず、私の鼓膜を不快に揺らすためだけに発せられている。意味をなさず?ほんと?嘘だワン。だって1匹で鳴いている。こんなにうるさくなるまで1匹で絶え間なく鳴き叫んでいる。無意味に鳴くと思うか?犬を馬鹿にするなワン。あの犬は私に何か言いたくて泣いている私の犬だ。話を聞いてあげないと。言葉がわからないなら、目を見て何を伝えたいのか汲み取ってあげないと。泣いているなら涙を拭ってあげないと。それが私の役割だから。どこ?どこにいる?
いつの間にかローラースケートを履いている私は知恵の輪に引っ張られるままに冷蔵庫に到着しそうだ。なぜ?なんで?さっきまであんなに安心だったのに、
いきなりこんな自分の意思が全く通用しない世界なんて。
「ルカさん、ごめんなさい、ルカさーん」
「え?」
目を開けると、ミナさんの顔があった。
「え?ここは。え?」
「あ、ルカさんの家です、お邪魔してます」
「夢?」
「や、ごめんなさい、起こしちゃって、夢じゃないです」
ただ目だけを開けたつもりだったけど、私の上半身は起き上がっていてミナさんが私の手首を掴んでいる。起こされたのか?そもそも何で家に?家?誰の?私の?今、私は起きてる?
「起こしてごめんなさい」
「あれ?え、でも」
「あ、大家さんにちょっとあのごめんなさい嘘ついて開けてもらいました」
「あ、え?」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
