
ぜんぶシールにしたい
ぜんぶシールにしたい。持ってるものぜんぶ。あらゆる薄いもの。葉っぱとかそういうのも、今書いてる文字も。
小さい頃はぜんぶシールにしていた。
スーパーのチラシの果物やお菓子のパッケージなんかはぜんぶ「シール以前」だった。子どもの時分の私には、両面テープという魔法みたいなテープがあって、裏側を覆ってはさみで輪郭を器用に切り取ったら、ぜんぶシールだった。価格の文字がときどき邪魔であった。クリスマスの時期のケーキのシールに心躍らせていた。宅配寿司や宅配ピザのシールもあった。兄はパソコンで印刷したありとあらゆるものでシールを作っていて、私も負けじと自分で書いたいろいろな絵をシールにしていた。布やお刺身の載っているトレーで作ったシールや、表面をセロハンテープで覆ってつるつるにしたシールもあった。
お店で買ったシールには、絵になっているのに剥がせない小さな花なんかがシールとシールのあいだよくあって、それもはさみで切ってシールにした。
売り物のシールにはそれほどつよい情熱はなかったが(と言うよりも、シールでないものがシールだったらよかったのにという気持ちや、シールでないものをシールにしたいという気持ちのほうがずっと強かったのだ)、「シールブック」だけは好きで、たびたびいろいろな種類のシールブックを買ってくれと親にせがんだ。シールブックは風景だけの、シールを無限回貼って剥がせるつるつるの絵本と、別個にたくさんのシールがついている本だった。風景とシールは連動していて、たとえば草原と動物、たとえば海の中と生き物など、さまざまであった。つるつるの風景に、私はすきなように万物を貼ることができた。大人になってからも風景がつるつるだったのは、シールブックが最初で最後だった。
ぜんぶシールにしたい。
今、ぜんぶシールにしたい本がある。東京でいちばん大きな本屋でいちばん背の高い本棚の、いちばん上の段の、梯子に乗らないと取れない高いところにこっそりある。右から三冊目。ロシアの絵本やポスターやそのほかのいろいろな挿絵がたくさん載っているぶあつ~い本。名前はおしえてあげない。私より富豪の大人がこっそり買って先にぜんぶシールにしたらむかつくから。
あの本に載ってある絵をぜんぶシールにしたい。貼る場所そんなにないけど。大人になるとシールを貼る場所がなくなる。貼る場所なんてないのにシールにしたいと思う。ぜんぶシールにしたい。シールにしたいというのは、じぶんのものにしたいのだと思う。紙に張り付いたままではなくいつだってそこから剥がして動かすことができる、貼ろうと思えばじぶんの貼りたいところへどこにでも貼ることができるということがほしいのだ。
いろんなものがぜんぶシールだったらいいのにと思う。ぜんぶシールにしたい。
でもぜんぶシールだったらどうしよう?
思わぬところがシールになってたらどうしよう。ある朝目が覚めて、いつも通りドアを開けようとドアノブを引こうとしたら、ぺろんと薄っぺらいドアノブが剥がれて、シールだったら?
え! ここ、シールになってるなんて。そんなの聞いてないよ。
さて、思わぬところがシールになっている共和国では、あなたが思ってもみなかったところがシールになっています。部屋にいてふと壁に目がいって、そんなまさかなと思いながらおそるおそるめくってみると、ピンポイントにある一箇所だけシールになっている。そんなまさかと思うでしょう? でもほんとなんです。それも、家の形にぺろんとめくれるの。なんて気が利いている。
そんな思わぬところシール現象はいたるところに転がっていて(というか張り付いていて?)、その国へ引っ越した者は引っ越してから3ヶ月と3日のあいだ、誰もが思わぬところシール探しにやっきになる。あれっここもめくれる。あれっここも。こっちもだ! そうして今までにおよそ6082人の3歳児から92歳の大人までがおそるおそるじぶんの体をめくっている。と、その国の大きな国会図書館の、なんでも載っているといういちばんぶ厚い本の、963ページの上から17行目には書いてあった。ほっ、ここはめくれない、よかったよかった。剥がした皮膚のところがじんわり赤くなって安心しているこわい国、思わぬところがシールになっている共和国。そんな人たちはみんな知らない。じぶんの身体の左足の薬指の爪だけはシールになっていることを。そのことに気づいた人はこの国でわずか17人だけであった。爪を剥がしたそこには10ケタの電話番号が載っていて、ものすごく小さな文字で、「ここに電話してください」と書いてある。17とは、そうして電話をしてきた人の数だった。電話をかけなかった人の数? 左足の薬指の爪を剥がそうとしたユニークな人々が、その剥がした左足の薬指の爪シールの後ろに急に現れた電話番号に電話をかけないなんてことが、一体あるだろうか?
思わぬところがシールになっている共和国で例えばめくれるこんなもの。日めくりカレンダー。日めくりカレンダーのありとあらゆるところはぜんぶめくれる。365枚のでっかい挿絵のシール。365枚でっかい数字のシール。なんとなく太ももあたりにはってみる、19と書かれた赤い文字。ふーんなかなか悪くない。ジーンズを履いていたって、みんなには見えないけど、おれの太ももには19の赤いシールが貼ってあるんだぜ。そんな気分だ。
それから、スカートもシールになっている。思春期の男の子がよくよその国からやってきて、スカートめくりをするたびにびっくりしている。なんてったってこの国では、男の子がスカートをめくっても、でれんときれいな色の(ときには柄付きのなんかもある)大きいシールだけが手の内に残って、女の子は平気な顔をしているからね。今度こそと思ってめくったあとの残りのスカートをめくる男の子も大勢いるが、ところがどっこい、思わぬところがシールになっている共和国では、スカートはなんと1234567890枚のシールからできていて、今のところ1234567890回スカートをめくった男の子はいない。この前8002回めくったところで息を引き取ったおじいちゃんが、スカートめくりひょん(それは、その国に昔からある妖怪をもじったものらしい)として、新聞に載っていたっけ。
思わぬところがシールになっている共和国は、めくれるものよりめくれないもののほうが少ないというくらい、とにかくいろんなものがシールになっている。時計の文字盤はぜんぶシールだ。文字盤がシールになっている時計しか、その国の時計屋には売っていない。だから多くの家の時計は、いたずら防止のために一度ぜんぶの文字盤シールを剥がしてから、接着剤でくっつけている。文字盤がシールのままの家は、子どもの心を失っていない大人の住んでいる家だけだった。そうした大人の家の時計の文字盤は決まってデタラメで、彼らの話しことばも時折デタラメであったが、子どもの心を失っていない大人にとってそんなことは全然お構いなしであった。
それから、横断歩道の白い線もシールだ。尤もいたずらで剥がす子どもたちが大勢いるからと、もとの横断歩道が消えないように白いシールは701枚重ねられていた。701はこの世で126番目の素数で、126とはいちばん立派だったと言われているこの国のかつての王様が生きた年の数であった。そしてそんな701枚の全ての重ねられた白い長方形を剥がしきった勇者は今までで一人だけであった。その子どもはそれから剥がした701枚の白で、思いつくありとあらゆる場所に、彼だけの横断歩道をいくつもつくった。彼の横断したいすべてのところに。たとえばすべてのものがぜんぶシールになっていない共和国との国境線や、子ども部屋の天井、好きな女の子の家の前の道路とそこと壁一枚隔てた彼女の部屋の中などに。女の子は彼が帰ってからすぐにそれを剥がしてしまったので、彼はそれから一度も彼女の部屋へは入れなかったけれど。
その国では、レストランのメニュー写真もシールになっていた。サラダはお皿のシールに、店主がその日手に入れた野菜のシールを日ごとに貼ったり剥がしたりしていた。でもいたずら好きのお茶目な大人が自前のシールを貼ったり、こっそりとじぶんのシール帳にプチトマトのシールを頂戴していたりしたから、その国のあらゆる飲食店のメニュー写真はほとんど役に立たなかった。パフェにはあらゆる人々のそれぞれの好物が、つまりあらゆるおいしいものが乗せられ、それはメニュー表をはるか高くはみ出していたし、文字を見れば済む話だと静かに言った気難し屋のおじいさんはまんまと嵌められた。いたずら好きの店主が一文字ひともじをシールにしていて、それらの文字列はもうめちゃくちゃだった。でも不思議とすべての入れ替えられた文字は、なにかべつの素敵な食べ物の名前になっていた。△△△△△なんかはいちばんひどくて、×××××になっていた。これにはおじいさんも一本取られたと、気難しい顔のまま、口元だけ緩んでいたそうな。
また、今だいたい90歳くらいのおばあさんがまだ16ほどの生娘だった時分には、若い娘には「シール布団」があてがわれるのがお決まりであった。その家代々受け継がれたシール布団の作り方があって、それぞれの特別なめくり方を知らないと、シールの部分だけがめくれて布団そのものは決してめくれなかった。それだから年頃の若い衆のあいだでは、あすこの家のシール布団はどうめくるだとか、なんだとか、そんな話題でいつももちきりだった。今となってはシール布団はもう古い骨董品のようなもので、古ぼけた小さな郷土博物館の片隅に、めくり方を書いた小さな紙きれとともにひっそりと保管されているだけであったが。
そんな国のある小さな町でいちばんの有名人であった129歳の老人は、なんと顔がシールになっていた。学校が休みの日は早くから子どもたちが集まって、その老人の顔でほんとうの福笑いをしていた。怒った顔をつくってもたちまちにょきっと笑顔になってしまう、ほんとうの福笑いであった。お祭りで彼はいつも引っ張りだこだった。
思わぬところがシールになっている共和国ではごくたまに、一部の木や家もシールであった。ひどいときは風景さえも。チャーミングな人々はよくあっちの風景とこっちの風景のシールを貼り替えたりしていた。そうやっていろいろな景色を楽しみながら、町の人々を少しだけびっくりさせ、そして少しだけ道に迷わせて、でもいつだってにこやかに笑っていたものだから(また、迷い込んだ人々に彼らはいつだって暖かい紅茶とクッキーをご馳走して、あたらしい風景での道を教えていたのだった)、人々はだれも彼らのことを責めなかった。
冬はさみしくて嫌だと言っていた無口な青年は、夜の間にぜんぶの落ち葉をシールにして、未明、じぶんの家の窓から見える裸の木に貼り付けた。ときどき葉っぱを色とりどりの絵の具で塗ったその木には冬の間も鳥が歌いにきていたし、隣町の彼のことがすきだった女の子はこっそりと、よく晴れた日に葉っぱにそっくりの封筒にしたためたラブレターを入れてその木に貼り付けた。彼女にこっそり耳打ちされた鳥はそれからというものその葉っぱの封筒の近くでばかり鳴いていた。彼とその女の子は、今ごろどうしているだろうか? 顔がシールになっている老人や、横断歩道をすべて剥がしきった少年は?
わたしが彼や彼女らに、あるいはもうすでに失われてしまったものたちに思いをめぐらせているあいだにもめくるめく日々は過ぎていって、月日(moon and sun)の経過はいろいろなものを忘れ去ることを強いる。しかし、今でも思わぬところがシールになっている共和国では、いろいろなところが今日もまたシールになっている。たとえばマンホール。たとえば雲。太陽もシールになっていると思った手の長いおばあちゃんは、触って以来、冷え性知らずだと言っていた。そしてロマンチストな恋人たちは、夜の間だけこっそり星を動かして、朝日の昇る前にきちんと元の位置に貼り直し、明るいうちは素知らぬ顔で過ごしているのだった。


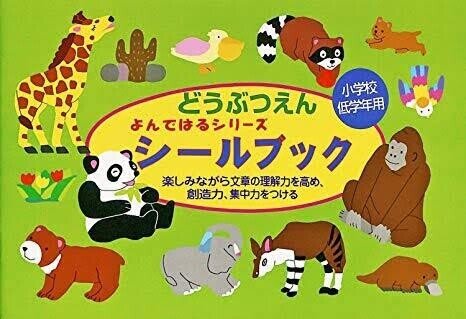
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
