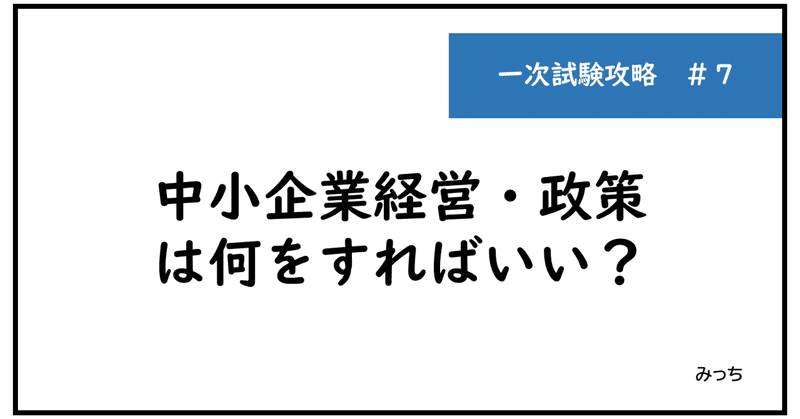
中小企業経営・政策の重要論点(一次試験攻略#7)
中小経営・政策は、出題問題数、範囲も広いです(試験時間も長い)
コツコツ覚えていくしかないですが、必ず出る問題などありますので、確実に取れる問題を増やしておきましょう。中小企業経営の白書・一般常識の部分は、白書をまとめている参考書などを活用しながら、大企業・中企業・小企業の傾向を把握しておきましょう。
これだけはやっておきたい3大重要論点
①中小企業基本法
②金融・財務支援
③共済制度
どんな問題がでるの?
イメージをもっていただくために、過去問を掲載しました。こちらをとっかかりとして、過去問題集や参考書で勉強してみてください。
重要論点①:中小企業基本法
令和4年:第18問
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
中小企業基本法では、第 2 条で①下線:中小企業者の範囲と②下線:小規模企業者の範囲を定めている。また、第 5 条では③下線:中小企業に関する施策の基本方針を示している。
(設問 1 )
文中の下線部①に含まれる企業に関する正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
a 従業員数 500 人、資本金 3 億円の製造業
b 従業員数 150 人、資本金 6,000 万円のサービス業
〔解答群〕
ア a:正 b:正
イ a:正 b:誤
ウ a:誤 b:正
エ a:誤 b:誤
正解:イ
(設問2)
文中の下線部②に含まれる企業に関する正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
a 従業員数 30 人、資本金 300 万円の製造業
b 従業員数 10 人の個人経営の小売業
〔解答群〕
ア a:正 b:正
イ a:正 b:誤
ウ a:誤 b:正
エ a:誤 b:誤
正解:エ
(設問 3 )
文中の下線部③に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
ア 事業の転換の円滑化
イ 創造的な事業活動の促進
ウ 地域の多様な主体との連携の推進
エ 取引の適正化
正解:ウ
重要論点②:金融支援
令和4年度:第20問
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
「経営革新支援事業」は、経営の向上を図るために新たな事業活動を行う経営革新計画の承認を受けると、日本政策金融公庫の特別貸付制度や信用保証の特例など多様な支援を受けることができるものである。
対象となるのは、事業内容や経営目標を盛り込んだ計画を作成し、新たな事業活動を行う特定事業者である。
(設問 1 )
文中の下線部の経営目標に関する以下の記述の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
A の事業期間において付加価値額または従業員一人当たりの付加価値
額が年率 3 %以上伸び、かつ B が年率 1.5 %以上伸びる計画となってい
ること。
〔解答群〕
ア A: 1 から 3 年 B:売上高
イ A: 1 から 3 年 B:給与支給総額
ウ A: 3 から 5 年 B:売上高
エ A: 3 から 5 年 B:給与支給総額
正解:エ
(設問 2 )
文中の下線部の経営目標で利用される「付加価値額」として、最も適切なものはどれか。
ア 営業利益
イ 営業利益 + 人件費
ウ 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
エ 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 + 支払利息等
オ 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 + 支払利息等 + 租税公課
正解:ウ
重要論点③:共済制度
令和4年度:第23問
以下は、中小企業診断士のA氏と、顧問先の情報処理・提供サービス業(従業員数 5 名)の経営者B氏との会話である。この会話に基づき下記の設問に答えよ。
A氏:「自社の経営が順調でも、取引先の倒産という不測の事態はいつ起こるか分かりません。そのような不測の事態に備えておくことが大切です。」
B氏:「確かにそうですね。どのように備えておけばよいでしょうか。」
A氏:「たとえば、下線①経営セーフティ共済という制度があります。この制度への加入を検討してはいかがでしょうか。」
B氏:「どのような制度か教えていただけますか。」
A氏:「経営セーフティ共済は、取引先企業の倒産による連鎖倒産を防止するため、下線②共済金の貸付けを受けることができる制度です。」
(設問 1 )
会話の中の下線部①の制度の加入対象として、最も適切なものはどれか。
ア 3 カ月継続して事業を行っている中小企業者
イ 6 カ月継続して事業を行っている小規模企業者
ウ 1 年継続して事業を行っている中小企業者
エ 新規開業する者
正解:ウ
(設問 2 )
会話の中の下線部②に関するA氏からB氏への説明として、最も適切なものはどれか。
ア 共済金の貸付けに当たっては、担保・保証人は必要ありません。
イ 共済金の貸付けは無利子ですが、貸付けを受けた共済金の 20 分の 1 に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
ウ 償還期間は貸付け額に応じて 10 年~15 年の毎月均等償還です。
エ 取引先企業が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合、この回収困難額と、積み立てた掛金総額の 5 倍のいずれか少ない額の貸付けを受けることができます。貸付限度額は 5,000 万円です。
正解:ア
上記の3問は、必ず出ます。頻繁に出る分野がありますので、確実に取れる問題を増やしていきましょう。
試験前半部分の、白書から出る問題は、難問が多いので、後半の制度の問題で確実に得点を稼げるようにしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
