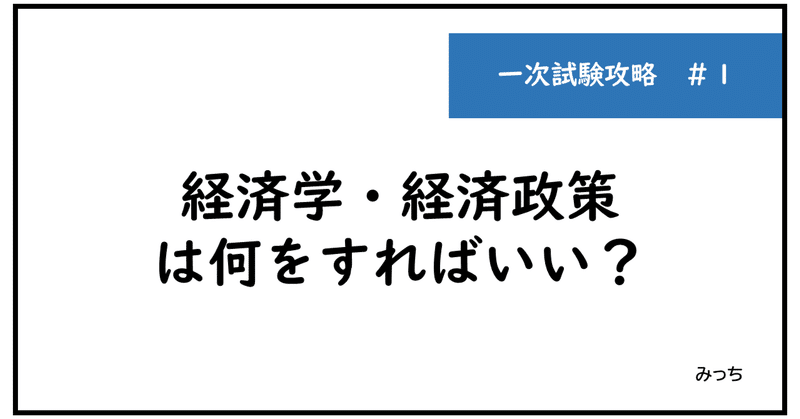
経済学・経済政策の重要論点(一次試験攻略#1)
経済学・経済政策は、4点×25問と、1問の配点が大きく、問題数は少ない特徴があります。頻出問題で点数を稼ぎましょう。
目標点数を55点と置いた場合、14問/25問が合格ラインです。確実に取れる問題を10問は持っておきましょう。
頻出問題を下記にまとめました。こちらの10個のテーマについて、確実に得点できるようにやっていきましょう。
これだけはやっておきたい10大重要論点
経済学・経済政策で最頻出問題を10論点をまとめました。こちらについては、考え方・グラフ問題・構造までしっかり押さえて、確実に得点できるようにしましょう。この論点でしっかり得点できれば、この科目の半分以上は得点できますので、繰り返し勉強してみましょう。
①総需要と総供給
②貯蓄と投資
③国民所得概念と計算
④AD-AS曲線
⑤貿易理論
⑥需要・供給・弾力性
⑦競争的市場の資源配分機能
⑧ゲーム理論
⑨代替効果と所得効果
⑩生産関数と限界生産性

どんな問題がでるの?
イメージをもっていただくために、過去問を掲載しました。こちらをとっかかりとして、過去問題集や参考書で勉強してみてください。
5年以上前の過去問と直近の過去問を掲載しますので、スキマ時間に、忘れないように見てください。
重要論点①:総需要と総供給
平成26年度:問4
財市場における総需要 AD は、消費 C、投資 I、政府支出 G の合計であるとする。所得を Y、限界消費性向を c、所得がゼロでも必要な最低限の定額の消費額をc0 とすれば、消費は C=C0+cYと書き表すことができる。総供給 AS と所得が等しいとすれば、これらの関係から⑴式と⑵式が得られ、下図のように示すことができる。いま、上記の標準的なモデルに追加して、所得 Y に対して定率 t で課税する線形の租税関数 tY を考えると、消費関数は C=C0+c(1-t)Yとなり⑶式を得る。
また、企業投資が⑶式の I から外生的に増加して I′ になった場合を⑷式で表記する。なお、税収は政府支出 G には影響を与えないものとする。このとき下記の設問に答えよ。
(1) AS=Y
(2) AD=C0+cY+I+G
(3) AD1=C0+c(1-t)Y+I+G
(4) AD2=C0+c(1-t)Y+I´+G

設問1
この図の中に⑷式を描き、⑵式と比較した場合の記述として最も適切なものはどれか。
ア ⑵式と⑷式の傾きは等しく、⑷式の縦軸の切片の位置は⑵式よりも下になる。
イ ⑷式の傾きは⑵式よりも急になり、⑷式の縦軸の切片の位置は⑵式よりも上になる。
ウ ⑷式の傾きは⑵式よりも急になり、⑷式の縦軸の切片の位置は⑵式よりも下になる。
エ ⑷式の傾きは⑵式よりも緩くなり、⑷式の縦軸の切片の位置は⑵式よりも上になる。
オ ⑷式の傾きは⑵式よりも緩くなり、⑷式の縦軸の切片の位置は⑵式よりも下になる。
回答
エ:傾きに注目して解く
設問2
他を一定として、企業投資が I から I′ へ 1.8 だけ増加した形で⑶式から⑷式
への変化が発生したものとする。このとき、所得 Y の変化として最も適切なものはどれか。ただし、限界消費性向 c は 0.8、税率 t は 0.2 とする。
ア Y は1増加する。
イ Y は1.8 増加する。
ウ Y は5増加する。
エ Y は9増加する。
オ Y は増加しない。
回答
ウ:代入して解く
令和4年度:第5問
生産物市場の均衡条件が、次のように表されるとする。
生産物市場の均衡条件 Y = C + I + G
消費関数 C = 10 + 0.8 Y
投資支出 I = 30
政府支出 G = 60
ただし、Y は所得、C は消費支出、I は投資支出、G は政府支出である。
いま、貯蓄意欲が高まって、消費関数が C = 10 + 0.75 Y になったとする。こ
のときの政府支出乗数の変化に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 貯蓄意欲が高まったとしても、政府支出乗数は 4 のままであり、変化しない。
イ 貯蓄意欲が高まったとしても、政府支出乗数は 5 のままであり、変化しない。
ウ 貯蓄意欲の高まりによって、政府支出乗数は 4 から 5 へと上昇する。
エ 貯蓄意欲の高まりによって、政府支出乗数は 5 から 4 へと低下する。
回答:エ
代入して解く
令和4年度:第6問
下図は、45 度線図である。この図において、総需要は AD = C + I + G(ただ
し、AD は総需要、C は消費支出、I は投資支出、G は政府支出)、消費関数はC = C0 + cY(ただし、C0 は基礎消費、c は限界消費性向(0 1 c 1 1)、Y は GDP)によって表されるとする。図中における YF は完全雇用 GDP、Y0 は現実の GDP である。
この図に基づいて、下記の設問に答えよ。

(設問 1 )
この図に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
a 総需要線 AD の傾きは、c に等しい。
b 投資支出 1 単位の増加による GDP の増加は、政府支出 1 単位の増加によるGDP の増加より大きい。
c 総需要線 AD の縦軸の切片の大きさは、C0 である。
〔解答群〕
ア a:正 b:正 c:誤
イ a:正 b:誤 c:正
ウ a:正 b:誤 c:誤
エ a:誤 b:正 c:誤
オ a:誤 b:誤 c:正
回答:ウ
(設問 2 )
GDP の決定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア ADF - AD0 の大きさだけの政府支出の増加によって、完全雇用 GDP を実現できる。
イ ADF - AD1 の大きさだけの政府支出の増加によって、完全雇用 GDP を実現できる。
ウ ADF - AD2 の大きさだけの政府支出の増加によって、完全雇用 GDP を実現できる。
エ AD0 - AD1 の大きさだけの政府支出の増加によって、完全雇用 GDP を実現できる。
オ AD0 - AD2 の大きさだけの政府支出の増加によって、完全雇用 GDP を実現できる。
回答:エ
重要論点②:貯蓄と投資
平成27年度 問4
消費がどのようにして決まるかを理解することは、経済政策の手段を検討する際にも、
また、景気動向を予測する上でも重要である。一般に、消費の決定に所得が影響すると考えられているが、具体的な影響の仕方についてはいくつかの考え方がある。
消費の決定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 恒常所得仮説では、一時金の支給によって所得が増加しても、消費は増加しない。
イ 絶対所得仮説によるケインズ型消費関数では、減税によって可処分所得が増加しても、消費は増加しない。
ウ 絶対所得仮説によるケインズ型消費関数では、定期給与のベースアップによって所得が増加しても、消費は増加しない。
エ ライフサイクル仮説では、定期昇給によって所得が増加しても、消費は増加しない。
回答:ウ
令和4年度 問4
絶対所得仮説によって所得と消費の関係を述べた記述として、最も適切なものはどれか。
ア 今月は職場で臨時の特別手当が支給されたので、自分へのご褒美として、外食
の回数を増やすことにした。
イ 将来の年金が不安なので、節約して消費を抑制することにした。
ウ 職場の同僚が旅行に行くことに影響を受けて、自分も旅行に行くことにした。
エ 新型コロナウイルスの影響で今年の所得は減りそうだが、これまでの消費習慣を変更することは困難なので、
これまでどおりの消費を続けることにした。
オ 賃上げによって給料が増えることになったが、不景気が当分続きそうなので、消費は増やさないことにした。
回答:ア
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
