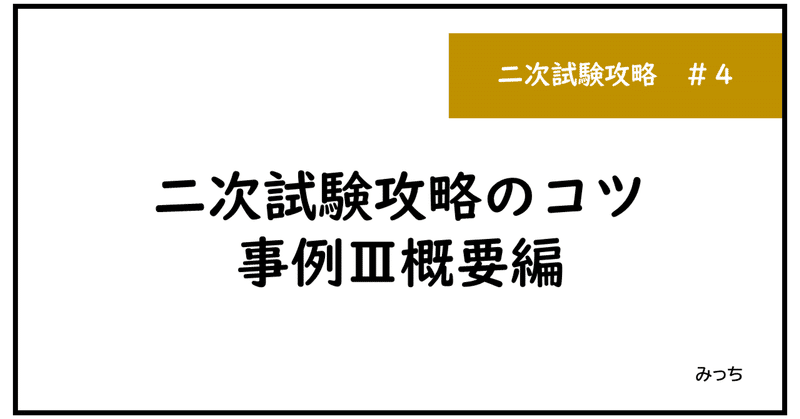
事例Ⅲ攻略法(概要編)
事例Ⅲは、オペレーションに関わる問題です。
コツをまとめましたので、このコツを実際の試験でも忘れないよう、事前の勉強で習慣化しましょう。
1.問題点を適切に抽出する
2.キーワード(問題点)と設問を紐づける
3.一次試験の知識を使う
4.あるべき姿、問題点、課題を整理する
5.全体の構成を意識する
参考:令和4年度問題※リンク
(設問)
第1問(配点 20 点)
2020 年以降今日までの外部経営環境の変化の中で、C 社の販売面、生産面の課題を 80 字以内で述べよ。
第2問(配点 20 点)
C 社の主力製品であるプレス加工製品の新規受注では、新規引合いから量産製品初回納品まで長期化することがある。しかし、プレス加工製品では短納期生産が一般化している。C 社が新規受注の短納期化を図るための課題とその対応策を 120 字以内で述べよ。
第3問(配点 20 点)
C 社の販売先である業務用食器・什器卸売企業からの発注ロットサイズが減少している。また、検討しているホームセンター X 社の新規取引でも、 1 回の発注ロットサイズはさらに小ロットになる。このような顧客企業の発注方法の変化に対応すべきC 社の生産面の対応策を 120 字以内で述べよ。
第4問(配点 20 点)
C 社社長は、ホームセンター X 社との新規取引を契機として、生産業務の情報の交換と共有についてデジタル化を進め、生産業務のスピードアップを図りたいと考えている。C 社で優先すべきデジタル化の内容と、そのための社内活動はどのように進めるべきか、120 字以内で述べよ。
第5問(配点 20 点)
C 社社長が積極的に取り組みたいと考えているホームセンター X 社との新規取引に応えることは、C 社の今後の戦略にどのような可能性を持つのか、中小企業診断士として 100 字以内で助言せよ
1.問題点を適切に抽出する
事例Ⅲは、オペレーションの問題です。
問題文に、オペレーション上の問題点がちりばめられています。
生産計画に関する問題点(生産計画をたてていない、期間が長い)
生産の問題点(ムリ・ムダ・ムラ)がある
その問題点を正しく、漏れなく、抽出することが必要です。
問題点については、比較的明確に書いてあるので、取りこぼししないようにしましょう。
2.キーワード(問題点)と設問を紐づける
多くある問題点と設問を紐づける必要があります。
例えば、設問3、4で両方とも生産上の問題点を求められるとします。その際、多少重複はあってもよいですが、設問3では、生産計画のこと、設問4については、生産工程のムリ・ムダ・ムラのことなど、バランスよく使い分けて回答したほうが良いです。どの設問で、どの問題点を使うかを整理して考えるようにしましょう。
3.一次試験の知識を使う
生産方法のメリデメ、生産計画、生産工程を把握しておきましょう。例えば、多品種少量生産なのか、少品種大量生産なのか、見込み生産か受注生産かを把握し、生産計画は細かくなっているか(月次・週次・日時)、生産工程にムリ・ムダ・ムラがないか(特定の作業員に稼働が集中している、特定の工程で遅れが出ているなど)判断し、アドバイスする必要があります。一次試験の生産工程周辺の知識を再度見直して、問題点、課題、解決策を整理しておきましょう。
4.あるべき姿、問題点、課題を整理する
回答を記載する際に、設問に応じた問題点と、あるべき姿、課題を整理して記載する必要があります。見込み生産の場合のあるべき姿と、現状の問題点、それを解決するための課題という風に、生産手法の特徴をしっかり把握し、記載できるようにしましょう。
5.全体の構成を意識する
2.とほぼ同じ内容ですが、再度、設問と回答全体を見て、しっかりと設問に対して問題点を紐づけて答えているか、重複感がないかを確認する必要があります。多少の重複はあってもよいですが、すべて同じ問題で回答できる設問の書き方だったりしますので、ピックアップした問題点と解決方法を全体を見ながらバランスよく回答しましょう。
事例Ⅲ攻略オリジナルフレームワーク
上記の1~5を試験で実践するためのオリジナルのフレームワークを作りました。こちらを使って解くことによって、回答の質向上させましょう。
今後、こちらのフレームワークを使って、各年度の解き方をUP予定です。

事例Ⅲは、問題点をいかにピックアップし、整理するかが攻略のポイントですので、問題点→あるべき姿→解決策をパターン化して回答できるように、事前に練習しておきましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
