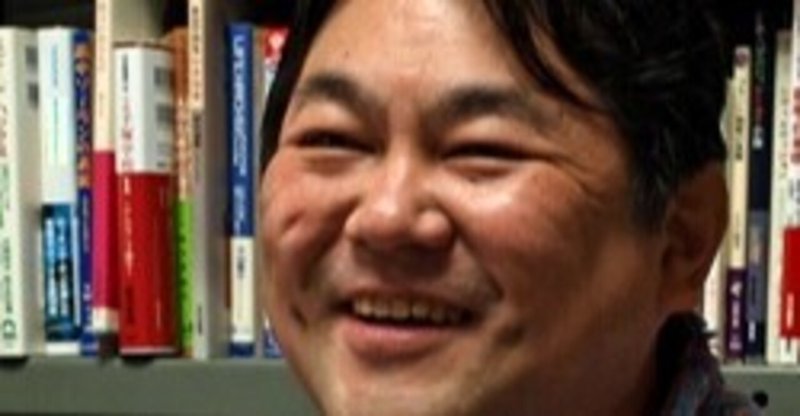
追悼・市川昌浩(没・2010年7月5日)
(1)市川昌浩くんの死
記・2010年7月10日 09:53
2010年7月8日の木曜日。僕らは、個別に仕事をしていて、毎週木曜日の14時からがオンブックの定例会議だった。約束の時間に市川がこない。これまでも寝坊したりして遅れることはあっても、必ず電話してくるのに、30分経っても連絡ないし、電話しても通じない。
なんだか胸騒ぎがして、市川の部屋には行ったことないのだが、中村さんが以前に家の前まで車で送っていたことがあったので、中村さんと二人で市川の部屋に向かった。瀬田の環八沿いにある。
部屋の鍵はしまっている。窓を覗くと電気がついてる。宅急便の不在証明がポストにささっていた。窓から何か異臭がする。大家さんに連絡して、部屋を開けてもらうように頼んだが、それはまずいと断られる。110番に電話して、警官に来てもらった。おまわりさんは、部屋の前に立つなり、「こりゃだめだ」と言った。僕らをドアの前から下げさせて、一人で入った。そして「お亡くなりになってます」と一言。僕は腰が抜けるように階段に倒れてしまった。
その後、警官が数人と刑事が来て、事情を聞かれた。あちこちに電話で連絡すると、月曜日までは電話したりメールしたりしているが、火曜日以降は留守電になってるとかメールの返事が来ないとかだった。
まだ検査の結果が届いていないので、分からないが、お風呂に入って、外に出たところで倒れているとのことだった。
市川は、ここ数年でどんどん体重が増え、昨年、心配して人間ドックの予約をとって行かせるようにしたのだが、緊急の仕事が入ってキャンセルしてようだ。今年こそはちゃんと行こうと、僕と二人で人間ドックの予約をしてあった。今更、何を言ってもはじまらないが、今はただ、市川昌浩くんのご冥福をお祈りするだけだ。良い奴が、50才になるまで良い奴であり続けるというのは、大変なエネルギーがいるはずだ。
皆さんに、愛され、信頼されてきた人生を、市川に代わって、御礼申し上げます。
(2)電子メディアの創世記
オンブックの取締役であり、デメ研のメンバーだった市川昌浩が死にました。誰も埋められない穴が内側にあいてしまった。痛くて、こんなことならあいつと出会うのではなかったと思うほど、寂しい。こんな文章も書きたくない。だけど文章を書くことは僕の宿命なんだ。市川も書けと言ってる。
市川昌浩は茨城の生まれ。近所にはタレントになった渡辺徹がいた。僕が市川と出会ったのは70年代の半ば。彼は工業高校生で、ロッキングオンの読者であり、ポンプの創刊に投稿者として協力してくれた。高校卒業後、CSKに入社して、大型コンピュータのエンジニアとして数年仕事をした。
1981年に、僕がロッキングオンとポンプを同時に辞めて、参加型メディアの発展型としての参加型社会の模索を始めると決めて、有限会社橘川幸夫事務所を恵比寿に開業した。その時に、これからはコンピュータが中心の社会が来ると思い、また僕らが描く参加型社会においてはコンピュータが必須のアイテムになると考え、まだ20才になったばかりの市川を仲間に巻き込んだ。
僕らは、電電公社(現在のNTT)から通信端末をリースして、カプラにつなぎ、国際電話回線でアメリカのダイアローグ(ロッキードがやっていたデータベース)にアクセスする実験をやっていた。恵比寿の小さな有限会社で、市川が中心となってオンラインデータベースの研究会を開き、未来を想像しながら勉強していた。1982年83年ぐらいのことだ。その研究会のメンバーは、当時は都庁に勤めていた滑川海彦(現在は翻訳家でありIT批評家)と、当時は東京印書館という印刷屋の営業をやっていた下中直人(現在は平凡社社長)と市川の3人だった。
この研究会の成果は1984年に東洋経済から『データベース "電子図書館"の検索・活用法』という書籍になった。東洋経済の担当の村瀬くんもまだ若く、滑川や下中は会社の仕事が終わると恵比寿の事務所に集まってきて、議論を続けていた。アマゾンのデータでは著者は滑川の名前しか出ていないが、滑川・下中も納得すると思うが、間違いなくこの本は、市川が中心となって、市川が書いた本である。まだ20才そこそこの少年のくせに、知識量、問題意識の先見性、几帳面さ、大人以上の器量、すべて市川には最初から備わっていた。僕たちは、ただただ市川の存在感に圧倒され、僕なんかは、「いつかみんなで市川に食わせてもらおうな」と言っていたものだ。

1984年の段階で、アメリカのオンラインデータベースにアクセスをし、パケット通信がどうのと新しい言葉を使いこなし、そして、オンラインデータベースの彼方にある、オンラインコミュニティの世界を、市川はしっかりと把握していた。そして市川の凄い所は、1984年にこのような作業をしていたことを、一度たりとも自慢気に話したことがない、ということだ。彼はいつも最先端の現実だけを問題にしていた。
その後、僕が持ち前の好奇心だけでいろんな世界に首を突っ込むたびに、いつもついてきてくれたのが市川である。アスキーでMSXマガジンを出すのを手伝った時も、ソフトバンクで新しい雑誌を出す企画にかかわった時も、バブルの時代に新宿の地上げ屋の中に入って新しい出版事業のためのデータベースを構築する時も、いつも市川が僕の女房のようにそばにいてくれた。
そして一度別れた。80年代の後半に、草の根パソコン通信がはじまり、市川は松岡裕典と一緒に「Wenet」というBBSをスタートさせた。僕はWenetのユーザーとしてかかわり、その後、自前のBBS「CB-NET」を立ち上げた。市川は、ジャストシステムに可愛がられ、一太郎関連の書籍をたくさん出した。そしてIBMの社内発行紙『PS FEEL』の編集長になり、PC雑誌『Power User』副編集長になったりして、インターネットの開始前後のITジャーナリズムの世界で活躍していた。
ここから先は
¥ 100
橘川幸夫の無料・毎日配信メルマガやってます。https://note.com/metakit/n/n2678a57161c4
