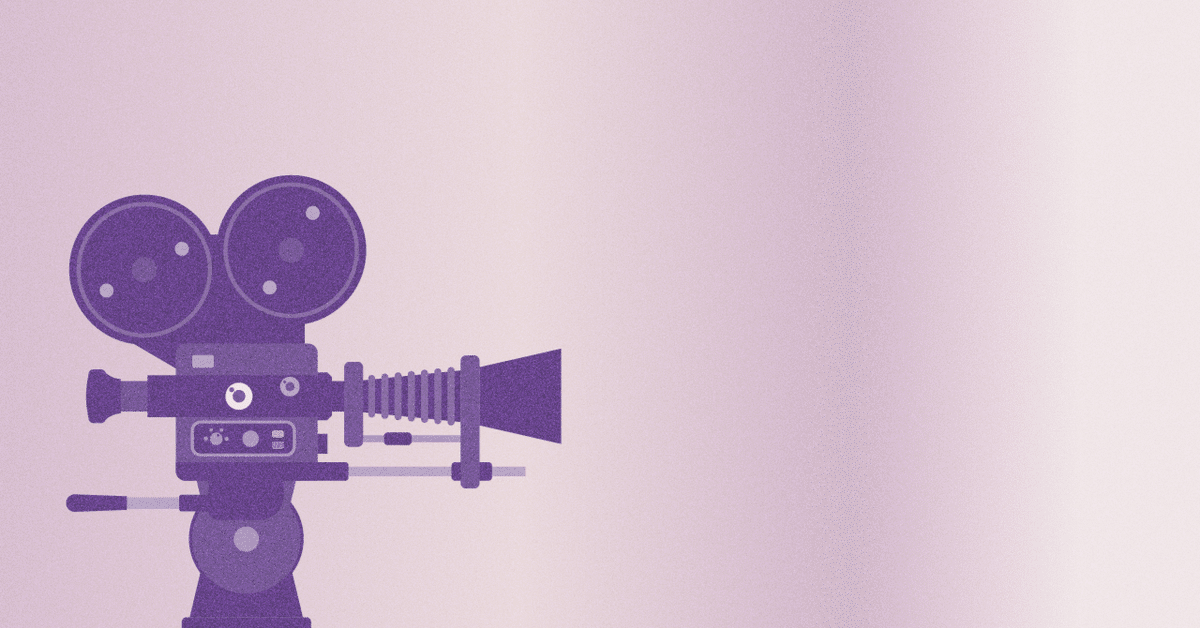
リアリティ・トランサーフィンの考察㉖『ポジ・スライドを作って活用する上での注意点など』
年に四、五回は近場の低山を登ってくるのですが、今年はまだ寒い時期に2回登ったのみです。とくに夏山が生命力にあふれていて好きなんですが、近年はスズメバチをよく見るようになりました。そこで昨年、これを買いました。
実際に使ったのは一回だけでしたが、そのときはハチとの遭遇はありませんでした。でも、もしかしたらおにやんま君のおかげで、わたしが気づく前にハチが逃げてくれていたかもしれませんね。この夏もどこかで一度は使ってみようと思っています。
さて、前回の記事では「目的の現実化について、理性がポジティブになれるように説得する」方法としてポジ・スライドを紹介しました。
その記事でも書きましたが、ポジ・スライドの効果の半面は「目的の実現に対して与えている重要性を適切なところまで引き上げる」というものでした。まったく実現できるとは思えない、ということは目的の実現に与えている重要性は過度にマイナスになっているということです。重要性はそれがプラス(過大)であるかマイナス(過小)であるかには関係なく、それが適切なところから大きく外れている場合に過剰ポテンシャルとなります。
目的の実現について過度にマイナスの重要性(重要性が著しく乏しい=まったく実現できるとは思えない)を与えているということを裏返すと、それは目的が実現しないということに過度にプラスの重要性を与えているということにもなりますね。これは、目的の実現にたいして理性がポジティブになれないのは、そこになんらかのネガ・スライドが関与している可能性を示唆しています。
いずれにしてもポジ・スライドを活用すれば、目的が実現にたいして理性が前向きになれるように、うまく調整することが可能です。
そしてさらに、ポジ・スライドの効果のもう半面として「快適域を拡大する」というものがあることをお伝えしました。
これらの効果はそれぞれ別のことではなくて、同じ効果を別の視点からみているものです。したがって、重要性が調整されて理性がポジティブになることと、快適域が拡大されて、目的の実現が快適域の中に入るということは、理性の観点からは、まったく同じことといえます。ただし、魂がその目的の実現を望んでいない(魂の不快)場合には、いくら快適域を拡大しても、それは実現しない可能性が高いでしょう。
ここまでが前回の記事のまとめです。今回は、ポジ・スライドを作って活用するうえでの注意点を紹介していきます。
スライドを傍観者として眺めるのではなく、スライドにふけり、たとえ仮想現実ではあっても、その中で暮らすのだ。スライドをスクリーン上の映画のようにイメージしようとしたら、その都度、自分をたしなめよう。それでは効果が薄いのだ。あなたは、自分が映画館の観客ではなく当事者であると感じながら、頭の中で演じなくてはならない。
(中略)
トランサーフィンにおける視覚化は、決して一般に理解されているような視覚化ではない。それどころか、トランサーフィンの法則による視覚化は、実際にとてもよく効く。その信頼性は保証つきだ。
ヴァジム・ゼランド著(以降の引用文も同じ)
このように述べてから、ゼランドは視覚化(目的の視覚化)については、大きく分類すると三つのやり方があると言います。
一つ目のグループは、夢想することである。実用的な観点からすると、これは最も弱くて頼りにならない視覚化の部類に入る。
(中略)
夢想家たちの目的をはっきり定義づけるとすれば、それは夢想することそのものであって、それ以上の何物でもない。
まず一つ目は「夢想する」というものです。これはただぼんやりと曖昧に目的を思い浮かべるだけということですね。夢想家の目的は夢想することそのものであると言っていますが、これはつまり「願望をただ願望として願っているだけで、そこに意図がない」と言えるでしょう。
二つ目のグループは、映画である。ここで私が言おうとしているのは映画館で上映される映画フィルムのことではなく、自分の願望についての思考上のフィルムのことだ。
(中略)
たとえば、あなたが家を欲しいとして、それをあらゆる細部にわたってあれこれ念入りに想像するとしよう。あなたの頭の中には、極めて鮮明な画像か、または、ほとんど目で見ているような明確な画像があり、毎日ずっとそのことを考えている。
(中略)
あなたは何を得られるか、当ててみよう。必ずやその家を目にすることはできる。あなたが想像したとおりの家か、ほぼそっくりの家だ。けれども、その家はあなたのものではない。
(中略)
あなたは、ほかの本の中で教わったとおり、視覚化のプロセスの質に気を奪われたため、その家の持ち主は誰かという一番大事な点を忘れてしまった。
二つ目は「映画」です。ただし、そこに主人公である「あなた」は登場しません。ゼランドがいうには、ほかの本、すなわち他の願望実現法が教えている視覚化(ビジュアライゼーション)はこれだということです。
この方法では、たしかに視覚化された対象はあなたの未来の現実に登場するだろうが、そのとき、それはあなたのものではないかもしれないとゼランドは指摘しています。言えることとしては、視覚化は目的の現実化において非常に強力な効果をもたらすけれども、そのやり方を間違えると残念なことになるということですね……🤔
もっとも、このトランサーフィンが発刊されたのはもう随分と前のことですから、令和最新版😌の願望実現法の本ではもはやこういうやり方は書いていないかもしれませんね。ただ、そのような最新の願望実現法における視覚化に、これからゼランドが述べるようなことが書かれているなら、そこにはもしかしたらトランサーフィンの影響もあるかもしれないです。
視覚化の三つ目のグループでは、あなたは観客として映画を見るのではなく、頭の中で映画に出演している。これはもうずっと効果的だ。あなたは自分の役割を演じながら、しかるべき人生ラインのパラメーターに同調する。
これがポジ・スライドにおける視覚化の方法論となります。単なる映画ではなくて、そこであなたは主役を演じるということですが、それによって人生ラインが移動する準備が整う(同調する)そうです。もうすこし詳しくみてみましょう。
たとえば、あなたの目的が家を持つことだとしよう。頭の中でその家を絵でも鑑賞するように眺めてはならない。
自分の家についての仮想現実的な夢を、ある意味、現実のものとして、自分の中に築き上げるのだ。家の中に入り、部屋から部屋へと歩き回り、周りにある品々に手を触れてみる。暖炉の前のひじかけ椅子に座ってくつろぎ、心地よいぬくもりを感じ、煙の芳ばしい香りを嗅ぎ、薪を暖炉にくべてみる。キッチンへ行き、冷蔵庫の中をのぞく。そこには何が入っているだろう? 寝心地のよさそうなベッドに横たわってみる。気分はどうだろうか? 家族とともに食卓を囲む。引っ越しのお祝いをしよう。家具の位置を変えてみるのもいいだろう。庭の芝生を手で触ってみよう。緑色で柔らかい芝生を。花を植えてみよう。あなたはどんな花が好きだろう? リンゴの木から実をもぎとってかじる。
自分が家にいることを実感してみるのだ。ここはあなたの家なのだから。苦悶する夢想家のような目つきで、手の届かないものや遥か遠くにある景色を畏敬の念をもって眺めるように、あなたの家を眺めてはいけない。あなたはすでにその家を所有しており、それが現実のことであると装うのだ。
こうして読んでみると、これはどうやら映画というよりも、現代の感覚でいうなら VR(仮想現実)といった方がしっくりときますね。第三者視点でそこに主役としてのあなたが存在している映像をイメージするのではなく、一人称視点で目的が現実化された世界の中を動き回るというのが、ポジ・スライドにおける視覚化のやり方です。
これによって重要性を調整するとともに、快適域を拡大することが可能になるわけですが、苫米地博士によればそこで重要になってくるのは「臨場感」です。脳は臨場感のあるものを現実として認識するため、より臨場感の高いポジ・スライドを作ってそれを常に再生していれば、脳はやがてそのポジ・スライドの中身を現実だと認識していくでしょう。結果として、そのポジ・スライドに写しこまれたコンテンツは快適域の中に入ってくるというわけです。
この視覚化がスライドである。このようなスライドはあなたの快適域を広げ、時間の経過とともに必ず現実化される。しかし、いつそれが起こるのかはわからない。長く待たなければならないこともあり得る。すべては、あなたがそのスライドをどれほど丹精込めて手入れしたかにかかっている。もし、少し手入れしては放っておくということでは、何も期待できない。奇跡が本当に起こることはないだろう。
単にスライドと言っていますが、ポジ・スライドのことですね。今後はわたしの記事でも、ポジ・スライドのことを指してスライドと呼んでいくことにします。
ここではスライドを作って活用していくには根気が必要であることを言っています。夢の中の世界とは違って、物質化されたこの現実では、ものごとの実現には相応の手順と時間が必要だからです。信じられないようなことが起こって、10年かかると思っていた目的がたったの半年で実現することももちろんありますが、この場合でも、それが実現するために必要な個々のできごとが半年の間に順番に起きています。
また、スライドは作ってそのままじゃなく、常に手入れしなくてはいけないということも指摘されています。手入れとは具体的には、スライドの内容をよりリアルに、つまりより臨場感の高いものへと作り込んでいくことと言えるでしょう。また、時間の経過とともに、目的の最終形そのものも少しずつ変化していくことは往々にしてありますから、スライドもそれにあわせてアップデートしていく必要がありますね。
ひとつ注意しておきたいのは、根気が必要とはいっても、スライドはいつかは消えてしまうべきものです。目的の実現が快適域の中に入り、理性が実現に前向きになれたなら、そこでスライドの役割は終わりです。もちろん、モチベーションが下がってきたり、ふたたび理性が後ろ向きになってきたなら、もう一度スライドの出番です。でも、理性がポジティブである状態でスライドをさらに使い続けると、目的の実現に与えられている重要性が過大になってしまって、過剰ポテンシャルを産み出してしまいますね。ここらへんは慣れが必要な気がしますが、ポイントはいつでも重要性にあります。
スライドについては、これで解説は以上になります。わたしが個人的に注目しておきたいのは、下記の部分です。
自分が家にいることを実感してみるのだ。ここはあなたの家なのだから。苦悶する夢想家のような目つきで、手の届かないものや遥か遠くにある景色を畏敬の念をもって眺めるように、あなたの家を眺めてはいけない。あなたはすでにその家を所有しており、それが現実のことであると装うのだ。
以前に書いた記事で、引き寄せの法則について触れたことがあります。そこで、引き寄せの法則では「欲しい欲しいと願うのはそれを持っていないと暗に言っていることになる」ので「そうではなく、それをすでに持っていると考え、自分の周波数をそれを持っている状態の周波数にあわせるのだ」と言っているが、そのように自分を偽ることはできないと述べました。
ゼランドはこれに対して、「それが現実のことであると装うのだ」と言っています。この違いが実はけっこう大きいとわたしは思っています。ここでゼランドが言っているのは「スライドを使って臨場感をコントロールして、目的を快適域の中に入れる=現実のことであると装う」ことができれば、理性はそれが実現可能だと思えるようになるということです。
そもそも、目的が現実化された(=すでに持っている)と思うことが本当にできるのであれば、魂もそれを望んでいる限りにおいては、どんな目的も実現できてしまいますね。
それが難しい(わたしは不可能だと思いますが)からこそ、ゼランドはそのようなことは一切言っていません。トランサーフィンは周波数の観点から人生を説明するものですから、もしゼランドが「目的はすでに実現している=すでに持っている」状態の周波数に自分を同調させることが可能だと思っていたのであれば、スライドという技法が登場することはなかったはずです。
今回はここまでになります。次回は、「目的と魂と理性の一致」について、もうすこし掘り下げてみたいと思います。読んでくださって、ありがとうございました🙂
記事へのリアクションや記事執筆への励ましのサポートありがたく頂戴します🙏 また、プロフィールにAmazonほしいものリストも掲載しています。こちらもぜひよろしくお願いします!
