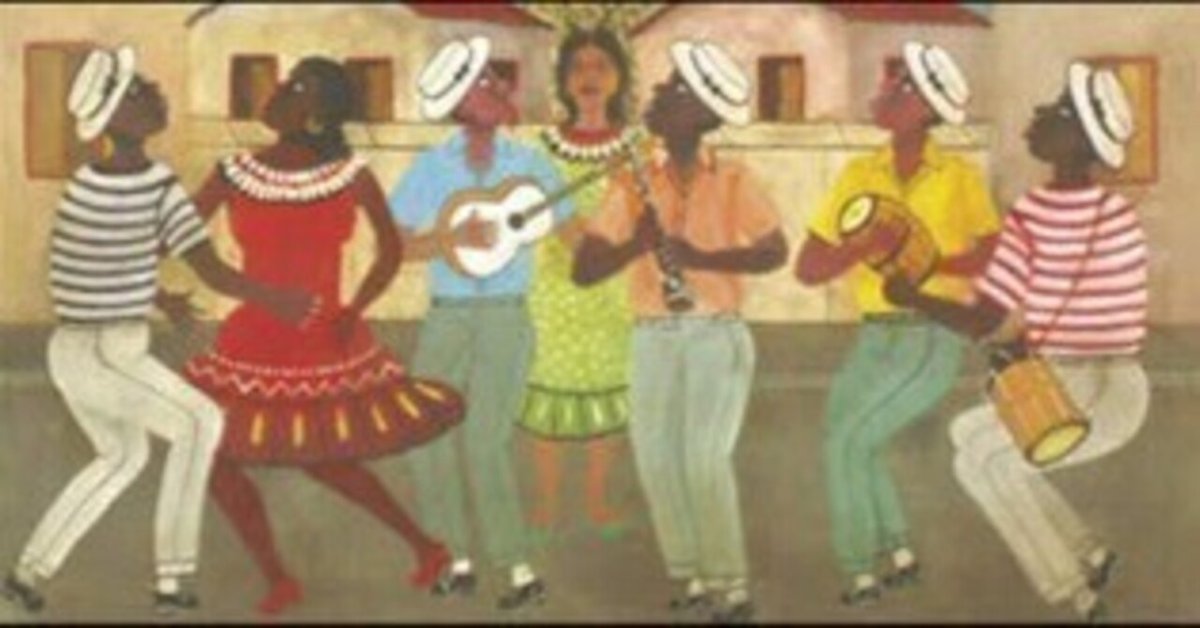
Cuicaクイーカという楽器
サンバパレードを見たことはあるでしょうか。
打楽器隊の最前列で太鼓の中に手を突っ込んでキュキュキューと異様な音を出しているのを見たことがある人だと、ああ、あれをクイーカと呼ぶのかと分かるでしょう。

統計データがあるわけではないので確かではありませんが、大変に珍しい 楽器で、きっと日本の奏者は100人くらいだろうと思われます。
北半球でも300人くらい、当のブラジルでも500人が精々でしょう。
濡れた浴槽に手をかけた時、キュッと音が出ることがあります。
英語にスクイキー・クリーン(squeaky clean)という言葉があって、 ピッカピカに磨いて、擦ったらキュッ、キュッと音がするくらい 綺麗になったという意味です。
スクイキーとクイーカ、どこか発音が似ているところをみると、 音感から名称になったのでしょう。
擦って出る音をコントロールして楽器にしたものは、洋の東西を問わず
結構あります。
一般的に擦って音を出す楽器と言えば、バイオリンやチェロが挙げられますが、太鼓型というと珍しい楽器の部類に入り、分類としては
フリクションドラム(friction drum) 擦奏太鼓(さつそうだいこ)に
属します。
クイーカの起源はアフリカで、逸話が色々とあります。
どれも真実味があってクスッと笑えるものもあります。
・狩りに出て獲物が捕れた、今から帰るから火を起こしておいてくれと
家族に伝えるのに鳴らしたという説。
西アフリカのブルキナファッソのモシ人が、打音の変化で遠くの仲間に
意思を伝えていたというトーキングドラムはよく知られており、
フリクションドラムも同じように使われたのかも知れない。
・集落に忍び寄り、食べ物を盗んでゆく小動物を脅すためにライオンの
唸り声を模して鳴らしたという説。
・また、さもありそうな話としては狩猟用で、雌豚が雄を誘う声を
模して、いい気分になってポーッとしている雄豚を捕らえるという説。
この話を男子にすると一様に同情して苦笑いになります。
クイーカの演奏で最高の褒め言葉は「セクシーね!」で、
この話があながち作り話とも思えません。
マルセロ・スドウ氏からサンバ楽器として取り入れられた時の話を
聞いたことがあります。
ブラジルでサンバの演奏でフリクションドラムが参加しているのを見て、
誰かが叫んだそうです。
「あれはアフリカの成人式の儀式で鳴らすプイータじゃないか!」
男子の成人式は、勇気を示すために高いところから飛び降りたり、
苛烈な通過儀礼があったそうです。
きっとそのような荘厳な儀式を猛獣の鳴き声の擬音で演出したらさぞかし
盛り上がったに違いありません。
クイーカの音は、不思議なことに動物に共振するようで、
家で鳴らしていると三軒先の家のシバ犬がつられて、
気持ちよさそうに遠吠えしたことがあります。
また、クイーカ仲間が屋形船を借り切ってお台場で空に向けて
鳴らしていたら、カモメが反応を見せました。
ある者が鳴らすとカモメは集まってきて上空を旋回しました。
ところが別の者が鳴らすとサーッと散って行ったのです。
摩擦音というのは、どうも生き物の本能に響くもののようです。
けだし、バイオリンの名曲チゴイネルワイゼンなんかを聴いていると、
間違いなく胸が高鳴り、血圧が高まります。
ヨーロッパのフリクションドラムは、ライオンの咆哮という意味の
ライオンズローア(Lion’s roar)と呼ばれています。
ドイツ人も、このフリクションドラムには思い入れがあるようで、
特別に名前をつけています。それは「ワルトトイフェル・森の精」で、
この音から大自然の神秘を感じているのでしょう。

擦って音を出す楽器は東洋にもありました。
「私家版 楽器事典」で菩薩様が演奏している絵を紹介しています。
信西古楽図(平安時代の巻物)

中国には古くから摺鼓(すりつづみ)や揩鼓(かいこ)という
楽器があって、太鼓の表面を指で擦り、裏面で叩いて調子を
とっていたようです。

この絵にあるように、演奏して恍惚に入る様子は、
現代のクイーカ奏者となんら変わりがありません。
こう見てくると、クイーカは音色の多様さという意味でフリクションドラムの中で最も進化した形といえるでしょう。
おそらく、日本人が初めてクイーカの音に触れたのは、「ゴン太くん」ではないでしょうか。
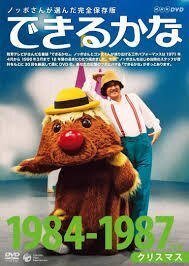
1970年から1990年まで放送されたNHKの子供向けの番組「できるかな」
の中に出てきたキャラクターのゴン太くんが発するグーググという声は、
聞き慣れない音で、久しく「謎」でしたが、後にクイーカだったと
明かされたのでした。
サンバ楽器としてのクイーカの役割
サンバの演奏においてクイーカには、どのような効果が
期待されているのでしょうか。
パゴージ(小編成の演奏)の場合は、曲の流れや切れ目に奏者の
個性を生かしたフレーズを入れて盛り上げたり、パルチードアウトで
安定感を持たせたり、合いの手を入れて哀愁を帯びさせたりして、
曲に奥行きや豊さを与え、サビでは感情の高まりを助長したりします。
一方、サンバカーニバルのパレードの場合、打楽器隊は高速でテクニカルな演奏を目指しますが、ややもするとそれは機械的で角ばった平坦な感じに
なります。
そこに異質のクイーカ音が入ることで丸みが出て、エンヘード(テーマ曲)の情感を醸し出すことができます。
それでも音量的には打楽器群に対して劣勢になり、リオの多くのエスコーラは、クイーカの音程を揃えて、同じフレーズで演奏して音を集中させて
音量を稼いでいます。
ジレトール(指揮者)は、スルド(大太鼓)の音が遠くてマラカサォンが
聞き取りにくく、隊列のすぐ前に位置するクイーカのフレーズを聴いているというので、責任は重大です。
マラカサォンとは「マークする」という意味で、リズムのポイントを決めてゆくわけで、クイーカの演奏もポイントを捉えたメリハリが
重要になります。
そう言う意味でクイーカは叩いて音を出しているわけではありませんが、
強く打点を意識した演奏が求められるのです。
ジャズやポップ音楽を聴いていて、たまにクイーカの音が聞こえたり、
テレビのコマーシャルなどで効果音として、瞬間的にでもクイーカ音が
聞こえると奏者として嬉しくなります。
最後にクイーカの名手オズワルジーニョの超絶技巧をご覧頂きましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
