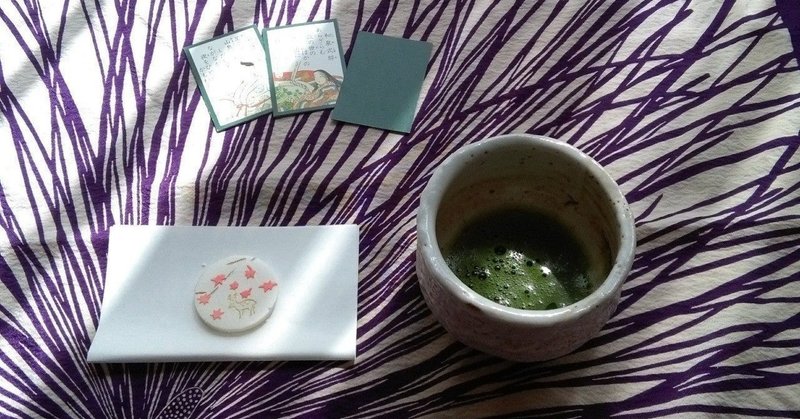
第18週 木曜日 作家・歌人・漫画家 高階貴子・高内侍・儀同三司母
18人目の作家·歌人·漫画家カテゴリーの女性は、平安時代の女流歌人で女房三十六歌仙に数えられる高階貴子,儀同三司母また高内侍です。
高階 貴子(たかしなの きし / たかこ)は、通称は高内侍(こうのないし)、または儀同三司母(ぎどうさんしのはは)とも呼ばれます。前者は女官名、後者は息子藤原伊周の官職の唐名(儀同三司)によるものです。
生年は不詳 です。
従二位高階成忠(923年 - 998年)の娘ということは分かっています
また生母も不詳。
兄弟に右中弁信順・木工権頭道順・伊予守明順らがいます。
和歌を能くし、女ながらに詩文に長けたことが当時から知られていて、『大鏡』など諸書にその名前があるそうです。
円融朝に内侍として宮中に出仕し、漢才を愛でられ殿上の詩宴に招かれるほどであった。
おなじ頃、中関白藤原道隆(953年 - 995年)の妻となり、内大臣伊周(974年 - 1010年)・中納言隆家(979年 - 1044年)・僧都隆円(980年 - 1015年)の兄弟及び長女定子を含む三男四女を生んだ。
夫・道隆が永延3年(989年)に内大臣、永祚2年(990年)5月に関白、次いで摂政となり、10月に定子が一条天皇の中宮に立てられたため、同年10月26日、従五位上から正三位に昇叙。一方、貴子腹の嫡男伊周も急速に昇進し、正暦3年(992年)十九歳にして権大納言に任ぜられ、翌々年さらに内大臣に昇ったため、貴子は末流貴族の出身ながら関白の嫡妻、かつ中宮の生母として栄達し、高階成忠は従二位と朝臣の姓を賜ったそうです。
ところが、長徳元年(995年)4月10日に夫・道隆が病死すると、息子の伊周と隆家は叔父道長との政争に敗れ、権勢は道長側に移りました。
翌年になって、伊周と隆家は、花山院に矢を射掛けた罪(長徳の変)によって大宰権帥・出雲権守にそれぞれ左降・配流されます。
貴子は出立の車に取り付いて同行を願ったが、許されなかったそうです。
その後まもなく病を得て、息子の身の上を念じながら、同年10月末に薨去した。四十代であったと推定されています。長徳2年(996年)10月のことでした。
百人一首の54番の歌が 高階 貴子の歌です。
中関白かよひそめ侍けるころ 儀同三司母
忘しの行末まてはかたけれは けふをかきりの命ともかな
意味
「いつまでも忘れない」という言葉が、遠い将来まで変わらないというのは難しいでしょう。だから、その言葉を聞いた今日を限りに命が尽きてしまえばいいのに。
この歌は『新古今和歌集』 第十三 恋歌三にもあり、また
藤原定家は『定家八代抄』にも撰んでいるそうです。
この歌はあった関白・道隆が夫として作者の家に通いはじめた頃に歌った歌です、という意味で、新婚ほやほやの妻が一番幸せな時期に読まれたものと考えられています。
平安時代の貴族の夫婦生活は一夫多妻制で、結婚当初は男性が女性の家へ通ってくるのが慣習でした。これを「通い婚」といいます。2人は新婚ほやほやのアツアツですから、毎日のように夫が通ってくるこの時期はさぞや幸せな日々だったでしょう。だから作者は幸せに心から喜び「今、このまま死んでしまいたい」と歌っています。
ただ、通い婚は一種残酷な制度で、夫が妻に愛情を感じなくなると家を訪れなくなり、そのまま離婚となります。家に通っている間は贈り物や生活費などが潤沢に妻の家に贈られるのですが、通わなくなるとそれも途絶え、妻の家はさびれて貧しくなっていきます。当時の女性は待つことしかできず、男が来なくなり子もなければ生活もできないかもしれない環境にありました。儀同三司母はそういう将来のことを、幸せの絶頂で感じたのかもしれません。将来に一抹の不安を感じながらも、それを知っているからこそ今の愛に命をかける。百人一首の愛の歌が典雅な中にも激しい情熱を秘めているのは、そういう当時の生活の姿があったからかもしれません。
この歌は技巧を好んだ新古今集の中には珍しいほど技巧をこらさず、素直に自分の想いを描いた歌なので、後世の歌人たちは、この歌を「くれぐれ優しき歌の体(ほんとうに優しい歌だ)」と評価したそうです。
めぐめぐがすごいと思う高階 貴子のこと
1文芸の盛んな家に生まれて、若いころから詩の才能を開花させられたこと。
2そして結婚、子どもを産み家族と共に当時キャリアを積まれたこと
3そして技巧をこらさず、素直に自分の想いを描いた歌を詠まれて多くの後世の歌人にも影響を与えたこと。
もしサポート頂けたらとても嬉しいです。頂いた貴重なお代は本代にいたします。どうぞよろしくお願いいたします!
