
300年かけてつくった恵みの大地を、次の世代へ。国分寺食卓会議レポート【後編:国分寺食卓会議】
春分をすぎ、うららかな春の暖かさを感じ始めた3月下旬。めぐるめく事務局は、全国で活動する方々と共に、豊かな水と緑、農地が残る東京都国分寺市とその周辺を訪れました。
午前中は国分寺周辺の地域の生産者の方々をめぐるフィールドツアーを行い、実際に畑を見学。それぞれの生産者さんの想いを伺ったり、地域の農業の変遷や現状を伺うなど、東京でありながら様々な農産物を生産している国分寺周辺の豊かさや人々の魅力を、自らの足や目で体感しました。
(フィールドツアーについて、詳しくはこちらの前編レポートでお伝えしています)
そして午後は「国分寺食卓会議」として、訪問メンバーと国分寺周辺で活動する方々とでお互いのプロジェクトを発表・共有しあう「チャレンジピッチ」と交流会を行いました。
後編では、午後に行われたチャレンジピッチの様子を紹介します。
お互いのチャレンジから新たな気づき、学びを得る
全25名が参加する「国分寺食卓会議」は、国分寺周辺を訪れた地域外メンバーのチャレンジピッチ、国分寺周辺の地域内メンバーのチャレンジピッチ、そして地域内外のプレイヤー交流の3部構成です。
まずは地域外のメンバーの発表から。ここでは三菱地所広瀬からのめぐるめくプロジェクト紹介のあと、さまざまな地域から訪れたメンバーによるプレゼンテーションの内容をお伝えします。

【山形県河北市:かほくらし社/菊地さん】

かほく町の地域課題解決を通じて暮らしを支える「かほくらし社」の菊地航平さん。大学4年生の時にかほく町に出会い卒業後からかほく町で働いています。
取り組んでいることのひとつが、マーケットインによる高付加価値の農業の形成。市場でニーズのある商品を見定めて生産者と一緒になって商品作りを推進しています。
たとえばワイン醸造については「かほくワイン用ぶどう研究会」を立ち上げ、国産ワインの需要が高まる中、ワイナリーを作ることで観光需要の喚起や新規就農者の呼び込みにつながることを目指しています。また、国産では珍しいヘーゼルナッツとアーモンドに着目し、「かほくナッツ研究会」を組織して耕作放棄地を活用し、無肥料無潅水で栽培を始めています。
3次産業として設けた東京・三軒茶屋のアンテナショップについても触れ、今後も閑散期に他の地域と連携して販路を共有するなど、地域を超えた方々とも連携していきたいと展望を語りました。
【愛知県豊橋市:中部ガス不動産/兵藤さん】

都市ガスのインフラを担う中部ガスの関連会社で、駅前再開発などまちづくりに携わる「中部ガス不動産株式会社」に所属する兵藤太郎さん。
兵藤さんたちが東三河エリアで目指すのは「フードクリエイターの聖地」。2008年に開業したホテルアークリッシュ豊橋では、地元の優れた食材の提供にこだわり続け、生産者との信頼関係を構築してきました。そこからさらに広がり、2021年には食文化体験の場としての「emCAMPUS(エムキャンパス)」が誕生。
また、優れた技術や経験を持つ生産者を集め、料理人と共に食材へのこだわりや思いを伝える「FARMERS COLLECTION(ファーマーズ。コレクション)」や、生産者と料理人をマッチングしてメニュー開発までを伴走支援し、地域内循環をフォローする「Farm to Table(ファーム・トゥ・テーブル)」など、生産者や料理人が主役となって輝けるような、数多くの取り組みが生まれています。
【愛知県豊橋市:豊橋百儂人/鈴木さん】

次は同じく東三河エリアで農業団体「豊橋百儂人」の鈴木直樹さん。鈴木さん自身はさつまいも農家で、皆さんにお土産として美味しい芋けんぴを持ってきてくださいました。
「豊橋百儂人」というのは豊橋周辺の農家の集まりで、現在は35歳~65歳の、15名の農家と2名の事務局で構成されている団体です。何か特定の品目の組合ではなく、それぞれ農家で品目が異なるため、多品目の農家集団となっています。
活動としては15年目。「農の価値を最大化してwell-beingに貢献するアグリイノベーター集団」を掲げ、イベントに参画、あるいは主催したり、生産物のブランディングなどを行っています。
意欲と思いのあるプレイヤーたちの、共創モデルをご紹介いただきました。
【都心部:STABLES/兼政さん】

「STABLES」の兼政さん。STABLESは、ルミネの事業部の一つが分社化して2019年に立ち上がった新しい会社です。「800°DEGREES」というピザの店を新宿、横浜、青山などで展開するほか、物販店やクレープ屋さんなども展開しています。
元々、宮崎、茨城の鉾田、山梨のワインなど、店舗で地域を独自にピックアップしていましたが、このめぐるめくプロジェクト参加をきっかけに「さとゆめ」と協働し、「Sato Tavola(サトターヴォラ)」という企画を始動しました。
日本全国のいい食材や、それらを取り扱う人を掘り起こして、自分たちが店を持つ、十分に集客力もある横浜や新宿でその地域や食材を紹介したり、ただメニューとしてコラボするだけでなく、来店者に実際にその地域に行ってもらうことで、お互いのファンの関係人口を増やしていこうという試みです。
この企画は、早速今年の2月から、山形県かほく町のかほくらし社さんと組んでスタートしており、今後も地域を変えて実施予定です。
【山梨県北杜市:FARMAN/井上さん】

山梨県北杜市で有機農業を営む「FARMAN」の井上能孝さん。
農業×X(エックス)という視点で事業開発を行っており、現在は5つの会社を経営しながら、「農業×X(エックス)」の深掘りを行っています
次々とユニークな事業を考えては実行に移している井上さんですが、そのひとつが「株式会社いろえんぴつ」という法人で行う事業。この会社では、都市部から地方への移住を考えている方に、一次産業系の作業に従事していただく派遣業を主にしていますが、今後は廃業支援も考えているとのことでした。
【マイナビ農業:横山さん】

農家さんや、農業に興味を持ってもらう方のための情報を発信する「マイナビ農業」の横山拓哉さん。
昨年6月にマイナビ農業の担当になったことを機に、農業や農家のことをもっと知らなければいけないと、全国230の農家さんを訪ね、その第一号がFARMANの井上さんだったのだそう。
今回は「マイナビ農業」をもっと農家目線で良い媒体にしていきたい!と意気込み、
「マイナビ農業」の新しい事業のヒントになればと、この会議に参加しました。
【静岡県三島市:tane/岡本さん】

三島市在住のデザイナーであり、「Salveggie(サルベジー)」というプロジェクトを主宰する「株式会社tane」 の岡本雅世さん。「Salveggie」を2021年に始めて、ちょうど3周年になります。
「Salveggie」とは、様々な理由でロスになってしまう野菜を「はじかれ野菜」と呼び、生産者や野菜のPRや収穫イベント、加工品などに楽しくチェンジしていくプロジェクト。
「廃品の再利用」などを意味する「サルベージ」ではなく、子供にも伝わるようにと「猿」と「野菜(vege)」をかけて「サルベジー」と命名。チームを作り、「野菜が美味しい」「楽しい」といった切り口で様々な取り組みにチャレンジしています。
【ユーグレナ:渡辺さん】

「株式会社ユーグレナ」は、世界で初めて微細藻類ユーグレナ(ミドリムシ)の屋外大量培養に成功し、サプリメントやエネルギーほか様々な用途に応用している会社です。
直近の事例として渡辺さんが関わっているのは、今話題の「クラフトサケ」を造る秋田・男鹿のベンチャー企業、「稲とアガベ」との連携事業。活用できずに年間400t廃棄されてしまっている酒粕をユーグレナの技術で肥料に変え、その肥料で栽培した米でお酒の醸造をするという地域資源の循環モデルを進めようとしています。
この循環モデルができるまでには少し時間もかかることから、第一弾として、「稲とアガベ」が製造販売する酒粕を使った調味料にユーグレナを加え、「発酵マヨ〈石垣島ユーグレナ〉」を2月に発売。2月8日にメディア向け試食会も含めリリースしたところ、最初のロットは1週間で完売したとのこと。
今後は本格的に男鹿の棚田で肥料を使って米を栽培し、実証実験をしていく予定です。

地域の中で起きていることを共有する、国分寺チャレンジャーピッチ
そしてここからは、国分寺メンバーの発表です。
【めぐるまち国分寺:南部さん】

今回の午前のフィールドツアーを案内してくれた南部良太さん。農業デザイナーのかたわら「こくベジ」の運営をしています。
開始して9年目になる「こくベジ」は、当初国分寺市役所がリクルートに業務を委託するところから始まりました。
国分寺産の野菜を飲食店に届ける、その配達を担う役目として、仲間と南部さんで「めぐるまち国分寺」を立ち上げました。「地域のことを隅々まで知る仲間がいるからこそできた」と話します。
現在の加盟店舗は約90店舗で、火曜・金曜の週2回配達。当初はボランティアでやっていましたが、今はようやく最低時給くらいは稼げるようになったとか。それでも、副業でやっているのと、配達は「農のあるまちと人をつなぐ手段」としてやっているという思いがあるからこそできるのだといいます。
少量多品目の農家が多いゆえに、急に予定していた野菜がなくなったり、大量の注文を受けて数え間違いが発生してしまったり、野菜自体が安いゆえの利益率の低さに悩まされたり・・・と、課題は山積み。
ですが、「小さいながらも続けられることを大切に、農のある暮らしを日常に溶け込ませるために、いろんな人たちを巻き込みながら広げていきたい」と思いを語っていたのが印象的でした。
【国立:エマリコくにたち/本多さん】

「東京農業活性化ベンチャー」をうたい、地元の旬と東京野菜の魅力を伝える企業「エマリコくにたち」の本多航さん。
本多さんは居酒屋の店長をする中で農業、地産地消に興味を持ち、エマリコくにたちが実施していた体験プログラム「イートローカル探検隊」に参加し、運営にも携わるようになり、そこから入社した経歴の持ち主です。
4月で創業12年目を迎えるエマリコくにたちは、「まちと畑が近いという魅力を次世代に繋いでいきたい」「美味しい料理、好きな人、素材を誰が作っているかを知る、といったことを含めた楽しい食卓作りに貢献したい」という2つの思いで事業を展開しています。
主な事業は、地元野菜を直売する「しゅんかしゅんか」3店舗・旬の野菜を提供する飲食店2店舗の運営のほか、日本橋三越等への東京野菜の卸売や体験事業に力を入れています。
そして、本多さんが今年から新たに担っているのが、「まちと農業研究所」という役割。エマリコくにたちのこれまでのノウハウをBtoBで活用していこうとしています。例えば農家さんの野菜の宅配や体験プランなどを企業の福利厚生と組み合わせたり、地元の大手スーパーと連携し、種を植えるところから収穫して食べるところまでをセットで体験するプログラムを親子向けに提供したりと、早速徐々に動き出しているとのこと。
企業の力を借りることで、「まちと畑が近い」の有り難さや価値が、今後より多くの人に伝わっていきそうです。
【立川:小山農園/尾崎さん】

「カラフル野菜の小山農園」、尾崎三佐男さん。スーパーなどであまり見かけない珍しい野菜を、年間160品目も生産しています。
尾崎さんは元々、日本蕎麦屋で調理師として10年間活躍していましたが、結婚を機に農業に転身。畑の場所は5か所で、耕作面積はなんと3000坪にもなるそうです。「畑の隣が横田基地なので、月に一度マルシェを開催していたら英語も話せるようになってきた」と、楽しそうに話します。
珍しい野菜を作るようになったのは、王道野菜の市場への卸価格があまりにも安かったのがきっかけ。キャベツ1個が8円にしかならなかったことに疑問を感じていたら、仲間のレストランが「赤い大根作ってくれたら、全部買い取るよ!」と言ってくれたのが転機となりました。
販路は年々拡大中。ホテルに営業に行ってみたら、見事に総料理長に大根を採用していただいたのをきっかけに、その後名だたるシェフにも営業。その結果、有名シェフやホテルへ納品したり、メニュー開発にも参加するなど、快進撃を続けています。
【青梅:岩蔵エクスペリエンス/本橋さん】
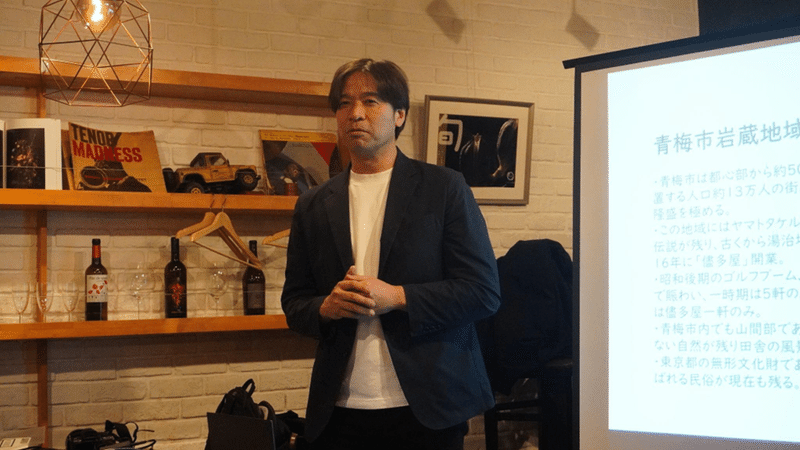
歴史文化や里山風情が残る青梅市岩蔵地域の魅力を体験などで伝える、「岩蔵エクスペリエンス」代表の本橋大輔さん。
青梅市岩蔵地域は、都心から約50km離れた多摩川の上流にあり、東京とは思えない自然が残り、田舎の風景が広がるところです。ヤマトタケルが岩蔵の温泉で傷を癒したという伝説もあり、古くから湯治場として利用されてきました。一時は5軒の旅館宿がありましたが、現在は1軒を残すのみ。
青梅全体で見ても宿泊客は伸び悩んでおり、農業環境も縮小している状況。そんな状況に懸念を抱き、里山文化と語り継がれる歴史を後世に残したいと青梅市生まれの本橋さんが仲間と立ち上げたのが、「岩蔵エクスペリエンス」でした。
これまでのような「温泉地として」ではなく、新たに旅館を中心とした賑わいづくりを目指し、「欲に負ける夜」と題した旅館を核としたイベントを取り組みの柱のひとつとしています。
また一方、「農業」も土地のもうひとつの魅力と捉え、CSA(地域支援型農業)の仕組みによって個性の違う4農家のブランディングを行ったり、建築士が設計したおしゃれな無人販売所を設置して珍しい野菜を置いたり、魚の養殖と水耕栽培を同時に行う「アクアポニックス」という農法で約10種類のハーブを育てたりといった取り組みも行っています。
【三鷹:冨澤ファーム/冨澤さん】
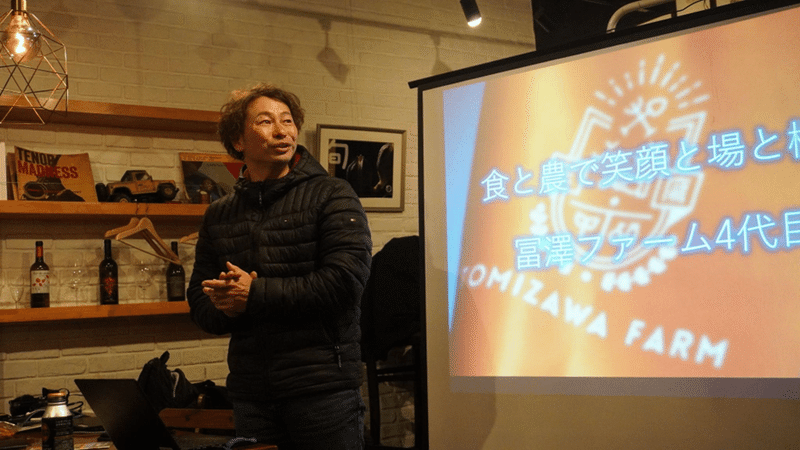
「食と農で笑顔と場と機会を創造する」を掲げる、冨澤ファーム4代目の冨澤剛さん。
栽培は80aの畑で、施設園芸と露地栽培を組み合わせ、旬野菜を年間30種類販売。資源循環型農業を掲げ、大学の馬術部の馬糞や酵素浴サロンの使用済み米糠、酒造会社の酒米糠、取引レストランからの生ごみ回収など、地域で出る、通常ゴミになってしまう有機物を上手に土壌に還元し、土づくりを行っています。
一方で、「作っているものは笑顔。農業はあくまで目的ではなく手段です」といい、農業の生産・加工・販売だけでなく、「農空間を利用したサービス業」に力を入れており、農場訪問者は年間のべ1000人も!「畑のオープンキャンパス」と名付けた取り組みでは毎月第4土曜日に畑をオープンにして、今では援農部・こそだて部・応援部・飲食部・大家部などが設けられています。
「子どもから60代の方まで、中には外国からの留学生もいて、多世代の方が参加してくれています。農業ボランティアも20〜30代と結構若い方も来てくれていて、農作業でリフレッシュ、ストレス発散になり、土に触れると癒されると言って参加しています」
休日に畑に来る人どうしはすぐにお互い仲良くなり、集まる方々との化学変化で取り組みが広がっていったのだそう。野菜がたっぷり入ったパウンドケーキの開発や、援農に来てくれた方に提供する賄いランチも、来てくれた方々のおかげで実現したこと。
【国立:くにたちはたけんぼ/小野さん】

コミュニティ農園「くにたちはたけんぼ」を運営する、NPO法人くにたち農園の会理事長の小野淳さん。コミュニティ農園を事業として維持しているポイントを、いくつか教えていただきました。
年間7000人もの人が訪れるコミュニティ農園には個人区画がなく、より多くの方が農園に気軽に関われる仕組みができています。うさぎ、烏骨鶏、ミニ山羊、ミニチュアホースなどの動物たちが訪れる子どもや大人たちを和ませ、遊具なども設置されています。
平日は子育て支援、休日は体験型観光用にと、サービス内容を変えて提供。最近は学校に行かない子が増えており、平日は放課後クラブ、森のようちえん、不登校フリースペースとして子どもたちを受け入れる場になっています。一方休日は、田んぼのステージでライブをしたり、グランピングをしたり、農体験を提供したりと、遠方からくる方に向けたサービスを提供。
また、立ち上げ初期に関わっていたメンバーが子育てしながら継続的に事業に関われるよう、子育て関連の事業が拡大するとともに、運営拠点も増えていきました。現在は、コミュニティ農園、子育て古民家、農泊ゲストハウス、認定こども園、畑つきレンタル平屋など、徒歩圏内に5つもの拠点を運営しています。
地域の農地・農的文化を活用し、不登校の子供に寄り添ったり、空き家を活用したりなど、社会課題に向き合いながら、うまく人材を確保して多拠点で事業を展開することも、利益を確保するポイントなのだそうです。
発表が終わった後はみんなで乾杯!

一人ひとりの発表が終わったあとは、美味しい料理とお酒で交流タイムです!
発表と交流会の会場となった「くにたち村酒場」は、本日発表されたエマリコくにたちさんが運営する、近隣の野菜がたっぷり食べられるお店。約30種類の農家さんから、毎日新鮮な野菜が届きます。
それぞれ感想を言い合いながら、お互いをより深く知ったり、一緒にできそうなことを探ったりと、ご縁を深める時間となりました。
食卓会議は、引き続き全国各地で開催していきます!
今回ここで生まれたつながりやエネルギー、参加者が得た知見などが、また多くの種を蒔き、そして育っていくことがとても楽しみです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
