
盲学校関係の行事・イベント まとめ
盲学校からの発信ということで、盲学校でのさまざまな行事やイベント、研究会について紹介していきたいと思います。
1.運動関係
視覚障がいスポーツの大会が各地区ごとに開催されています。盲学校は各都道府県に1校だけのところも多く、初戦が地方大会からスタートになります。平成29年度から全国盲学校フロアバレーボール大会が開催されています(それ以前は野球大会)。
(1)地区フロアバレーボール大会
フロアバレーボールは全盲や弱視の視覚障がい者と健常者が一緒にプレイできるように考案されている球技で、6人制バレーボール競技規則を参考にしています。多くの盲学校の体育授業や部活動として取り組まれています。
ルールの詳細は全国盲学校フロアバレーボール大会を参考にしてください。またJFVA日本フロアバレーボール連盟ホームページでボールやルールブックを販売しています。
地区大会を勝ち上がった代表が、全国盲学校フロアバレーボール大会へ出場します。

(画像は全国盲学校フロアバレーボール大会より)
(2)全国盲学校フロアバレーボール大会
毎年8月に、北海道、東北、関東、東海、北信越、近畿、中国・四国、九州の各地区の代表が集まる全校大会が開催されています。
令和元年には、第3回全国盲学校フロアバレーボールいわて大会が開催されます。
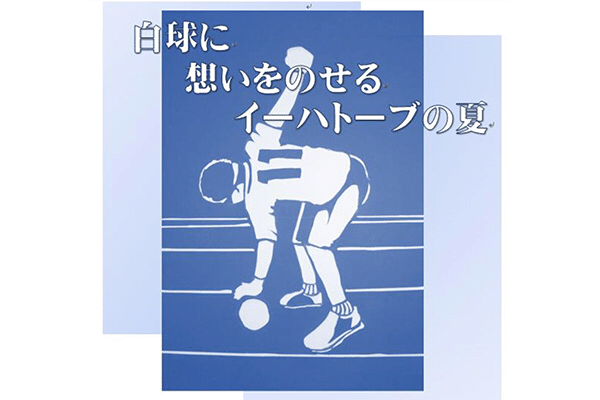
(画像は全国盲学校フロアバレーボール大会より)
(3)地区水泳大会
盲学校では水泳にも取り組みます。見えない子の水泳では、ゴールやターンの前に壁に激突しないよう、棒や釣竿の先にスポンジがついたタッピングバーで壁の前でタッチ(タッピング)して位置を伝えます。

(画像は日本パラリンピックサポートセンターより)
地区によっては一般の個人種目(自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ、メドレー)以外に、リレー種目も行なっています。
水泳はパラリンピック種目にもなっています。競技の詳細は日本障がい者スポーツ協会の「かんたん水泳ガイド」を参考にしてください。
(4)地区野球大会(グランドソフトボール)
ハンドボールを使用し、ボールの転がる音を頼りにプレーする、グランドソフトボールは、別名「静かな野球」とも呼ばれます。
視覚障害のある選手が1チーム10人で競技をします。男女の区分はありません。
10人のプレーヤーのうち4人以上は全盲の選手、その他は弱視の選手です。
全盲プレーヤーはアイシェード(目隠し)を着用し、ボールなどの音を頼りに守備や走塁、バッティング、ピッチングを行います。
ルールの詳細は全国盲学校野球大会を参考にしてください。


(画像は全国盲学校野球大会より)
かつては毎年8月に全国盲学校野球大会が開催されていましたが、生徒数の減少などもあり、平成28年度 第31回全国盲学校野球大会北海道大会を最後に、全国大会の競技はフロアバレーボールに変更になりました。
(5)地区卓球大会(サウンドテーブルテニス)
視覚障害者のために卓球をアレンジしたものが「サウンドテーブルテニス(STT)」です。通常の卓球と基本的に同じですが、視覚障害者のため、①卓球台のまわりが高くなっていて、球が落ちにくくなっている、②ネットは、低く張って、球はその下をころがして通す、③ボールの中に鈴が入っていて、音で球の位置が分かるようになっているなどのルールや用具に工夫がなされています。

(画像は富山県立富山視覚総合支援学校より)
各地区によっては、サウンドテーブルテニスの全盲の部・弱視の部以外に、通常の卓球をするものもあるようです。
ルールの詳細はこちらを参考にしてください。また日本視覚障害者卓球連盟ではルールブックを販売しています。
(6)地区ゴールボール大学
ゴールボールは縦18m横9mのコートで1チーム3人のプレーヤーがアイシェード(目隠し用のゴーグル)を着用し、鈴の入ったボールを相手チームに転がしてゴール数を競う視覚障害者スポーツです。パラリンピック種目になっています。

(画像は毎日新聞より)
ルールの詳細は日本ゴールボール協会を参考にしてください。ルールブックのデータも掲載されています。
(7)全国盲学校通信陸上競技大会
全国盲学校体育連盟(全盲体連)が、全国盲学校新体力テストとともに集計を行い、全国に結果を知らせています。
また地区によっては陸上競技大会が開催され、50m音響走、100m円周走、100m、200m、800m、1500m、4×100mリレー、立ち幅跳び、走り幅跳び、走り高跳び、砲丸投げ、ソフトボール投げ、ジャベリックスローなどの競技が行われているようです。

(画像はJAMA日本ブラインドマラソン協会より)


(画像は栃木県立盲学校より)
(8)全国視覚障害者学生柔道大会
毎年8月に開催されています。対象は盲学校在籍か中学校・高等学校・大学・視覚障害者関係施設に在籍者する学生生徒です。

(画像はFacebook@NPO法人日本視覚障害者柔道連盟より)
視覚障害者柔道と晴眼者柔道との大きな違いはお互い組んでから始まることです。組み手争いがないため、組み合った状態からいかに相手を崩すかが勝負の分かれ目になります。
ルールの詳細は日本視覚障害者柔道連盟を参考にしてください。
2.文化関係
(1)地区弁論大会
7分間の弁論を行い、論旨や声量、感銘度などをもとに審査されます。各地区の代表が、10月の全国弁論大会へ出場します。

(画像は毎日新聞より)
(2)全国盲学校弁論大会
各地区の代表が集まり、点字毎日との共催で毎年10月に開催されます。

(画像は住友グループ広報委員会より)
平成30年度の第87回全国盲学校弁論大会の様子は、NHKハートネット 視覚障害ナビラジオで聴くことができます。
また弁論大会特別協賛の住友グループ広報委員会で過去のものも含めた弁論を聴き、また原稿を読むことができます。
(3)全国盲学生点字競技大会
点字での50音書き、転写、聴写の3つの能力を競う競技大会で、各盲学校で開催される通信大会です。
偶数年の点字の日である11月1日を基準日に開催されます(奇数年は珠算競技大会)。
対象は盲学校在籍の児童生徒で、選手は小学部・中学部・高等部に分かれ、各部2名以内になっています。
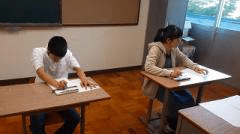
(画像は京都府立盲学校より)
(4)全国盲学校珠算競技大会
読み上げ算など4種目で競われる競技大会で、各盲学校で開催される通信大会です。
堀江そろばんという視覚障がい者用のそろばんがあり、玉を前後に倒して使います。プラスチック製の23桁で、位取りをわかりやすくするために3桁毎に凸点が打ってあります。
奇数年の点字の日である11月1日を基準日に開催されます(偶数年は点字競技大会)。

(画像は愛知県立名古屋盲学校より)
(5)視覚障害者珠算検定
毎年日本商工会議所委託で開催され、各盲学校が会場になります。
AクラスからFクラスまでの6段階に難易度が分かれており、Aクラスが一般の珠算検定試験の3級に相当します。
視覚障がい者用のそろばんで計算し、計算後は
点字盤やパーキンスブレイラーなどで答えを記入します。それ以外は「願いましては、 ○○円なり、○○円なり、...」と一般的な読み上げ算 などと同じです。
実はアメリカの盲学校でもそろばんを使った計算練習をしているそうです。
(6)全国盲学生短歌コンクール
岐阜県立岐阜盲学校の高等部生徒会が主催。対象は盲学校に在籍の児童生徒です。毎年10月末が締め切りで、翌年2月頃に特選、入選、佳作が発表されます。
平成30年度 第62回の特選作品を紹介します。
風に乗って 走るのが好き ひらひらの 服がパタパタ 空までとべそう

(画像は千葉県立盲学校より)
(7)全国盲学校・台湾・韓国囲碁大会
平成29年度から囲碁の町、岩手県大船渡市で開催さ」ています。平成30年度は台湾、韓国の盲学生も招待されているそうです。

(画像は奈良県立盲学校より)
視覚障がい者用に立体囲碁アイゴが販売されています。盤面の線が立体に浮き上がっており、碁石の裏面には切れ目が入っているため、しっかりと碁石を盤面に固定できるようになっている商品です。裏面は九路盤として使えます。

(画像は日本ライトハウス情報文化センターより)
(8)ヘレン・ケラー記念音楽コンクール
ヘレン・ケラー記念音楽コンクールは、1949年(昭和24年)12月13日、全国盲学生音楽コンクールとして、東京・有楽町の毎日ホールで始まりました。
2009年のバン・クライバーン国際ピアノコンクールで優勝した辻井伸行さんら、国際的に活躍する音楽家を輩出しています。また、このコンクールで得た自信を、その後の道に生かして 音楽とは別な分野で優れた業績を挙げた人も少なくありません。
詳細は東京ヘレン・ケラー協会のホームページを参照してください。

(画像は東京ヘレン・ケラー協会より)
3.学習・進路関係
(1)科学へジャンプ
①サマーキャンプ
科学へジャンプはこのサマーキャンプからスタートしました。毎年8月に4日間にわたり開催されます。
このキャンプでは、視覚障害のある中高生の皆さんに科学に対する関心を高めて頂くため、モノ作り・理科実験・数学・コンピュータ・コミュニケーションスキルなどを、少人数のグループに分かれて楽しみながら学んでいきます。
詳細は科学へジャンプのホームページで確認してください。

(画像は科学へジャンプより)
②科学へジャンプ地域版
北海道、東北、北陸、関東、東海、近畿、中国・四国、九州の各地域で盲学校を中心に科学へジャンプ地域版が開催されています。詳細はお近くの盲学校又はこちらから確認しでください。
③ITワークショップ
プログラミングなどに特化した、ITワークショップも開催されています。詳細はこちらのページから確認してください。

(画像は科学へジャンプより)
(2)視覚障害高校生のための高大連携プログラム
広島大学大学院教育学研究科 氏間研究室(うじらぼ)では、高校生と過年度卒業生を対象に大学進学へ向けて、大学を知る、補助具やICTの活用、合意形成のコミュニケーションを身につけるためのスキルアップセミナーを開催しています。

(画像はうじらぼより)
4.生徒会関係
地区盲学校単位で、生徒会同士の交流も行われています。
文化祭での交流や、夏季研修会でキャンプやスポーツ、あん摩などを通して交流する地区などもあるようです。

(画像はTwitter@invote_officialより)

(画像は奈良県立盲学校より)

(画像は千葉県立盲学校より)
表紙の画像は近畿農政局より引用した京都府立盲学校の写真です。京都府立盲学校は京都盲啞院にはじまる、日本で最初の盲学校で、その初期の史料は国の重要文化財に指定されています。
