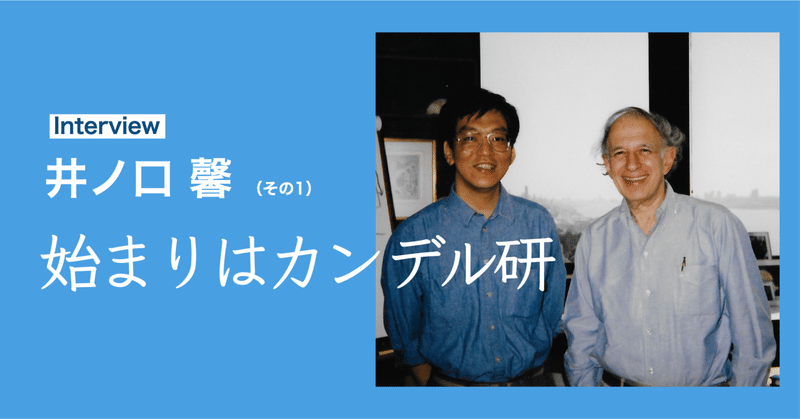
始まりはカンデル研 ── 井ノ口 馨
井ノ口 馨 富山大学学術研究部医学系 卓越教授
ちょうど36歳の誕生日にアメリカに渡り,コロンビア大学のEric Kandel(エリック・カンデル)先生の研究室でポスドクとして約3年間研究を行いました。それまで,日本では分子生物学の研究を行っていたので,神経科学の研究はこのときがスタートです。
分子生物学から神経科学へ
以前から脳の研究に興味はあったのですが,脳は複雑で,分子レベルでどうやって切り込んだらいいかわからずにいました。そんなときに偶然読んだ塚原仲晃教授(大阪大学)の著書『脳の可塑性と記憶』(1987年刊)が,私の人生を変えたのでした。
塚原博士は,成獣の脳でもシナプスが発芽することを発見し,世界的に注目されている科学者でしたが,1985年の日航機墜落事故でお亡くなりになったのです。この著書は,お弟子さんたちが博士の草稿をまとめたもので,そこには,次のような内容が記されていました。「記憶の過程では新しいシナプスが作られていると思われるので,記憶,特に長期記憶では,遺伝子による制御が働いているだろう」と。私ははっとしました。それでは,この遺伝子を見つければいいのか。それなら分子生物学者の私にもできる。そう気づいたのです。
ちょうどその頃でした。Kandel先生もNatureに総説を発表し,長期記憶を分子レベルで解き明かしていくことの重要性を説いていました。それならば,Kandel研究室に行き,長期記憶で働く遺伝子を見つけてやろう。そう決心したのです。
Kandel研に行く
大脳生理学者であり,精神科医でもあるKandel先生。当時はまだノーベル賞受賞前でしたが,すでに世界的に名を知られていました。Kandel先生のもとで研究するために,まずは日本人の著名な大脳生理学の専門家に推薦状を書いてもらおうと考えました。しかし残念ながら,脳研究が未経験の私にはそれを書いてくれる専門家はいませんでした。それどころか,「遺伝子で脳がわかるわけないだろう」とまで言われたりもしました。
しかたなく,自分で手紙を書くことにしました。「このような手法で記憶に関係する遺伝子を見つけることができるのではないか」とKandel先生に提案したのです。その手法は,分子生物学者にとってはごく普通のものでしたが,「面白いからどうぞ来てください」という手紙が,すぐに返ってきました。しかも,シニアーだったこともあるでしょうが,破格のサラリーで。私は家族3人を連れ,ニューヨークのコロンビア大学に向いました。
先見の明があったKandel先生
神経科学の「し」の字も知らない私をKandel先生は受け入れてくれたんですね。先生は,記憶研究や脳科学にとって,これから分子生物学という新しい技術が重要になることを,すでに予見していたのだと思います。Kandel研究室に行ってわかったのですが,私の前後には,分子生物学を専門とするポスドクが続々と入っていました。Kandel先生は明らかに戦略的に,分子生物学ができる人間を集めていたんです。私は,たまたま運がよかったのだなと思います。
Kandel研究室では,モデル動物としてアメフラシを用いて,記憶に関する遺伝子を網羅的に探すという作業に取りかかりました。アメフラシはエラひっこみ反射と行動を学習するので,その長期記憶が形成されるときに発現が上がってくる遺伝子をつかまえたのです。マイクロアレイもハイスループットのシークエンサーも登場する前の時代ですから,網羅的といっても,ディファレンシャルスクリーニングを行い,得られた候補遺伝子を1個1個クローニングし,塩基配列を決定していきました。同時に,遺伝子1個1個についてノーザンブロットを行い,発現レベルの変動を確認しました。数十種類以上見つかってきました。
たくさん遺伝子をつかまえても,それが本当に記憶にかかわっているかどうか簡単にはわかりません。しかし,得られた候補遺伝子のリストの中に,ユビキチンC末端ハイドロレース(UCH)遺伝子がありました。Kandel先生の古くからの同僚であるJim Schwartz先生の研究室では,以前からユビキチン系のタンパク質分解が長期記憶に重要なAキナーゼの働きを制御していることを発見していました。Schwartz先生は『カンデル神経科学』の原著初版からの共同編集者で,隣に研究室を構えていました。そこで直ちに共同研究を開始し,遺伝子の機能の詳細な解析をSchwartz研の別なポスドクが担当し,UCHが長期記憶の形成に必須の遺伝子であることを証明できたのです。論文は,Cell*に掲載されました。
Kandel先生の記憶力の良さに驚かされる
忙しい人でしたが,1週間に一度程度は研究室を回って,どんな実験結果が出ているのかと一人一人に聞いて回ります。とても明るい方で,「ハーイ,カオル」とにこやかに声を掛けてくれるのですが,そのとき必ず聞いてくるのは,「How is cooking?」(今どんなふうに「料理」してるんだい?)「What’s new?」(何か新しいことを見つけたか?)。毎回必ずです。
また,私は,1週間前の話は覚えていないかもしれないからと,先週した説明を話の前段として繰り返そうとすると,驚いたことに,「それはもう先週聞いたよ」と言われたのです。30〜40人もいる研究室のメンバー個々の話を,ちゃんと覚えているのです。メモもとらずに。記憶力の良さには本当に驚きました。
こわいと思ったことはありません。褒めて伸ばすタイプです。小さな発見でもすごく喜んでくれるから,ヨーロッパから来た口の悪いポスドクなどは,どうせ口だけなんだろうって言ってましたけどね。
好奇心の塊
各自の実験の進捗状況は,研究室で報告するだけでなく,「日曜日の定期便」でも行いました。毎週日曜日。そうです,夜9時頃にKandel先生から電話がかかってくるのです。「土曜と日曜で何か新しいこと見つかった?」と。ヨーロッパの学会に行っているときからでも,どこからでもかかってくるのです。
なんで電話? 土日に実験しろという圧力? などと最初は驚いたのですが,Kandel先生にはプレッシャーをかけるような気持ちは全くなく,単に新しいことを知りたいのだとわかってきました。研究に対してすごく貪欲であり,新しいことを知りたいという好奇心がとても強い人なのです。まあ,私も,金曜日に研究室で質問されても全部は報告せず,土日報告分としてとっておくことを学習しました(笑)。
あるとき,リボソームに関係した実験をしていたときです。リボソーム研究で高名な教授がコロンビア大学を来訪し,講演をすることになりました。神経科学にはまったく無関係な分野におけるリボソーム研究でしたので,私は気にとめてはいませんでした。しかし,Kandel先生は違いました。なんで聴講に行かないんだと言いながら私を誘い,自ら車を出して,マンハッタンの北はずれにある医学系キャンパスから50ブロック以上も南に離れたところにある別なキャンパスまで講義を聞きに行ったのです。少しでも研究に関係する可能性があるなら,どんなことでも吸収するという方でした。この好奇心の強さが,視野の広さをもたらしているのだろうと思います。
『カンデル神経科学』の各章の著者たちが交代で医学部の講義をする
私がKandel研究室にいたときに,『カンデル神経科学』の原著第3版が出版されました。原著第3版は,おそらく著者全員がコロンビア大学の所属だったかと思いますが,医学部の神経科学の授業では,この本が教科書に使われていました。
1年間の通年講義。著者たちが自身の書いた各章を担当して,学生相手に講義をしていたようでした。すごいですね。なんと贅沢な講義だったことでしょう。
Kandel研究室で学んだ一番大事なこと
Kandel研究室には,NatureやScienceに論文をぽんぽん出しているポスドクたちがいます。彼らはすごく優秀なんだろうと,最初は自分とは別世界の研究者だと感じていましたが,いっしょに議論してみると,考えていることは自分とあまり変わらないので,それがすごく不思議でした。
しかし,そのうちにわかってきたことがあります。自分と何が違うのか。それは,研究で一番大事な疑問(question)が何かを,彼らはしっかりと把握しているということです。
研究で一番大事なこととは,どういう疑問に取り組むか,ですよね。例えば,自分が見つけた疑問は面白く,重要だと思って取り組む人は多いと思いますが,その疑問が解かれたとしても,その影響はあまり大きくないものが往々にして,というかほとんどでしょう。その疑問が,今の神経科学の中でどれだけ重要かということをしっかり意識している人は,そう多くはないのではないでしょうか。
しかしKandel研究室のポスドクたちは,一切実験せずに,毎日毎日談話室でコーヒー飲みながら同僚と延々と議論していることがよくありました。最初は,しゃべってばっかりで怠けているようにさえ感じました。しかしそのうちにだんだんわかってきました。今この瞬間に,記憶研究でどういう疑問が一番重要なのかをしっかりと把握しようとしていたのです。その疑問が解けたら,その結果は記憶研究の分野にばかりでなく,神経科学全体に波及効果がある。そういった疑問を的確に把握しようとする彼らの力がすごいと思ったのです。この能力は,Kandel先生といつも接しているうちに,先生が無言で発する「これは大事,これはつまんない」といったオーラの中から,自然と身についてきたのかもしれません。
しかも彼らは,そういう大事な疑問を見つけたときに,「自分たちは,やり遂げられる」という自信をもっていました。この感覚は,実際にKandel研究室に所属してみないとわからないことでした。そうした大きな問題への取り組みが別世界で起きていることではなく,自分とあまり変わらないレベルのポスドクたちによってなされている。それを目のあたりにして,自分でもできるだろう,そう思えるようになるということです。これが,Kandel研究室で学ぶことのできた最も大きいことです。そして,その経験を共にした多くの仲間とは,現在までも交流が続いていて,私を支えてくれています。
2022.10.2
聞き手:藤川良子
* Hegde AN., Inokuchi K., et al., Ubiquitin C-Terminal Hydrolase Is an Immediate-Early Gene Essential for Long-Term Facilitation in Aplysia. Cell, 89: 115-126, 1997
