特集・ウクライナ侵攻とメディア マスメディアが伝えないこと
放送レポート297号(2022年7月)
明治学院大学名誉教授 吉原功
犠牲になるのは民衆
ロシアがウクライナに軍事侵攻してから3ヵ月を迎える。この間、日本のメディアは連日、ロシアの蛮行とウクライナ市民の被害を報じている。ゼレンスキー・ウクライナ大統領のプーチン・ロシア大統領およびロシア軍への非難、国際社会への支援の訴えも、絶えることなく流されている。強大な軍隊を持つ侵略国が弱小の国家をすぐにでも制圧するのでは、との予測は大きく転換し、軍事的に敗北しているのはむしろロシア側だと指摘されはじめた。
国際法に違反するロシアの軍事行動に対し批判・非難が集中するのは当然である。だが腑に落ちない点も数多くある。「戦争」は国家権力同士の争いであり、犠牲になるのは民衆だ。マスメディアはこの点を曖昧にしているのではないか。ウクライナをこれだけ報道しながら、その社会がどうなっているのかが一向に見えてこないのは、そのためではないか。最も重要なことに触れないで、視聴者・読者を一定の方向にミスリードしていることはないか、等々の疑問、疑念が湧き上がる。
以下では、侵攻に至るウクライナ、ロシア、欧米諸国の動向を、主としてジャック・ボーの「ウクライナの軍事情勢」(原文フランス語、邦訳:https://note.com/14550/n/ne8ba598e93c0 抄訳:ピープルズ・プラン研究所のメーリングリスト=ML、ppl5月4日)に依拠して概観し、この「戦争」の本質はどこにあるか、報道はそれを視野に入れているかどうかを考えていくことにしたい。なお、ジャック・ボーはスイス情報局の元大佐で、NATO職員として2014年からウクライナの危機を担当し、支援プログラムにも参加しており、事実をつぶさに捉えることができる立場にあった人物である。
「侵攻」に至る道
ウクライナの歴史は政治的、民族的、文化的に極めて複雑で、どこから始めていいかわからないが、第二次世界大戦で東部はソ連軍、西部はナチス軍に組み入れられ、敵同士として戦ったことをまず確認しておこう。東部はロシア語を話し、西部はウクライナ語を話す。しかしロシア、ベラルーシなどとは通婚圏であり『戦争は女の顔をしていない』の著者アレクシェーヴィッチの母はウクライナ、父はベラルーシの生まれであった。
ソ連崩壊後、独立国となったウクライナは親露派、非露派が入れ替わり政権の座につく。2014年マイダン革命によって親露派大統領が放逐されると新大統領が、20%ほどの支持率があった共産党を非合法化し、東部では公用語であったロシア語の使用を禁じる。一方プーチンは軍事力と住民投票によってクリミアを併合した。
新政権は、ロシア語を禁止しただけでなく、それに反発する住民を弾圧、虐殺を始めた。それに抗して東部自治政府が武器をとり、中央政府との戦闘に入る。戦闘は政府側の敗北が続く。軍の幹部が腐敗して弱体化し、予備兵を招集しても応じない者が多かったなどのためである。
そこで、ウクライナ国防省はNATOに依頼し、準軍事的な民兵を徴募、19ヵ国から応募があった。米、英、仏、カナダが資金を提供し武装化させ、訓練を施したという。この民兵たちは猛烈な反ユダヤ主義者で、獰猛で民間人に対する数々の犯罪(レイプ、拷問、虐殺)を犯した。国連機関はそのいくつかを確認しているが、欧米の政府もメディアもこれらの犯罪を問題としていない。プーチンが「ネオナチ」と呼ぶのはこの民兵たちであり、アゾフ大隊などに組み入れられている。
政府軍と東部反乱軍との戦闘は、ロシアの「侵攻」まで続くが、その間に東部自治州の自治を認めるなどを内容とする「ミンスク合意」(停戦合意)が3回、仏独などの仲介で成立している。しかしいずれも破られ長くは続かなかった。
2021年3月、ゼレンスキー大統領はクリミア奪還の政令を発し、南方への軍備配置を開始し、NATOも黒海・バルト海間で5回の演習をし、つづいてロシアも行った。ウクライナ軍は、ミンスク合意を破って、東部ドンパスにドローンでの空爆を繰り返す。同年秋、ロシアはウクライナ国境近くに軍隊を集め「演習」を展開。11月以降、米国がロシアのウクライナ侵攻が近いとの予告メッセージを発し続ける。
2022年2月7日、マクロン・フランス大統領がモスクワに飛び「ミンスク合意」遵守努力を約束、翌日ゼレンスキーとの会談でそれを求める。しかし2月11日のベルリンにおける政治顧問会議では何の成果も得られず、ゼレンスキーはミンスク合意の適用を拒否した。米政府の圧力だったといわれる。
2月15日、ロシア議会がドンパス地方の二共和国の独立をプーチンに要請するが、プーチンはこれを拒否。翌16日以降ウクライナ政府軍のドンパスへの砲撃が劇的に増え、民間人の犠牲も激増した。翌17日、バイデン米大統領が、ロシアが数日以内にウクライナを攻撃すると発表した。
プーチンは、東部への激しい攻撃を座視しえず両共和国の独立を承認、友好・援助条約に調印し、両共和国の軍事支援要請に応え、国連憲章51条発動というかたちをとり、24日の侵攻開始となった。
戦時下のウクライナ社会
ロシアの軍事侵攻直後、ゼレンスキー・ウクライナ大統領は、意見を異にする11の野党の活動を停止させ、成人男性の出国を禁止・徴兵する戦時体制をとる。2014年から親欧米、新自由主義、民族主義の言説が強まるが、それらを批判する政治家、運動家、ジャーナリスト、メディアが弾圧されていた。ウクライナの社会学者ウォロディミル・イシェンコはネットやアルジャジーラなどで、政府のこれらの制裁体制は、国内で批判を集めてきており、安全保障上の必要からというより、一部のグループが腐敗した利益をさらに追求するため、と指摘している。
これは「ピーピルズ・プラン」のML、ppml5月2日付で太田光征氏が紹介していることだが、同氏は同MLで、ウクライナの平和主義者ユーリー・シェアリンコを中心とした反戦運動が制裁を受けながらも展開されていることも紹介している。
つまり日本メディアが流しているような、ゼレンスキー中心の一致団結したウクライナという状況ではなくて様々な動きがあるということである。この大統領は日本メディアが描き出しているような反戦主義者では決してなく、制裁や弾圧を平気で行う政治家だということも注意しておかねばならない。
もちろん、ロシアの侵攻によって犠牲になっている人は日々増加しており、これまで親ロシアだった人も反ロシアになっているという流れは当然あるだろう。
米国・NATOの狙い
「侵攻」に至る道や戦時下のウクライナ国内の状況を以上のように見ると、この「戦争」における米国、NATOの役割が浮き上がってくる。
米国・NATOは、プーチンが「ネオナチ」と呼ぶ獰猛で好戦的な民兵を多額の資金を投入して育てた。これらの民兵は現在、東部地区でロシア軍と戦い英雄視されている。ロシア「侵攻」理由の一つがこの「ネオナチ」の排除であった。もう一つはウクライナのNATO加入阻止。ワルシャワ条約機構の解体と同時に西側首脳たちは、明文化はしないが、NATOは拡大しないと約束した。その約束に反しNATOはどんどん拡大、ウクライナまで視野に入ってきた。実現すればロシアの軍事的・経済的死活問題とプーチンは考えており、米国もNATOもそれを充分知っている。
2021年暮れから22年にかけての首脳会談において、プーチンはこれを強く要求したが拒否された。米国はじめ西側諸国はこれらを拒否すればロシアは軍事行動に出ると解っていたはずだ。だが戦争回避の対応をとらなかった。ロシアは欧米の術中にはまったと、考えられなくもない。この戦争でもっとも利益を享受しているのは米国であり各国の軍事産業であろう。「侵攻」後、いやその前から欧米は多額の資金と武器をゼレンスキー政権に供給し続けている。その武器がロシア軍の進軍を阻止し追い返している。新着の武器をウクライナ兵士が容易に使いこなしているのはなぜか。米国を中心に兵士をウクライナに送り、または自国にウクライナ軍人を招致して訓練してきたからである。小野寺五典元防衛大臣・現自民党安保調査会長がそのことを平然とテレビで述べている(BS-TBS『報道1930』5月11日)。
米国・NATOは早期に和平を実現するために努力するのではなく、ゼレンスキーの戦闘を軍事的・財政的に支援し、世界各国に呼びかけ、ロシアに対する経済制裁を強めている。このことによってロシア軍は敗走し、武器不足に苦しむ事態になっている。メディアはそれが必要でありより強化すべきとの情報を繰り返しているが、戦争を長引かせウクライナの民衆の命をより多く奪い、ロシアの民衆の日常生活を苦しめていることにはあまり注目しない。だが米国の国家権力・経済権力は民衆の犠牲などは視界に入らないようだ。
「米国にとって大歓迎」
本橋哲也東京経済大学教授がこの「戦争」の意義について興味深い視点を提供している(『週刊金曜日』22年4月22日号「クレア・デイリー欧州議会議員の演説を考える―武器供与も経済制裁も平和をもたらさない!」)。氏はこの戦争が示しているのは「自由主義陣営」対「権威主義陣営」という新冷戦ではなく、かつての植民地支配をひきずった南北の経済格差問題であると喝破する。「すでに超大国の位置を降りつつあるアメリカの最大の恐れは、中国をリーダーとした世界の多極化だ。アメリカは経済問題を安全保障問題にすり替えることで中国の孤立化を図ろうとしてきた」。中国とともに多極化を推進してきたロシアの衰退につながる今回の「侵攻」はロシアのオウンゴールであり「米国にとっては大歓迎の事態」なのだと。
同じような議論を展開しているのが、パリ在住のイタリア人社会学者・思想家マウリツィオ・ラッツァラートである(「ウクライナ戦争の背景」『現代思想』6月臨時増刊号)。ここで詳しく触れることはできないが、彼もまたアメリカの標的はロシアの向こうに控える中国と見る。本橋哲也氏と同様に、3月の国連におけるロシア非難決議に反対した国と棄権した国に注目している。それらは欧米諸国がかつて植民地支配した国々だからである。「多極化」とはこれらの国の存在が、デッドロックにぶつかっている資本主義体制を揺るがしていることを示す。
軍事力増強を容認する方向
以上の記述から、日本のメディアが何を見ていないかはかなり明らかになったと思う。他にもさまざまな二重基準がまかり通っていること(米国による数しれない他国への軍事侵攻への非難はないこと。「難民」と「避難民」の差別など)があるが、ここでは、ウクライナ報道の解説・コメンテーターに自衛隊の元幹部、防衛省防衛研究所の研究員などが連日のように登場していることに注目したい。日米軍事同盟の深化ということで安全保障問題での従属化がどんどん進む中で、かれらの言説は当然のことながら世論に大きな影響を与えていることだろう。かれらの説明は概ね米軍の見方と重なっており、それが憲法を遥かに超えた軍事力の増強を世論が容認する方向に向かわせているように思う。
「敵基地攻撃能力」「核共有」議論が普通に行われるようになり、米国の圧力は一層強まることだろう。南西諸島のミサイル基地化が進んでいるが、そこに米国の核を配備することを容認する要因になるかもしれない。憲法改正につながりかねない本年の参議院議員選挙にも大きく影響するはずだ。
かつて日本も植民地支配国だったことも想起しておく必要がある。ウクライナで起こっていることはかつて日本がやったことと同じだという認識はどれだけのメディアにあるだろうか? 軍事力を増強すれば再びそれを繰り返すことになるかもしれない。
意図しているわけではないと思うが、今盛んに報じられているウクライナ報道にはそのような危険性が大きく含まれているように思う。
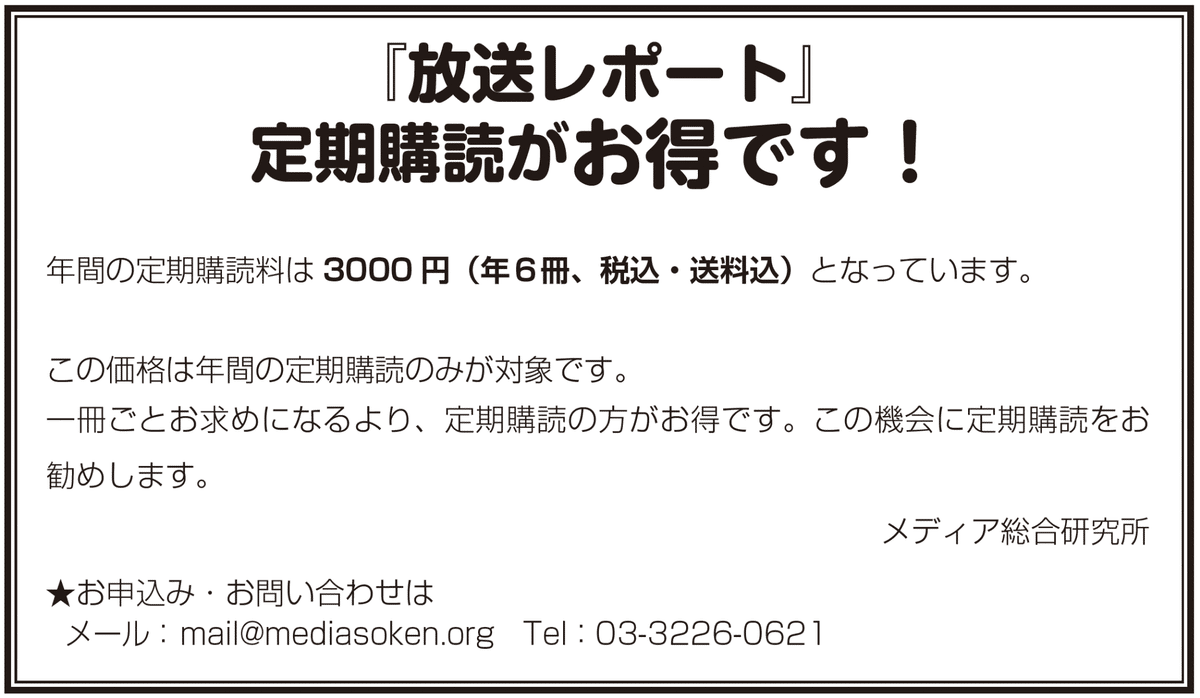
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
