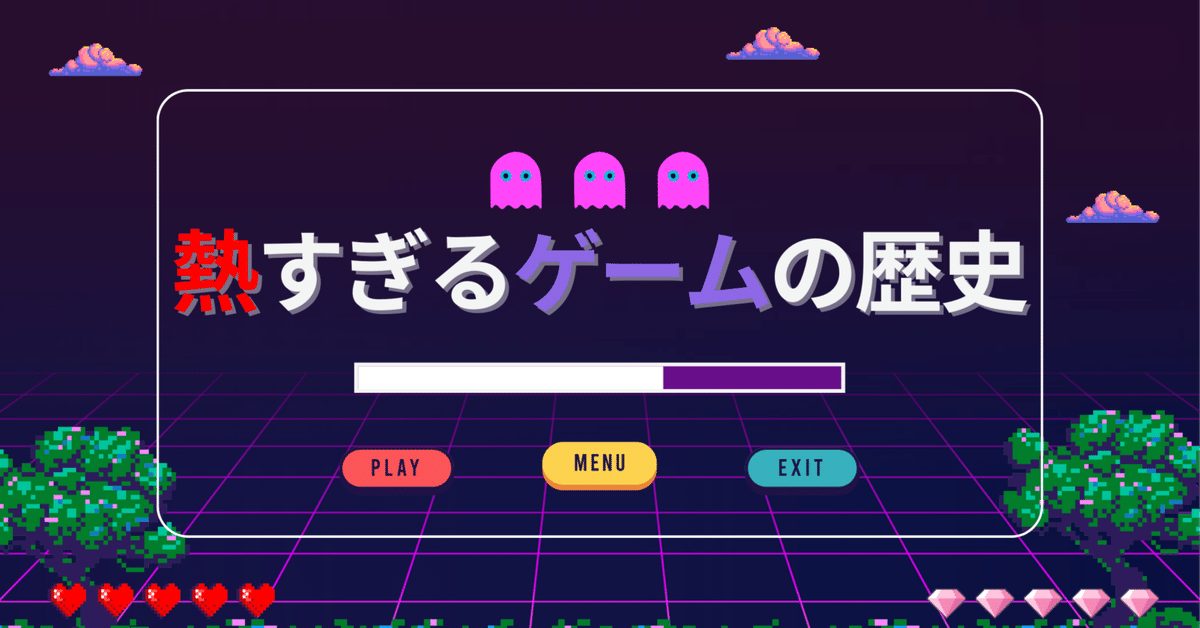
熱すぎるゲームの歴史#01
ゲームは子供から大人まで簡単に家で楽しめる素晴らしいものです。そんなゲームをこよなく愛するゲーマーが輝かしいゲームの歴史を紹介します。ゲームにもボードゲームなどがあるがここでは、コンピュータゲームについてのことをゲームと指すことにします。
目次
・1970年代 ゲーム機の始まり
・1980年代 ゲームの成長期
・1990年代 次世代機戦争とアーケード
・2000年代 ゲーム機の進化
・2010年代 オンラインとソシャゲ
・まとめ
[1970年代] ゲーム機の始まり
1970年代に入るとゲームが商業的に成功を収めるようになり、世間に対するゲームの認知度が高まり始めました。
1972年世界初のゲーム機である「Odyssey」がマグナボックス社から発売されました。その後アタリ社が「PONG」という家庭用ゲーム機が大ヒットし、ゲーム産業の礎を築きました。
1977年任天堂が日本で初めてテレビゲーム15という15種のゲームが内蔵されたゲーム機が発売されました。
「PONG」を作ったアタリ社が1978年に「スペースインベーダー」という大ヒットアーケードゲームが発売され、その人気ぶりから”インベーダーハウス”と呼ばれるゲームセンターが全国に生まれました。
引用始め

引用終わり
引用元https://www.famitsu.com/news/201808/20162576.html
[1980年代] ゲームの成長期
1980年代に入ると、ファミコンやPCエンジンなどの家庭用ゲーム機が登場しました。また、パックマン、ドンキーコングといったアーケードゲームも登場し、様々なジャンルが登場、多様化が一気に進んだのでゲームの成長期だったと言えます。
1980年アーケードでナムコから「パックマン」、1981年に任天堂から「ドンキーコング」が発売されました。パックマンは今でも最も成功した業務用ゲーム機としてギネス登録されています。
1983年には「ファミリーコンピューター」通称ファミコンが遂に発売されました。ファミコンの特徴としては様々なソフトがあるほか、他のゲーム機よりも圧倒的に安くコストパフォーマンスが高かったのが特徴です。
引用始め

引用終わり
引用元https://www.famitsu.com/news/202307/15309235.html
1985年にはファミコンの成功を確定させた超有名タイトル「スーパーマリオブラザーズ」が発売されました。世界で最も売れたゲームとしてギネス登録されています。1986年には「ドラゴンクエスト」、1987年に「ファイナルファンタジー」が発売など今でも超人気タイトルが発売された年代でもあります。
[1990年代] 次世代機戦争とアーケード
1990年代に入ると、16ビットのゲーム機が普及し、グラフィックやサウンドのクオリティが各段に向上しました。スーファミやプレステ、セガサターンなど次世代機が続々と発売され、次世代機戦争が起きていました。
この年代のアーケードでは「ストリートファイターⅡ」や「ぷよぷよ」が発売されゲームセンターは長時間並ぶアーケードの黄金期でした。
1990年「スーパーファミコン」がファミコンの後継機として発売されました。人気タイトルの続編が次々と発売され最強のハードの座をとりました。しかし、1994年「Play Station」が発売され印象的なCMを数々展開し、「FF」や「ドラクエ」などといった人気タイトルを味方につけ、初めて任天堂に勝利したゲーム機となりました。
1991年には「ストリートファイターⅡ」、「餓狼伝説」、1993年に「バーチャルファイター」、1994年に「鉄拳」などといった対戦格闘ゲームブームが起きました。当時は、対戦相手はコンピュータというのが一般的でしたが、プレイヤー同士が戦うというコンセプトは革新的で一気に広まりました。
引用始め

引用終わり
引用元https://www.capcom-games.com/cfc/ja-jp/title/hsf2.html
[2000年代] ゲーム機の進化
2000年代に入るとソニーは「PlayStation」の後継機として「PlayStation2」を発売、ファミコンやセガの「次世代機」達がやっていなかった前機とのソフトの互換性を実現しました。それだけではなく、ソフトがCD-ROMの7倍の容量を持つDVD-ROMになった上、ドラクエ、FF、バイオハザードといった人気ソフトを次々販売したことで長いゲーム機歴史の中で最も売れたゲーム機となりました。
引用始め

引用終わり
引用元https://www.famitsu.com/news/202003/04193813.html
さらにソニーは2004年に初の携帯ゲーム機「PlayStation Portable(PSP)」を発売した。当時携帯できるゲーム機としては破格の性能をしており、潜在スペックはPS2並みまでとも言われていました。
それだけではなく、ソニーは2007年に「PlayStation3」を発売した。しかし、当時は、価格が5万円以上とかなり高価なため売り上げがあまり振るいませんでした。
一方この年代の任天堂は大人向けのソフトが多い「PlayStation」シリーズに対し、ライトな層向けに2001年「ゲームキューブ」、2004年「ニンテンドーDS」、2006年に「Wii」を発売するなどこれもまた、「PlayStation」に負けないヒット作を生み出していました。
「ニンテンドーDS」はダブルディスプレイやタッチセンサーによる仕掛けなど誰の目にも真新しく、ライトユーザーに広く普及しました。価格も1万5千円前後と比較的安めだったのも広まった要因だと思います。
[2010年代] オンラインとソシャゲ
2010年代に入るとオンライン技術が進み、MMORPGやソーシャルゲーム、VRゲームなど新しいゲーム体験が提供されるようになりました。また、オンライン技術が進んだことで家でオンライン対戦ができるようになり、競技性が高いeスポーツなども注目され始めました。
2012年には「Wii」の後継機である「Wii U」が発売されました。「マリオカード8」や「スプラトゥーン」などのヒット作が誕生しましたがその後の人気ソフトがあまり出ず2016年には生産を終了してしまいました。
しかし、2017年には累計売り上げ1億2953万代という怪物級の売り上げを出した「nintendo switch」が発売されました。気軽に2人プレーを楽しめる、据え置き機でありながら外に持ち運べるという二つをコンセプトとしていました。カジュアル層とコア層というゲーム人口の二極化が進む中その両方の層を見事捕まえたのです。ソフトにも恵まれ、この先ずっと語られる伝説のゲーム機となると思います。
引用始め

引用終わり
引用元https://www.nintendo.co.jp/hardware/detail/switch/
一方ソニーは任天堂がカジュアルそうに向けハードを出している中、圧倒的な画質と性能をもった「Play Station4」を発売しました。実際私も、初めてプレステ4で「モンスターハンター:ワールド」をプレイしたときはあまりの画質のきれいさとリアルさで驚きました。
まとめ
こうしてみるとゲームはものすごく長い歴史があり、10年という区切りでまとめてみたがその間に考えられないような進化をしてきました。任天堂とソニーはゲーム機の2トップでその二つが競いあうからこそより良い、面白いゲームが生まれ私たちゲーマーを楽しませてくれるようなゲームを作ってきたと実感した。これからも競い合って面白いゲームを作ってほしいと思いました。
