
バングラ旅の記録10
9/13 11日目
9/14 12日目
今は9/14の夜
最後の一泊
明日の昼過ぎにバングラデシュを出国する
ホッとしたり寂しかったりする
この感覚は最終日の明日最大になるだろうな
理解できたらまた書く
この9/13は目的のボーダレスの工場見学の日
結局9/13はボーダレスとロヒンギャ族
9/14はBRACのAarongとグラミン銀行について色々学べた
濃い時間だった
ちなみに今までボーダレスの名前を伏せていたのは「普段は個別の工事見学を受けつけてない」と言われていたことへの配慮で、当日発信大丈夫か聞いてみたらいけたのでオープンにした
その代わり工場の中は技術的な観点から写真NGだった
なので前半は全く写真がないです(スクショばっかり)
朝起きてすぐNGOの集まるミルプールに出かける
ちょっと渋滞しててギリギリになったが、迎えの車も渋滞に巻き込まれて遅れたので大丈夫だった
バングラでは相当バッファを取った移動時間の見立てが要る
今回工場を案内してくれるのはボーダレスのインターン生のマリさん
休学してバングラに住んでる
元々ロヒンギャ族支援の活動や研究のために来たらしい
もう半年も住んでいるらしくて、ベンガル語でコミュニケーションが取れる
めちゃくちゃかっこいい

工場に着く
写真は昨日撮ったやつ
BLJ Bangladesh Corporation Ltd.って書いてる



これだ
日本のBUSINESS LEATHER FACTORYの商品を作ってる

日本で見に行ったときの写真
絶対もう一回行こう…!!!!
中に入る
ボーダレス・ジャパンの説明を改めてしてもらって、工程をゆっくり全て見せてもらうことに
俺1人のために案内・説明・疑問解消もしてくれて、しかも働いてる人に喋りかけてOK
ベンガル語できるから相手が英語無理でもOK
なんて贅沢な
ボーダレスはもちろん児童労働を禁止している
若く見える人に年齢を聞いても18歳より上だった
採用基準も、ホームページに書いてる通り本当に貧困層優先だった
求人はちょっと出してるけど口コミが多いらしい
家庭の事情というのも理解できた
女性の割合がめちゃくちゃ高い
6割超えてるんじゃないかな
イスラム教なのでお見合いが多いのだが、当然合わないとかDVとかの問題が起きることもある
そこでシングルマザーになると、かなり厳しくなる
ここまでのバングラ生活で、バングラ人女性はめちゃくちゃ熱心に子育てすること、パートナーは人生で1人というのが常識であること、そこらへんの仕事は肉体労働が多いことは知ってた
ボーダレスはそういう女性たちにちゃんと仕事を与えられていた
子供を預かるスペースまであった
工程はめちゃくちゃ細分化されていて、一人一人がやる作業はとても単純だった
これなら大量に採用できるし、どんなハンデがあっても比較的就業可能だ
ここら辺はコンセプト的にマザーハウスと比べてもはや逆の印象を持った
マザーハウスは職人の輩出という色が強いからだ
これまで似てると思っていたが、こんなに対照的にうつるとは思わなかった
工程を細分化していっぱい雇うことは、リストラのような経営合理化の観点から見ると不合理が生じることもあるだろう
特に日本でバッグが売れなければかなり厳しいはず
ところがこの事業の目的は革製品を売ることではなく雇用を生むことなのだ
そもそも革を選んだ理由に工程を細分化できることが含まれる
経営合理化こそ無意味だ
まず雇ってしまって、そこからどうやって必要な量を売るか考えるような義務感、使命感、焦燥の中で戦っていた
そしてバッグは売れていた
クールだった
支援では感じない、ビジネスの世界で勝利して社会貢献するクールさ
実際にやっている人から直接聞くと、動いている工場を見ると、ゾクゾクするくらいかっこいい
ちなみに革を選んだもう一つの理由は宗教だ
毎年牛を殺す祭りがあり、一家で一頭牛を殺す
そこから買い取っている
捨てるよりよっぽどいい(ボーダレスが来る前から売っていたらしいが、余っていたのか、そこに参入して問題は起きてなさそう)
同じ工場の中にもう二つ会社が入っている
Bangladesh Leather Inspectionという、検品の会社
BLJで作った商品を検品している


検品というのは目以外の障害ならあっても就業できる
たしかに、バングラデシュに来て思うのは、障害者の物乞いがとても多いこと(もちろん盲目もいるが)
素晴らしく細かい仕事をしていた
問題なく就業できる、という条件の上では、彼らは普通のプロフェッショナルだった
三つ目の会社はJOGGOという、カスタムオーダーの革製品の会社
元々のコンセプトは日本の精神疾患を持った人が職人として働くこと
その生産調整をバングラデシュでしている
ボーダレスの中の企業がリソースをシェアできるという強みは、それがなければ実現しないソーシャルビジネスを成立させられる
強い


工場にはちょこちょこ日本語を喋れるバングラ人がいた
日本に研修に行ってたらしい
日本を絶賛していた
自分もガイドをしてくれていたリキシャドライバーに日本に連れて行ってって何度も言われたが、彼らにとっては日本に行くこと自体がものすごい限られた人にしか与えられないチャンスだ
とまぁここまでほとんどホームページに書いてある内容ほぼそのままに感想を載っけたようなことを書いたが、それでいいと思う
「本当にホームページ通り」
それが大事だった
「雇用を目的にしてるって、まじで?」
「貧困層を優先で採用してるって、まじで?」
と、まずは疑念があったからだ
これは自分も社会貢献についてずっと考えたり実践したりしていたからこそ、口で言うことと実際にやることにどれくらいギャップがあるかなんとなく想像してしまうから、実際見ないと拭えない疑念だった(別に弊団体がギャップだらけだと思ってるわけではないよ)
ここまでかなり事業内容の話だったが、率直な感想としては、「めちゃくちゃ楽しそうに、嬉しそうに働いてる!」ということ
見学してる谷口に笑顔で話しかけてくれる人もいた
マネジメント層との仲も良い
これはバングラではあんまりないらしい
階級社会だから
とにかく、自分もソーシャルビジネスやるなら、これくらいビシッとうまい仕組み、紛れも無いアウトカム、笑顔になってる人を作らないといけないと思わされた
偉そうに疑念とか言ったけど、自分の中のハードルはかなり上がったと思う
昼ごはんはチキンカレー

後半、Business Leather Inspectionの社長の仲渡さんと喋る時間がいただけた

ものっっっっっすごいかっこいい女性だった
ものすごいかっこいい
ここまで書いた内容にはかなり仲渡さんと喋った内容がすでに含まれてる
かぶる
とにかく色んなことを聞きまくった
ほんとに雇用が目的なのかの確認から、
工程は一般的なものより細分化されてるか、
細分化はもはや仕事を増やそうという意図があるか(実際検品の工程が非常に多かったように感じた)
完全には経営合理的でないとしても雇用を生めるほど好調か、
彼らの給料についてはどう考えてるか、
機械による大量生産とハンドメイドについてはどう考えてるか、
採用基準として貧しさをどう聞いてるか、
インパクトとしてはこの工場の雇用で完結するのか…
谷口の不躾な質問にめちゃくちゃ丁寧に熱く答えていただいた
印象に残ったのは、
「手作りは消えないと思う。これは機械ではできない」と仰ったこと
この確信がないとモノづくりできない、したら危ないと思う
本当に言い切られていた
仰ったとき凄みを感じた
もうひとつは「インパクトとしては、いずれこの工場のような労働環境などがロールモデルとして他の工場、さらに他の国に広がったらいいと考えている」と仰ったこと
どんどん与える、どんどん真似していい、という姿勢
この回答は予想通りだったというか、谷口もインパクトとしてそれがないと社会が変わっていかないと思っていたが、
大事なのは普段(自分も含めて)自分の周りで聞く「社会を変える」のイメージと少し違う意味合いを工場で感じたのを、共有したかったことだ
「社会を変える」というと、今までの社会を否定し、全く新しい圧倒的にうまい仕組みをサービスとして世の中に普及させるイメージだが、この工場に「全く新しい」要素はあまり感じなかった
ただ「みんなが知ってる良い」を高いレベルで実現していた
だからバングラデシュの社会から問題がなくなればそれだけでこの工場の特殊性はなくなる気がした
もっと遡ると、バングラデシュに来てしばらく経ったときから、「社会を変える」という言葉にかなり違和感を感じるようになっていた
みんな頑張って頑張って社会を成り立たせ、こぼれ落ちる人は何とか社会の恩恵に預かりたいと必死で努力していた
発展途上国だからこそ、「既存の社会は間違っている」「既存の社会を破壊する」ようなモチベーションは感じられなかった
何が言いたいかというと、バングラデシュに来てから「社会を変える」のではなく「社会を進める」ような考え方が大事なのではないかという転換があった
みんな社会を進めるのに必死だった
そしてボーダレスがやっていることも、「みんなが知ってる良い」で良いのだ
そうやって社会を進めている
それがインパクトだ
日本は成熟した社会だから「社会を変える」必要がある
近代化はとっくの昔に終わり、脱近代化の時代、転換の時代に入っている
それはわかっている
しかし、既存の社会へのリスペクトを忘れてはいけない
社会は先人たちがこのバングラデシュ人のように死に物狂いで築き上げてきた人を生かすための装置であって、殺すための装置ではない
全く新しい仕組みが必要と気負わなくていい
既存の社会に必ずしも問題があると思わなくていい
そのかわり、何が自分にとって「良い」のかシンプルに見出す必要があると感じた
最後に、ボーダレスアカデミーを勧められた
チェックしよう
仲渡さんとお話しした後はすこしインタビューを受けて、マリさんにロヒンギャ族について教えてもらった
実際に行って活動しているので写真もいっぱい見せてもらった
去年の、まだ支援も来てなくて本当に酷いときの写真だった
ミャンマーで家族を殺されてバングラデシュに逃げて来た人々
男は戦うから女子供がとても多い
もちろん家族とはぐれた子もいる
その中で子供に綺麗な服を着させてあげられないことを嘆く母親の強さ
同じムスリムだから助けようとしたバングラデシュの優しさ
そうは言ってもロヒンギャ族は不法にコックスバザールの街に低賃金で働きに行き、バングラデシュ人が仕事を取られる
最初は協力的だったバングラデシュ人の中にも不満が募る
うまくいかない
もらった配給をさらにみんなに配るロヒンギャ族の精神的な美しさ
仏教徒はなんでこんな酷いことをするんだという怒り
色んなことが起きてると教えてもらった
マリさんはロヒンギャの人に正式に仕事を与えたい
だからボーダレスでインターンしているらしい
こういう時「人材として…」とか思っちゃう自分がすこし悲しいけど、本当に笑顔にしたい人のために実践していること、チャレンジしていることが一貫していてすごかった
頭痛がひどくてぐったりしたりして、17時まで工場にいて、そこかミルプールに帰る人みんなで帰ることに
まさに半日一緒にいた
帰りのバスではキセキや奏が爆音で流れてたり、バングラデシュソングが流れてマリさんが口ずさめてたり(すごい)、JICAが作った日本とバングラデシュの友好ソング(ベンガル語と日本語で交互に歌う)が流れてたりした
マリさんはなんと日本人宿でおれと一緒に泊まってる人たちと遊んだらしい
世間狭いな
お別れして8時半とか
本当にぐったりしてしまって、フラフラしてドブにはまった
ガチで汚い
それもあって晩ご飯食べに行く気がしない
でも食べないと回復しないので、日本人宿についている日本料理店に入ることにした
明日は帰国前日でベンガル料理食べる予定なのでラストチャンスだしちょうどいい



至福だった
9月14日
12日目
帰国前日
とりあえず心置きなく食べ歩きをする
ベンガル料理を食べる
そんでお土産を買う
が今日のミッション

朝、グラミン銀行でインターンしてるぽんがバナナをくれた
昼前から行動開始
ゲストハウス出て早速サモサがあったので食べる



ジャガイモのカレーが入っている
かなり日本のカレーに近い味がして美味しい
アイスも食べてなかったので食べる
当たり前だけど普通に美味しい

お土産になるかわからないが、行きたい店があった(結局買わなかった)
世界最大のNGOが運営するバングラデシュの伝統工芸の雑貨屋、Aarongだ
ゲストハウスから徒歩で行けた
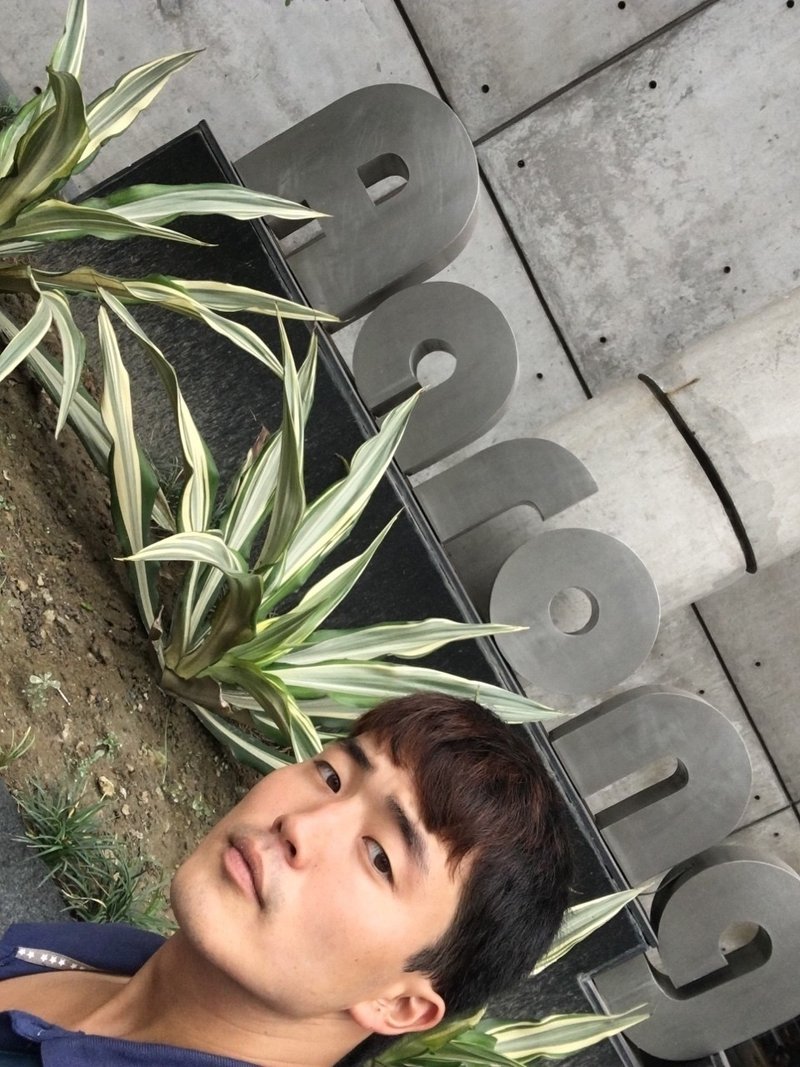
セレクトショップみたいな大きさかと思っていたが、ロフトみたいに建物1棟全部Aarong
この規模で全部伝統工芸!?
さらに入ってびっくりした
めっっっちゃ現代的でおしゃれ
蔦屋書店に似た雰囲気
というかもはや日本のスタンダードより高い空間だった




売ってるものは本当に伝統工芸品
買ってる人は外国人ではなくバングラデシュの富裕層(この国外国人ほとんどいないのもあるけど)









軽い気持ちで来たけどこれは考えさせられた
というのも、かなり谷口のビジョンに関わる領域だった
モノづくりが大量生産から生産の個別化にシフトすれば、どんどん最適化が進む
もちろん風土に最適な方がいい
グローバルで画一的なモノの世界からローカルで最適なモノの世界になる
その最適の参照として文化が見直されると思っていたからだ
現状は"現代日本文化"は再定義されていないように感じる
日本で建物1棟使うならAarongではなくロフトやヨドバシカメラだ
ロフトやヨドバシカメラこそ現状の"現代日本文化"と言えるかもしれない
これは何ともおもしろくない
すでに日本人の暮らしに日本人らしさはなく、グローバリゼーションの植民地だ
伝統工芸こそ日本らしさであるという主張ではない
あくまで参照だと思っている
でもモノづくりにはこれから"日本最適"を生み出す余裕ができる
せっかくならいち早く創りたい
そしてAarongを目指そう
これが今日決まった
ゴミの件もそうだが、この国ではビジョンがどんどんアップデートされる
日本に帰ったらひたすら整理して勉強する日々が始まりそう
地階から4階まで全部Aarongで、5階におしゃれなカフェがある
ここで休憩


チョコレートブラウニー、バニラアイス、アイスコーヒー
そのあと少し作業した(Facebookでのイベント探し。みんなに通知いってんのかな…。いってたらめっちゃ申し訳ないな…)
カフェインで過集中に
気分が悪くなった
外に出たら食べたかった屋台のフライドチキンがあったので、食べた

そのあとお土産買った
谷口も食べたことないお菓子(あるある)
でも来る前から面白そうと思ってたやつと、マリさんからのおすすめのやつ
今日は日本人宿の仲間と晩ご飯を食べる約束をしていたので、急いで帰った
多分最後のベンガル料理
マトンのカレー


あとぽんの頼んだチキンを分けてもらった
大食いすぎてびっくりされた
しかも今日一日中食べてる
(もちろん書いてる頃は腹痛がやばすぎて寝れないです)
帰り道、物乞いキッズにエンカウント
現物でメシを奢ってあげた
見た目的に物乞いビジネスとかではなさそうだったが、現物をあげると子供は助かるけど物乞いビジネスの利益にはならないのでまだマシな行為だ
メシに行ったメンバーで物乞いについて話す
この考えの共有は大事だと思った
宿に戻ってグラミン銀行のインターン生のぽんと色んな話をした
グラミン銀行について色々聞いた
どんな融資やってるかとか、それで村の人はどう思ってるのか、生活はどう変わったのかとか
ローンに種類が沢山あって、ひとりひとりに合わせて組める
目的も色々ある
仕事のための初期費用はもちろん、家のためとか、教育のためとか
教育のローンは無利子だったり、村の人に夢を聞くと子供に教育を受けさせることだったりと、教育は悲願みたいだ
あと旅について語り合った
ぽんはひとり旅初めてではなくて、カンボジアとかも行ったらしいけど、バングラデシュは初めて本当につらくて一回本気で嫌いになったらしい
でも、そういう国だからこそひとり旅の意義がわかりやすかった
ひとり旅は逆に一番多くの人の話すことになる
バングラの魅力も結局そこにある
寝る用意をして、荷造りをして、最後の一泊
布団で裸でも生きるを開く

ずっと噛み締めてたページ
このページを理解するために来た
ただただ生きるために、生きる。
彼らには選択肢がない
僕らは何のために生きてるかわからない
いや、生きるために生きればいい
そこにそれ以上意味はない
生きるってなんだろう
死んでなければ生きてるのか
やりたいこと、できること、自分の心の中の声
そこに生がある
彼らは全力でそれらを拾い上げようとしている
僕らもそうしていい
死んでも生きてもない状態から、生きるために生きればいい
ただただ生きるために、生きる。
かわいそうなことだろうか
羨ましい、尊敬できることだろうか
ファダブユもバブーもルーベルも問いかける
「僕は今日もできることをやって生きたよ!マサシはどうだい?」
堂々と「生きたよ!」と言おう
今日も生きよう
おやすみなさい
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
