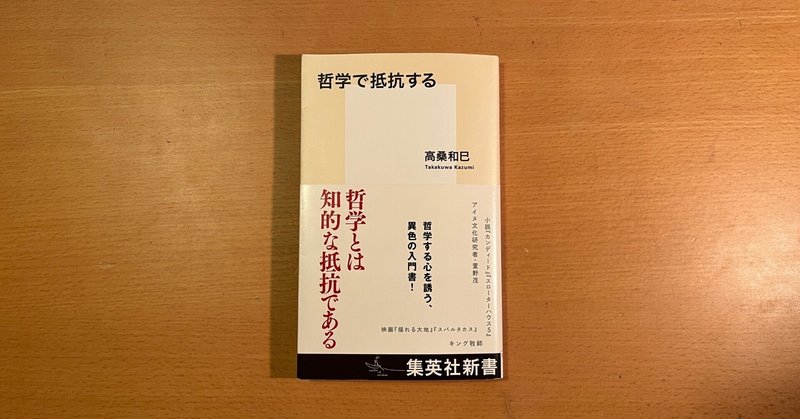
【読んだ】高桑和巳『哲学で抵抗する』
書物としての戦略と思い切りが凄い。試みられるのは「哲学の民主化」だろう。哲学の入門書の趣ではあるものの、プラトンだのカントだのといったような「狭義の哲学者」に言及される事は殆どない。代わりに試みられるのは、日常と地続きの実感の中で「哲学」の契機を見つけ出す事であり、それは誰にでもできるし、実は既に多くの人がやっている事である。そして日常の中に「哲学」を定位する事ととは即ち、日常の中の「抵抗」の契機を示す事である。
本書での「哲学」の定義は、冒頭に端的に示される。曰く、「哲学とは、概念を云々することで世界の認識を更新する知的な抵抗である」(p27)。本書はこの定義を見事に終始一貫させながら、『揺れる大地』『スパルタカス』という2本の映画、『カンディード』『スローターハウス5』、そして萱野茂の『アイヌの碑』、キング牧師の『黒人はなぜ待てないか』という4冊の書物の登場人物を取り上げる。
「概念」について。何らかの単語や言葉が「概念」として使われる時、そこには意味の一貫性、即ち「頑固さ」が生じる。そしてその頑固さによって、「議論の全体が、論理の場として一種の緊張を帯びる」(P29)。どういう事か。例えばアイヌの権利回復に取り組む中で萱野茂が概念化したのは「主食」である。和人の入植によって持ち込まれた漁業管理制度は事実上、アイヌの人々に鮭を獲る事を禁じた。言わずもがな鮭はアイヌにとって極めて重要な存在であり、それを奪われる事は文字通り死をもたらす。萱野は言う。
「私はこれまでパスポートを必要とする旅を24回していて、行った先ではなるべくその国の先住民と称される人びとと交流をしてきたが、侵略によって主食を奪われた民族は聞いたことがない。」(P107、萱野茂『アイヌ歳時記』より孫引)
「もし、よその国から言葉も風習もまったく違う人たちがどさっと日本へ渡ってきて、おまえたち、今日から米を食うな、米食ったら逮捕するぞ、という法律を押しつけたらどうであろうか。これと同じことをアイヌに対して日本人はしたのである。」(P107-108、萱野茂『アイヌ歳時記』より孫引)
ここで「主食」に焦点化する事には、決断と戦略がある様に思う。鮭を「主食」という概念で包摂する事は、その「食糧」や「狩猟の対象」としての側面ばかりを強調してしまうことになりかねない。何よりも、アイヌの人々が和人からが受けた剥奪や侵略は多岐に渡り、食糧を巡る問題だけではない。にも関わらず敢えて「主食」という概念で運動を駆動させるのは、それが感情移入をもたらすからである。「当たり前の、意識されない、空気のようになってしまっている慣習のなかに存在する「主食」なるもの」(P108-109)を突如奪われるという事態、その怖ろしさは「迫害全体の陰湿さのイメージを一挙に立ち上がらせる」のだ(P110-111)。
無論ここで言う感情移入は、同情や憐れみとは違う。両者の差は、認識の更新を迫るか否かである。同情はいわば安全圏から成されるものであり、マジョリティにその優位性を再認させるものですらある。しかし萱野の戦略はそれとははっきりと異なる。「主食」という概念にこだわる事で「丁寧に、道理をもって、感情移入の回路を起動」させる(P106)ばかりか、「感情移入を無理強い」させるからだ。和人に対して投げかけられる問いはこのようなものだ。
「世界は、私たちの側には主食の禁止された世界としてこのように認識されているのだが、同じ認識の視点を自分に対して提供されたとき、あなたたちにはいったい世界はどう見えるのか?」(P121)。
萱野の戦略に哲学を見出される所以もここにある。高桑は言う。「ここでは、もはやマイノリティはマジョリティの同情を買わない。マイノリティは、マジョリティに対して自分たちへの感情移入を丁寧に無理強いし、感覚と認識において、主食禁止のイメージで彼らを慇懃無礼に苛む」(P121)。事程左様に「主食」という概念を立ち上げ、それにこだわる事で、「世界の支配的な認識に揺さぶりをかける(P68)」のだ。
もうひとつ本書で強調されるのは、「抵抗は成否によっては測られない(P68)」という事であり、更には「抵抗にいいも悪いもない(P50)」という事である。抵抗とはつまり「大きなものに流されそうなときに、断固踏みとどまること」である。それは狭義の政治運動に限らず、例えば「自分が叩かれたら「痛い」と言う」こと、さらには「「痛い」と言っている人がいたら、そちら側に立つ」こと、それだけで既に抵抗となり得るのである(P210)。それは「勝とうが負けようが関係がなく、当の哲学の営みによって、そのとき「世界の見えかた」はすでに変わっている」が故に、哲学たり得るのだ(P52)。
本書はいわば「哲学」「抵抗」というふたつの概念にこだわる事で、哲学を体現するのが目論見であろう。そこでの抵抗の対象は、「地道に議論を組み立てることよりも嘘や屁理屈や言い逃れでその場をしのぐことのほうを現実主義的と評価する冷笑主義」であり(P210)、「重要なのは、そのような傾向に対してしつこくノーと言い続けること、基本的な倫理感覚に息を吹き返させること」なのだ(P210)。
