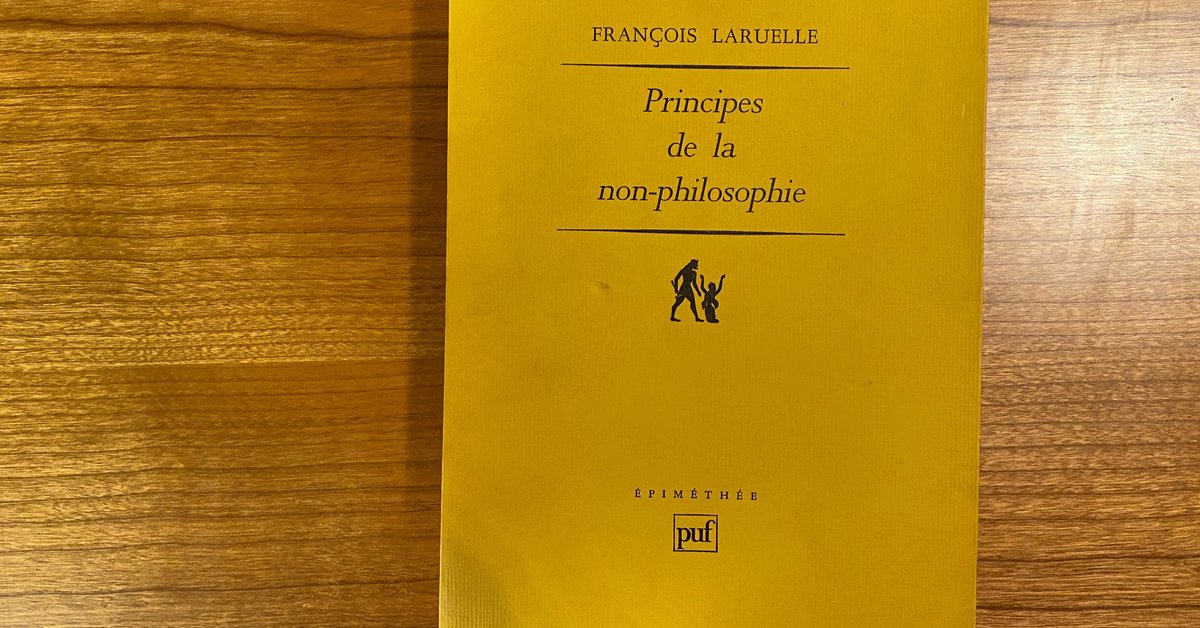
ラリュエルの構造(1)
コロナ蟄居状態でなんとなくラリュエルのあれを読もうという気になり、Kindleで買った『普通の人のバイオグラフィ』を読んで、別の本(『哲学と非哲学』とか『非哲学の原理』といった主著)とつながって考えがまとまってきたので、後々論文にするつもりでノートを書いておきたい。
で、ラリュエルとは誰か。1937年生まれ。世代的にはドゥルーズ、デリダより下で、バディウと同い年である(『アンチ・バディウ』という本もある →書評)。フランス現代思想のきら星時代にナンテール(パリ第10大学)にいて、僕はマラブーさんに教わるためにナンテールに行っていたのだが、そのときに授業に出たことがある。とてもジェントルなお爺さんで、でも授業にはなぜかフランス人はおらず、アジア系、とくに韓国の留学生が多かった。聞くところでは韓国で熱心に読まれているという。フランス国内にはややカルト的な信者、弟子筋がいるようだが、一般にはあまり読まれていない様子である。
そのラリュエルが、例によって「おフランス」を商品にする英語圏の現代思想ビジネスに巻き込まれ、近年妙に再評価というか再商品化され、英訳や研究書がたくさん出ている。フランス語の原著は入手困難なものも多いので、英訳だとKindleで買ってその場ですぐ内容がわかるから助かる。『普通の人のバイオグラフィ』も原著は中古しかなくて謎のオーラを発している本だった。
で、英語の研究はいろいろあり、アレクサンダー・ギャロウェイのLaruelle: Against the Digitalなどは大胆にしてよくツボを押さえている。だが、日本ではほとんど言及されていない。最近仲山ひふみくんが「ラリュエル的ホラー」と題するものを書いたようなので、後で見てみる。それからツイッターでリンクを挙げたが、上野俊哉さんが2019年に井筒俊彦と比較するという形でラリュエル論を英語で書いている。
前置きを書き始めると色々思いついて長くなってしまうのでそろそろ本題に入る。
ラリュエルになぜ興味があるのか。なぜいま読む価値があるのか。……というか読む価値があるのかだが、これがまだ測りかねている感もあって、理論の基礎部分については読む価値ありなんだけれど、応用や展開にどこまで「付き合う」べきかは微妙。近年は量子力学を取り入れた展開に向かったのだが、それは大丈夫なのか心配……
ラリュエルは「非哲学 non-philosophy」というプロジェクトを80-90年代に展開した。それが哲学者としての独自性である。まあ、非哲学なので哲学者と言っちゃうとアレなのだが、まあいいとする。
非哲学とは何か。僕の目には、それはある種のメタ哲学でもあるし、また、哲学総体に対して外部的であろうとする「別の思弁的言説」である。経験科学とも違っている。とにかく、ひじょうに独特な抽象理論なのだ。それをラリュエル自身は「科学」と呼んでいて、そのことにも狼狽する。非哲学こそが哲学総体に対する科学なのだ、というのである。しかしこの科学は経験科学ではない。いわば「思弁科学」である。
と言ってもハア?という感じだろうから、ともかく理論構成を説明する。
ラリュエルは、哲学は「実在」を捉え損なっていると考えている。ひとまずそう始めるのがわかりやすいだろう。実在、それを彼は「一者 the One」と呼ぶ。で、哲学にはそれを捉えようとするのだが捉え損ねる、という無限遠点のようなXがあり、それは「物自体」だったり「存在それ自体」だったりするわけだが、この「捉えようとするのだが捉え損ねる」という構造の外に、そのXとは区別されたものとして「一者」を置くのがラリュエルの独自性なのである。
すぐさま言えば、これは日本現代思想の観点から見れば、柄谷行人-東浩紀が明示した否定神学的構造の外部を描こうとするものだ、ということに他ならない。哲学はつねに否定神学的Xを構造的に必要としているのだが、そういう哲学の有りよう全体の外に自らを位置づけるのがラリュエル、ノンフィロソファーなのだ。
古来、「存在」と「一者」の重なりは色々議論になってきたが、二つを切り離すという概念操作がまずポイント。「存在論」より「一者論」が先に立つ、というわけである。
で、この「一者論」というのはヘノロジーと呼ばれて、後期ラカンがそれを語っていたという事実もあり、つながりが気になるところではある(が、ラリュエルとラカンの影響関係はいまのところ調べられていない)。
一者とは実在であり、ただそれ自体に内在的である。純粋な内在性、イマナンス・ピュール。まずそれである。ということなので、ラリュエルは内在主義哲学者であって、ミシェル・アンリなどの系譜にあることになる。だが、そういう系譜と俺は違うぜ、というのを言葉を尽くしてアピールするのがラリュエルなのだ。
他の内在主義者は、超越との対立において内在を語っているが、俺は「あらゆる対立関係の外部」という意味で、絶対的な内在性を考えているのだ、と主張するのである。ラリュエルの一者は、内在-超越のペアよりも「手前」にある。概念対立を使ったロゴスの範疇外に位置する、ただそこにあるだけのもの、なのである。
ラリュエルは、おおよそ哲学というものを、〈概念対立あるいは二元論の複雑な組み合わせによって物事を分節化する営み〉だと見なしている。ところでその意味での哲学は特殊専門化することで近代の諸学問へと分化したわけで、だから、ラリュエルが相手取るのは哲学のみならず、哲学から分化した諸学全体である。その外部に、ただただ内在的でいかなる分節化(または述語づけ)も受け付けない一者=実在を置くわけだ。
中間整理。哲学および哲学から分化した諸学は、二元論的構成をとっていると同時に、それで捉えようとしても捉えられないX(否定神学的なもの)に関わっている。というこの構造全体の外に、一者=実在を置く。哲学内的な二元論はdualismと呼ばれ、それとは区別して、哲学全体とその外部の一者の対立関係はthe dualと呼ばれる。後者の二元性こそが根本的で、前者はそこから派生している。
ところで、先に柄谷-東の構図との比較を述べたが、東は否定神学的構造の成立の失敗によって想定される「郵便空間」の理論を提示した。ポジション的には、それはラリュエルが提示する外部性と重なるように見えるが、ここは慎重な議論が必要だろう。
これはまだ考え中のアイデアだが、おそらく東において「郵便空間」は消極的に定義されるものである——というのは、否定神学的なものは二元論的ロゴスの失敗の点なのだが、それが「必然的失敗になる」ことを批判して(はしょって言うと、それがカント以来の「有限性の分析論」としての近代的ロゴスを保証していることを批判して)、いわば「失敗を徹底する」ことでロゴスを「本当に」破産させるのが郵便論である。
だが、ラリュエルは逆向きに考える。そのような失敗の徹底という方向はシステムに対して依然として寄生的なのであって、外部からシステムへという「一方向的 unilateral」な積極的立論をするのだ。ただ、「本当に失敗する事物」という形で、実在性ないし内在性の措定が東にないのかというとそれも微妙だろう。(続きは定期購読マガジンで書く予定)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
