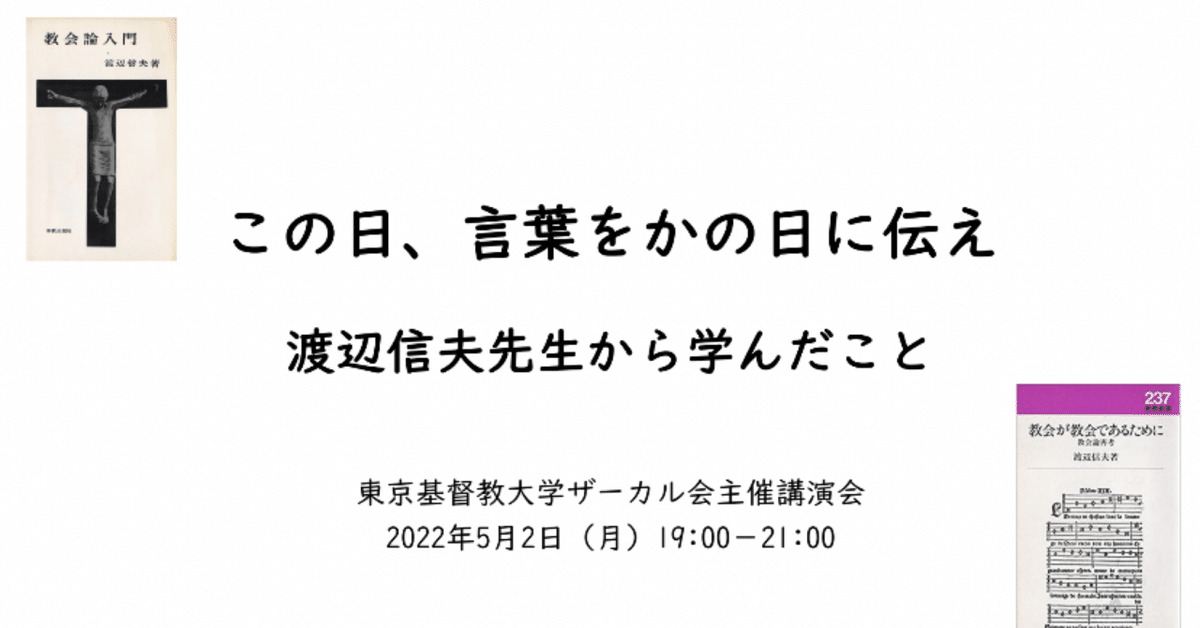
この日、言葉をかの日に伝え
はじめに
こうしてザーカル主催の講演会で、皆さんとともに学ぶ機会が与えられたことを感謝します。TCUに来て、こうして学生の皆さんと一緒に学んだり、考えたりする機会があることは本当にうれしいことです。今年2月の集会のあとで、半ば押し売りのようにして話す機会をいただいて、今日の集まりが実現しました。貴重な時間、ともに考える時としたいと思います。
1.渡辺信夫先生との出会い
2020年3月27日、渡辺信夫先生が主の御許に召されました。97歳のお誕生日を迎える直前のことでした。最後に先生にお目にかかったのはその前の年の5月、先生が開拓し、生涯礼拝を捧げ続けられた日本キリスト教会東京告白教会の修養会に招かれて奉仕した時でした。渡辺先生は1923年(大正12年)に大阪でキリスト者の家庭に生まれ、20歳の時に学徒出陣で海軍に召集され従軍します。この戦争経験が先生のその後の人生に決定的な影響を及ぼしたとうかがっています。戦後、京都大学大学院で学ぶ傍ら、関西学院大学で教鞭を執り始め、ある経緯から無牧になった所属教会で信徒説教者として御言葉の奉仕を始めるようになり、そこで主からの召命を受けて伝道者となることを決心され、以後、一貫してその召命に応えて歩んで来られました。とりわけ先生は16世紀宗教改革史、また宗教改革者カルヴァンの研究者、翻訳者として数多くの著書、訳書を記され、特にカルヴァンの主著である『キリスト教綱要』を生涯で二度翻訳するという偉業を成し遂げられました。これらもまた先生にとっては主からの召命への応答であったと思います。
私が「渡辺信夫」という名前を最初に知ったのは、16歳の時に癌で召された父が浜松のホスピスで最後の日々を過ごしていた時、渡辺先生が父の病室を見舞ってくださったというエピソードを母の看病記『生きるにしても、死ぬにしても』(いのちのことば社、1984年)で知ったことでした。この時のことを渡辺先生もよく覚えていてくださり、後年に「あなたのお父様のことは心に残っています」と言ってくださいました。私と先生との出会いは「書物」によるものです。将来伝道者となる召命を確信した高校三年生の冬、「神学校に行ったら、ここに書いてあるようなことを学んで来なさい」と言って、当時、土浦めぐみ教会の副牧師の先生が私に手渡してくださった一冊の小さい書物。それが『教会論入門』(新教出版社、1963年)でした。この本との出会いは、その後の私の歩みに決定的な意味を及ぼすものとなっています。以後、父の書棚にあった渡辺先生の著書、訳書を引き継ぎ、自分でも次々と読み進め、渡辺先生のことばを通して多くのことを教えられ、問われ、考えさせられながら歩んで来ました。ですから私にとって渡辺信夫先生は、本の背表紙で見るお名前だったのです。その後、1994年に岡山で2.11集会の講師にお迎えしたことをきっかけに個人的にお交わりが与えられ、岡山時代、神戸時代はお手紙のやりとりを通して、そして東京に来てからは折に触れては先生のもとをお訪ねして様々に語り合う機会を与えられるようになったのでした。
2.思考の修練ということ
私が渡辺先生から学んだことは数多くありますが、最も大きいのは「ものごとの考え方」です。先生は大変厳しい方で、浅薄で生半可な知識、分かったような物言い、深く考え抜くことなく一貫性のない意見についてはそれを厳しく問われました。よく先生は「節操」ということを仰いましたが、戦前から戦後の日本の教会を見つめながら、教会で、とりわけ説教壇から語られて来た言葉が一貫性がなく、神に対する節操を欠いてきたのではないか、その時々の情勢の中で教会としての節を曲げてきたのではないかという問いを持っておられました。そしてそこに日本の教会の罪責の原因を見ておられたように思います。
また先生はしばしば「悔い改めが起こらなければならない」と言われました。単なる後悔、単なる反省でなく、真の意味での「メタノイア」、すなわち生き方が変わるということが起こらなければならない。生き方が変わることにまで達しなければ、それは真の悔い改めとはならないと言われました。そして日本の教会に真の悔い改めが起こらないのは、福音の真理が本当のところ分かっていないからだと、分かっていないのに分かっているつもりになって本当に深く学ぼうとしない傲慢さと怠慢さとをいつも戒めておられたように思います。こうして先生は謙遜に学び続けることの大切さを教えてくださいました。努力して知ろうとしない姿勢は厳しく問われましたが、知識の足りなさを見下すことはなさいませんでした。そして問題意識が一時のもので終わるのでなく、思想になるまで考え続けるようにと言われ、しばしば「修練」(エクササイズ)ということを語られました。
3.歴史的思考の大切さ
思考の修練ということで学んだのは、「歴史的思考」の重要性です。よく取り上げるエピソードですが、牧師の務めに就いて数年たった二十代半ばの私は教会や社会の様々な出来事について問題意識は触発されるものの、自分で深く考える知識も意識もなく誰彼かまわず問いを発し、問題意識が共有されないとまた熱量が上がって空廻りするという悪循環に陥っていました。そんな自分を自分でもどうしてよいか分からず悶々としていた時、先生の『カルヴァンとともに』(創文社、1973年)という書物のあとがきに出会ったのです。
「思えば、若い頃のわたしは、神学を学んでいるつもりでいて、実は神学的意識ないし神学的感覚の先走りと空廻りに終わっていたのではないだろうか。それではいけないということに割合早く気づいて、書物を揃えるようになったものの、カルヴァンと直接関係がないと思われるものの多くは、まともに読んでいなかった。それらを読まざるを得ない機会を半ば強制的に与えられたわけである。今ではわたしは、若い牧師や神学生にむかって、『神学的意識ばかり先走っても何にもならない。歴史的知識を蓄積せよ。知識が一定量以上に達してはじめて、神学的思考は作動しはじめるのだ』とえらそうなことを言うのだが、自分の若いときはそれだけのことをしていなかったのである。不幸にして、若いときのわたしの身近には、そのような注意を与えてくれる先達もいなかった。わたしは長年かかって、カルヴァンからこれを聞きとったのである」。
ここで先生の言われた「神学を学んでいるつもりでいて、実は神学的意識ないし神学的感覚の先走りと空廻りに終わっていた」とは、まさに私のことだと思いました。そしてその状態から抜け出す一筋の光がようやく見えたように思いました。そこであらためて落ち着いて、基本的なことを一からコツコツ学び始めようと思ったのです。
4.教会論的思考の大切さ
また私にとって渡辺先生から学んだ最重要のことは、「教会論的思考」です。それは神学の一つのテーマとしての「教会論」に留まらず、キリスト教信仰におけるものの考え方そのものということでした。事柄を教会論的に考えること、教会をかしらなるキリストのリアリティとして捉えること、教会のアイデンティティがこの生けるキリストのリアリティにあること。これらのことを徹底して教えられました。この点での私の最良の手引きは宗教改革に学ぶこと、とりわけ宗教改革者カルヴァンの神学と実践に学ぶことでした。そこで私は渡辺先生の訳された『キリスト級綱要』(全7巻、新教出版者)、『改訳版 キリスト教綱要』(全3巻、新教出版社)を精読し、またカルヴァンから始まって宗教改革全般について意識を持って学ぶように心がけて来ました。特に先生が京都大学に提出された博士論文をもとにした研究書『カルヴァンの教会論』(改革社、1976年)からは多くを学ぶことになりました。またここから導かれるようにして、宗教改革時代の信仰告白文書、信仰問答文書についても学ぶようになりました。渡辺先生はカルヴァン研究者としてのみならず、日本における信条研究者でもあります。その成果の一部は『古代教会の信仰告白』(新教出版社、2008年)に現れていますが、これらの古代信条から始まる信条学の研究は、先生のまさに教会論的思考の実際そのものであり、私はこの先生の引いてくださった線を自分なりに細々と辿ってきたという思いです。
渡辺先生の教会論的思考の中心にあったのは、「教会と国家」というテーマでした。特に1960年代後半から日本の教会が靖国神社国営化反対運動に進んでいくようになり、それを契機として天皇制の問題とあらためて向き合うようになっていったとき、これをいち早く神学的な課題であると把握し、単なる政治運動や社会運動でなく、教会論的に位置づけなければならないとし、その基盤を教会の歴史と実践、とりわけ宗教改革者カルヴァンや古代以来の信条に求められたのです。そこには事柄が個人の問題意識では太刀打ちできる問題ではないということ、世俗のイデオロギーからの借り物のような論理では戦い抜くことはできないこと、情緒的でナイーブな意識でなく、徹底して信仰の事柄として受けとめて神学的な理論を構築し、教会のテーマとして考え行動しなければならないという認識と把握があったのだと思います。こうして渡辺先生の教会論、そして神学そのものは必然的に絶えず実践を伴うものでもありました。
5.「すわって論じておれる」教会論を越えて
「教会と国家」という神学の課題は、突き詰めればイエス・キリストの主権に関わるものであり、またその主権をどのように信じ、告白するかという教会の態度決定に関わるものでもあります。渡辺先生はその著書『神と魂と世界と 宗教改革小史』(白水社、1980年)においてエラスムスやルフェーブル・デタープルたち16世紀の人文主義者たちと宗教改革者たちの生き方を分けたものを「決断」と評されました。体制批判はしてもその内部に留まり続けた当時の知識人たちと、実際に改革のためにその枠から出て行った教会人との対比もまた、イエス・キリストの主権性をどこまでの事柄として信じ、告白するか、という信仰の実存的認識に結び付くものであったのです。
渡辺先生は宗教改革の教会論が今の私たちに示した課題、しかし私たちがそれらをいまだ十分に理解、咀嚼、継承できていない課題として二つのことを示しておられたように思います。一つは「信仰告白の事態」という課題、いま一つは「抵抗権」という課題です。「信仰告白の事態」ということについては、先生が1958年に世田谷で開始された教会に「東京告白教会」と名づけられたように、1930年代ドイツにおけるナチ政権の出現を「信仰告白の事態」として戦ったドイツ告白教会闘争の継承を意識しておられました。教会と国家を巡る戦いを一貫して「信仰告白の戦い」と受けとめておられた事実がこのことを証しています。またカルヴァンが『キリスト教綱要』第四篇、教会論の論述を「抵抗権」で締め括ったことの重要性を指摘され、信仰の良心に基づく為政者への抵抗の権利である「抵抗権」を思想的に深めることを続けておられました。著書『信仰にもとづく〈抵抗権〉』(いのちのことば社、2016年)は、その取り組みの一端を示してくださったものです。
渡辺先生はこの二つの課題を追求していくことを単なる知的な作業とはせず、実際の教会の実践において追求していかれました。そこには「神学の帰結としての実践」と「実践の根拠としての神学」の分かち難い内的な結びつきがあったと思います。先に挙げた『教会論入門』の締め括りの言葉がこの自覚をよく表しています。「もっとよく教会は目覚めて、世の働きをとらえねばならない、といえば答えにはなっていますが、それは理論だけです。わたしたちに求められているのは理論だけではない。わたしたちがどのようにして、実際にキリストの証しをあらゆる領域において立てるかが問われるのです。たしかに、今、教会をふたたびおびやかし、キリストの主権を無力化する動きが権力の側で起こっています。わたしたちは二度とあやまちを繰り返さぬようにしなくてはなりません。しかし、それはもはや論議によって片づく問題ではありますまい。わたしたちの『教会論入門』のすわって論じておれる部分はここで終わります」(同書、169頁)。
この結びのことばから大きなチャレンジを受け取っています。拙著『教会に生きる喜び』(教文館、2018年)のあとがきにこの一文を引用した後、「これが、私にとって教会を神学的に考える始まりとなりました」と記したとおりです。そして今もこのことばにどう応答するかを問われ続けています。
6.戦争の罪責を担って
渡辺先生の神学と実践の根底に絶えずあり続けたのは、先の戦争に対する強烈な罪責意識でした。御自身の戦争体験については多くの書物で触れておられますが、特に若い世代の人々に向けて遺言のように記されたのが『戦争で死ぬための日々と、平和のために生きる日々』(いのちのことば社、2011年)です。ここには戦争という経験が一人の人間に及ぼした影響の大きさ、そしてその一人の人が戦争の責任を自分自身の大きな重荷として担って戦後を生きてきた貴重な証言があります。戦後75年の夏にこのことを受け取る責任をあらためて覚えるのです。
この罪責を背負いながら、渡辺先生は先の1960年代の靖国闘争から始まって天皇制復古や憲法改悪の流れに対する教会としての態度表明はもとより、かつての戦争罪責の悔い改めと真の和解のために、近隣アジア諸国に対する真摯な取り組みを続け、韓国、中国、台湾、インドネシア、パプアニューギニアなどの人々との積極的交流に努められました。特に台湾の元従軍慰安婦の方々の補償を求める裁判の支援会代表を務めたほか、信仰の自由、良心の自由、平和と人権を守るための様々な訴訟活動にも深く関わられました。その同じ意識のもとで沖縄に対しても絶えず強い関心を示し続けておられました。終戦間際、海軍士官として沖縄に向かった経験があったことも忘れてならないことです。
渡辺先生との思い出の中でも強く印象に残っていることの一つをご紹介します。かつて私が教団の「教会と国家」委員会の委員長であったとき、主催した講演会の講師に先生をお迎えすることになりました。その準備の打ち合わせで他の委員の先生方と一緒にご自宅を訪問し、集会の趣旨を説明し、先生のお考えをうかがっていた時のことです。当時、先生は日本の教会の中にも歴史修正主義的な考え方が入り込み、かつての戦争の罪責を直視しようとしない傾向が強まっていることに危機感を抱いておられました。そして私たちに向かって「日本の教会の罪責を裁く教会法廷を開いてほしい。そして自分を被告としてその場に立たせて欲しい」と言われたのです。恥ずかしながらその時には、私はそのことの真意を十分に理解することができず、曖昧な受け答えに終始したように思います。後に先生が「自分は本気でこのことを幾人かの人に提案したが、だれ一人まともに取り合う人はいなかった」と言われたのを聞いて深く恥じ入ったことを思い起こします。戦争経験者の一人として、ここまでのことを言われた先生の思いを今も思い起こし、問いかけられているのです。
7.この日、ことばをかの日に伝え
私自身があらためて渡辺信夫先生から学んだことを振り返るとき、心に思い浮かぶ御言葉が、詩篇19篇2節の文語訳「この日、ことばをかの日に伝え」です。渡辺先生は「教会における伝承行為」ということをとても重視されました。『教会論入門』の続編にあたる『教会が教会であるために 教会論再考』(新教出版社、1992年)の「最も大事なことの伝承」の章で、こう言われています。「本当に大事なことこそが言い伝えられねばならなかったのです。したがって、本当に大事なことが何であるかを凝視し・確認する厳粛な営みが教会の中で行われなければなりませんでした」(同書、121頁)。
これは初代教会の信仰伝承の営みについての言及ですが、しかし同時に今日の教会への注意喚起でもあります。今日私たちもまた何を受け継ぎ、受け渡すかを真剣に考えるように促されているのです。渡辺先生が教会の伝承行為、受け継ぎ、受け渡す役割について語られる時、しばしば引き合いに出された二つの譬えがあります。一つはリレーのバトンタッチの譬え、一つは木から落ちる落ち葉の譬えです。リレーのテイクオーバーゾーンでは、走ってきた走者は手を伸ばして次の走者にバトンを渡す。次の走者もまた手を伸ばしてそれを受け取る。どちらも精いっぱい手を伸ばして受け渡し、受け取らなければ伝承、継承は起こらないと言われました。
また一つの世代が死をもって過ぎ去っていくことを、木の枝から落ちる落ち葉になぞらえ、そうやって地に落ちた葉がやがて堆肥となり、根元の土を豊かにし、次の幹や枝を育てていく。教会の伝承行為、継承もまたそのような世代を繋ぐいのちの継承なのだと言われるのです。そしてこの継承を可能にするもっとも大切なこととして、渡辺先生がしばしば引かれた聖句が、ヘブル書13章8節、「イエス・キリストは、昨日も今日もいつまでも変わることがありません」でした。イエス・キリストはいつまでも同一者である。だからこそこのキリストの伝承行為が成り立つのだというのです。私自身も伝承行為の担い手として、特に次の世代への継承ということを強く意識させられています。
おわりに
一昨年の3月、渡辺先生が召された直後から新型コロナの影響でオンラインでの自宅受講に切り替わった数名の神学生たちとzoomを使って週に一度の読書会を続けました。渡辺信夫先生の『教会論入門』を読み、続けて『教会が教会であるために 教会論再考』(いずれも新教出版社)を読みました。『教会論入門』(1963年)から『教会が教会であるために』(1992年)までが約30年、そこから今までが約30年。私が両書を読んだのは10代の終わりから20代前半、そして皆さんの多くは今20代。こういう時間軸や世代を意識しながら学ぶことであらためて自分自身の立ち位置を確認する機会にもなっています。自分もかつての若い日から教えられ、手ほどきを受けてきた者として、今度は皆さんにバトンを受け渡す側に回らなければならない。このリレーを途絶えさせてはならないという思いを強くさせられているのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
