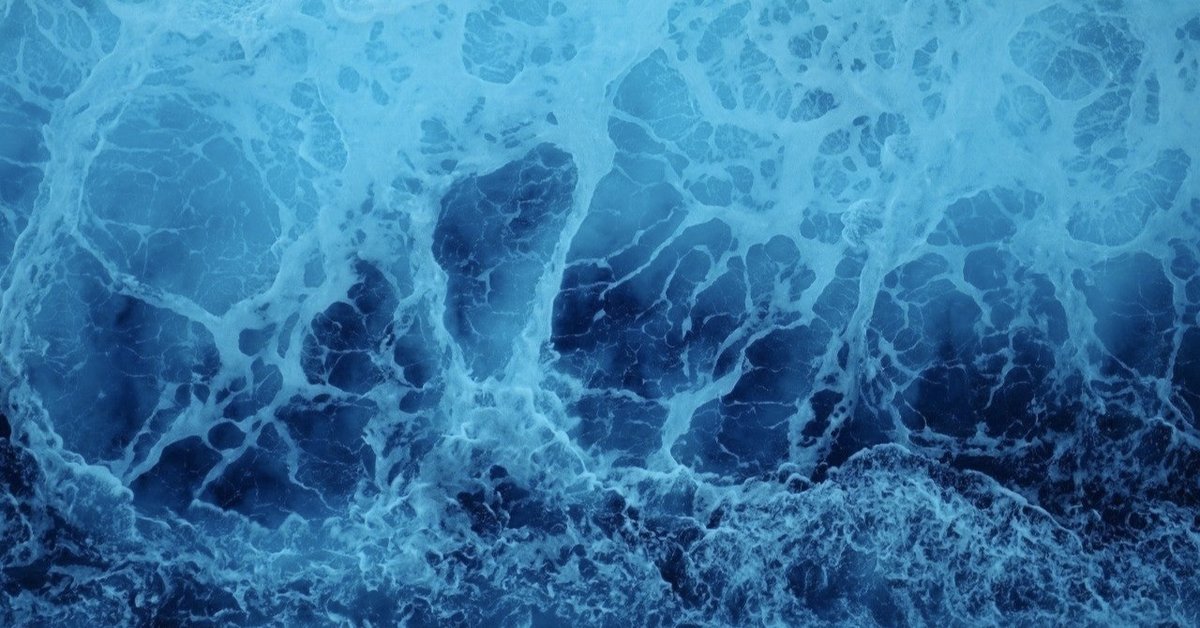
「死の海を泳いで」を読んで
スーザン・ソンタグの最期の日々 デイヴィッド・リーフ
スーザン・ソンタグ(享年71歳)をあらためてウィキペディアで見てみると、小説家、エッセイストなどと書かれている。本人はエッセイストという肩書が好きだったらしいが。
私はもう20年以上前に彼女の著作である「写真論」読んでいた。きっかけは写真だった。アート、特に写真に興味を持ち、写真集を観るのが好きだった。そのうちに「なぜ、こういう写真を撮ったのか」という疑問が湧き、今度は写真論を読むようになった。そんな当初にソンダクの「写真論」を読んだと思う。しかし昔過ぎて内容は覚えていない。
すっかり哲学者だと思いこんでいたが、小説も書いているし、映画製作もしていたとは知らなかった。写真論では有名な著者なので、名前だけは覚えていて、先日古本屋でこの名前を目にし、しかも「スーザン・ソンタグ 最期の日々」という副題から亡くなったことを知り、題名の「死の海を泳いで」に惹かれてページをめくると、ご子息による闘病記だった。
死に直面した作家の死に対する態度や思想とはどういうものなのか知りたくて、購入した。
この本の著者である、スーザンの息子デイヴィッド・リーフは作家である。所々に詩や小説などからの引用があり、それを伺わせる。
母の死から約二年後に書かれた本書には、未だに拭えない息子の悔恨が満ちている。時に重複するような記述、もっていきようのない不満、悲しみが、冷静でいようと努めながら書かれている行間から漏れてくる。
二年という月日は、悲しみは癒えていない中、冷静さを取り戻しつつあり、熱量も高い時期なのかもしれない、それが表出しているのだろうか。
そして、四十代前半で初めて癌を患って以来、癌を患ったことのあるすべての人々と同様、母は再発という「ダモクレスの剣」(訳注 王位の幸福をうらやんだダモクレスを、ディオニュソス王は自分の王座に座らせ、頭上から髪の毛一本で剣をつるして王位の危険を教えた故事による)に怯えながら生きてきた。
母は何でも吸収しようとした―吸収されることは望まなかった―まして永遠に、虚無の中に呑み込まれることは望んでいなかった。
若い頃から希望と意志しかなかった彼女は、創造欲から生への執着心を持っていた。そしてその強い意志は
母が常に未来に生きていたということである。その実に不幸な少女時代、母は大人になった未来の自分を想像しながら生きていた。家族全員には全く馴染めず、その家族という足枷から自由になった自分を想像していたのだ。
原点はこの家族に対する反抗心からだったようだ。そして自分だけは例外になる可能性が高いという信念が生まれた。
かといって、魔法を信じていたわけではなく、科学を宗教のように愛し、信じていた。
母にとって癌と闘うことは正しい情報を得られるかどうか、正しい医師に会えるかどうか、正しい事後処理をするかどうかの問題となった。そして何より、どんな苦しみにも耐える気持ちがあるかどうか。
しかしその情報の取捨選択と深度は彼女にとって微妙なさじ加減が必要だったらしく、癌研究の進歩は追わなかった。
癌研究の現実を全て吸収してしまうこと―それは、想像力という悪魔をすべて解き放ってしまう危険性を孕んでいたのだ。
現実を一つ一つと増やしていくと、善悪が混合された想像という枝葉が更に広がっていってしまう怖さがあったのだろう。それに病に対する情報(知識ではない)を集めたところで、患者には利用手段が無い。
微妙なさじ加減は本人だけではなく、周りの者にも求められるし、応えようとする。
スーザンは病状が進むにつれて、情緒不安定になり、一人でいることを嫌がるようになった。その時のパートナーや友人との会話を求めた。友人たちもそれなりに神経を使いながら接していたし、友人の前では気持ちを抑えていたようだが、息子と二人になるとそれらの接し方への不満が爆発する。
彼らの希望の表現が、愛を打ち明けているとしか解釈できない時は満足しなかった。スーザンはなにより客観性を欲していた。愛を持って、前向きな表現で伝えようと思っても、そのことに客観性がないと、スーザン自ら客観的なデータを持ち出して、彼らの希望の表現を否定してくる。
息子のデイヴィッドに関しては、母が聞きたがっていると思われることを答えることが、息子としての役割であり使命だった。
私の母子関係と対比してみようと思う。
母は子宮筋腫と乳癌を患い、左乳房を全摘出した。それは私が中学生の頃だったので、逆に母が気を使い心配させないようにしてくれていた。
そして約四年前に軽い脳梗塞になり、高次機能障害を患い、盲腸近辺にほとんど進行していない癌に罹患している、八十七歳の老人だ。
そう、母は自他ともに認める老人なのだ。しかしスーザン、デイヴィッド親子は自他共に老人であることを認めない。母を老人として向き合うことは、死の可能性に、本当に向き合うことになるからだそうだ。
確かに私は母の死の可能性を大いに認め、明日死んでもおかしくないとさえ思っている。そしてそんな現実にたいして動揺もせずに暮らしているのは、徐々に老いていく母と日々接し、その老いを認めているからだろう。
母も生への執着は強い。スーザンが創作欲ならば母は金銭欲だろうか。そのためには努力もするが。
対して父は欲のない人で、生に執着せず流れるように亡くなっていった感がする。宗教でも欲をいかにして無くすかを題目にするが、それは死への恐怖をいかにして無くしていくか、なのではないか。
私には到底デイヴィッドのような接し方はできない。それほどこの親子の愛情は強く確固としたものなのだろう。
先日朝日新聞にこんな引用が載っていた。
死の意識とは、死の日づけを知らないままに、死を絶えず繰り延べる意識である。エマニュエル・レヴィナス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
