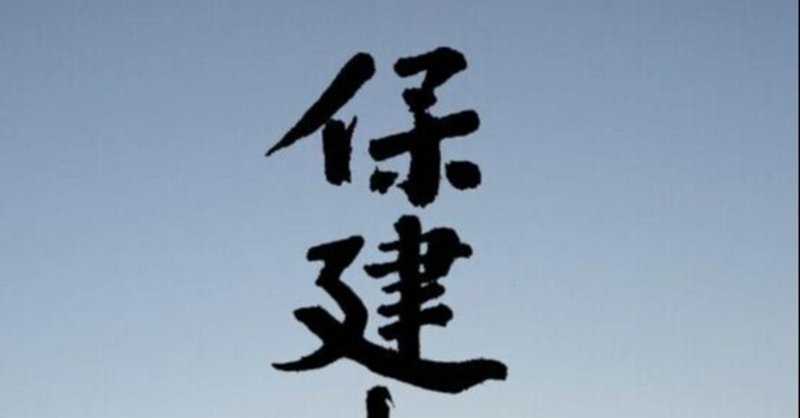
天皇の失徳が国を危機に陥れた~保建大記~(前編)
前稿では保建大記を山本七平の著作で取り取り上げられた形で紹介しましたが、本稿では保建大記をそのまま取り上げてみます。
保建大記では史実の紹介とそれに対する潜鋒の論評が交互に書かれていますが、長くなるので史実の方はほとんど省略します。そして潜鋒の論評を20項目に整理してみました。投稿が長くなるので2つに分けています。
「なるほど!」と頷ける内容も多いのではないかと思っています。国に限らず、会社みたいな共同体なら同じことが言えるように思いました。もしそうなら、これが「消された」思想の元ということかもしれません。
【概要】
・『保建大記』は保元元年(1156)から建久末年(1198)までの30余年に起きた歴史的大事件 を記すもの。後白河の即位に始まり、後鳥羽の退位で終わる。
・天照大神が邇邇芸命(ににぎのみこと)に三種の神器を授けて以来、一姓の王統が明白に連綿と続いてきたわが国。
・幸いなことは、この期間の天皇の不徳失政、武権の専横がこれほどまで酷くても、臣下の分際で王位を簒奪する者がいなかったこと。これも皇祖以来の歴代天皇が徳を積んできたおかげであろう。

【20の問題点】
①後白河天皇が近衛天皇の後を継いだ問題:
・近衛天皇は17歳、後白河天皇はその12歳年長。そんな年長の後白河が近衛の後を継ぐべきではない。(かつて顕宗・仁賢天皇の事例はあるが、これは特殊事情があること)
・鳥羽は「天」が定めた皇位継承順序や人望も考えず、ただ寵妃美福門院に言いなりに人事を動かし。そして関白藤原忠道がそれに盲従していた。
・皇位継承順序が慣例に沿っていないことで、鳥羽の崩御後、後白河と崇徳の争いが勃発した。正統性が証明できなくなったのだ。(注:よくありますよね、理屈では解決できない跡目争い。力で解決するか、前例を研究して話し合いで解決するか)
②天皇家と共に藤原氏も没落:
・藤原頼長は驕慢で、兄の忠道とは仲が悪かった。
・藤原氏は良房までは天皇(清和)を助けていたが、基経が意のままに天皇を廃立させる(光孝、宇多)に及んで天皇は政治から阻害されていった。藤原氏は官職を私物化、要職は一族郎党で占めていた。
・後三条の時代になって天皇善政が復活した。後三条の崩御では、あの頼通(道長の子)ですら嘆いたほどであった。
・しかし残念ながら、その後を継ぐ白河・鳥羽は私生活が淫乱過ぎで子孫に禍根を残した。更に藤原忠道と藤原頼長は利己心に逞しく、人民を振り返ることはなかった。結局、藤原氏も天皇家と共に没落することになった。
(注:トップが乱れば会社とか共同体全体が乱れる。一部が乱れるだけなら、そこだけ切り離せば済む)

③天皇と上皇はどっちが偉いのか:
・天皇と上皇が争う時、どちらにつくのが「義」なのか原則が見えない。慣例に基づく原則が失われると、正統性争いの決着がつかず諍いになり、力で勝ったものが正統ということになる。つまり力がすべての世界。
・崇徳は兄だが既に位を去って久しいし、後白河は弟であるが現天皇であり未だ失徳しているとは言えまい。結局、この場合は三種の神器を擁する方を正統とすべき(注:ここは頼りないが他に妙案はなさそうか)
・とはいえ、この崇徳と後白河の場合はどっちもどっち。両方に非がある。
④平清盛も後に罪を犯しているとは言え、以前の忠勤は評価されるべき:
・清盛は重仁(崇徳の子)とは乳兄弟だが、崇徳側には付かず美福門院の招集(後白河側)に応じた。それを「血も涙もない」と非難する人もいるが、王法(王の取るべき正しい道)では義を優先させても情を優先させたりはしない、公を論じても私を論じないことは明らかである。
(注:リーダーは上位になればなるほど公が優先される。トップの頂上は100%公と言っても良いでしょう。だから給料は高いのです。)
⑤(藤原)頼長と信西(藤原通憲):
・当時経世家と呼ばれていたのはこの頼長と信西の2人。
・頼長は博識を自慢するのみで世の中を見下すような輩。信西はというと深沈確実で臣下としての忠節を失うことはなかった。頼長は単なる賊に過ぎないのにご厚遇されすぎであろう(正一位太政大臣)。
・とはいえ、両者とも自己の利益のみを考え、義を忘れ、私を先にして公を後にするのは同じ連中ではある。
⑥恥知らずで人望のない崇徳:
・崇徳は逃げる際に弟の覚性法親王を頼ったが、弟は後白河に通報した。一夜の宿を借りることさえできなかった。
・崇徳は謀を巡らして乱を構えたが、負ければ剃髪して命乞いをした。非を悔い改めたからではなく、単に死を恐れたから。
・桓武以降、廃天子はあったが流天子はなく、讃岐に流された崇徳は悪しき前例となった。(注:次は3上皇を流した北条義時)
⑦信西の謀、源義朝による父の惨殺、その命を下した後白河:
・信西は叛徒を流罪にするかのような噂を流し、多くを自首させたが、ことごとく死罪にした。
・臣は君の為、子は父の為に忠孝をまっとうして死ぬものだ。勝負が決した後は、子はあくまでも父の為に孝を尽くさなければならない。どうして子が君命に従って父を殺さなければならないのか。そんなことなら共に釜茹でになった方がましだ。
・国が亡びる時は正気(天地間に存在する物事の根本で正しいもの)は萎縮し堕落し人心は道を忘れる。
(注:中国の儒教や朱子学では忠より孝が上で、孝が最上位の徳。日本では忠孝を同レベルにしてしまった。この辺りは以前の投稿を参照ください。)
⑧保元の乱の原因は:
・美福門院の口出しとそれに誑かされた鳥羽。
・しかし、白河の璋子(孫の鳥羽天皇の皇后)への淫乱も問題。その後は貴賤を問わず淫乱堕落が風俗になってしまった。天下の治教は夫婦に端を発する。
⑨後白河の丸投げ:
・君主は自修に努め、徳教に励まなければならない。
・仁徳天皇は御所で粗末に倹約して先に庶民を富ませた、醍醐天皇は冬に御衣を脱いで庶民の寒さを体験した後に格式を制定、後三条は北斗を遥拝する孝の後に度量衡の統一や公正な荘園整理を実施した。(注:すみませんが、この後三条天皇の話はよく分かりません。)
・後白河は順序が逆で信西に丸投げ。なので後宮から反乱がおきた。徳を修めぬ過ちである。
(注:くどいですが、組織は頭から腐る)
⑩平治の乱の主因は藤原信頼(後白河のいわゆるホモだち):
・男色の害でこんな酷い事例はかつてない。かつて孝謙天皇が道祖王を侍童との姦通の罪で廃した事例はあるが、孝謙天皇の淫乱放縦さを考えると濡れ衣と思われる。信頼の場合とは比べられない。
⑪信西は惜しい人物:
・今をときめく信西との姻戚関係を皆が望んでいて、義朝もその例外ではなかった。しかし信西は「我が子は皆学者で、武家のお役には立てない」と断っていたが、平清盛の娘を我が子の嫁にもらうことにしたため、義朝は信西を恨むようになった。
・信西の政治手腕には評価すべきところが多いが、清盛という男を見抜けなかったのが残念。
・「信頼は大将の器でない」と信西は後白河を諫めておきながら、一方で自分の子らを要職に就けることが公私混同とは思ってなかった。
・凡人はいつも自分に関係ない公務に一生懸命で、智者の多くは公私のけじめが付けれない。
<続く>
