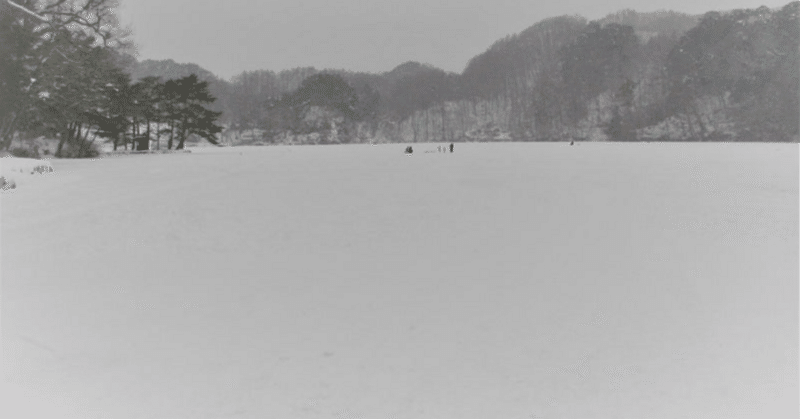
風
車で駆けつけた、三ツ矢サイダーでお付き合いの、一見のバーから出ると、首元から北風がひやり、しみ入るのを感じる。気温はいつもより、うんと高いのであるが。かたくなに封印した「物を考える」ことを、ふとわたしは思い出した。いつも私の正気を紙一重でたもってくれた、関東のあのするどい寒風に似ているから。救いがたい風のなかで、わたしの冬はいつも、物思いの季節であった。多忙の極であった年始を過ぎ、どの年のわたしも、いちど全きからっぽになる。一から十までその身に負った若い責任は、その正しさと過ちを仮借なく洗いだす。そしてどうにも居たたまれなくなったこの身は、当てもなく、外へ飛び出すのだった。やるせないような、誇らしいような、一種異様な感傷、ともかくも、曲がりなりにも、この年度を納めることができた甘美さ、いつもそれは、強い北風とともにあった。その日々ははるかに遠ざかり、一体わたしの人生のどこかであったやら、ときに、それさえも不分明になるのだが、ささやかな匂い、空気の肌触り、そんなものが、命の連続性をかろうじて保証してくれる。いつか遠からず、その連続性が絶たれるとき、どれもこれもが永遠の店じまいをし、とは言え、戻ることのないあの日々と、戻ることはないこの生命と、大したちがいがあるようには思われない。この日々は、進んだぶんだけ、あの日々となり、この生命は、日を経るぶんだけ、あの生命となる。たちまち骨となり、朽ちて土になる。冷たい吹きさらしにあてなく舞う、風になる。わたしであるところのその風は、だれの頬に吹きつけるのだろう。その日々を、わたしは楽しみに待っている、そんなことに気づいて、気づけば、なんと遠い道を、わたしは歩いてきたものだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
