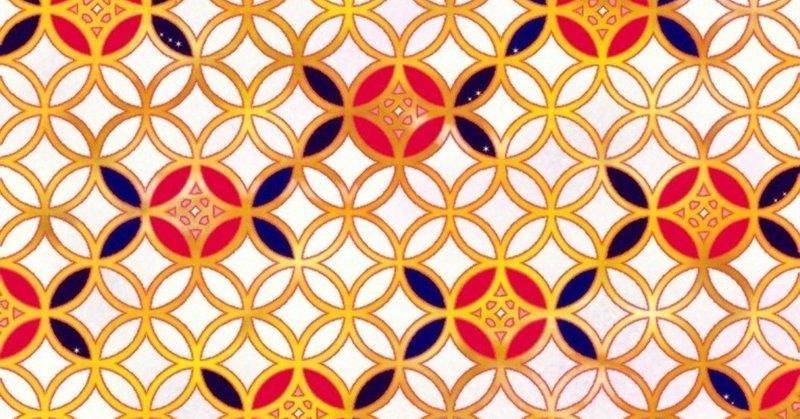
きもの生活復権を考える
(1)「洋服」と「きもの」
キモノは、日本の民族衣装である。日本の歴史、風土、美意識が育んできた日本精神の結晶だ。
現在、多くの日本人は、当たり前のように洋服を着ている。しかし、洋服の本質を知る人は少ない。「なぜ日本人は洋服を着ているのか」「洋服とは何か」「どのように洋服の形は成立したのか」「美しい洋服とは何か」「身体と服の関係性とは」等々の疑問に答えられる人はどれほどいるのだろうか。
私は文化服装学院で洋裁やファッションデザインを学んだ。一般の人よりも、服装史や民族衣装に関する知識もある。それでも「洋服について、どれだけ知っているのか」と問われれば不安な気分になる。
洋服のルーツはヨーロッパにある。洋服には、ヨーロッパの気候風土、キリスト教の価値観、都市や建築、ヨーロッパ人が理想とする人体のプロポーション等が反映されている。洋服に使うテキスタイルの色、柄にも歴史や文化がある。それらを頭で理解するだけでなく、血や肉としなければ、本物の『洋服』は作れないのかもしれない。
一方で、日本にはきものがある。しかし、現代人がきものを着用する機会は少ない。きものに関する教育も受けていないし、きものに関する知識も少ない。大多数の人は、きものを着ることも畳むこともできない。
それでも、きものを見れば美しいと思うし、きものへの憧れもある。私もきものを着ると、何とも言えない心の落ち着きを感じる。頭で分かっているのではなく、DNAが喜んでいる気がするのだ。
日本人が洋服を着用するようになったのは外圧からだ。幕末から明治にかけて、アジア諸国は次々と西欧列強の植民地となり、日本にも植民地化の危機が迫っていた。日本は独立を保つために自らの歴史や文化を否定し、ヨーロッパ文化を受け入れて見せた。鹿鳴館を建設し、武家の婦人達に社交ダンスを踊らせた。その様子は、世界中に報道され、嘲笑の的となった。我々はそうした先人の努力のお蔭で日本が独立を保ったことを忘れてはならない。
日本に導入された最初の洋服は軍服だった。日本国民に、洋服文化を示したのは明治天皇の写真だった。日本の近代化は江戸を否定するところから始まった。皇室の正式な衣装がきものではなく、洋服であるのも歴史的必然だ。
日本の洋服は「建前の場面」から普及していった。1950年代まで、男性は会社に行く時には背広を着て、帰宅するときものに着替える人が多かった。日本の住宅も、客間は洋室にしたが、茶の間は和室だった。建前の空間は洋風で、本音の空間は和風。当時の日本人の感覚では、それが自然だった。
女性の洋装については、1932年(昭和7年)の白木屋火災が契機となり、洋装下着が普及したという風説がある。真偽はともかくとして、このころから女性の洋装が普及したようだ。
女性の洋装は安価な普段着から普及した。正装はあくまできものだった。安価な日常のきものは洋服に置き換わり、きものはフォーマルウェアとして生き続けた。きもの小売市場のピークは1981年であり、その後はフォーマルウェア分野でも洋装化が進んでいった。
洋服の視点から見ると、日本にきものがあったために、イブニングドレスは定着しなかった。ヨーロッパのデザイナーは「ソワレ(夜のドレス)こそファッション」というが、日本の洋服は昼の服だけで、ソワレはほとんど見られない。その意味で、日本人はファッションデザインの本流を経験していないのかもしれない。
(2)きものに対する二つの視点
現在のきものを取り巻く状況を見るには、二つの視点が必要である。
第一は、小幅織物産地、呉服卸等、呉服業界の視点。彼らにとって、きものとは着尺の反物である。
呉服業界から見たきものは市場規模も生産量も減少を続けている。当然、着用人口も減少し続けている。呉服業界が自らのビジネス存続のために、「きものの復権」を訴えるのは当然である。
第二の視点は、消費者の視点である。生産者にとってきものは反物だが、消費者にとっては、古着でも、広幅の生地を仕立てたものでも、きものである。
1984年、新装大橋がラフォーレ赤坂で撫松庵「キモノ・リ・エボリューション」を発表。小売店を対象にした閉鎖的な展示会ではなく、消費者を対象に、仕立て上がりのキモノを、帯、小物と共にコーディネートして展示した。反物ではなく服として、ファッションとしてのきものの提案だった。
同じく新装大橋は、1985年にきものリサイクルショップ「ながもち屋」を開設。現在まで続く、古着ブームの火付け役となった。
1993年、伊勢丹美術館で開催された第一回「日本のおしゃれ展(池田重子コレクション)」は、明治、大正、昭和のきものを再発見する試みであり、美術品や骨董ではない生活の中で息づいた美しいきものを紹介した画期的な展覧会だった。
冠婚葬祭のフォーマルウェアとしてのきものではなく、美しい日常着、生活着としてのきもの。現在の市場では見ることのできないきものの数々。当時の日本人はこんなに豊かな衣生活をしていたのか、という感動を与えるものだった。
日本人にとって、きものは誰の所有物でもない。呉服業界の商材でもないし、商品でもない。日本の伝統文化そのものである。しかし、現在きものを生産し、流通、販売しているのは呉服業界である。
できることなら、呉服業界が業界として成立し、消費者が望むキモノを供給してくれることが望ましい。それには、まず現在のきものを再考する必要がある。
(3)きものと着付けの問題点
現在のきものは、窮屈で苦しいというイメージが強い。これは成人式で晴れ着を着たり、花火大会で浴衣を着た時の着用者の実感である。幅広の帯を胸高にきつく締めれば、食事をすることも困難だ。
一方で、きものを着慣れている年配の女性は「洋服よりきものが楽」と言う。同じきものなのに、評価が正反対になるのは「着付け」に原因がある。
そもそもきものとは、立体の身体に平面の布を巻き付ける服である。従って、運動に伴い、身体ときものはズレる。洋服は、身体の立体に添わせた立体の服であり、運動しても身体と服がズレにくいし、ズレても元の位置に戻る。
きものは、構造的に着崩れる服であり、着用者は常に崩れた部分を直す。襟元に手をやって、着崩れを直す仕種そのものを美しく見せることが重要であり、同時に、「きものが着崩れないように動く」という所作が、きものの美しさを際立たせる。
歩き方、身体の動かし方やちょっとした動作にいたるまで、洋服ときものでは異なっており、それぞれに美しい動作がある。動作そのものが文化の表現であり、動作を様式化したものが舞踊である。日本舞踊はきもの文化から生まれた仕種や動作の芸術と言えるだろう。
日常的に洋服を着ている現代人は、きものを基本とした所作の文化を失ってしまった。洋服を着ている時と同じように動くので、きものは余計に着崩れる。着崩れても修正する方法を知らないので、着付けの人は最初から着崩れないようにきつく着付ける。それが「きものは苦しいもの」と言われる所以である。
現代のきもの姿は、洋服のように固定されている。しかし、元々きものとは洋服的な視点から見たらだらしなく、しどけない姿に見えるものだ。江戸時代のきもの姿を見れば、現在のきものとは全く異なる印象を受けることだろう。それを見た人の印象も、当時は美しく感じたものが、現在はだらしないと感じるかもしれない。既に、日本人の価値観や美意識そのものが変化しているのだ。
現代のきものを見ている視点は洋服文化のものであり、きものの着付けも洋服文化の美意識に基づくものである。
きものという服があり、そこから日本独特の所作が生まれる。そして、所作を基本とした建築が生まれ、交通手段が生まれ、都市が生まれる。江戸時代の都市は、きものを基本に構築されていた。
しかし、明治になってヨーロッパ風の洋館が建設され、江戸は東京へと生まれ変わった。その変化は、きもの住宅から洋服住宅への変貌であり、きもの都市から洋服都市への変貌とも言えるだろう。
きもの復権を唱えるならば、きものという服だけでなく、その動作や建築、都市計画に至るまでトータルに考えるべきであると思う。
その意味では、「きもの復権」ではなく、「きもの生活復権」が重要だ。「きもの復権」とは、呉服業界が婚礼衣装、振り袖、訪問着、七五三等で着用するきものの売上を復権したいという意味に近い。しかし、「きもの生活復権」となると、生活スタイルの問題であり、生活空間の問題にもなっていく。
呉服業界は、きものの売り出しの時に、きものを着用するのは当然として、会社そのものを、あるいは個人の生活そのものを、きもの中心に再構築していくべきではないか。
(4)「きもの復権」は「日本人のアンデンティティ確立」
本来、きものは着物であり、日本人が着る服は全て「きもの」だった。半纏とどんぶり、彫り物とふんどし、野良着、パッチのような下履き、坊主の袈裟、神主の束帯に至るまで、職業や地域によって様々なきものが存在していた。女性のきものも、武家、商家、花魁、百姓とそれぞれが異なっていた。
その中から、日常のきものが次第に失われ、最後に残ったのが現在のきものである。基本的に武家の奥方の着物がモデルとされているが、現在のきものに定着したのは昭和以降である。つまり、現在のきものは昭和以降のスタイルであり、江戸時代のきものとは異なるものだ。様々なきもののうち、かなり特殊な形に整理されたのが現在のきものであり、きものの名称や、着付けのルールも昭和以降に整理されたものである。
私は、現在のきものを以て、きものの代表とは考えていない。現在のきものを作ったのは、呉服業界や着付け教室であり、そのビジネスが基本となっている。その特殊なきものだけを日本の伝統文化と定義して良いのだろうか。きものの世界は、もっと広く多様なものではないだろうか。もっと自由で個性的なものではなかったのか。現在のきものを維持することが、即ち、日本文化に貢献すること、と決めつけるのは危険だと思う。
産業革命以降、世界の繊維産業は大きな変貌を遂げた。もし、日本が洋服を導入せずに、独自のきものを維持したとしても、やはり時代と共にきものは変化したはずである。
江戸時代にも、様々なきものが流行したことが記録に残っている。黒づくめの着物が流行ったり、短い羽織が流行ったり、その反対に非常に長い丈の羽織が流行ったり。柄や色の流行だけでなく、形の変化もあった。
その延長であれば、当然、洋服の要素も取り入れただろうし、他の国の民族衣装の要素も導入したかもしれない。最先端のハイテク素材やデジタル技術も取り入れただろう。きものを伝統工芸の世界に閉じ込め、それを保護することだけを考えるのも、きものにとって健全ではない。
「きものの復権」が、現在のきものだけを対象としているのなら、私はあまり興味を感じない。それは呉服業界のためであり、懐古趣味の人達の趣味を満足させることだから。
「きもの復権」とは、日本のアンデンティティの確立であり、西欧文化からの自立であると考えている。そう考えると、呉服業界の活性化などという小さな問題ではない。日本の将来の問題である。
(5)生活着としてのきもの開発
現状、きものは特定の場面で着用するフォーマルウェアである。あるいは、コスプレとしてのきもの、趣味のきものもあるだろう。勿論、きもので生活している人も存在するが、それは少数派だ。
きもの生活を考えるならば、生活着としてのきものが必要になる。生活着として考えると、正絹、ポリエステルのきものだけでなく、様々な素材のきものが欲しくなる。最近、デニムきものが人気を集めているのも、フォーマルではない日常シーンで着用することを想定しているからだ。
素材だけでなく、形の工夫も必要である。江戸時代には様々な丈のきものが存在していた。日常着であれば、袖も筒袖やマチ付きの袖があってもいい。カルサン、野良袴、庄屋袴等の袴のバリエーション。作務衣のような野良着のバリエーション。羽織も袖のあるもの、ないもの、丈のバリエーションが必要になるだろう。
呉服業界に身を置くのならば、まず会社で働く時のきものを考案してはいかがだろうか。そして、会社のレイアウトや内装もきものに合わせる。例えば、床を上げ、畳を敷き、掘ごたつのように床を掘る。クッション付きの座椅子の開発も必要かもしれない。
こうした環境で快適に仕事をするには、パソコン操作に邪魔にならないように袖を工夫するなど、様々なニーズに対応する必要があるだろう。それがそのまま、生活着としてのきもの開発につながる。そして、会社全体がきもの生活を実践すれば、国内外へのPRにもつながるだろう。
(6)「きもの特区」の提案
世界中の国では、洋服を国際標準にしようとしている。ある意味、西欧文化が世界を支配しようとしている。
勿論、民族衣装も存在しているが、多くの国は西欧文明を取り入れる段階で、実質的に民族衣装から洋服へと移行している。日本だけが、接ぎ木のような衣文化なのではなく、ヨーロッパ以外のほとんどの国も同様なのだ。
日本は早い段階で民族衣装から洋服へと切り換え、西欧文明を取り入れ、先進国への仲間入りを果たした。そして現在、世界から日本が評価されているのは、西欧化しながら、独自の伝統文化、食文化、ポップカルチャー等を世界に発信しているからである。
日本はマルチカルチャーの発信基地であり、ハイテクとローテクが同居し、西欧文明とアジア文明が共存している希有な文化を持っている。その内の重要な要素を「きもの文化」が占めていると思う。
例えば、きもの文化復権のために、「きもの特区」はできないだろうか。
前述したように、きものを基本とした会社ができれば、それを次第に拡大していくこともできるだろう。レストランも商店も、きものを着た従業員が対応する。きもの着用のお客様を想定した店の設計、内装をする。地方都市等では、歴史的な町並みを保存するために、景観条例を設け、古い建築デザインを保存している。同様に、地域単位できもの生活に相応しい景観条例を作ることも可能だろう。
「きもの特区」は、地域の観光資源になるだろう。少なくとも、商店街単位できもの特区に指定する。あるいは、テーマパークのように特定の商業集積やオフィス、住宅等を丸ごと「きもの生活」をテーマに開発することもできるのではないだろうか。
「きもの特区」の中核施設として、日本文化を教える全寮制の大学ができないだろうか。外国人は日本のイメージを「武将」「侍」「忍者」「芸者」「マンガ」「ゲーム」等で捉えている。伝統的文化から現代のポップカルチャーそれらを教えるための教育機関である。そして、世界中から学生を募り、きもの生活を実践してもらう。
大学の他にも、「きもの生活デザインセンター」等の研究開発機関を設け、新たな生活スタイルの提案と実践を行う。「きもの生活博物館」「きもの観光拠点としての商業施設、飲食施設」等々、考えればきりがないほどだ。
この「きもの特区」は、既存の呉服業界のために設置するのではない。しかし、結果的に呉服業界にとっても大きなチャンスになるだろう。最初から大がかりなプロジェクトである必要はない。小さなスケールからでもスタートできれば、何かが確実に変わっていくはずだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
