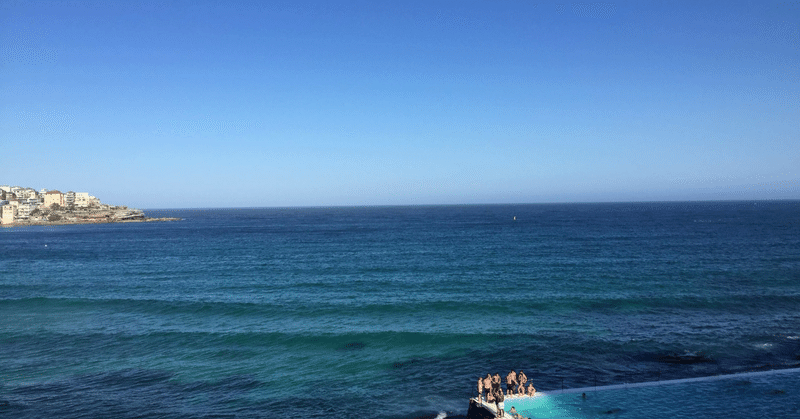
Photo by
ozfukumango
物理苦手でも気象予報士試験に合格したい!#44 エルニーニョ現象
あけましておめでとうございます。年明け初の投稿になります。
こんにちは、まさごんです。
気象予報士試験の合格を目指すべく、日々の勉強内容を記録しています。
勉強内容
学科の勉強範囲を一周したため、ここからは過去問で間違えた問題で大事だと思ったものをピックアップしてまとめていきます。
使用している過去問は、気象予報士試験研究会が編集している、2022年度版の過去問です。
学習ポイント エルニーニョ現象
エルニーニョ現象とは、赤道海域東側のペルー沖の海面水温が上昇することによっておきます。通常の年の太平洋赤道域では、西側(日本やオーストラリア側)に海水温が28℃を超える断水が広がっていますが、一方で東側(ペルー、南米側)では22℃以下の低温になっています。
毎年12月ごろになると、太平洋西側では深海からの冷たい湧水が衰えるのに加えて北から暖流が流れ込んでくるため海水温が上昇します。
12月~1月のピーク時には2~3℃も上がるそうです。
そして3月ごろにはもとの海水温に戻ります。
しかし、数年に一度くらいの間隔でこの季節的な変化が崩れ、3月になっても海水温が高いままの状態が続くことがあります。この状態をエルニーニョ現象といいます。
エルニーニョ現象が発生すると、赤道付近の海水温分布が変わり、対流活動にも変化が生じます。
赤道付近で形成される亜熱帯高気圧の位置や強さが変わり、日本では暖冬・長雨・冷夏が起きやすくなります。
気づいたこと
暖冬・冷夏が続くと稲が不作になり、おコメの値段が上がるイメージがあります。
今日は寝坊したため、いつもの半分の量になってしまいました…。寒いとhン等に早起きが苦手です。年明け初出社、頑張ってきます。
ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
