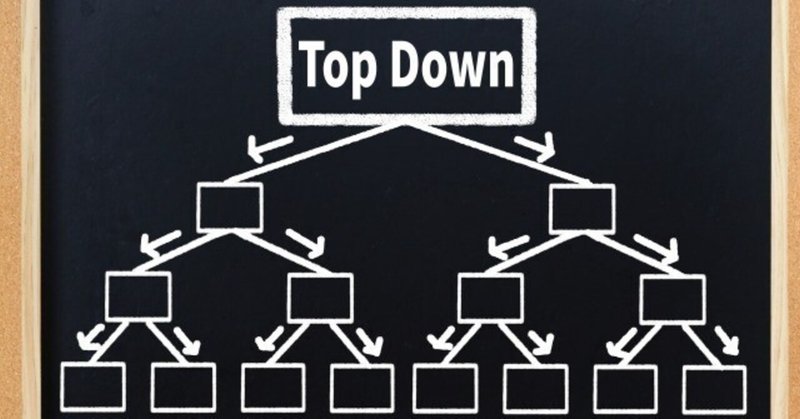
上意下達のコミュニケーション
最近忙しくてめっきり更新が止まっていました…。
中小企業の社長の仕事とは何か?
以前は大企業に類する会社でサラリーマンをし、今では中小企業で社長をやっています。大企業も中小企業も触れたことがある身として、面白い話になればなと筆をとります。
さて社長の仕事とは何でしょうか?取引先とのお付き合いはどこでもありますし、大企業なら財界活動もあるでしょう。中小企業なら地元の商工会議所といったところでしょうか。でもここでは社内向けの仕事に限定します。社内向けの社長の仕事は本来「ヒトモノカネのリソースの配分を決める事」だと思います。それは即ち「会社として何にどれくらい力を入れて行くか」ということの明示であり、「会社としての戦略を決める」ということです。
これが非常に難しくなるのは大企業の場合で、リソースはあるのだけど、既にたくさんの事業があり、社長自身も触れたことも無い事業もある中で「キミんとこの事業縮小するから」というのも決めにくく(決めてクーデターが起きた企業も有りましたね)、逆に個人として強烈に思い入れを持ってしまった新規事業に沢山のリソースを突っ込んで大失敗というのは過去の例が星の数ほどあります。組織が複雑で、専門性も異なるので、本当に大所高所で正しい判断するというのは難しいと思います。
他方私達中小企業では人の顔も大体全部見えるし、そんなにいくつも事業があるわけでもありませんので、判断がつけやすいという良い点はあります。悪い点は慢性的にヒトモノカネのリソース不足だという事でしょうか。笑
半年に一回の全社集会
当社ではコロナ前、元々半年に一回全社集会をやっていました。先日はコロナの影響で3年ぶりに開催出来ました。色々プログラムはあるのですが、最初はいつも私が半年の業績やビジネス環境の振り返りと、それを踏まえた今後の課題の話をします。意識の高い話や小難しい話は出来るだけ避け、とにかく簡単に、そして実感を持てるように具体的な話で纏めるように心がけています。
そしてもう一つお決まりにしているのは「私達の基本戦略はこういうことだよ」というのを毎回必ず入れることです。代わり映えが無くても必ず入れます。新卒や中途で入社した人達に改めて説明する意味もありますが、何回も伝えることで理解してもらうという意図があります。
基本は「コミュニケーション不全」
社内では常々言っていることですが、「組織とは基本的にコミュニケーション不全」です。何故なら「経験も、育った環境も、権限も、何もかもが違う人たちが集まって、問題なくコミュニケーションが取れるはずがない」からです。ですから、手を変え品を変えて何度も伝えないといけないし、確認をしないといけないのです。一度曖昧に指示して「だから言っただろ」と説教をするのは私は上司先輩側の怠慢だと考えます。
日常の業務においてさえそうですから、普段顔もなかなか合わせない社長が考えた「戦略」なんてものが一度聞いただけで分かるはずも無く、むしろ内容的には雲をつかむような話になりがちで、日常業務より伝えるのがはるかに難しい。また社長は毎日のように戦略が正しいのか考え続けているわけですが、一般社員は半年に一度聞かされるだけなので、社長と同じレベルに理解できようはずもありません。だから毎回必ず粗筋は話をするようにしています。これは私が偉いという話ではなく、客観的事実の話です。
具体性が無いならそれは自己満足
戦略というのは往々にして「いかにももっともらしく、当たり障りが無く、実現性が怪しいもの」になりがちです。その方が反対意見も出にくいし、作ってる本人も満足しやすいからです。
大企業の場合はそれを各事業の具体的な行動に落とし込むのは担当役員の仕事、ということになるわけですが、中小企業の場合は具体的な行動まで含めて説明して、個々のケースについては各役員に判断してもらう、くらいのことをしないと大企業よりスピーディに話が進みません。大企業よりリソースも無いわスピードも遅いわでは滅んでしまいます。また、先述の様に理解が進みにくいのだから、出来るだけ具体的なところまで話を落とし込んでおかないと、正しく実行されません。
正しく実行されないということは、社長のフラストレーションがどうしたこうしたの前に、「間違っているので修正する」という判断が出来なくなるということです。「間違っている」のと「正しく実行されていない」というのは、上手く行っていないという結論だけ同じで課程が全く異なります。課程が異なるなら対策が全然違ってきてしまいますからね。部下からすれば迷ってアッチにふらふらコッチにふらふらされる方が迷惑です。(経験談w)
徹底することはとても大切です。
コミュニケーションは絶対量
何事も他人には伝わりにくい、ということを述べてきましたが、それに対する対策は「絶対量」しかないと考えています。「時間×頻度」です。「1を聞いて10を知る」という諺もありますが、まぁそうそう起きませんよそんなことは。5回聞いて分かる人と10回聞いて分かる人という差は生まれるかも知れませんが、それとてやはり5回~10回は繰り返し話合わなくてはいけないのです。
また、伝言ゲームの難しさもあります。社長の話を管理職が部下に伝えたとしても、社長(理解度100)→管理職(理解度80)→一般社員(理解度50)といった感じで伝わりにくくなります。当然です。これを補うには、回数を重ねたり、社長が直接語り掛ける場を持たねばなりません。全社集会は大事なのです。
大企業では管理職の階層がたくさんあったり、動画撮影して社長が語ろうにも、その原稿は部下が書いていたりして、伝わり難い要素が山盛りです。大企業というのは規模の強みは代え難いものがありますが、引き換えにするものも大きいです。
上意下達の難しさ
上意下達の究極の形は軍隊です。命がかかりますので、一つ一つの命令は形式が定められ、絶対服従前提で徹底されます。しかしながら企業やスポーツ、あるいは家庭内でのやりとりであっても、上(上司・監督・親)から伝えるということは簡単ではありません。聞く耳を持っていなかったり、意見を持ったりすることは、人間なのだから自然なことです。時間と回数をかけて粘り強く伝えていくしかないということなのだろうと思います。手間を惜しんだら負け、簡単に伝わるだろうと思うのも負けです。
でも、それくらい難しいことなので、伝えるということをキチンと出来るだけで他者より抜きん出ることは可能なのだろうとも思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
