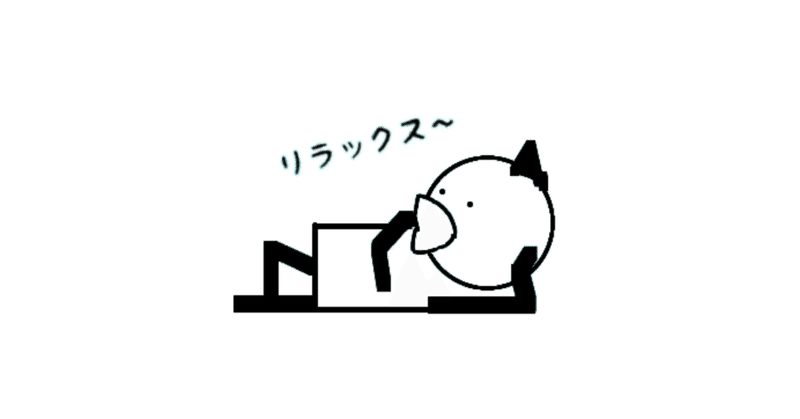
<社会の中のアリス>
*この記事は「脱サラをする前に」というサイトから転載したものです。
「水俣病は環境省が生まれた原点であり、…」
と、涙を浮かべながら話している伊藤環境大臣の姿に僕は感動しました。以前、ある大臣が会見で、自分が所管している行政に関連する地名を読めなかったことがありましたが、それに比べますと伊藤大臣の涙は政治家として尊敬に値するものでした。
もちろん、意地の悪い人の中には「政治家のパフォーマンス」と揶揄する人もいるでしょう。ですが、俳優でもない人があそこまで感情を表に出すのは不可能です。僕が見た印象では、あの涙は心の底から思いがこみ上げてきたように感じました。仮に、もし本当に演技であったなら、それはそれで賞賛されてもいいほどの会見でした。
ニュースでなんども流れましたのでご存じの方も多いでしょうが、ここまでに至った経緯を簡単に説明します。今月の1日に、熊本県水俣市で水俣病犠牲者の追悼慰霊式のあと、環境省と患者団体などとの懇談の場がありました。その際に、団体のメンバーが発言している最中に時間制限を理由にマイクのスイッチを切ったことが今回の騒動の発端です。
マイクのスイッチを切る前に、懇談会を仕切っていた環境省のお役人が「話を切り上げるように」と発言をしていました。それからマイクのスイッチを切ったのですが、同時に発言者からマイクを引きあげる職員の姿もありました。無理やり懇談会を終了させる意図がありありの光景でしたが、その光景はつまり、「形ばかりの懇談会」だったことが露わになったシーンでもありました。
その懇談会には伊藤大臣も出席していた、といよりは患者団体が「大臣と懇談する」のがメインだったはずです。そうした中での、環境省お役人の無理やりの懇談会「切り上げ」でした。もちろん患者側からは強制終了に対して非難の声もあがりましたが、そのとき伊藤大臣は取り立てて対応はせず、役人にうながされるままに退出して行きました。その後、マスコミで大きく報じられたことでの冒頭の発言・会見となったわけです。
僕がその会見を見ていて思ったのは「政治家と官僚の関係」についてです。大まかにざっくりと分けますと、大臣と官僚の関係には二通りのパターンがあります。一つは官僚が完璧に上の立場で、大臣を「自分たちの思うがままにコントロールする」パターンです。あと一つは正反対で「大臣が官僚をコントロールしようと試みる」パターンです。
30年くらい前までは政治の世界は完全に前者のパターンでした。なにしろ、「政治は官僚が動かしている」と豪語するお役人もいたくらいです。当時は毎週1回各省の事務次官が会議を開き、いろいろな課題について話し合いを行っていました。その議長を務めていたのが「官房副長官」という役職ですが、事務方のトップといわれる立ち位置です。最も有名な官房副長官は石原信雄さんという方ですが、なんと昭和から平成にかけて7人の首相に仕えています。いかに政治家から頼られていたか、がわかります。
話をもどしますと、伊藤大臣は直接水俣病患者代表者のところまで出向き謝罪をしましたが、その際に代表者から「もう一度懇談会を開いてほしい」と要望を受けました。一般の感覚で考えますと、大臣は環境省で一番偉い立場ですから自らの意思で決めることができそうなものです。しかし、伊藤大臣はすぐに返答しないどころか、言い淀んでいました。最終的には、なんどめかのお願いでようやく「開きます」と答えていました。
僕の推測では、環境省における伊藤大臣と官僚の関係は先ほどの2つのパターンの中間です。逡巡していた大臣が押し切られる感じで懇談会開催を受け入れてしまったわけですが、官僚側との調整が並大抵ではないことは容易に想像がつきます。懇談会を仕切っていた官僚も謝罪に出向いていたのですが、伊藤大臣とは対照的に謝罪が目的であるにもかかわらず冷たい表情は変わっていませんでした。
謝罪を受けた患者代表者から「担当者を変えてほしい」と言われるほど謝罪の気持ちが伝わっていない光景でしたが、仮に、もしあれが演技であったなら、これもまた賞賛されて然るべきものでした。その官僚を見ていて、僕はある本を思い出しました。
「福祉の国のアリス」山内 豊徳 (著)。1992/11/1
「不思議」ではありません。「福祉」です。著者名の山内豊徳はペンネームなのですが、本名でないのは当時の環境庁の官僚だったからです。まだ「省」になる前の「庁」の時代の官僚なのですが、成績でいいますと本来エリートが目指していた大蔵省に十分に就職できたにもかかわらず、「弱者に寄り添いたい」という思いから厚生省に就職した変わり者です。
当時僕はたまたま新聞の囲み記事でこの方の連載を読んでいましたが、そのときは山内さんのことは知りませんでした。単に、心優しい人が書く記事だと思っていただけです。その後、僕が山内さんのことを知ったきっかけは映画監督の是枝裕和さんが、これもまたたまたまなのですが、ある新聞に記事を投稿していたことです。
詳細は省略しますが、その後いろいろな情報がつながって是枝監督が山内さんのことを描いたドキュメント作品でギャラクシー賞優秀作品賞(1991年)を受賞していたことを知りました。僕が是枝監督を好きになったのもちょうどこの頃です。山内さんは53歳のときに自死しているのですが、その理由は行政の立場と被害者の気持ちの板挟みになったことと言われています。
山内さんが自死した当時、山内さんは水俣病の国側の立場にいたらしいのですが、本心では被害者の立場にいたかったようです。適当に仕事をしている人ですと「仕事とプライベートは違うよな」と割り切って苦しむこともなかったのでしょうが、まじめに仕事に取り組んでいた山内さん、しかも被害者の気持ちも十分に理解できる山内さんでしたので苦しくなって当然です。
このコラムのはじめのほうで懇談会のようすを描写しましたが、その中で「発言者からマイクを引きあげる職員の姿もありました」と書きました。そのマイクを引き上げたお役人は50半ばくらいの女性でした。実は、僕はその女性がどんな気持ちでマイクを引き上げたのかが気になりました。マイクを発言者から取ったときの雰囲気は、強引というのはなく発言者を気遣っているようすがうかがわれましたが、「心中はどうだったのだろう」と思わずにはいられませんでした。
余程の悪党の行動でもない限り、世の中で起きていることを「悪」と決めつけるのは困難です。例えば、普通に暮らしている家庭に強盗が入った場合は、その強盗を完全に「悪」と決めつけることができます。しかし、世の中にはどちらの言い分にも「一理ある」場合は少なくありません。現在、イスラエルで起きているハマスとの紛争も歴史をさかのぼりますと「どちらが悪い」と単純に決められるものはありません。
水俣病も「被害に遭った人を救う」という点ではだれも異論はないでしょう。しかし、50年以上揉めているのは、その線引きが難しいからです。どこまで補償するかを決めるのは簡単ではありません。できるだけ補償範囲を広げたくない国側とチッソに原因があると思われる被害者をすべて補償してほしい被害者側とでは、合意に達するのは並大抵のことではありません。
5月は新卒の社会人の退職が多くなるそうです。昔の感覚では「3年くらいは辛抱」というは普通でしたが、今の感覚では違うかもしれません。僕は昔の世代ですが、「意に沿わない」環境と思ったなら「退職するのもあり」と思っています。「弱者のために働きたい」と思っている人が、結果的にではあろうとも「弱者を切り捨てる」仕事に就いていることほど不幸なことはありません。
たとえ、仕事が生きるための手段であったとしても、手段が意に沿わないことで「生きる」ことができなくなることもあるのですから。
じゃ、また。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
